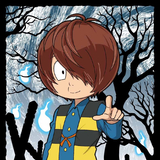はちどり(2018)のレビュー・感想・評価
全115件中、81~100件目を表示
ことごとく、予想が外れるんだ…
今までなんとなく使っていたけど
「空気感」ってこういうことなんだなあと、改めて思った。
ウニと家族たち
ウニと親友
ウニと塾の先生
ウニと病院の先生
ウニと彼氏
ウニと年下の女の子
全てのバランスが良くて、ついつい「映画」ということを忘れてしまう。
いつの間にか自分がウニになってしまう。
一つ一つのシーンの中で、自分が予想していたことが全て外れてしまう。
うまく裏切られてしまう。
最高の裏切られ方で、気持ちがいい。
こちらからは、以上です。
曇天の見える小さな窓
どれだけ多くの人と出会うかが人生の財産であると常々思っている。広く浅く人付き合いをせよという意味ではない。自分がどうあるべきか、どんな人間でありたいかを教えてくれるのは良い人、悪い人も含めた他者との出会いがあってこそであり、多くの人との出会いが自分自身を形成していくからだ。
偉そうなことを書いたが、私がそんな価値観を持ったのは30歳を過ぎてからだ。14歳の子どもにそれを理解せよと言っても、難しいだろう。14歳にはその年代の世界がある。友人関係、進学へのプレッシャー、反抗期に伴うストレス。とてもじゃないが、自分の見ている以外の世界を見る余裕などない。いや、他の世界の存在すら知らないのかもしれない。ましてや本作の舞台は1994年の韓国。学力至上、男尊女卑が今よりも顕著だった時代に生きる主人公・ウニの目に映る世界はどこか理不尽で、学校でも、家庭でも自分の立ち位置が分からないものだった。
そんなある日ウニは一人の塾の教師・ヨンジと出会う。だが、その出会いが劇的に彼女の人生を変えるような予定調和な話ではない。例えるなら、この教師は真っ暗な閉ざされた部屋の天井に突然できた小さな窓のような存在だ。窓からは見えるのは曇天で、この後で雨が降るのか、日差しが降り注ぐのかは分からない。ウニはその窓を見つめるが、天気と同様に人生の変化は能動的に起こるものとは限らない。自分が動かなくても、自分とは無関係と思っていても、社会情勢や出来事が間接的に、もしくは時間をおいて自分の人生を変えていくこともある。
自分が望むと望まざるとに関わらず、他人や社会は絶えず変化していく。周囲の変化をどう受け止め、自分をどのように維持、或いは変化させていくのか。そして、その難しさを家族も同様に抱えているという不器用な事実までも描く妙。物語の後半、ウニがある重大な出来事の現場を訪れるシーンは、それまで天井の窓を見つめ続けていたウニが自らの意思で梯子に登り、窓から外の世界を覗き込んだようにも思える。そこから続く家族との食事、そして柔らかな日差しの中でのラストシーンの美しさ。もしウニが実在する人物であるとしたら、40歳になった彼女に聞いてみたい。あれからあなたはどんな人と出会い、そして、どのように輝いたのですか?と。
兄は生徒会長に、妹ウニは“不良”に選ばれた。
94年の韓国。民主化されてから間もない頃だ。儒教による家父長制も根強く残り、兄からは暴力を受けていたウニ。教育には力を入れていて、特に英語教育熱が日本とは段違いなほどなのに、英語は全くダメなウニ。同級生からはタバコも吸うしカラオケにも行く“不良”のレッテルを貼られていた。
結構マイペースな性格なのか、冒頭では団地の階を間違えるという異様な始まり方。そんなウニでも同じ漢文塾に通う親友との仲もいいし、ボーイフレンドだっている。ある日、その塾の先生が突然辞めて、キム・ヨンジ先生が赴任するのですが、「知り合いの中で心まで知る人は?」という漢文を教えてもらい、自分の周囲を改めて見直すウニであった。
ウニ自身の大きな変化となったのは耳下腺炎と、万引きしたときの親友の裏切り。ついでに電話をかけた父親にも裏切られたというショッキングな事件。そして、ボーイフレンドにも裏切られた気分になった。
94年は4年後のソウルオリンピックのために経済発展した年でもあり、ソンス大橋崩落や、翌年の百貨店崩壊など大きな事件もあった頃。ヨンジ先生と歩いた道端には工事のために「死ぬまで立ち退かない」という看板もあったが、その近代化における見捨てられた土地をも描いていた。歴史的に北朝鮮との緊張も高まった年なだけに無邪気さも相当なものだった。
少女の成長、特に心の変化は見ていて清々しいものがあり、世間知らずの14歳の目から見た風景は一種のノスタルジーをも感じ取れる。ハチドリが見えない世界の中で羽ばたくように。だから、意味の分からない謎の部分も一つの風景なんだろうし、記憶の中の1ページに過ぎない。
残念なことに、音楽がひどすぎて、全体的な評価は下がってしまいます。先生が辞めた謎や、伯父さんの死因なんてのも描写が少なすぎたこと。餅屋の家族ぐるみでの忙しさが描かれたのは良かったけど、後半には全く登場しなかったこと。餅屋なのにチヂミがメイン。そして、兄ちゃんの将来もきになるところだし、何といってもみんな昼寝ばっかりやん・・・ってとこ。
芸術的。よくわからない映画
綺麗な音楽、可愛い女優、素敵な映像、雰囲気の良い映画でした。
が、私が通俗的過ぎて、なんのことやら、理解に苦しむ箇所多数。。
いちいち説明したりしないところも、芸術的だし、意味がわからないところはすべて「揺れ動く思春期特有の心の何か」で片付きますが、理屈がつかないと消化不良。
ネットでネタバレや解説を調べたけど、特に解説見つからず。
見終わって、あのシーン何の意味あったのかな?
そもそもこの映画、何が言いたかったのかな?という感想
主役の子はとても美少女で、少しキムタクの娘のkoki似。
先生役の女優さんも、黒木華的な、演技のうまい名女優だった。
この2人を愛でる映画としては大成功。
あとは韓国料理を食べるシーン多数で、観てると食べたくなりました。
そもそもの韓国のカルチャーなのかなんなのか、家父長制度が強いのはわかるが、ボーイフレンドときっかけもなく別れたりくっついたり、後輩の女の子と当たり前のように同性同士で恋愛したり、なんのことやら。
ただ、これまた理由もなく、心変わりした後輩女子の言い訳が秀逸。
主人公「私を好きって言ったくせに」
後輩「前の学期の話です、先輩」
わざとだな。わざと学期とか、中学生らしい言葉を使った監督のあざとさに、まんまと笑った。
これも韓国カルチャーなのか、女の子が全員同じオカッパ頭なのと、やたら登場人物みんなキムさんなので、紛らわしかった、、、
そんなことがあったなぁと思える思春期のにおい
高評価に惑わされてはいけない
何で兄ちゃんはひとりで嗚咽?
韓国の1990年代という設定らしいが、1970年代後半ぐらいの感じがした。
メッセージ入力可能なポケットベルが唯一1990年代だなぁと。1980年代は呼ばれたら、電話するだけだったような記憶。
音楽、古くさかったなぁ。ディスコも。
カセットテープ出て来ましたね。
韓国映画はほとんど観ないです。台湾映画はわりと観ます。
韓国の1990年代のビッグニュースは北の将軍様の死去とソウル大橋の事故なのかな?
主人公のお嬢さんはかわいいけど、その他に魅力的な人はお母さん以外には特にいなかった。
ゆったりとした映画は嫌いじゃないですが、中盤から後半は眠くなってしまいました。韓国映画としては珍しい一作なんだとは思いました。女性監督の自叙伝的映画らしいので、納得はできる。
主人公は絵をかくことが好きである以外には能動的ではない感じ。
首のしこりは耳下腺腫瘍で、おおそらく、良性腫瘍。取った腫瘍を捨てるのはあり得ない。病理検査に出すはず。町医者の場面は安っぽかった(インチキくさかった)。丁寧で、親切だったけど。
韓国のお受験競争は日本にも増して熾烈だが、それは今に始まったことではなく、昔から公務員、官僚になることが最大級の関心事のお国柄で、遊び幅が狭いというか、みんな同じベクトル向いている感じで、あんまりおもしろくないなぁと思ってしまった。
儒教の弊害で家長制度が強い(お父さん、長男を過度に持ち上げる)と、長男筆頭に娘二人だと必ずと言ってよいほど、上と末っ子の二人が仲悪く、真ん中は世渡りが上手くなる。
私は感情移入できる登場人物がいなかったので、はまらなかった。
お兄ちゃんはなんで食卓を家族全員が囲むなか、ひとりだけ嗚咽していたのか?大橋の事故に巻き込まれて恋人が死んだとしか思えない。しかし、家族は知らないふり。妹たちも立ち入らない。実はあの漢文の先生とお兄ちゃんは付き合っていたのか?だから、あんなに荒れたか?長女(妹)の高校の生徒と付き合っていた可能性も大。でも、よくわからんなぁ。
外国の映画祭で賞取りまくりとの前情報だったので、外れなしと思ったのだが・・・ちょっと(かなり)残念。
やっぱり、日本映画はいいものはちゃんといい! と思ってしまった。
餅屋の描写は良かった。のっけから、今年の冬はトッポギ買って、豚キムチ鍋にしようと思ってしまった。
ちょっと木村佳乃似の漢文の先生の名前はキム・ヨンジだった。キム・ヨンジャの北空港やベサメムーチョが懐かしい。🎵夜の札幌~ 大麻をやって~ だっけ? あっ違った、それはケイ・ウンスクだった。
私小説ならぬ私映画
1994年の韓国で暮らす女子中学生を描いた青春物語。鑑賞後、監督の体験をもとにした話と聞いて驚いた。それなら意味がわからないシーンがいくつかあるのも仕方ない。
冒頭のシーンで団地の階数が違うことにかなり引っかかっていたのだが、あれもあんな間違いがあった的なエピソードなのだろうか。
ストーリー的にはラスト近くまでこれといった大事件は起こらない。淡々と主人公の周りで起こる出来事が描かれる印象。友人や彼氏との関係性がコロコロと変わる。そして、塾の先生や後輩との関係が同性愛テイストが濃くなったりもする。女子中学生っぽい。
あと記憶に残っているのが食事シーン。いつも韓国映画は関係の近さの象徴のように食事シーンが使われ、演者たちが美味しそうに食べる印象がある。でも本作では美味しそうじゃない。成長するための通過儀礼のようにモクモクと食べていた。周りの大人がたくさん食べろと勧めるのもそんな印象を後押ししていた気がする。
塾の先生とのやりとりはすごく好きなんだけど、個人的にはそんなに高い評価にできない。これは完全に好みの問題。たくさんの人を元気にさせることができた未来でよかったなとは思う。
この世界が、気になった。
思春期の少女の日々
女子中学生
先生、私の人生もいつか輝くでしょうか?
なによりも、主人公ウニの心情描写のみずみずしさが見事で、震えがくる。
自分が学歴社会の落ちこぼれのくせに、子供をけしかける父親。家庭の事情で勉学を諦めて平凡な男と結婚した母親。鬱屈したストレスを弱者である妹にぶつける兄。ただ同じ時間を過ごしているだけの友達。そんな人間に囲まれた日常に現れた塾講師ヨンジの柔らかな存在感は、窮屈で居場所の不確かなウニにとって、ひとつの指標のように思えた。闇夜の山中で見つけたほのかな人家の灯りのような。
全編にわたり何かを示唆・代弁する表現に胸がざわついて仕方がない。タイトルは未成熟者の足掻きだろうし、耳の下のしこりはウニの心のしこりだろうし、呼びかけても応えのない母はウニの将来への不安や疎外感の表れだろうし、ヨンジの歌う歌は抵抗すれど成せぬ無力感だろうし、崩壊した橋は当時の韓国社会の暗示なのだろう。時代設定が漠然とでなく1994年と明示する意味もそこにある。
劇中、ヨンジがウニに問う。「知り合いは何人いますか?その中で本心まで知っている人は何人いますか?」と。黒板に書かれた「相識満天下、知心能幾人」は、”相知るは天下に満つるも、心を知るは能く幾人ならん 知っている人は何人もいるけれども、心から分かり合える人は沢山はいない”という意味。ちょうど今のウニに響いたのだろうなあ。なんでみんなは私をわかってくれないの、って。でもウニ自身も他人をわかってあげれていないって気付いたのかな。だから、手術や事故を機に、実は父も兄も心が弱く脆いのだと目の当たりにしたとき、お互い仲が悪いと思っていた家族の愛を知ることができたし、その感情は蔑みではなかった。
自分がちっぽけで、何者でもなくて、何をなすこともできない、なんて諦めることはない。ヨンジの言うように、指を動かせるって些細なことさえも「神秘」なのだから。ウニの可能性は、むしろ何も書いていないまっさらなスケッチブックのようなもの。そう、僕の好きな歌に「何も持っていないことは、何でも持っていることと同じ」という歌詞があるのだが、ウニはまさに、今それだ。
ヨンジとの最後をどう受け止めて自分のものにしていくかは、ウニ自身だ。そう思えたとき、ヨンジの言葉が頭に浮かんできた。
「誰かと出会い何かを分かち合う。世界は不思議で美しいわ。」
ウニの中に自分を見る
14歳ってまだ自分のことを自分で決めることも出来ない、なんの責任も取れない年齢です。
でも今の自分の核となるものはすでに確立されているように思います。
そういう思春期のぐらぐらふわふわした心の動きがすごく丁寧に描かれている映画でした。
ウニのような家庭環境ではなかったし学校生活も全然違うものでしたが、それでもウニと自分が重なるところがあるように思いました。
ソンス大橋の崩落事故や金日成主席死去など1994年にあった大きな出来事も出てきます。
この辺りのことはその衝撃を体感した韓国の人々の方がより深く心に響くものがあるでしょうね。
ヨンジ先生とウニは歳は離れているものの良い友達関係を築いていけたんじゃないかな。
再会した時にどんな話をしたかったのか聞きたかったです。
忘れかけた青春
#46 1994年が舞台の意味
が日本人の私にはわからなかった。
当時は社会全体がウニの目線のやうに狭かったが、その自己中心的なウニの目線が漢文の先生と触れ合うことで拡がって行く。
両親は兄ばかりひいきしてると思ってたけど、ちゃんと子供たちみんな可愛いがってることとか、姉も兄も友達思いのこととか。
先生の言いたかったことは分からずじまいだけど、そこにもう答えはあった気がする。
私も今度辛いことがあったら指を一つ一つ動かしてみよう🖐
曇天のち木漏れ日
韓国映画っぽくない
理不尽な痛み
中学生の少女の気持ちを描いた、青春映画。
子ども故の「痛み」と「成長」を感じられる、繊細な表現が染みる。
(淡々としたシーンが長く続くので、少々眠気を誘発する可能性が高いのですが)
1994年、急激な経済発展に沸くのに反して、超学歴社会がいびつな価値観を作り、男尊女卑が残る韓国。
日本でも昭和50年代に覚えのある、カオスな時代の空気。
横暴な父親の言葉の暴力、兄の直接の暴力、親友の裏切り。
理不尽なことばかりに押しつぶされそうになりながら、少しずつ強さを得ていく主人公を愛しく感じました。
主人公のような女の子が多かったんだろう、ということもまた、考えさせられます。
そして女性が理不尽と戦う心について言及し、フェミニズム視点でのあの時代を捉えているのも興味深かった。
その数年後に、街のあちこちで手抜き工事による建築物崩落や、IMF管理下に置かれる通貨危機と失業率アップという地獄の始まりがあることを知っていると、大学進学が難しい彼女が、高卒では仕事を得ることが難しくなる世代であることに気づき、より切なくなります。
全115件中、81~100件目を表示