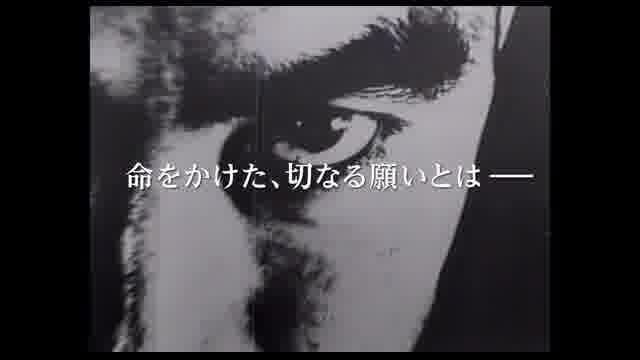三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実のレビュー・感想・評価
全213件中、201~213件目を表示
おもしろかった(雰囲気)です
知的闘争だな
三島由紀夫の優しさ
三島由紀夫と東大の学生。
一人の小説家と日本最高学府の学生たちの対決という題。
圧倒的な三島由紀夫のカリスマ性には、対決という中身にはならなかった。子ども相談で回答する大人のように見えたのは言い過ぎか。自然観念めいた複雑そうなことを、学生が三島由紀夫に問いかけるが、それはこの場で行う議論ではないと思っていたら、別の学生からヤジが飛んだ。この会は三島をぶん殴る会なのではないのかと。血気盛んな展開になると、思いきやそれ以上は過激にはならない。いや、三島のオーラでいなされてしまったようだ。三島由紀夫の優しさを感じた。作品の中の瀬戸内寂聴の言葉でもある。
三島由紀夫にとっては、母校での凱旋公演会であったかもしれない。終わった後の感想が、「ゆかいな体験をした」と。
イメージが変わります。
今年の日本映画は『37セカンズ』とこの一本だけでも歴史に残ると思う
【三島由紀夫の昭和天皇への思いについての考察】4/1追記
最近読んだ『9条入門』(加藤典洋)。
大雑把に言えば、護憲派、改憲派がずーっと議論してきた憲法9条は、実は象徴天皇についての1条とセットで成り立つという仮説を300ページ強をかけて根拠をあげながら推察していくスリリングな論考です。
帰国後の大統領を目指すマッカーサーには占領統治を手際良く終結させたいという思惑があり、早期の日本国民の統制のためには天皇を戦犯として裁くわけにはいかない(もし、天皇を絞首刑にしたら、各地で反乱が起き、占領政策が進まなくなる)。そして、天皇を裁かないことに納得出来ない他の連合国への交換条件的な意味合いで、世界に類を見ない自衛権まで放棄する内容の9条が必要だった。
(他にも色々な要素が複雑に絡み、もっともっと深く楽しめます。くれぐれも、なんだ、もう分かったから読まなくてもいいや、などと思わないでください。著者に申し訳が立ちません)
マッカーサーやGHQに利用されることと引き換えに処刑されることのなかった昭和天皇。東條英機ら7人の戦犯の処刑の報に涙した時の天皇の思い。理念だけでは国を守れないことを冷徹に見定めて、マッカーサーの呪いを解いた日米安保条約の前の決断……。
当時の昭和天皇の本心は誰もわかりませんが、もしかしたら、三島由紀夫さんはこの本で語られる文脈とは違う形で直観的に見抜いていたのではないか。
映画では学習院高等科卒業時の昭和天皇の姿勢に打たれたと語られていましたが、そんなことも影響していたのではないか、と思えるほど説得力のある論考でした。興味のある方は是非ご一読されることをお勧めします。
(以上、2020年4月1日)
ひとりの命がけの覚悟を持った人の振る舞いから何かを感じて欲しい。
これは、あくまでも個人的な願望です。
でも、なるべく多くの、できれば若者に、この映画を見て何かを感じて欲しい。
心からそう思いました。
戦後史や政治思想や哲学的な解釈など色々と複雑で難解な論点がこのシンポジウムに含まれていることは、内容はさっぱり理解できない私でも分かりました。
でも、この映画で最も感動したのが、三島由紀夫さんのどこまでも誠実な人間性です。
・自分の考えを分かりやすく伝えようとする姿勢
・相手の発言を最後までしっかりと聞き、理解しようとする姿勢(相手の考え方に対しての先入観があると自分に都合よく解釈してしまうことは日常的にありますが、三島由紀夫さんは相手の立場で理解するようにしていました)
・自分が抱える、理屈では語れない部分のバックボーンを晒してそれが議論の上では弱点になることがあると分かっていながらも潔く認める姿勢
そして、それらのすべては相手へのリスペクトがあるからこそだし、『言霊』という表現には、自分が何を発言しようがその場限りの発言なので責任なんてない、という不誠実さがもしあるのなら、それは将来的には自分自身を損ねることになるんだよ、という意味での若者への愛情を込めた警句なのだと、私は受け止めました。
(忘れないうちに追記)
序盤の方で、三島由紀夫さんがモーリヤックの小説からの引用の後、『諸君も体制の目の中に不安を見たいだろう。私も見たい』というようなことを言ってましたが、今は国民の大多数、特に若者の方が目の中に不安がたくさんあります。
長期安定政権の有用性自体は否定しませんが、為政者に絶えず不安を与える程度の国民の意思が無いと、モリカケ問題やその他の諸問題がみな、何もなかったことで収束しているのも事実だと思います。
三島由紀夫さんはもっと観念的な不安のことを指してるのだと思いますが。
【"熱と敬意と言霊" 】
ー 1969年 ”政治の季節” に "あやふやで猥褻な日本の現在" を憂いた者達の、各々が寄り添う思想的背景の大きな乖離を乗り越えた討論を映し出したドキュメンタリー。ー
・彼らの、時にユーモアを交え、時にハイレベルな知識に裏付けされた討論をする姿、内容に一気に引き込まれる。
・その姿からは、彼らが如何に当時の日本の状況を憂い、真剣に行く末を考えていたかが良く分かる。
・それにしても、当初、三島由紀夫を論駁してやる、と息巻いていた駒場キャンパス900番教室に集まった1000人を超える学生たち(と、彼の身を案じた一部の楯の会メンバー)の緊張感が、東大一の論客と言われた芥正彦が幼き娘を抱きかかえながら登場し、”三島さんは敗退してしまった.
”と言い放ったシーンで最高潮に達した時も、
<三島由紀夫の、近い未来の”自らの死”を覚悟した上での余裕なのか、
自らと思想的背景は違えど、日本を憂う若者達の姿を近しく思ったのか・・>
・終始、微笑みを浮かべながら熱い湯に浸るかの様に、東大全共闘の論客たちと”実に愉しそうに”煙草を分け合い、会話する三島の姿には瞠目した。
そして、彼の丁寧な言葉遣いや態度に、緊張感が徐々に解れていく学生たちの表情も印象的である。
・三島が”天皇”を語るシーンでは、且つて自らに銀時計を贈ってくれた人間宣言をした”昭和天皇”に対する”人”に対する畏敬の念を”やや恥ずかし気に”語る言葉と共に、彼が信じる”絶対的天皇”への想いが交錯するアンビバレントな感情の機微が微妙に表れる表情にも魅入られてしまう。
・そして現代、当時の楯の会のメンバーや、対立していた筈の東大全共闘のメンバーが三島を語る数々の言葉には、不覚にも涙してしまった。
<今作は、最近の”言霊”の端くれもない”国を憂うべき人々”の国会討論及び地方での講演会と称する自己アピールの場での発言内容の空虚さと品性の無さと愚かしさ”が、心底情けなく思えてしまう作品。
又、猛烈に知的好奇心を刺激された作品でもある。>
■追記
現在70代になられた当時の東大全共闘及び楯の会に関わっていた方々の眼力の鋭さ、頭脳の明晰さ、男として長い年月を様々なモノと闘ってきた”漢の顔”にも感服した作品である。
<2020年3月20日 劇場にて鑑賞>
結局「三島劇場」
良かった。
全体的に、全共闘と三島はお互いリスペクトしあってた。
それは三島が大人だったからに尽きる。
三島の決して相手を否定せず、かといって相手の言ってることを
全く無視して持論を述べる事に終始するわけでもない、
あの絶妙な距離の取り方があの場を成り立たせる全てだった。
その距離の取り方は、三島が文筆家として執筆する際の行間を読ませる技術から
来ているのかもしれない。
今回の討論も、この映画も、全ては「三島由紀夫」という人物ありきのものであり、
三島が人生を通じて行動し、結果を出し、評価され、名を挙げたからこそのものである。
全共闘側も真摯に対応したし、共感できる部分もなくはないが、結果を見ると「ごちゃごちゃ言ってるやつより行動したやつ」に寄って掛かる代物である以上、結局「三島劇場」と総括できる。
主張と反論、そして傾聴と理解。
三島の言葉と肉体
1000人が集う駒場の900番教室一杯にエーテルのように満ちているのは、熱情ではない、やや光を失いかけながらも輝くサルトルの亡霊。
肉体を持とうとした作家と肉体を失ないながらも標榜を立ちきれない集団が、サルトルのなかでもがき続ける。
単純な右翼と左翼などといった世間の煽りの対立構造はそこにはない。反米愛国の単純化でもない。日本固有の歴史と文化は、あくまでも生きた言葉で残せば良かった、死に体の思想も生きた言葉で残せば良かったのだ。
そんな観念論なんか聞きたくないんだよ、という異論は直ぐにかき消されたが、今では最もらしいその言葉は、当時の世界的な潮流の前では無力であり、もしそのような議論にいければ、少なくとも継続する思想として、肉体の一部位は持ち得たのだ。
226事件からわずかに30年後、226事件の再現を夢見みた無理やりの強引な殉職劇に肉体を捧げた三島は、言霊と英霊の二つとなった。
言論の大切さ
言論による闘いは必要
採点なんかできるか!
自己顕示欲と虚栄心だけの人。猿回しの猿と猿回し。そしてコメントを寄せる猿に寄生をしているノミ・ノミ・ノミ....
この映画の元になるフィルム映像を見たことはあるが正直な話...
主人公・作:三島.. 家来として共演:東大全共闘1000人。公演時間:2時間30分
黒い半そでのポロシャツからは、彼流の短期間でのビルドアップの成果の衣を身にまとい、彼自身が既に学生の惨めな出で立ちに完膚なきまで勝利をしている群像舞台劇を延々、嫌々見せらつけれている感覚...彼を紐解き心を覗くと虚栄心をくすぐるエクスタシーという感覚...その感覚の余韻のまま陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で最初で最後の絶頂期を超える。良かった?きみたけちゃん!ひっしょうちゃん?聖セバスティアヌス ちゃん?...字余り
ただ彼の計算違いか計算ずくかは...自衛官の質とその後の自分の死によって負の遺産を面白おかしくバイオとして残されたことかもしれない。本当は、最高の舞台となったはずの総監室での出来事が...
終始、重要な場面になると彼、三島は向かって右側の演出書類に目を落とす。それって演劇人としては...失格
猿回しの猿は、生死をくぐり抜けたサバイバーなんです...全共闘では役不足のため家来という役柄に....降格
日本は自由な国で...なんて神話か? 最初からないのか?
1985年公開の”ハリウッド”映画...製作総指揮、フランシス・フォード・コッポラ、ジョージ・ルーカス。監督、映画タクシードライバーの脚本を手がけたポール・シュレイダー。配給はワーナー・ブラザース。最初で最後の日本を描いたハリウッド映画...チンケなラストサムライを思い出すチンケ...失礼。全編日本語..ただし英語圏ではナレーターに映画「ジョーズ」に出演されたロイ・シャイダー。
ある国の辺ぴな田舎町のビデオ店でこの映画と出会う...時間がなく日本でまた見れるとサラッと見てしまったのが...この映画、実は日本ではビデオ化もされず、それでも放映されるのを待っていたが、待ちぼうけに...でもYouTubeで見ることが...三島夫人の反対ではなく、一部の右翼のうわさ話に過剰反応した映画配給会社?
カンヌ国際映画祭最優秀芸術貢献賞受賞作品なのに....
何故、今、三島由紀夫なのか? 今でも三島ブランドが中年以上の男性に受けると思っているのか、それとも全共闘としての”student movements”の過去を思い出すためか? 地獄に落ちたノスタルジーのためか? 全世界で起きた学生の数が増え経済成長に伴う反意識による何でも揃う不安感をもう一度味わうためか?
オヤジのオナニーには付き合っていられない。
両極の立場の人間が... ”Yesterday’s enemies could be today’s friends.”
Right-wing novelist Mishima Yukio, who extolled antiquated ideals of bushidō and prewar Japancentrism, also became popular among Zenkyōtō students, despite the fact that their political leanings were in opposition to Mishima's.
For a moment he was live.
「僕は論理の通り行動しようとは思っていない....つまり意地だ。もうここまで来たらね。これは諸君に論理的に負けたってことは意味しない。つまり諸君が天皇を天皇と一言言ってくれれば僕は喜んで諸君と手をつなぐんだ(野次).....いや日本をよくしようと思うのは、みな同じじゃあないか。僕たちは、そんなにかけ離れていると思うかい。僕たちはここで真剣にトランプをやっているんだ。お互いこれこそはという”テ”を持ってね。これを遊びと思う君たちはナンセンスなんだよ。良く考えろ。いいか、そこが君たちが持っていない物が僕には一つだけある...........(それはなんだ?)それは何だ
天皇というジョーカーだ
映画「Mishima: A Life In Four Chapters」より
全213件中、201~213件目を表示