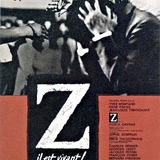TENET テネットのレビュー・感想・評価
全979件中、901~920件目を表示
注意‼️逆行してもどうやら若返るわけではないらしい。
【2回目の鑑賞記】2020.9.21
1回目にスッキリしない理由がその難解さ以外にもあるとすれば、私の場合、ラストの主人公とニールの会話が、本人たちだけが分かってて、こちらには「えー、もう少し分かりやすく種明かししてくれないかな」という部分があったからだと思います。
そこで、2回目はニールの観点に立って展開を追いかけてみました。すると、想像以上にクリアに見えました。特にレッドチームとブルーチームの戦闘シーン以降は、1回目と違う映画を見ているかのようでした。
1回目が『父親たちの星条旗』、2回目が『硫黄島からの手紙』と例えてもオーバーではないほどに。
自分が逆行モードの時、周囲は逆に動いていても、自分はあくまでも普通に懸垂トレーニングなどもできるわけですが、1回目に見た戦闘シーンは、今はどちらモードの目線?と混乱していたことも分かりました。ニール目線で追いかけていると、始めはブルーチームの逆行から始まり、その後……という具合に、割と混乱せずにクライマックスまで見通すことができました。
そして、1回目には思いが至らなかったニールの◯◯◯に大いに感動することになりました。思いのほか、深い余韻に浸ってます。
1回目は、合格基準点60点の試験にギリギリで受かったつもりでいたら、実は50点も取れてない不合格。2回目は、それなりに復習と過去問をやったから、もしかしたら75〜80点くらい取れたかも。
というところまでやっと来れた感じです。
(満点とるのは一生無理そうです)
【1回目のレビュー】
(2回目の鑑賞前に、こういうことかな、という拙論追記あり)
私はノーラン監督の大ファンです。
野球とかサッカーの贔屓チームと一緒で、客観性や公平さとはまったく無縁のレビューですが、贔屓の引き倒しとならないよう気をつけながら、書いてるつもりです。
まさにファン心理のなせるワザだと思いますが、見終わった直後の印象は、そのまま始めからの期待と100%一致してました。逆に言えば期待を超えるほどのことはなかったということなのですが、『インターステラー』には及ばなくても満足度という点では文句なしです。
(個人的に『もののけ姫』と『インターステラー』を今まで観てきた映画すべての中で、東西の横綱(結構、張出横綱もいますが)思っている私としては、番付の変更をしなくて済むことに妙な安心感もあったりしました。)
正直、科学的な理屈の部分は半分も分からなかったのですが、〝分からないのに大満足〟という不思議な昂揚感が得られます。それはたぶん、スポーツの名勝負を見た時のカラダ全体で感じるアドレナリン出まくりの興奮状態のようなものです。
例えば、昨年のラグビーワールドカップ。
前半35分のあの交代がインパクトをもたらした、とか、後半早々のあのタックルが分岐点となった、などと後になっての振り返りで感動が一層深まることがあります。
でも、ゲームを見届けた瞬間は、そんなこと知らなくたって間違いなく、いいものを目撃できた、という高揚感に浸ることができます。なので、あとから他の方のレビューやネタバレ情報などで当初の満足度がさらに高まったり、もう一度観て確認しなくちゃ、という二次的三次的な楽しみがある点もスポーツの名勝負と似ています。
この映画、分からないことが多くてもなんだか凄いぞ、というシーンの連続なので2時間半ずっと映画の世界に引き込まれっ放しになります。
感染予防で付けてるマスクなのに、主人公が逆行するときには、ちょっと待って❗️過去に戻っても、順行の時はマスク無しでも平気なんだよね?死なないよね?とまるで自分もそこにいるかのような気持ちになって自分の口元を確認してました。
ノーラン監督のこれまでの映画なんかよく知らないという〝にわか〟の人だろうが、前からのファンだろうが、この一戦(この作品)は〝劇場で観た甲斐があったよね〟と観たもの同士で大いに語り合える濃密な作品です。
(以下、2020.9.20 追記)
エントロピーという専門用語と時間の関係が今ひとつ分からないままだったので、一日中考えてたら、科学的に正しいかどうかは別として、自分なりには納得できたので(でもすぐ忘れてしまうので)記録化。
まず、相対性理論による時間の伸び縮みについては、こんな感じで理解したつもりになってます。
距離=速度✖️時間
日常生活の感覚では、時間は不変なので、同じ速度の新幹線であれば、東京•名古屋より東京•大阪の方が時間がかかる。
光速の宇宙船が走ってるとします。
その中でキャッチボールをした時、乗組員にとっては1秒で10メートルだとしても、宇宙船の外の動かない場所から見てる人からは、光速30万キロ/秒➕10メートルの移動距離に見えます。日常の感覚であれば、同じ経過時間に動いた距離が圧倒的に違うのだから、宇宙船と共に動いているボールの速度が異常に速いことになるはずです。
観測者の位置やスピードによって(例えば、平行して走ってる宇宙船から見た場合とか)ボールの見かけの移動距離も違うので、上記の距離は色々と違ってきます。
ところが、『光速度はどこにいる観測者から見ても秒速30万キロで不変』という宇宙誕生以来の原理があるので、上記の算式で距離がどれだけ増減したとしても、光速はその原理によりどの観測者から見ても〝不変〟なので〝時間〟を調整するしかありません。それでも光速で移動中の人にとっての体感は日常と同じ1秒なので、時間が伸びた、としか言い表しようがないのです(と、私が理解してるだけで、正しいかどうか分かりません)。
そして、どうやらエントロピー(何かの乱雑さ)というのも、ビッグバン以来、『時間が進むにつれて必ず大きくなる』という宇宙の不変の法則のひとつらしいのです。
それは『熱力学の第二法則』と呼ばれているのですが、乱雑さと熱がどう関係するのか。
弾んでいるボールが永久に弾み続けないのは、運動エネルギーが空気分子やボール分子や地面分子の熱に変わってしまうということだそうです。
ややこしいので、もっと大雑把に言います。
宇宙誕生直後、超高温の無限の質量を持つ小さな火の玉は大爆発(ビッグバン)以来、ずっとエントロピーと呼ばれる乱雑さが増し続け(例えるならば、秩序のある塊が熱を放出しながら、銀河や太陽系のように局所的には秩序のある部分はあるけれど乱雑に散らばり続けているということ?)、最終的には秩序立った構造はどこにも見当たらなくなり、宇宙の乱雑さが最大限に達する。それを『宇宙の熱的死』というそうですが、その時間の経過中、宇宙全体の平均のエントロピーが小さくなることはなく、必ず大きくなる。
つまり、宇宙における絶対的な〝不変〟のうち、光速は時間を伸縮させました(相対性理論は既に実証的に確認されている。だからGPSの誤差…地上と人工衛星における重力による時間差が調整できる。ここでは光速と重力の関係は割愛)。
もうひとつの〝不変〟である『エントロピーは時間と共に必ず大きくなる』という法則も、この映画のようにもし小さくすることができれば、時間の流れを変えることができる、ということになります。
ただし、時間の流れの向きを変えることはできても、一足飛びに過去のある瞬間に行けるわけではないし、まだ起きていない未来へも行けないということになります。
以上、私の理解が大筋で間違っていなければいいのですが、このまま、2回目の鑑賞にチャレンジします。
ノーラン好きなら見て欲しい
とにかくヤバイ映画!!
「こんなの普通の観客に見せて良いのか!?」
そんなアホな感想が飛び出た作品。
ぶっちゃけ、シナリオも大まかなあらすじとして言えば世界もヒロインも救おうとするありふれたものだし、個々の演出も別に目新しいものではない。
だが、恐ろしいのはその組み合わせ方だ。
最初は何が何だか分からない。
徐々に謎が明かされるのだが、それらはパズルのピースのようにバラバラ。
その為、内容を理解しようとすると観客はその複雑なシナリオパズルをいくつも自身の脳内で組み直さないといけない。
正直、ここまで観客の脳内を酷使させる映画とか観たこと無い。
これが難解すぎて意味が分からないような内容ならいっそのこと何も考えないのだが、絶妙な加減で考えれば分かる事だからどうしても考えさせられる。
これから観に行かれる方がいるなら、十分な糖分摂取と複数回の視聴をオススメする。
最悪!クソオブクソ!ノーランは二度と見ない。
自分の映画経験の中で過去最悪、と言っていい程つまらなく、拷問の2時間半でした。
まず冒頭のテロシーンで、「アレ?なんかつまらんな」と思ったのが始まり。面白い映画って、冒頭で引き込んでくれるもんね。その後のチェイスシーンも、アクションシーンも飛行機シーンも全てつまらなかった。
とにかく難解さを売りにしてるみたいだけど、難解かどうかなんて関係なくつまらない。だって、登場人物達が何を目的に右往左往してるのか、さっぱり分からないんだよ。面白い訳がないだろそんなもん。
そもそも、難解にする理由も必然性も無いじゃないか。
登場人物同士の会話劇も、全てが意味不明。会話が会話たりえてなく、観ててどんどんどうでも良くなってくる。会話があまりに成り立ってなくて、登場人物が全員アスペに見えるんよ。
とにかく吐き気がするほどつまらなかった。主人公が最後、ニールと話してて急に泣き出すけど、全く感情移入してないこっちからすれば、ただただ不快。主人公にも全く魅力ない。ダークナイトがそこそこ面白かったのは、ヒースレジャー力に尽きるな。
重ねて申し上げるが、この映画がつまらないのは「難解だから」ではない。ストーリーもゴミ、動機もゴミ、キャラの魅力ゼロ。そんなゴミを混ぜて分かりにくくした結果、気が遠くなるほど退屈でつまらなくてイライラする作品になった、ということだろう。
こんなもん、日本では絶対爆死するよ。
ノーランは二度と見るか!1800円丸々損した気分になったのは久しぶり。オールウェイズ3丁目以来か?テネットよりは、オールウェイズの方がまだマシやな。
大作の公開が次々と延期される中、よくぞ!
途中寝た
うーん、ハッキリ言って、ストーリーがよくわからん。
逆行するって、逆行して、流れを変えるというか、起きたことを無しにできるのが、メリットだと思うんだけど、そもそも映画内で逆行したメリットが全然わからん。
(こういう時空トラベル系の映画なら、12モンキーズが自分的には秀逸(この映画の元ネタは「ラ・ジュテ」っていうフランスの短編映画)。見るといつも切ない気持ちになります)
久々に上映途中に寝ました(笑)。
キャット役の女優さんのキレイさしか
印象に残ってない…
クリストファー・ノーラン、前のダンケルクも自分的には駄作だったし…
典型的な観客おいてけぼり映画ですね。
追記
後で映画の説明見たら、主演がデンゼル・ワシントンの息子さんなんですね!
そう言われると、目元が似てるわ。
トレーニング・ディとか印象に残ってるな~、好きな俳優さんの1人です。
全く理解できない、でもなぜかつまらなくはない
感想を書けないレベルで、物語についていけませんでした。これまでのノーラン作品の中でも、ダントツ難解に感じて、そもそもの設定や目的さえ把握できぬままどんどん先に進み、後半は考えることをやめました…。笑
何のために何をしようとしているのか。
この人のこの行動が何に作用するのか。
何がどうなったら世界が終わって、何をどうすれば世界を救えるのか。
敵?味方?
巡行でどうなって逆行で何が変わる?
ずーっとハテナばかりが浮かび、物語を楽しめたかというと全然。だけど、視覚効果がとにかく物凄くて、理解できてないけど凄い!というアホな感想ですが、それだけで既に一定の満足感があるのはノーランの凄さなのでしょうか。
この手の作品は有識者のみなさんの解説を熟読して理解を深めて、再トライするのもまた醍醐味だと個人的には思っているので、これはこれで全然アリです。
混&乱!はやく誰か図解してえー! 最近ずっと円城塔を読んでいて、カ...
単なる逆再生だろと思ったが…
いや〜、面白かった🙄💯👍
逆再生って単純そうな手法だけど、そこは監督の手腕。
天才ですなぁ。
相変わらず、
よく分からん難解なストーリーだけど、
見応えのある作品であった。
ちなみに…
相棒役が次期バットマン役で、(たぶん初めて見た。)
ヒロイン?の女性がめっちゃ長身で綺麗でした。
理解力がいる
①乗れんぞノーラン(通常) ②やっぱノーランすげぇ(IMAX) ③気が済んだずら。
《10/9 大混乱の感想文整理》
初回(通常)鑑賞後。
まず、色んなカラクリが呑み込めず、理解できず、見落としだらけ。ストーリーの理解度は30%、多分。逆行のルールも思い込みと勘違い。始末に負えないのは、「深読み」してしまったこと。結果、今一つ乗れませんでしたが、せっかくのノーラン作品。パンフと解説サイトに頼らず、自力での謎解きを決意。
二回目鑑賞後(IMAX)。
ストーリーは理解できた、完璧に。と、思い込んでしまう。実は、まだたくさんの勘違いあり。エントロピーの教科書引っ張り出して、解説サイトと動画で復習。これで、逆に混乱してしまいました。物理の解釈について、言葉では飲み込めた気分になるけれど肝落ちしてないから、画面で起きていた事と、脳内に出来上がった理解が一致してくれないジレンマw
ニールの決意に胸を撃ち抜かれて感動はしたけれど、混乱だらけの頭の中をすっきりさせるために三回目の鑑賞を決意。と言うか、もともとその予定。
三回目鑑賞後(IMAX)。
二回目鑑賞後、混乱だらけになったので、三回目鑑賞でチェックするポイントを決めました。三回目は、映画を見ていると言うよりも、チェックポイントの検証をした、みたいなもん。
結果、6つの勘違い発覚。ベトナムとスタルスクには時間差無し。ビルは全壊していない。マックスとニールは別人の可能性が高い。最後のナレーションはニールで「世界を変える可能性がある爆弾」とはアルゴリズム。セネター少年が殺害したのは知らない誰か。キャット殺害阻止はパラドクスそのもので説明可能。理由は割愛。
スッキリすると、過去作に比べると結構つまらない。主人公とニールの別れの場面に全ての「萌え」が集約されてる映画でした。
------------------
以下、一部解説サイトの説明に対するオブジェクションや、勘違いしてしまった個所についての修正記録。
◆ニールとマックスは別人
①ニール≠マックスの方がクール (好みの問題w)
ニールと主人公の最後のやり取り。
「俺にとっては、これが美しい友情の終わりだ」
「俺にとっては始まったばかりだ」
この後、ニールの身に起きることを知っている主人公はニールに問いかけます。
「違うやり方で、結果を変えられないのか?」
「起こった事は、起こった事だ。それは、世界の仕組みの中の運命って奴だが。何もしないことの言い訳にはならない」
ニールは立ち去ろうとするアイヴスを呼び止めます。
「待ってくれ。カギを開ける役が要るだろう?」
「お前は、カギを開ける名人だったな」
「教えてくれ。君の雇い主は誰だ」
「君だ。君にとっては数年先。俺にとっては数年の過去。」
振り返って主人公に別れを告げるニール。
「過去を作りに行くよ」
ニール=マックスだとしたら。ニールが死を覚悟して作戦に加わる動機づけの中に、「男を救うことは母親と、もしかしたら自分を救う事になる」と言う、やや甘ったるく、また多少の打算も含まれることになります。最後のやり取りは、ニールのクールさや覚悟が別れの切なさを引き立てており、甘さや打算を含まない方が心に刺さります。脚本的には、そちらの方が俺的には好み。
②ニールのお守り
ニールのお守りはベトナムのお守り説。東南アジアの華僑は、四角い穴(地)が空いた丸い古銭(天)を使います。ニールの背中にぶら下がっていたのは、着色表面処理された丸ワッシャーの様なもので、古銭ではありませんでした。スタルスク12の地下で、クレーンに絡まりアルゴリズムを地下の穴に下ろす作業を邪魔していたハーネスの端末に、類似したワッシャーが付いていました。ニールは、後日、主人公に作戦の詳細を聞き、このワッシャー付きの紐をお守りにした、と言う設定ではないでしょうか。
③年齢
ニールは物理のマスターを終了しており、軍事訓練も受けています(プリヤ軍の主要メンバーとは旧知の仲)。推定10歳のマックスが「数年」で、ってのは無理があるし、数年先の未だあどけないマックス少年を、主人公がスカウトするってのも、ちょっと違和感があります。
◆鍵を開けるのが得意技
オペラハウスまで時間逆行したニールは、どうやって順行時間に戻るのか。あの時点では、二箇所の回転ドアはセイターの管理下にあるから。ってのが疑問でしたが。順行のまま過去に行けるのかとも考えだんですが。オスロの回転ドアに入り込んだんですね、ロック解除して。それがアイヴスのセリフに繋がる。スタルスク12の扉だけでなく、過去に錠前を破った実績があるから「得意」なのだと解釈。
◆オスロの空港に戻った理由
順行時間のキャットは、逆行時間のセイターに「ウラン弾」を撃ち込まれます(回収される)。原子核崩壊する「ウラン弾」から放出された中性子は、キャットの体組織を徐々に崩壊させて行き、崩壊していくキャットの体組織から放出される中性子は、キャットの体組織を更に崩壊させて行きます。
つまり、ウラン弾を体外に取り出しても、一旦始まってしまったキャットの体組織の崩壊は止められません。
そこで、時間を逆行する事を考えます。一度起きたことは取り消せない=一旦始まったキャットの体組織崩壊はキャンセルできませんが、「極小レベル=中性子」レベルのエントロピーが減少し崩壊が止まる可能性がある。そこで、逆行時間で数日でも過ごせば、命が助かるかも知れない。けれど、数日も前は回転ドアはセネターの支配下にありました。
よって、あの場で即座に逆行時間に入り、オスロの空港で順行時間に戻るしかない。
◆冒頭のスパイ・パート
会社に「出だしからして判らない」と言う人がいてですね。スパイものの文法に沿っての解釈は、ミリヲタの得意分野なので、以下推測込みの解説です。
登場勢力は5者+1で6者。
①主人公(CIA)
②主人公達を案内するCIA協力組織(裏仕事の何でも屋)
③テロリスト
④ウクライナ&ロシアの特殊部隊
⑤CIAの諜報部員(VIP席)
⑥最終的に主人公を「回収する」国際的組織
前提条件
ウクライナ政権は親ロシア。テロリストは反ロシア。
⑥に操られるCIAが③に「正体を偽って」指示を出しオペラハウス占拠のテロ実行。
④はテロ制圧に向かうが、③を極悪組織として国際的に印象付けるために、制圧と同時に、観客ごとオペラハウス観客席の爆破を企てる(テロリストが自爆したことにする)。
①は⑤に回収したウランを渡して逃がした後、④が仕掛けた爆弾を回収しようとする。
①は④に正体を怪しまれ危ない場面を迎えるが、逆行弾を撃つニールに助けられる。
①は②の裏切りに遭い拷問を受ける。CIAが対ロシアに送り込んだ諜報部員の情報を渡せ、等と推測。
②は正体を偽っている⑥の指示を受けて、全てを実行している。
自決カプセルは偽物で致死量の毒薬は入っていない。
⑥はCIAに対して影響力を持ち得る立場。②に対しては正体を告げていない。金だけの関係。
②は偽装工作・破壊工作等の裏仕事を引き受ける、東側諸国出身者の民間軍事団体。最初はCIAの手引をしながら、直後裏切る。
ここでガバガバなのは、オペラハウスの出入り口を固めていないテロリスト。また、制圧側が観客の命をなんとも思っていないのであれば、「テロリストを制圧して観客を助ける」のではなく、「テロリストをオペラハウスに閉じ込める」作戦を取れば良い。催眠ガスではなく神経ガスや榴弾、機関銃の使用など。ロシアなら「やりかねない」と思ったりしますが。
そもそもCIAは⑥を信用しない。オペラハウスから①を回収するのが⑥と言うのは①を見捨てることもいとわないと言う作戦。作戦を実行してしまったら、証拠を残さないために回収は重要であるため、見捨てる作戦を立てることは無い。逆に言うと、この作戦が「主人公のテスト」だと思えば、「見捨てる事もありえる作戦」は納得が行く。
◆エントロピー減少とマクスウェルの悪魔では、この映画の「逆行」は説明できない
パンフでも解説サイトでも、エントロピー減少による逆行を説明する図として、陸上トラックのコーナーを周回して行く様なイラストが使われています。原理として「マクスウェルの悪魔」に言及しているものもあります。仮に、エントロピー減少を時間逆行の原理として解釈するなら、「直線で進んできた時間を、その軸上に戻る」ことになり、時間軸からそれて逆方向に戻ることの説明にはならないのではないでしょうか。
インターステラーでは「5次元世界」が登場しました。時間を軸にし、その軸上を自由に移動できるにしても、クープは「軸上から眺める世界」に入り込むことは出来ませんでした。その世界には、すでに自部自身が存在するから。これが、マクスウェルの悪魔が否定され、インターステラーの中では、ブランドが「過去に戻ることは出来ない」と発言した背景にあります。
回転ドアは、更に原子レベルで複製をつくり時間の逆行も可能にしてしまうと言う、超技術。現時点の、物理の仮説では、ちょっと説明は無理だよねぇ、って思います。
映画の中では、女性科学者に「多分、原子核(だった?)の逆放射」と発言させていますが、ここは、ぼやぁっと誤魔化せ、って事で。
謎ではなく混乱
何度も見ないと意味不明だが、
面白いけどストーリーや時間軸が難解
よく睡眠をとってから見に行こう
中盤で話についていけなくなってしまい…
(週末の疲れも手伝い眠気が)
ネタバレ見てからもう一回見ます
—————
10/7toho日本橋にて2回目鑑賞
解説読んでから行ったが、やはり難しかったw
今作の見せ場である逆走ハイウェイでのプルトニウム241の争奪戦、ラストのスタルスク12での10分間の挟撃作戦、これらが「分かりにくい」のは映画としてどうなんだろうと疑問。
誰が見ても分かるような『ネタバレからのジャーン驚いたでしょう⁉︎』をノーラン師匠に求めるのは違うのだろか。
観客がノーランのセンスについていかなければいけないのでしょうか。
これだけ複雑な話なので、大事な場面はしっかり映す、ダサくてもスローにする、分かりにくさを補うセリフを喋らせる、など演出が必要なのではないでしょうかね。
と思ってしまい、2回見てもすっきりせず。
そしてバックトゥーザヒューチャーはやっぱり名作だと再認識しました。
時系列を整理しながら観る映画
参った、この映画に嵌まった、面白い
上から読んでも下から読んでも
コロナ禍での上映が相応しい映画。メインビジュアルでワシントンがマスクをしているし、仕上げの段階(少なくともプロモーション)でコロナパンデミックを相当意識していると思われ…途中息苦しくて思わず自分がマスクしてて良かったと思ってしまうシーンもあり。圧倒的な力技のSFスパイアクション超大作なのだが、ハリウッドのルールを逸脱しておりとてつもなく難解なのだ。前半の007的スパイ映画セクションは無駄のないカット割りでスタイリッシュにテンポよく進むが、問題は時間を遡ってしまう後半。事前に攻略本を精読してから観ないとまず理解できないであろう。恐らく理解しているのは監督のみ。150分は少し長いので15分短くして説明的シーンを5分増やせばもっともっと良くなると思われ…「ダンケルク」の1週間・1日・1時間の無茶苦茶スパン同時進行といい、相変わらずのノーラン天皇のわがままゴリ押し感満載で観客に対してすごく不親切なのである。「2度3度見て楽しもう」とおっしゃる方もいるようだが、1度で観終わって「面白かった」と席を立たせるのが本来の映画ではなかろうか?
<もう二言>
フットブレーキを手で押さえるシーンが納得できん。あれじゃ絶対止まらないでしょ?
現場でフィルムを逆回転させて撮影することにどれほどの意味があるのか?
全979件中、901~920件目を表示