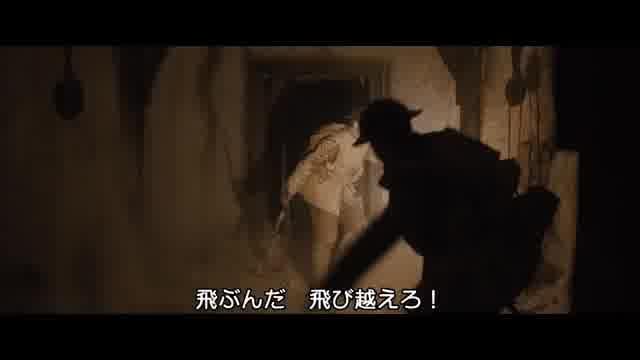「☆☆☆★★★ 〝ハラハラはするがドキドキにまでは至らない〟 (又は...」1917 命をかけた伝令 松井の天井直撃ホームランさんの映画レビュー(感想・評価)
☆☆☆★★★ 〝ハラハラはするがドキドキにまでは至らない〟 (又は...
☆☆☆★★★
〝ハラハラはするがドキドキにまでは至らない〟
(又はその逆とも言える)
2020年2月15日 本編を鑑賞しましたので↓ 参考作品の下にレビューを書き込みました。
【注意 先ずは参考映画として或る作品の詳細を載せておきます】
誓い (映画)
1981年のオーストラリアの映画
言語
ウォッチリストに追加
編集
『誓い』(ちかい、原題:Gallipoli)は1981年のオーストラリアの映画。ガリポリの戦いに参戦する二人の青年を描いた戦争ドラマ。ピーター・ウィアーが監督を行い、『マッドマックス』で一躍有名になったメル・ギブソンが主演を務めた。
誓い
Gallipoli
監督
ピーター・ウィアー
脚本
デビッド・ウィリアムソン
原案
ピーター・ウィアー
製作
ロバート・スティグウッド
パトリシア・ラヴェル
製作総指揮
フランシス・オブライエン
出演者
メル・ギブソン
マーク・リー
音楽
ブライアン・メイ
撮影
ラッセル・ボイド
製作会社
Associated R&R Films
配給
オーストラリアの旗ヴィレッジロードショー
アメリカ合衆国の旗パラマウントピクチャーズ
日本の旗CIC
公開
オーストラリアの旗1981年8月13日
アメリカ合衆国の旗1981年8月28日
日本の旗1982年3月20日
上映時間
111分
製作国
オーストラリアの旗 オーストラリア
言語
英語
製作費
A$3,000,000[1]
興行収入
A$11,700,000[1]オーストラリアの旗
$5,732,587[2]アメリカ合衆国の旗
テンプレートを表示
同年のオーストラリア・アカデミー賞で、作品賞・監督賞・主演・助演男優賞など多数の賞を獲得した[1]。
Wikipediaより一部を転載
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クリエイターとゆうのはとことん強欲だ!自身の作品製作の成功の為ならば、どんなに困難な要求でも突き付けて来る。
勿論、全てが受け入れられる訳ではないので、どの辺りで折り合いをつけるか…が重要になる。
〝 映画全編をワンカットでの撮影 〟
…との触れ込みで、本場のアカデミー賞でも本命視された本作品。観終わって「ワンカットじゃあなかったな」とは思いつつ。「そりゃ〜そうに決まっている。現代の技術を持ってすれば、スケールの小さい作品ならば可能でも。これ程のスケールの大きな作品でそれは不可能と言うものだ!」…と。
それでも、見事にアカデミー賞を取ったロジャー・ディーキンズの撮影は、本当にお見事と言うしかない。あの条件下に於いて、あれほどまでの流れる様にスムーズな撮影は、素晴らしいの一言ではありました。
映画黎明期には、映画撮影に於いてカットを割る…とゆう概念は存在せず。更には、カメラが移動する事すらなかった。役者はフレーム内の中で動き回り。「カット!」の声が掛かるまでは、サイレント映画特有と言える過剰な演技が続いて行く。
かって、あのヒッチコックは。映画全編をワンシーン・ワンカットで撮る野望を『ロープ』で実践する。
果たしてヒッチコックがワンシーン・ワンカットでの映画製作のはしりだったのか?の真意ははっきりとは分からないのだけれど。以降、多くのクリエイターが、この撮影方法に挑戦している。
但し、それらの作品の中で。どれくらいの作品が《成功作品》としての地位を築いたのか?…は、どうだったのだろうか。
ヒッチコックは『映画術』の中で、トリュフォーとのインタビューに(はっきりとは覚えてはいないが、自身の体験談として)「無理があった」…とゆう意味合いの発言をしていたと記憶している。
映画が、作品の世界に観客を引きずり込む為に必要な《モノ》それこそは、編集に於ける〝リズム感〟に他ならないのではないか…と。
※ 1901年
再現ドキュメンタりー映画「マッキンリー大統領の暗殺」公開 「火事だ!」
イギリスでアルバート・スミス(写真師)とジェームズ・ウィリアムソン(薬剤師)がショットをつなぐ手法を用いて完成させた映画でストーリーのある映画第一号と言われています
※ 映画の歴史【編集】でネット検索より。
(昔、この短編を紹介した映画を、旧ユーロスペースで観た様な記憶が…)
映画に始めて【編集】とゆう概念が生み出され、その技術を最大限に発揮・発展させ。芸術の域に押し上げたのがエイゼンシュタインであり、グリフィスであったのだろうと思う。
エイゼンシュタインは【モンタージュ理論】を確立し。グリフィスは自身の作品の中のクライマックスで【クロスカッティング】を実践し、観客の心のハラハラドキドキ感を見事に操ってみせる。
奇しくも『1917』年は、グリフィスが『イントレランス』でクロスカッティングを最高に発揮し完成させた翌年の物語。
冒頭の防空壕の中を縦横無尽に動き回るカメラワークにはじまり。その後も戦場・都市や草原・川を…と、主人公目線で動き回る。
指令を受けた2人の若者は、途中で思いがけない出来事が起こり…と。ここまでで映画本編の凡そ半分弱。
以降は、指令以上に【約束】とゆう大きな〝任務が生まれ、主人公は〝それ〟に命を投げ出し。遂行する使命感に心が突き動かされる。
ある程度の嘘は、映画に於いては必要と考えてはいる。この作品の中で突如銃撃を受け、画面はブラックアウトを起こす。
正確を期すならば。この時点で、全編に及ぶワンシーン・ワンカットの概念は崩れる。それはまあ良いとして、この直後に主人公がドアを開けるといきなり目的地周辺の都市に入るのは…う〜ん、どうなのだろう?映画に多少の嘘は必要とは思いつつ。流石にドラえもんのどこでもドアみたいなのはどうなのよ?とは思って観ていた。
そして、この時の《敵陣突破》の場面を観ながら感じたのだった。「映画には、やはり編集とゆう概念が必要なのだ!」…と。
主人公が敵陣突破を果たす時。その時、当たり前だけど映画は主人公目線で展開される。
画面には絶えず主人公が映る。観客は主人公と同化している為に、主人公同様に不安感を感じながらこの敵陣突破を体験する。
これがもしも普通のサスペンス映画だったならばどうだろう?
静かに周りを見渡しながら進む主人公。そんな主人公を殺そうと物陰から密かに待ち受ける敵の姿。
そんな描写があるからこそサスペンスは盛り上がり、観客は固唾を呑んで画面を見つめる事となる。そんな状況をどうやって主人公は駆け抜けて行くのだろう?…《ハラハラ》と《ドキドキ》が最大限に盛り上がる。
『1917』はそんな状況を(敵は彼に気が付いていない)一気に駆け抜けて回避しようと行動する。
その為に敵は突如襲っては来るが、(当たり前だけど)敵側から見た主人公の動きがスクリーンに映る事はない。
常に主人公目線だけで進むと。ハラハラ感は持続するものの、ドキドキ感が最高調に達するには至らない…とゆうこのジレンマ。
更に、映画のクライマックス。司令官にこの指令が届くのかどうか?しかし、既に攻撃命令は発せられてしまい。多くの若者たちが命を散らし…
主人公は走る。全身全霊で自分の力の限りを全て使い果たし走る。
(編集の概念がないこの作品では)当たり前の様に、この時のカメラは1台であり。この主人公の周りを回り込みながら「果たして間に合うのだろうか?」とハラハラさせる。
その為に、この時の主人公の走りを数台のカメラで撮影し、それをクロスカッティングで繋いだりはしない。
主人公の周りをカメラが絶えず回り込む事で生まれるワンシーン・ワンカットによるタイムログは。必ずしもアクションシーン等の場面では、最善ではないのではないか?クロスカッティングで瞬時にその瞬間を切り取り。【編集】によってリズム感が生まれ躍動する技術こそが(勿論、絶対だとは思っていない) 観客の心を掴む最良の方法への近道なのではないか?…と。
2020年2月15日 TOHOシネマズ西新井/スクリーン10