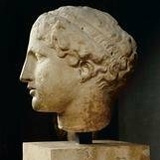私のちいさなお葬式のレビュー・感想・評価
全22件中、1~20件目を表示
主人公のささやかな決意と行動が、人生の真理を柔らかく伝えてくれる
人生の最後を意識することで、人の生き方は大きく変わるという。私は未だそういった境地に立てずにいるが、本作の主人公のささやかな決意と行動力は、その人生の真理を優しく、柔らかく伝えてくれているかのようだ。
医師から余命いくばくもないことを告げられた彼女にとって、ロスタイムがどれだけ残されているのか皆目わからない。だがその中で彼女はやれるだけのことをやろうと一つ一つ物事を処理していく。このあたりの几帳面さにはかつての教師歴とも関係しているのだろうか。今やすっかり中年になった教え子たちに「先生、先生」と慕われる主人公は、彼らや友人や隣人らを巻き込みながら、自らの手で準備を着々と進める。こうして過ぎ行く日々は、死へのカウントダウンではなく、むしろ生をぎゅっと凝縮させた時間と言えるし、冒頭から登場する「鯉」はまさに生の象徴として印象を刻む。深遠さを感じさせるこの映画の美しいラストが私はとても好きだ。
素晴らしいロシア文学
2019年ロシアの作品
ウクライナ戦争前日(比喩)の作品
そしてこの作品は、日本でいう純文学に近い。
未だ読む気になれないが、ロシアと言えばトルストイやドストエフスキーなど数多くの偉大な文学作家を輩出している。
この作品にもその片鱗を窺うことができる。
まず気づくのが挿入歌
1963年日本で大ヒットしたザ・ピーナッツの「恋のバカンス」
これを1965年にソ連がリメイクしたものが使用されている。
この些細な設定は、監督が日本に対して何らかのメッセージを届けたかったのかなと感じた。
さて、
鯉だ。
この作品の原題名Karp otmorozhennyy 意味は「凍った鯉」
鯉とはいったい何だったのだろう?
おそらく鯉は想い出の象徴で、その中心地にいるのがオレクだ。
もちろん視点はエレーナ
この物語に描かれているのが過去
エレーナがかなり深刻な心臓病だということを診断されたことで、彼女は無の周りの整理をし始め、同時に自分が死亡したことを証明して諸々の手続き総てを他人任せにせず自分で行うという奇妙な行動をとる。
つまり、コメディタッチだ。
オレクにしても都会の会社で忙しい毎日を送っていて、恋愛さえしていない。
真っ白な高級外車とぬかるんだ実家の前
田舎特有の着古された衣類と都会のファッション
届かない電波
古い家と貧しい生活
母が倒れたと聞き駆け付けたオレク 実に5年ぶり
体裁上の嘘は、この地域のみならず、概ね世界中にあるのだろう。
失踪と偽り実は収監されている人
エレーナもオレクのことを「忙しい」からなかなか実家に顔を出さないと友人たちに言っている。
あの舞台の町は、古く朽ちて行ってしまう想い出そのものかもしれない。
オレクは母を病院から実家まで送るが、会社からの電話が絶えない。
母にとって最新の製品など使ったこともなく、車の中で突然話し始めたオレクや、携帯電話で話し続けていることよりも、俺にに何かおいしいものを食べさせたい。
しかしまったく会話はかみ合わず、実家にもかかわらずその古さと汚さに何も触れたくないオレク
母が見送りに出てくるのを待つことさえせずに、早々とホテルへ引き上げる。
ただ、
オレクには一抹の想いがまだ残っていたのだろう。
途中で車を停め、一瞬母の顔を思い出す。
さて、、
死んでもないのに棺桶まで用意して葬儀の支度を始めるエレーナ
彼女の奇行に友人たちが駆け付ける。
同じ年代の友人たち
エレーナの気持ちを汲み取りつつも、病気ではないので、死を実感として捉えられない。
しかし、エレーナの奇行によって皆で会う機会ができ、教え子たちとも会う機会をえる。
そしておそらく、自分が死ぬということを意識したことで、この日常の一瞬一瞬がとても貴重なものに思えてきたのだろう。
心臓病でいつ発作が起きて死んでもおかしくないと言われた直後から、教え子がくれると言った鯉を〆ようととする行為を止める。
この恋を冷凍庫に入れ、オレクのための食事用に解凍 ところが生き返った。
この生き返ったという点が非常に文学的でメタファーで多義的でありながらこの作品の中心を示している。
物理的に聞き返った鯉
比喩的には暗示で、失いかけたオレクが戻ってくることを示唆している。
オレクは何か変なセミナーで儲けているが、彼はそれを「成功」と位置づけ、どうすればみんな成功できるかというセミナーで稼いでいる。
それは誰もがしていることで、その事が正しいと思い込んでいる。
オレクにとって鯉は非常に厄介なもので、母の大切にしているものだが、車のキーを飲み込んでしまったもの
厄介さは彼の現在の仕事と母とどっちが大切なのかを問いかけており、それをオレクが認識してしまっている。
母に含まれるのが実家であり田舎であり想い出であり、過去ではあるものの現在でもある。
エレーナは友人に嘱託殺人を依頼
しかしどうしてもそんなことはできない。
友人と一緒の食して酒を飲んで、酔って寝た。
友人はオレクにメールした。
オレクは母が死んだと勘違いしてやってきた。
そして、お決まりの反省と涙。
しかし息をした母に驚き、怒り、キーを投げつけた。
感情をぶちまけてしまえば、落ち着いてしまうのだろう。
鯉からキーを取り出す方法を獣医に相談し、必要なものを買うために売店へ行く。
ナターシャ
オレクの元カノだが、今はろくでもない男と付き合いアル中になっている。
想い出 人生の分かれ目 荒んだ心
オレクは、彼の生き方の延長線上に今のナターシャを見たのかもしれない。
人生において、転換点は必ずある。
概ねそれは迫られるような選択を求められる。
それを選択だとみなさないでいることもできる。
久しぶりに食べた母の手料理
毎日ジャンクフードしか食べてなかったのだろう。
眠れずに引っ張り出したアルバムと、昔隠れて吸っていたタバコ
外に出てタバコを吸いながら、この場所について考えてみた。
「もっと母さんと話したかった」
これがオレクの本音で、ほとんどの人が思うこと。
オレクはタバコを吸いながら、自分に本心を尋ねたのだろう。
やがて鯉を持ち出し湖に放流した。
都会生活としばらく決別して、幾日もないかもしれない母との生活に寄り添うことに決めた。
眠る母の脇に立つ。
オレクが決めたこと。
凍った鯉の復活は、まさにこのことを暗示していた。
この純文学 素晴らしいロシア文学だった。
この、都会と田舎 日本でも多くの人が感じるのではないだろうか?
監督はこの部分に日本に向けてメッセージしたのかもしれない。
終活コメディ? いや、余韻深き名作!
ロシアの田舎、その大きな自然と何もない素朴さが
死をごく自然なものに感じさせてくれる。
向かい合い、その中でせっせと身支度を整える主人公の健気で可愛らしさよ。
そんな具合に自分で自分の葬式の用意をするのだから
全編コメディーでしかない。
だがその分、際立つ侘しさが秀逸だった。
それでいて主人公に辛さを語らせない脚本も素晴らしい。
作品は「死」をテーマにしつつも、
すればするほど近隣、友人、息子と生活へフォーカスし、活気あふれる。
鯉の存在感も絶妙だ。
だからして実際に死が訪れた時、それら余韻はよぎり
悲しみと幸せ、後悔と満足を交錯させる。
この味わい深さ、ロシア映画も侮れない。
またロケーションも、衣装も、小物全てがとにかく
ノスタルジックで丁寧で可愛いのだ。
主人公の女優さんを見ていてあの役、もし市原悦子さんが生きておられたら、
日本版でぜひ演じてほしいと思った。
これもいわゆる終活か
ロシア映画って私の中ではレアですが。
これもある意味「終活もの」と言えるでしょう。
心臓病を指摘され、主人公である老婆がとった行動は。
「自分で自分の葬儀を段取りしよう」。
その気持ちはわかるけど、順番が逆を辿っていくのが結構笑え。
火葬は嫌だからと、亡き夫の墓の横に「自分用の墓穴」を掘ってもらい。
棺桶を買う→死体安置所→死亡診断書を今日付で書いてもらう。
クソ真面目なのが余計ツッコミ。
でもなぜ自分でするのか。
それは「離れて暮らす忙しい息子だと、できないだろうから」。
前半は近所に住む友人との話、後半は息子との話。
終盤ちょい前まで、笑うエピソードが多かったので。
「え、そこで終わる⁈」。
100分ほどであっという間の掘り出し物でした。
⭐️今日のマーカーワード⭐️
「お前は幸せかい?」。
息子に迷惑をかけたくない
寡婦の主人公は余命宣告を受け、都会で暮らす一人息子に迷惑をかけまい、と自分の葬式の準備を始める。
徹底しており、死体検案書まで作ってもらい、棺桶を購入する。
母と息子の関係がなんとも言えず、可笑しいやら悲しいやら、見入ってしまった。
息子の立場から見てみると
自立
人生の仕舞い方
「解凍された鯉」という原題が意味するもの
死んでまで迷惑をかけたくないと自ら終活に勤しむ母親と、命あるまで有意義な生活を送ってほしいと願う子。
互いを思いやりすぎてボタンをかけ違えてしまう親子の確執からの調和がテーマだが、高齢化社会や老人介護事情への関心は、日本だけじゃなく海外も同様なのだということを実感。
原題の『Karp otmorozhennyy』とは、「解凍された鯉」の意味だが、この鯉は息子のメタファーでもある。
ロシアでは国民的ソングとして知られているという「恋のバカンス」(本作になぞらえるなら「鯉のバカンス」か)が、軽妙な曲調なのに哀愁を誘う。
ちょっと変わってるが愛すべき隣人たちも、イイ味出してる。
正直、観る前は期待値が低かったが、同年代の母親を持つ身として、観終わってから心にジワジワ来た。
ラストの解釈は観た人に委ねられるが、個人的には建設的に捉えたい。そう思わないと、あまりにも切なすぎる。
「終活」をデフォルメしただけの物語
主人公エレーナの行動は、日本では法律的にありえないこともあって、一見すると、遠い外国の作り話だ。
「火葬されないように見張って」というのも、他我の違いを感じた。
しかし、表面的なことに惑わされずに見れば、日本でもありふれた「終活」をやっているだけ。
エレーナの行動原理は「矜恃」であり、むしろ“核家族”化した現代社会においては、普通の態度だと思う。
そういう、本来なら映画になるはずがない話を映画にするために、エレーナや息子のオレクに、デフォルメされた行動をとらせて、無理矢理、悲しいストーリーをひねり出しているように見える。
だから予告編の印象よりは、シリアスで穏やかな話であったものの、感情移入ができない作品だった。
デフォルメするのではなく、リアルな社会問題として描いて欲しかった気がする。
なお、ザ・ピーナッツ「恋のバカンス」の前半部の方が、明らかにロシア民謡をパクっており、ロシア側からすれば“逆輸入”と言った方が良いと思われる。
まさかの「恋のバカンス」♪
現代の問題、国の高齢化、過疎化、一極集中化などを明るく面白く表してますね〜
親友のリューダ(アリーサ・フレインドリフ)の演技がとても素晴らしい!!ぜひ観て欲しい!
まさかの「恋のバカンス(63年レコード大賞受賞曲)」が流れてきて、あっこの曲って海外の曲をザ・ピーナッツがカバーしてたんだ〜と思いウィキったら…
(Wikipediaより)
人気歌手ニーナ・パンテレーエワが1965年に「カニークルィ・リュブヴィー」("Каникулы любви")のタイトルで大ヒットさせた。
って!?
歴とした日本の歌謡曲でありました!!
----------------------------------------
(Wikipediaより)
原曲
作詞:岩谷時子
作・編曲:宮川泰
演奏:松宮庄一郎とシックス・ジョーズ・ウイズ・ストリングス
出版者:渡辺音楽出版株式会社
発売レーベル:キングレコード
・エンディングまじでびっくらこいて、一瞬ポカンとなった ・声出して...
現在ロシアの不安と恐怖
ロシアのインテリおばあちゃんの終活物語である。ソ連からロシアに変わって、商売が自由になって儲ける人たちも出てきたが、社会保障はかなり後退したと聞く。ソ連時代はリタイアした年寄は年金だけでも悠々自適だったのが、ロシアになって生活がギリギリになってしまったらしい。ロシアになって生まれた格差は着実に大きくなっており、若者は不満を抱え、年寄は不安に苛まれる。そして社会の裏側では新興のマフィアが政権に貢いでいる。
本作品のおばあちゃんは年金で裕福に暮らしているように見えるが、ロシア映画だけに検閲を受けている可能性は捨てきれない。実際はもっとずっと貧しい筈だ。心臓の不調でいつ死んでもおかしくないと医者から宣告された設定だが、本当は生活苦で自殺したいのがおばあちゃんの本音かもしれない。本作品からは、描きたいことがあるのに描けないもどかしさのようなものを感じる。
ロシアの現状はさておき、死がテーマの筈の映画なのに、死に直面したり死を深く論じたりする場面は殆どなく、死は鯉に任せて、人間は専ら金の計算である。ロシア人は金の計算が殊の外好きなようで、ドストエフスキーの「白痴」にも将来の生活費を計算する場面が出てくる。
本作品のおばあちゃんは自分の葬式と後始末の費用を計算し、息子の世話にならなくて済むようにあちこち奔走する。その姿はどこか物悲しい。息子は息子で、人生の真実よりも金儲けが大事だという演説をする。かつての彼女は浮浪者になって道端で金の無心だ。
現在のロシア人が抱えている不安と恐怖が凝縮されたような作品で、生活の温かみを喪失してしまったような雰囲気が映画全体を包んでいる。冷戦構造の崩壊、ベルリンの壁の崩壊は歴史的には価値のある出来事であったが、ソ連を始めとする東側諸国の人々にとってはそれほどいい出来事ではなかったようだ。プーチンの牛耳る政治の末端には顫えながら死んでいく人がたくさんいるのだろう。
元教師が挑むささやかで切実で型破りな終活
ロシアの小さな田舎町で一人暮らしをしている元教師のエレーナは主治医からいつ死んでもおかしくないと宣告される。自宅で昏倒し病院に担ぎ込まれたエレーナの元へ離れて暮らしている一人息子のオレクが駆けつけるが、多忙なオレクはすぐに仕事に戻ってしまう。迫っている死期を悟りながらもオレクを煩わせたくない一心のエレーナはかつての教え子や友人達の力を借りながら型破りな終活を始めるが・・・。
どこに行っても教え子に遭ってしまうような小さな町で夫の墓の隣に埋葬されたいというささやかな願いの前に横たわる様々な障害を真正面から突破するエレーナと彼女の奮闘に巻き込まれる隣人達が織りなすおかしなドラマですが、彼らやオレクが思い出すエレーナから教わったことにも滲んでいる通り彼女の行動はあくまでも知性に裏打ちされた真面目なもの。その真摯さが隣人達の歪に閉ざされた固定観念をパックリとこじ開ける様はとにかく痛快。
一方でその町に横たわっているのはアル中と老人しかいないという田舎あるある。そんな現実も容赦なく見せることでエレーナの願いが ささやかでありながら身につまされるほど切実であることが浮き彫りとなっています。火葬されることを本気で嫌忌するお年寄り達、冷蔵庫から奇跡的に生還する鯉、そして『恋のバカンス』。突然さりげなくやって来る終幕を彩るのはモノクロなのに鮮やかな想い出たち。老夫婦が終活の旅に出る『ロング、ロングバケーション』と通底する切なさと温かさに満ちた美しい作品でした。
全22件中、1~20件目を表示