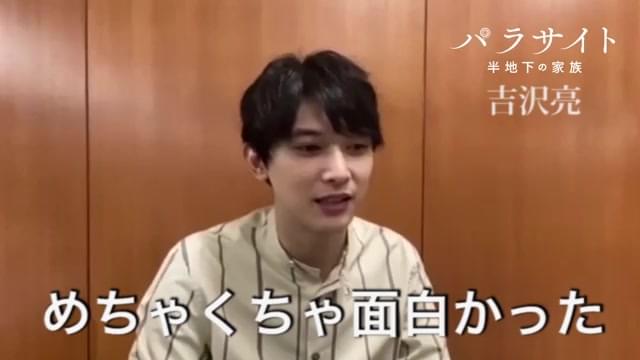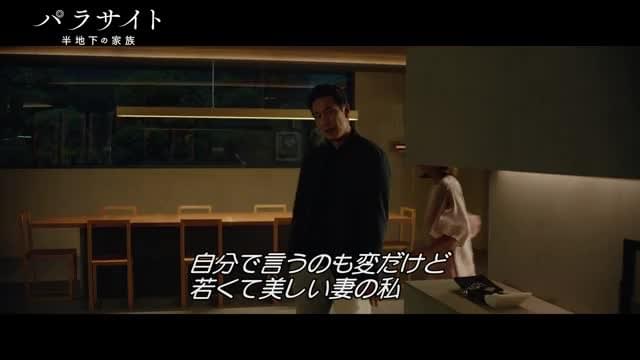パラサイト 半地下の家族のレビュー・感想・評価
全982件中、201~220件目を表示
人のいい善人でお金持ちの家族が不幸になっていく様子を、さも金持ちは...
人のいい善人でお金持ちの家族が不幸になっていく様子を、さも金持ちは
不幸になって当然のように描き、全編加害者目線でお情け頂戴的な描写は、
日本人の道徳感としては受け入れがたく、見終わったあとなんとも後味の悪く、
二度と見たくない映画だった。
評価が高いのが信じられない。
細かい表現から大きく感情が現れる場面、すべていい
素晴らしい
起・承・転・結
何処までも半地下家族目線
知ることは幸せか
・どちらかと言えば、上流階級の家庭が下流家庭に侵食されるサスペンスだと思っていた。しかし実際主人公は下流家庭の方で、しかも物語の途中から主人公の階層は最下層ではないことがわかる。
気づき
・物語の途中から出てくるある人物こそタイトル通りのパラサイトであるとわかる。そしてこのパラサイトは上流家庭のおこぼれに預かって生活していることになんの罪悪感どころか負い目も感じていない。寄生虫が宿主になんの感情も抱いていないのと同じだ。感謝すらしているのだ。半地下どころか陽の光すら差し込まない最も昏い闇の中で彼はバレない程度に飼い主の血を吸い、あろうことか幸せすら感じている。
・一線を越えるとはなんなのか。それは認識すると言うことである。上流家庭の父親は一線を超えてほしくないと主人公にいう。最初は妻に隠れて愛人などいるからなのかとも思ったが、どうやら見たくないものを見せないでくれ、と言う意味らしいことがわかる。上昇してきた彼は下のことなど見ない。いや、下の世界があることすら認識したくない。地下室のパラサイトも、暗闇の中でなにも見えないため、自分がどれだけ不幸な境遇なのかなど考えない。生きるということしか考えない。しかし半地下に住む主人公は闇も陽の光も見えるのだ。見えるというこそは幸せなのか。この映画は明確にこの問いを否定する。見えるからそ、不幸なのだ。そして見えるということはこの現代社会の中ではある言葉に変換できる。知るという言葉だ。
・インターネットの台頭により、誰しもが大量の情報をインプットできるようになった。そして自分の境遇が他の誰かよりもある意味不幸(当たり前だが)であることを知るようになった。アフリカの原住民の幸福度はシカゴのホームレスよりも高いことが判明しているが、それはアフリカの原住民に快適な家、豊富な食事、刺激的な快楽など、生活の情報を与えていないからだ。つまり人間の幸福とは他者の幸福との相対的な差で決まるということ。幸福とは仏教的に言えば妄想の一種なのである。しかし我々は知る術を持つ限りこの妄想から逃れることは酷く難しい。インスタグラムやツイッター。承認欲求を満たそうと大量の人数が大量の幸福をインターネット垂れ流している。今までのテレビや新聞で得ていた情報の量とは桁違いである。現代の我々は知ることにより不幸になることを余儀なくされている。知ることで不幸になるなんてことが、これまでの人類の歴史で想像できただろうか。少なくともスティーブジョブスがiPhoneを発明するまでは誰も想像できなかったはずた。スマホはインターネットをそれまでインターネットを使っていなかった層にも、与えた。それは幸福だとしんじられていた。しかし、知ることは必ずしも幸福でないことを我々はこのコロナ禍の中で思い知っている。
匂いについて。
金持ちなのか貧乏なのか見分ける材料として、この映画では臭いが挙げられる。
つまりどれだけ装っても話し方を変えても、貧乏臭さが消えないと言うことである。また、ある意味それは現代では目の前の人がどのような人物であるか、服装や言葉遣い、持ち物で見分けることは不可能であると言う暗喩である。匂いと同じように、機能しているのがスマホである。全ての人がスマホを持ち、大量の情報に晒されている。その点は上流であろうが半地下であろうが関係ない。しかし、富の分配、格差は埋まらない。では上流と半地下を分けているものはなんなのか。
答えはそんなものはないと言うことである。能力だけでいうと半地下の家族の方が明らかに上流の家庭より優秀である。父親は除き、母親、息子、特に娘はとてつもなく優秀で能力もある。しかし格差は埋まらない。つまり、格差はとは格差でしかなく、所持している富の総量そのものでしかないということだ。これが何を意味するか。格差とは金であり、金とはいわゆるHPであり、手札の枚数であり、誰しもに与えられるし、得る権利はてられるが、絶対的な量があまりにも生まれながらにして違いすぎるということ。そして今のところそれは覆せそうにないと言うことである。最後息子は父がいるあの地下室がいる家を金を稼いで買う計画を立てるが、監督によるとその金額は彼の年収500年分ということだ。つまり、夢物語ということだ。彼の父は半地下から地下まで、落ちるところまで落ちた。しかし、息子にはまだ落ちる先が残っている。人生は結局は転がる石のように、緩やかだが確実に落ちていくことしかできないと感じ、なんだかひどく気が滅入った。
称賛する声が高い。私にとってこの映画に感情を入れられないというか
何件かコメントを読んだが、称賛する声が高い。私にとってこの映画に感情を入れられないというか、つまらないというか。。。飽きてしまったので途中でやめようと思ったが、友達曰く、『アカデミー賞』をとったんだよと言われたのを思い出して、これからがもっと観れば興味が持てるのではないかと思い見続けた。それに、私の教えている大人の学生が、『絶対見るべきだ、だから、ストーリーを言わないよ』といって、内容を説明してくれなかった
。前評判がこんなにいい映画は今までになかったから、ものすごく楽しみにしていた。
一時間も見たが、私の期待を外れ、まるで、悪賢い家族のコメディのようだし、スリラー映画のようだ。悪賢い家族は揃って、ピザの箱を薄給で折っているが、彼らの動きには、苦悩が見えるどころか怠けているようにしか見えなかった。もっと、苦労しているという実写、描写、が必要だと思ってみていた。大学受験で浪人を重ねて、仕事もなくしているという長男や長女には、浪人しながらなんでもして働けよと言いたくなった。貧困層は浪人もできないのが多くの現実だ。でも、あくまでも私感であることを理解していただきたい。私は、ケン ローチ監督とポール ラヴァティ脚本家、レベッカ オブライアン製作の『家族を想うとき』の『はたらけど、はたらけど、暮らしは楽にナララズ』、そして、社会構造の不公平さをもっと実感できると思っていた。か少なくても黒澤明の『天国と地獄』のような映画を期待してみていた。
https://eiga.com/movie/91138/review/02385180/ 家族を想うときのレビュー
前の家政婦が雨の中、金持ち家族がキャンプに出かけているとき、インターホンを鳴らすシーンまで観た。私にこの映画を楽しむ感性が欠けているのも残念だし、普遍的な格差社会の問題点を『家族を想うとき』のように感じられない私にもがっかりしたが、ビデオをストップした。
それから、あらすじを全部読んだ。『雨』を恵の雨と考えない文化(?)には驚いた。だから、この概念には興味があった。でも、もう一度観ようとは思わなかった。
アカデミー賞を受けるような大作に感激できない私のセンスに呆れた。
喜劇と悲劇が共存した良い映画
やたらと評判が良かったのでアマプラで視聴。
金持ち一家に貧困層が潜り込むという設定自体はどこかで見たような気もしますが、これが家族全員というのは新しいと思いました。
家庭教師、家政婦、運転手とよくうまいこと潜り込むなぁ関心すると同時に、それぞれがキチンと仕事をこなせていることから決して能力が低いわけではなく環境のせいで貧困層となっているのだなと分かり生まれって大事なんだなと感じましたね。
前半の一家が寄生していく様は喜劇、後半の新事実判明から悲劇が始まりこの高低差は非常に引き込まれ最後まで集中して鑑賞できました。
国独自の社会問題を娯楽の中にうまいこと落とし込んだいい作品ですね。
ネタバレとか見ずに鑑賞していただきたいですね。
逆にネタバレしてると楽しさ8割減の作品かな。
なんだこれ?(褒めてます)
格差の是正……?
無数に張り巡らされる演出、徹底した描写、コメディやスリルとしての面白さ。
とにかく完成度が凄まじい。
韓国に暮らす家族に焦点を当て、貧富の格差をテーマとしていたけど、これは韓国だけにとどまるものでは当然なかった。
どの国にも存在する格差社会を堂々と描いたポンジュノン監督。階段など徹底して高低差を際立たせたり、水の流れや雨、匂いなど格差を表すための演出が美しかった。今まで知らなかった自分が恥ずかしい。
個性の強い登場人物の中でも、地下に住んでいた男の存在感が際立っていた。
特に家主の帰りに電気を付け、また崇拝するシーンは狂気そのものだった。
でも、私たちの立場もソコだと知った途端、この作品を見るのが恐ろしくなった。
富めるものが富むことをよしとし、状況を改善することはなく、ただおこぼれに預かろうと、寄生する。
世界的に(もちろん日本にも)蔓延した格差社会における思考なのかもしれない。
近い時期で流行った「JOKER」も然り、格差を描くストーリーが人気を得ていた気がする。
動くにせよ動かないにせよ、あのような結果となった2つの作品を見ていた限り、社会に溜まった不満がどのように噴出されるのかがとても怖い。
主人公たちの能力の高さと、それでも仕事がない韓国社会の現実もまた、恐ろしいものだった。
世の中そんなに甘くない
全982件中、201~220件目を表示