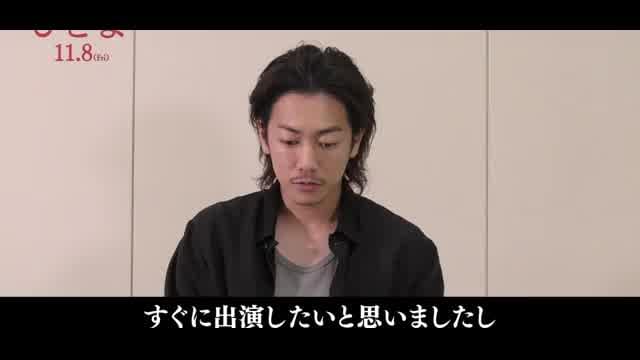「母がくれた自由」ひとよ movie mammaさんの映画レビュー(感想・評価)
母がくれた自由
一夜。人の世、日と夜、一世、人酔、他人与
様々な他の字も当てたくなるような、心模様が織り混ざった複雑でこれぞ邦画、な作品。
ずっと観てみたくて、でも気持ちに余裕がある時にと後回しになっていた。
意外と目に余る暴力シーンは最低限にしてあり、テンポよく展開してくれて助かった。
観終わって思う事。
これは15年長引いた育児の話。
子供を2人ではなく、3人も産んでいるのだから、父と母の間には楽しい家族の時間が流れていたこともきっとあった事だろう。それでも、家業のタクシーもあるのに何がきっかけで変わってしまったのか、父は酒を呑んでは機嫌を悪くし、子供たち3人に毎日えげつない暴力を振るっていた。
ある日夫を轢き殺した母は、夫の亡骸にこうべを垂れていた。ごめんなさいでも子供達を守る方を優先しますという意味か、やってしまったなのか、やっと終わったの意味なのか、真意はわからない。
ただ、母親にとっても苦渋の決断であったであろうことは見て取れた。
母は、3兄妹が母がいなくても生きていかれる歳になるまで待っていたとまで語り、「これからは何も心配しなくていい、自由に生きられる、なんにでもなれる」「15年したら戻る」と言い残し自首。
それから、子供達3人は殺人犯の子供として世間の冷たい目を浴び、嫌がらせを受け、過酷な人生を歩んでいた。
15年前、肉体的に自由にしてくれたのは母だった。
父の生前から、度重なる暴力虐待のせいなのか、どもり症の長男大樹は、バイト先で結婚相手に出会い小学生の娘もいるが、妻にも本音を話せず母のことも隠しており、離婚届突きつけられ済。
次男雄二は、父の生前からボイスレコーダー片手に日々の被害を吹き込むような子供。誕生日にエロ本を万引きして母に迎えに来てもらった事もある。今はそういった大衆本の記者として、東京でなんとか生計を立てている。あろうことか母親と家をこき下ろす記事を自ら書いている。
末っ子長女の薗子は、美容師になりたかったが、美容学校で嫌がらせを受けてスナック勤務に。母の出頭後は父の兄が継いだタクシー会社に送迎されるが、タクシー会社のメンバーからも扱いが難しいとされている。
3人とも、ストレスが溜まると煙草をすぱすぱ。
はすっぱにしか生きられない、肩身の狭い人生を嘆いても仕方なく、傷を隠すように、自分なんてこんな風にしか生きられないと卑下して生きていた。
それぞれ、母による父殺害の影響で散々な人生をどうにか生きてきたところに、父の命日であり母の出頭日からちょうど15年。約束通り、突然母が帰宅した。
刑期を終えて、ほとぼりが冷めた頃を待ち、帰宅したようだ。
感じよく出迎えてくれるタクシー会社の面々と、これまで味わった苦悩があるため、母にどのように接すれば良いかわからない3兄妹。
松岡茉優演じる薗子が、あんなに待ったのに、という台詞が印象的。突然両親両方いなくなり、幼い薗子は刑期満了時に母を迎えにも行っていた。会えなかったけれど。母の帰りを待ち続けたのに、いざ会えたらどんな顔をして良いかわからない。
母の帰宅と同時に、タクシー会社への嫌がらせもまた始まる。母には隠そうとする長男と妹、母不在期間の3人の苦悩に謝る様子がない母に、知らしめたがる
次男。
でも、母の残した言葉を何度も何度も反芻する兄妹の中でも次男が1番、生き方の信念にしていた。
「これからは自由に生きていける、なんにでもなれる」
父の暴力が続けば、いずれ子供達は死んでしまうところまで手を出されていたかもしれない。父から子供達を守るために殺したと世に認識され、聖母と書き立てられる事もあった母が、実際にどう考えていたかはわからない。
雄二はその疑問と葛藤しながらも、母が刑に服してまで子供達に作ってくれた「自由」を叶え成功することこそ母への報いだと考え、居づらい地元から東京に出て、記者からいつかは小説家になりたいと夢に立ち向かっていた。誕生日にエロ本を万引きした日、母は駆けつけて怒るでもなくコンビニで息子を庇い、雑誌や本が好きな雄二を応援してくれた。そして、万年筆と迷ったがこれからはPC社会だから、とボイスレコーダーを誕生日プレゼントにくれたのだ。母に夢を応援して貰った大切な想い出があるからこそ、耐えてこられた雄二は、殺人者の息子が身を立て夢に近づく唯一の材料として、母の殺人を記事に起こしていた。母を悪く書くなど良くないと葛藤もありながら、これしかできないと腹を括って。
一方、「父は待っていればいずれ死んで解放されたかもしれないのに、母が服役する事態になり、いない間随分苦労した子供達にどう思ってるのか」とレコーダー片手に雄二に聞かれても、「お母さんは悪くない」と言う母。
母としては、母自身が父を殺さなければ良かったと言ってしまえば、子供達が味わってきた苦悩はしなくて良かった不要なものと同義になり、子供達がなんのために生きてきたのか、歩んできた人生否定となり、子供達の歩みが崩れると見越していた。だから、父を殺害した判断は肯定すると決めていた。
タクシー会社のメンバーが母や子供達の隙間隙間に入ってくれて、支えてくれたり本音を引き出していく環境が有難い。そのメンバーも、忙しいタクシー業の合間に認知症介護をしていたり、精一杯なのだが。
中でも酒なし煙草なし真面目一本と採用された佐々木蔵之介演じる新米ドライバー堂下さんが、実は実は元ヤクザ。
足を洗ったはずが、昔の後輩が、高校生の息子をシャブ漬けにして、息子に借金を背負わせていた。
離婚してたまに会える息子との時間に幸せを感じ、お金も渡していたが、まさか覚醒剤に消えていたなんてと、やけくそに。酒瓶を抱えながら運転する車に、なんと母も乗っている。
親の心など子はわかりもしないと嘆き怒る堂下だが、親の業を子が背負う輪廻がここにもかと見ていて辛い。
暴走タクシーと化した車は、海に突っ込みに行こうとするが、次男雄二が運転する別のタクシーで3兄弟も駆けつけ、親の車に思いっきりガツンと飛び込み、暴走を止める。
「てめえ誰に何してくれてんだ!」と飛び蹴りを喰らわす次男。母の事を誰より大切にしているとわかる瞬間。実はあの日も、自首しにいく母を追い、兄妹を乗せて中学生無免許で運転して追いかけたのは次男だった。
本作は、原作がおそらくインターネット普及前だから、叩かれる範囲も住む街とタクシー会社への嫌がらせくらいで済んでいるが、実際には一生どこへ行っても居場所がないのが加害者家族だろう。
加害者でも被害者でもある子供達には、子供達で肩を寄せ合い過ごすしかなく、なんとか生きているようで、母親が戻った後の3人は思いっきり母に甘えているように見えた。
長男16歳、次男14歳、長女小学生で母親が不在となり、それまでも虐待家庭にいた3人。
反抗期も自立もこれからという時で、母親の力をまだまだ求めていたんだなと。
長男に至っては、家庭を治められず、母が仲裁に入っている。妻は離婚届を突きつけながらも、本当は夫婦で相談しあって深い家庭を築きたい。
20代後半になっても、母の布団に入って寝たがる長女。
ずっと反抗期から抜けていない振る舞いの次男。
それぞれ、不在の間溜め込んだ感情をそれぞれのぶつけ方で母に表す。
愛想の良い母ではなく、口が上手くもない。次男にはあの時のことを思い出しなさいと言わんばかりに、わざと母が同じお店に週刊誌を万引きしに行き、子供達に迎えに来させたりと、不器用な行動を取る母。
それでも。聞いてくれて、無条件に甘えられる母親の存在は確かに聖母。一方確かに、刑期を終えた殺人犯。
それを世がどう見るかなんて関係なく、母は母なんだなと。親子共通の希望「これからは自由に生きられる、なんにでもなれる」を兄妹みんなの片隅に持たせてくれた母。
鈴木亮平演じる長男大ちゃんがどもりながらも母を庇う哀しき大男。夫婦喧嘩で暴力父の片鱗を見せる長男。それだけは避けてきたはずなのに。
夫と心からの会話をすべく夫の気持ちを引き出したいのに、ぶつけるしかできない妻役のメグミの演技が引き立つ。母が戻り、他者に感情を伝えない心のストッパーをはずせた時、家庭にも円満が訪れる気がした。
次男役の佐藤健は、絵に描いたようなすれっからしとして強がる次男雄二。母が聖母なのか殺人犯なのかなんなのかという世間の疑問を代弁するとともに、母はたとえどんなでも母であると作品内で示す役どころ。耐え難い理不尽を消化しないといけないから、悔しさや怒りをぶつけたり熱くならないように、あえて関係性に距離を取るが、母本人に疑問をぶつけ、自分の生きざまを吐き出せた時、カタルシスの重要性を感じた。母の記事用の原稿や写真、心を奮い立たせるのに使っていた母が残した言葉の録音は削除され、やっと心の足枷なく小説を書きたい雄二の人生を歩み出す事だろう。
長女薗子の松岡茉優は、ただひたすらに、お母さんは自分達を守るために動いてくれてこうなったと一途に思い続けていた。母親の前では、甘えたりないまま大人になり損ねて止まった子供時代から取り戻そうとしているようだ。
15年間母親にしかぶつけられない想いを、それぞれが溜め込んできた描写が印象的だった。
15年後、精神的に自由にしてくれたのも、母だった。
親は子供達の未来の事だけ考えて生きているから、
子供達が自ら未来をなし崩しにしたら悔しいし、
でも子供達は親の業を背負う。
切り離せない親子の関係性が、何かをきっかけに突然切られた時、人間が飢え求めるのは結局母性なんだなと感じた。
タクシー会社の面々が随分と3兄妹を支えてきたが、母にしか埋められない深い傷。
堂下さんの子にもそういうものがあるのだろう。
母は最後まで家族にぶちまけたりしないが、庭で空の青さを1人立ち上がり見つめる後ろ姿に、全てを背負ってきた孤独や母としての大きさを感じた。
15年間止まっていた育児の再開。
あと15年したら、3兄弟みんな夢を叶えて安定した大人になっていることを予感させられた。