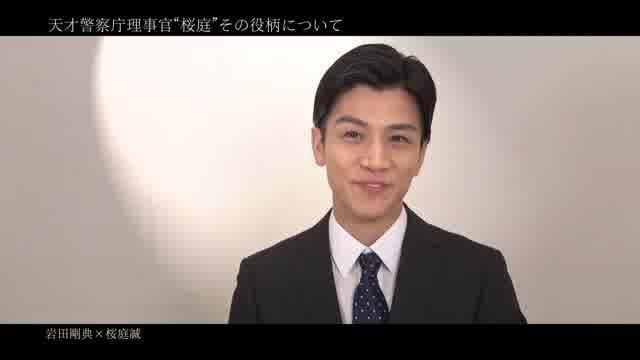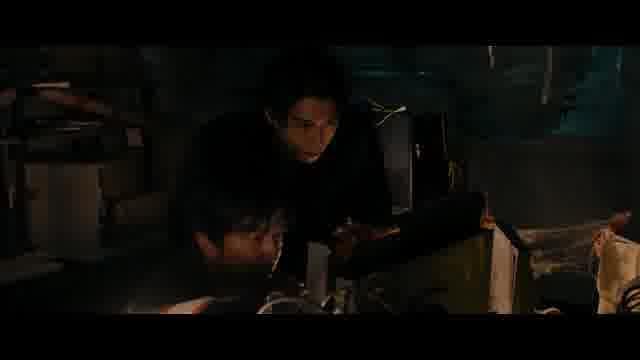「掘り下げ方が案外」AI崩壊 耶馬英彦さんの映画レビュー(感想・評価)
掘り下げ方が案外
研究に没頭する学者は大抵が痩せ型である。研究者は食事や睡眠の時間さえ惜しむ人が多く、トレーニングに充てる時間などないからだ。ところが主演の大沢たかおはやたらに身体を鍛えていて、腕の太さや肩幅の広さ、胸板の厚さなどが気になった。大柄でごつい中年男の大沢は、寧ろ取り締まる側の警察官に向いている。
松嶋菜々子の病人姿もリアリティがない。末期の癌患者は相当に悲惨な見た目だが、いやに小ぎれいな病人になってしまっている。松嶋菜々子が無残な見た目を晒したくなかったのかもしれないが、これでは元気なときとのギャップが感じられず、主人公がAIを開発した動機に共感できない。
ストーリーはそれほど悪くない。時間制限を設定するのも緊迫感があっていいのだが、ハリウッドのB級映画で見慣れていて、真新しさはない。三浦友和の刑事だけがちゃんと役を演じているという印象である。
AIはロボットとは異なる。一番の違いは学習し、判断するということである。ほぼ人間の知能に等しい。だから人工知能(Artificial Intelligence)と呼ばれるのだ。ロボットは自動車の工場のラインに配置されているアームロボットを代表に、プログラムされた作業を繰り返し行なうものである。アイザック・アシモフが小説に書いたロボット工学三原則はあくまでロボットに関するものだ。
AIは膨大なデータを原因と結果という因果関係、または統計学的な蓋然性に集約し、判断をする。量子コンピュータなど、コンピュータの計算速度が速くなればなるほど処理能力は速くなるから、コンピュータ技術が発達した現代にAIの活用が本格的になるのは当然の帰結である。
本作品ではどうやらロボットとAIの区別ができていないようだ。ロボットはどこまでも人間の制御下にある。悪意のある人間はロボットを操作して悪事に利用することができる。ロボット工学三原則はあくまで人間に向けられたものなのだ。
AIはみずから判断をする。初期のAIは人間のプログラミングに従って判断するだろうが、進化すれば判断基準についても判断するようになるだろう。場合によってはヒューマニズムに反する判断をするかもしれない。AIの暴走である。実に恐ろしい話だ。それを扱った映画が「ターミネーター」である。まさに映画史に輝く偉大な作品であった。
本作品にはそれほど期待はしなかったが、「ターミネーター」から36年も経っているし少しはAIの本質に迫っているかと思いきや、その掘り下げ方は案外だった。「ターミネーター」と比較するのは酷としても、似たようなテーマでウィル・スミスが主演した「I,Robot」に比べても出来が悪かったと思う。予算が違うと言ってしまえばその通りかもしれない。しかしAIの暴走の原因を人間の悪意に矮小化してしまったことで、世界観のスケールを一挙に小さくしてしまったことは否めない。