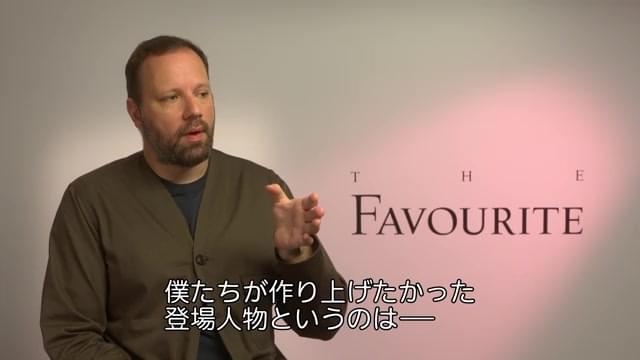女王陛下のお気に入りのレビュー・感想・評価
全228件中、1~20件目を表示
薄っぺらい人間たちの深き情念。
ヨルゴス・ランティモスという監督は、一貫して人間は愚かで自己愛が強く下卑た生き物たと捉えているところがある。もちろん人間は愚かなことをしでかす一方で、思わぬ英雄的な行為に身を投じることもあるのだが、ランティモスはそんなことは素知らぬ体で、本作でも身勝手な欲得三昧な女たちの姿を時代物の宮廷劇というジャンルに当てはめる。
なので後味がいい物語にはなりようがなく、なりふり構わぬ女たちの権力闘争に、呆れたり笑ったり戦慄していればいいのだろう。魚眼レンズの長回しやとにかく読みづらいテロップのデザインなど、ちょっと才気が走り過ぎてはいないかと思うところもあるが、実際才気がほとばしっているのだから、存分に好き放題にやってくれ!という気持ちにもなる。
ただしレイチェル・ワイズが演じたサラにだけは、善人ではないが誇りと信念が宿っている。このランティモスらしからぬ人物像は、次なる可能性への布石なのかどうか。このヘンテコな才人からまだまだ目が離せそうにない。
バラバラに見える表情を一つの体内に納めたコールマンの怪演はまさに絶品
アン女王は、スペイン継承戦争や国内政治に頭を悩ませ、私生活では子供たちが幼くして亡くなる不幸も経験した。このような精神状態の中、頼りになる側近との絆が深まるのは当然のことだったろう。
コールマン演じる女王はコロコロと表情が変わる。ある時は高慢なオバちゃんのようであり、またある時には甘えん坊の少女のようでもあり、かと思えば突然かんしゃくを起こしたり、不意に女王としての威厳を振るい出したりもする。これら一貫性のない表情をすべてひとつのキャラクターとして成立させ、そこにユーモアすら醸し出すコールマンの怪演たるやまさに絶品だ。
この危うげに回転するコマの軸が揺るぎないからこそレイチェル&エマの個性も際立ち、宮廷内の三角関係はスリリングかつ破天荒で、予測不能の極みとなった。3人の女性たちの誰に寄り添うかによって、万華鏡のように色彩が変わる。鑑賞するごとにフレッシュな感覚を味わえる逸品でもある。
低位置からの広角レンズ映像は小動物視点のよう
ヘンテコで不気味な異色作を撮り続けているヨルゴス・ランティモス。「ロブスター」と「聖なる鹿殺し」は非現実的な設定や超自然的な出来事を含む話だったので、新作が英宮廷を舞台にした歴史劇と聞いて意外だったが、蓋を開けてみればやっぱり一癖も二癖もある怪作。閉環境での力関係と愛憎は「籠の中の乙女」に共通する要素でもある。
三女優の熱演の激突は観客にまで飛び火しそうな激しさだ。英女優オリビア・コールマンも、これを機にハリウッドでの仕事が増えそう。
太陽光やろうそくの火でほぼ全編を撮影した映像は、キューブリックの「バリー・リンドン」のように大昔の宮廷にタイムスリップしてのぞき見しているような気分にさせる。
そしてあの、低い位置から仰ぐアングルでの広角レンズの映像!ウサギなどの小動物が尊大で愚かな人間を冷ややかに眺めているような、なんとも皮肉の効いたショットにほくそ笑んでしまった。
大仰なイメージとは裏腹な艶笑劇
権力はあるものの、孤独と欲求不満の極みにいる英国女王を挟んで、そんな女王を影で操る幼なじみと、没落貴族の娘が、愛情と権力を奪い合う。欲望を剥き出しにした女たちの愛憎劇を、側で見守る男たちはみんな、まるで去勢されたかのようだ。ヨルゴス・ランティモス監督はえげつなく、時に笑える宮廷内ドラマを、特にローアングルから嘗めるようにとらえて、観客を押しつぶすような圧迫感を演出している。誰も決して傍観者にはしないという意気込みが、特異なカメラワークからはひしひしと伝わってくるのだ。それは、3人の女優たちの演技にも言えること。これほどまでに人間の醜さと、それ故に漂うおかしみを体現したアンサンブルはないと思わせるほどに。特に、女王を演じるオリビア・コールマンの怒りと嘆きが交互に現れる感情演技は一見に値する。フェミニズムを極端な形でテーマに据えた意欲作。大仰なイメージとは裏腹に、けっこう笑える艶笑劇なので、気楽にシートに身を沈めて欲しい。
狡猾女の戦い
クセになりそう?
昨年公開の「憐れみの3章」(24)を観たのが、初ヨルゴス・ランティモス監督作品でした。とにかく衝撃でした。意味不明、不快、不可解。捉えどころのなさが逆に心に引っかかるような不思議な体験でした。他の映画とは一線を画す、独特の作風。面白いのかさえよくわからなくなります(汗;)。今作も似た感じがしました。基本的なストーリーは史実がベースになっているようですが、創作部分に監督の趣味が濃厚に詰め込まれている感じでしょうか。17羽のウサギさんの話には、うるっときました。事実、17人の子を産み、流産、死産などで死別しているようです(涙)。側近としてアン王女を支えた少女期からの友人・サラ(レイチェル・ワイズ)とサラの従妹・アビゲイル(エマ・ストーン)は、性格も生い立ちも違い、さらに政治的姿勢も真逆、昼夜のリップサービスの対比は監督の嗜好かなと思いますが、2人の間でアン王女(オリヴィア・コールマン)が葛藤し、身もだえする展開がとてもスリリングで見応えがありました。3人の女性を巡る心の変遷が歴史をも揺るがすことになった史実は、普遍的な一面もあり見所でしたが、一筋縄に描かないところにヨルゴス監督作品の魅力を感じました。そうそう、オリヴィア・コールマンは「パディントン 消えた黄金郷の秘密」(25)、サラと敵対する政治家ハーリー(ニコラス・ホルト)は「スーパーマン」(25)でそれぞれ重要人物を演じていましたね。
アン女王の寵愛を取り合う二人の女
複雑な三角関係ドロドロの愛憎劇が面白かった。アビゲイルの野心と狡さ、病弱なアン王女を操るサラのしたたかさ。アン王女はワガママで感情の起伏も激しく扱いづらいが、この中では一番自分に正直で純粋な人だと思った。
オスカー受賞のスピーチはまんまゆりあん
エマ・ストーンの没落からの立身出世を軸にした物語はとても分かりやすく、それぞれのキャラクターも際立って描き込んである。このジャンルの映画としては非常にとっつきやすい。
なかでも女王陛下の天真爛漫な無能ぶり、そして不健康な振る舞いはとても演技とは思えない自然さ。オリビア・コールマンがオスカーをはじめ、各映画賞を総なめしたのもうなずける。体調が悪く、徐々に身体が壊れていくさまは順撮りだったらともかく、スケジュールによっては逆転することもあったろうに、そこに本当に女王がいるようにしか思えない存在感を醸していた。
逆にエマの振る舞いは、時に不思議な印象を伴う。心の底から清廉な気持ちを持つでもなく、時に性的なサービスもいとわない狡猾さ。それでいて嫌われ役にならないのは、キャラクターの芯の強さと、王宮という特殊な環境のなせる効果なのだろう。女優魂を見せるようなセックス描写は、コメディとエロティシズムの境界線を器用に渡り歩く。頑張りの割に、賞レースでノミネートされるものの、受賞をことごとく逃し、意外に評価は低い。
カメラワークも独特で、スクエアな印象を与えるよう、特殊なズームとカメラのスイングで工夫していたり、文字の配列を本のように並べたりして、見たことのない画作りをしている。豪華なセットや衣装はもちろん、並んでいる料理や菓子、調度品に至るまで、映画の世界観にこだわって配置されている。
敢えて必要を感じなかったのは、ちょっとあけすけなセックスの描写で、レズビアンのオーガズムをはじめ、毒のように散りばめてある。これがなければレイティングで損をすることもなかったろうに、片乳を放り出して眠るエマ・ストーン、手コキをするエマ・ストーンなど、とてもリビングで家族そろって見られるような映画ではない。
そして、音楽がバロックで統一されているのも、こだわりを通り越して逆効果。果たして映画の効果としてのBGなのか、本当に宮中音楽家が奏でている状況音なのか、すぐには理解できない。実際に、女王が癇癪を起して、庭で演奏をするバンド弦楽を怒鳴りつけ、追い出すシーンがある。王宮に音楽が奏でられていた状況が日常にあったということであり、例えば官能的な夫婦の初夜の様子や、勇ましい乗馬のシーンなんか、音楽がかすんでいる。
監督のこだわりは各所に感じることができるが、映画としての見やすさはちょっと不親切。そこが楽しめるかどうかの境界線になるだろう。
タイトルなし
役者の個性が弾け飛ぶ
女王は元より、側近、重臣と、それぞれの個性が豊か過ぎて最初は笑っていたのだけれど。
放題にヒントが隠されているように、どんどん泥沼化としていく宮殿内。
プライドが高過ぎても、バカを演じてもバカにはなれずに自滅する。
うさぎたちを亡き子供と思い愛おしむ女王の勝ち。
主演女優賞
恐ろしく素晴らしい、宮廷ドラマの傑作だ。
18世紀初頭のイングランドを舞台に、アン女王をめぐる、マールバラ公爵夫人サラと、サラの従姉妹で没落貴族の娘アビゲイルの暗躍を描く宮廷ドラマ。
オリヴィア・コールマン(アカデミー主演女優賞を受賞)が、健康不安で情緒不安定なアン王女を見事に演じ切る。アビゲイル役、エマ・ストーンと、サラ役、 レイチェル・ワイズも、強烈に印象に残る好演だ。
権力を求めて、容赦なく陰謀を企む人間は、結局は抑制が効かなくなることを、痛烈に辛口で、英国らしいユーモアで描いている。ヌードを伴う同性愛のシーンや、口淫を示す台詞など、刺激的な描写も、非常に効果的だ。
愛憎が入り組んだスキャンダラスな権力闘争だが、決して下品になることなく、野性的かつシニカルに描き切っている。非情なまでの苛酷な謀略が興味深く展開された、恐ろしく素晴らしい、宮廷ドラマの傑作だ。
強欲な女たち
映画は総合芸術であると誰が言ったか知らないが、この映画は、まさにその言葉がピッタリ当てはまるような作品ではないだろうか。
絢爛豪華とはちょっと違う、自然光と蝋燭の薄暗さのなかに英国王朝の歴史と美が浮き上がるような宮殿。ヨルゴス・ランティモス監督のことだから、セットもVFXも駆使して作り込んでいるのだろうが、地下廊下や下女の部屋など細部に至るまで手抜きがない。
音楽もクラシックのような音楽も流れる場面もあれば、工場の機械音のような不協和音が続く場面もあり、それぞれのシーンと登場人物の心理状態の表現に深みが出ている。
そして、広角の魚眼レンズで撮る女王の部屋や廊下。画面の両端の歪みは、これまた3人の心の歪み、言いようのない嫉妬、妬み、憎しみを表現しているかのよう。
富と絶対権力を持つ女王は、子を亡くし、病に冒され、愛に飢えている。しかし、女王としての誇りを持っている。
女王をバックに権勢を振るうサラは、その能力で国を動かす野望を持つが、女王あっての自分という限界の中でもがいている。
どん底から這い上がろうとするアビゲイルは、愛を知らず、富と権力のためには手段を選ばない。
3人の女たちは、愛を、権力を、富を、それぞれ求め、それぞれの檻の中から自由を求めて這い出ようとするが、出られない。映画のほとんどのシーンが宮殿内である。宮殿は彼女たちにとっての檻なのだ。
サラは、権力の座を追われ、国を追われる。彼女の捨て台詞が心に残る。
宮殿に残った女王とアビゲイルはこのあとどうなるのか。恐らく2人に幸せはないであろう。
一歩間違えば、とんでもない駄作になるかもしれないような題材を、ここまでのクオリティに高めた監督をはじめとする制作者、俳優陣にただただ脱帽する傑作。
上昇志向の着地点
オリビア・コールマンが何といってもすごかった。特に心に沁みたシーンは、目、特に左目の視力がどんどん落ちて、書類を斜めにしながら見て読む時のオリビアの顔の傾けと目の感じ。辛いだろうなあと悲しくなった。
サラとアンの面白い関係。変てこな化粧を「アナグマ」とサラに言われて納得するアン女王。強くて親密でサドマゾで我慢とは無縁の二人。そんな二人の間に飛び込んだアビゲイル。最初はやられっぱなしのアビゲイル:馬車の中で若い男が変なことしてるのを目にする、馬車から泥道に放り出される、冷水ぶっかけシャワー、床掃除の灰汁入りバケツに素手を入れて手が真っ赤、お仕置きの棒叩き刑(6回が4回で済んだ)、散歩のつもりが男にいきなり土手に突き落とされる、サラにいきなり発砲される、図書室でサラから本をガンガン投げつけられる。でもアビゲイルはへこたれない。のし上がるためだ、自分で自分の顔を本で殴りつけおでこも頬も真っ赤で鼻血ブー。四文字悪い言葉を叫びながら次の対策考える。サラの不在中に急いで貴族と結婚ー!サラからの結婚祝いの言葉には「ケッ!」、エマ・ストーンいいじゃないですか!でもそこまでだったね、アビゲイル。アンの通風の手当てをしても飼っているウサギに込められた悲しみに共感しても上っ面でした。
アン女王はサラが不在だったり男と踊っていたりすると強烈に嫉妬する。サラの直裁過ぎる言葉に笑ったり悲しんだりするが彼女もサラには何でも言える。大勢の人の前から逃れたいとき、サラは高速スピードでアンを乗せた車椅子をビューン!と走らせてアンを朗らかにする。一方、どんなに優しく話しかけマッサージもベッドの中でも上手なアビゲイルをアン女王が嫉妬することは決してない。最後の長いシーンがそれを表していた。
エマ・ストーンはコスチュームものの映画がとても似合う。レイチェル・ワイズのハンサム・ウーマンぶりかっこよかった。
おまけ
サラの夫役は「SHERLOCK シャーロック」のカンバーバッチ=シャーロックの兄(マイクロフト・ホームズ)役のマーク・ゲィティス!顔、鼻ですぐわかったー!
アン女王かわいそう
哀れなるものたちのヨルゴス・ランティモス×エマ・ストーンコンビだと聞いて鑑賞
エマ・ストーンのお顔が好きなので、惚れ惚れ…
見所はコールマンのアン女王役、演技が凄かったですね。アン女王の孤独と哀しみ、体調不良が伝わってきてつらかった。
史実をベースにしていて、サラもアビゲイルも実在の人物。アンが17人の子を失ったというのも、サラを追放してアビゲイルを登用したのも、史実。アンの風貌がWikipediaに載っていた肖像画とそっくりだったので驚いた。
アビゲイルは必死のし上がったのに、達成したあとは馬鹿騒ぎするわウサギ踏みつけるわ、でなんだかつまらなそう。アン女王もアビゲイルも救われない空虚なラストが何とも…
サラのお手紙、アビゲイルが読むことを見越して書いたのだろうか?
シーンごとにタイトルをつけるのと、魚眼レンズは哀れなるものたちと共通しており、監督お気に入りの手法である模様。
追記
再上映に行ってきた@歌舞伎町タワー
音楽の使い方が際立っていて、劇場で観てよかった
マーク・ゲイティスがでてくると、あ〜イギリスの映画観てる〜って気がする(笑)
初回は比較的アビゲイルに共感してみていたけど、2回目はなんだか、サラの方が愛情深く、管理職としての能力も政治家としての志も高いように見えた。
主演女優3人の圧巻の演技×ヨルゴス・ランティモスのオリジナリティ
◇全てが変動値の世界観
女王陛下権威とは、国を司る根幹を成すものであるべきなはずです。この物語の中心人物であるアン女王は1702年から1714年の長きに渡り、初めはイングランド王国・スコットランド王国君主として、やがて初めてのグレートブリテン王国君主として在位したステュアート朝最後の国王です。彼女の心の優柔不断がこの物語の不穏に揺れ動く歪な軸を為しています。
女王陛下の「お気に入り❤︎」の座を巡って、二人の女性が双方を潰し合うように、何でもありの抗争を繰り広げていく展開が、ぐちゃぐちゃに泥臭い人間模様をグツグツと醸し出します。そこに正義はあるのか、「愛はあるんか?」いえいえ、人間の情動も行動の動機もそんな単純なものではありません。
ヨルゴス・ランティモス監督作品に共通して感じるテーマは、人と人の関係性の中で揺れ動く価値観の姿、その滑稽な流転です。われわれは、自分は冷静で客観的な判断を下していると思い込みがちですが、その時の気分とか周りに関係する人々の機嫌とか時代の環境とかによって判断基準は揺れ動くのです。正義と悪、愛情と憎悪、それぞれ複雑に絡み合いながら変動していく残酷な#人間喜劇 がそこにはあるのでした。
全228件中、1~20件目を表示