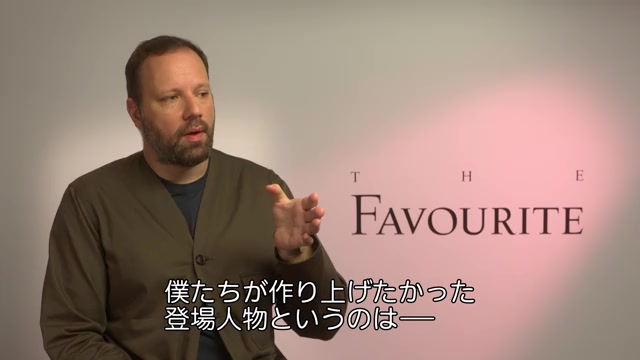「女の権力闘争」女王陛下のお気に入り 耶馬英彦さんの映画レビュー(感想・評価)
女の権力闘争
人類にとって民主主義の歴史は浅い。
共同体の最初は王政だった。文明初期の治水権をはじめとした諸権利を持つ者が共同体の王となり、王政のもとでは当然のごとくヒエラルキーが定められ、共同体は国家となり、国家の価値観がそのまま人々の価値観となった。差別は当然で、そもそも差別という言葉さえなかったに違いない。ヒエラルキーの下層にいる人々は不満しかなかっただろう。中には生に倦み、絶望して死ぬ者もいただろうが、大抵は生への執着を捨てきれず、恐怖と不安と苦しみの毎日を死ぬまで生きたに違いない。
時代が下って人々の連絡手段や交通手段が発達すると、不満を持つ人々の連携が生まれる。連携は連帯となり、やがて革命が起きて共同体は違う権力者によって統治される。初期の革命で成立した政治体制は、まだ十分な民主主義とは言えなかった。そして現代に至っても、民主主義は完成途上である。フランス革命のスローガンであった、自由、平等、友愛が実現されるにはまだまだ困難な道のりが残っている。
革命によって民主主義体制になっても、婦人参政権の実現は遅れた。イギリスでは、映画「Suffragette」(邦題「未来を花束にして」)に登場する20世紀初めのサフラジェットたちの活躍を待たねばならなかった。他にはもっと遅い国もあり、スイスでは婦人参政権が認められたのは1991年のことである。わずか28年前のことだ。
アン女王が統治した18世紀のはじめは、政治家は当然ながら全員男で、女は男に対して失礼があれば服を脱がされ鞭打ちの罰を受ける。女性差別も甚だしい時代だ。女たちはひたすら蹂躙されながら生きていた。唯一政治的な権限がある女は、他ならぬアン女王ただひとりである。従って女王の側近の女たちは国中で数少ない権力を持つチャンスのある女たちだ。もちろん自分自身で権力を持つことはできないが、アン女王を取り込めば権力者同然に振る舞える。
本作品はそんな女同士のエゲツない権力闘争を赤裸々に表現したものだ。脅しすかし、苦言と甘言、場合によっては肉欲にさえ訴えて、アンのお気に入りになろうとする。愚劣極まりないが、こういう権力闘争によって歴史が作られてきたのは事実である。人類の歴史は即ち負の遺産なのだ。
役者陣はみんな演技が達者で、エマ・ストーンももちろんだが、女王役を演じたオリビア・コールマンの演技が秀逸だった。サラを演じたレイチェル・ワイズとともに、スクリーンに広がる圧倒的な存在感で女の情念と女の計算高さ、そして女の肝っ玉を見せる。差別され虐げられてきてもなお、人類の存続の片棒を担ぎ続けてきた女というものの強かさをこれでもかとばかりに見せつけられた気がした。