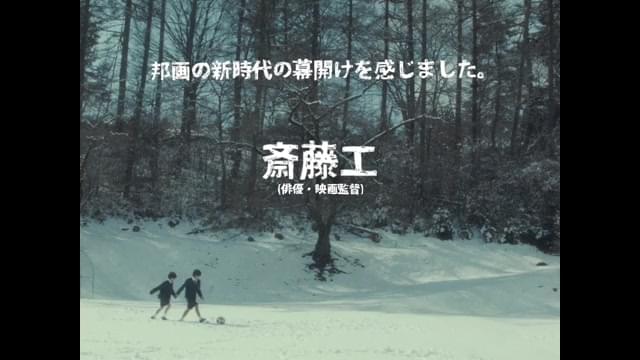僕はイエス様が嫌いのレビュー・感想・評価
全55件中、41~55件目を表示
まったくもって素朴な、神様ってなんだろう?
神の沈黙を明かる過ぎず軽過ぎず
神の沈黙、不在、迷える子羊たちとの関係は、
明確な答えが出ない永遠のテーマ。
教会であるいは懺悔室で、嘆く映画は数知れず・・・
シェイクスピア、ドストエフスキー、ニーチェ、ベルイマン、
そしてスコセッシ『沈黙』。
いずれも暗くて重い。
暗い重いを、
明るい軽いに、
最大限にズラす→
「聖☆おにいさん」
「ブルースブラザーズ」
そこそこズラす→
「天国から来たチャンピオン」
ジム・キャリーのタイトル忘れました。
「オー!ゴッド」
本作は明るくて軽い・・までズラしてないが、暗くないし、重くない。
世知辛い世の中になっているからこそ、
炎上するような内容を、
上手く炎上させない技術、
多くの人を傷付けしまうような内容でも、
誰も傷付けないユーモア、
常にそんなアイデア、武器を身体中のあちこちにぶら下げている人にとって、ターゲットは常に明確で、使用する武器、その影響、責任も想定してるはず。
と仮定して考えるならば。
ちょっとだけズラした、チャド・マレーン。
立派なコロンブスの卵でしょう。
「この窓からなんにも見えねーな」は竜二。
穴の先に見えていたものは?
チャド・マレーンのフィギュアをカバンにぶら下げたい。
静かなる鬱屈
やっぱり「みずみずしい」という表現になるのだろうが、どうもその言葉はありきたりすぎて、どこかパーツが足りない感じがする。
映画としての画づくりは、恐ろしく安定していて、観る人にやさしい。画の中身は家庭のビデオとして撮ったような印象もあり、親近感が湧く。画面サイズが昔のテレビの縦横比くらいで、最近の横長の情報過多な画面より、静かで落ち着いて観れるように感じた。そういえば、ケイシー・アフレック主演の”a ghost story”も同じような画面だったが、視点の動きを少なくした静かな映画は、画面サイズを横長にしないほうが、うるさくなくて見やすいかもしれない。
ストーリーは、とても優しく描いた「沈黙」のようだ。自然に神様の存在を感じられる主人公のユラは、何度も裏切るキチジローとは全く違うが、何故か重なるところが感じられる。宗教色は抜きに出来ないが、監督から「子供の頃こういうことがあってね」と、語られているようで、違和感はまったく感じなかった。
子供を中心に物語が進む中、とても綺麗に掃除されているが、どこか埃っぽさを感じる部屋のような、独特の感覚が沸き起こる。
「面白い小品」として、心に留めておきたい作品だ。
荒んだ大人には心に堪える
これを観てもイエス様を嫌いにはなれなかった。それは私が信じていないからだろう。嫌いになるのは信じているからだ。
東京から雪深い田舎のカトリック系小学校(しかも小さい)への転校という半ば三重苦のような体験をする主人公が、「イエス様」(これがまた大変戯画的で...)を見るようになり、願いを叶えられて、それを信じるようになっていく。
前半の牧歌的感と絶望というか、「嫌い」になる後半が色を基本的に変えずにやっているところは凄いなと思った。あそこで物語の様相を完全分断もできるのに。
物語は...私は信心もないし子どもの無垢も信じていないので、結構心に堪える映画でした。正直、主人公に見えていたものは幻想であり、願いは偶然であり、そして願いはいつも叶うのではないし、どうしようもできない事がある。そこで神さま(まあイエス様は神様じゃないけど...)に怒っても仕方ないでしょう...という穿った見方をしてしまう。私は信じる、が向いていないな...。
私が子どもだったとして、嫌いになるだろうか。もう想像もできない。そういう意味では若い人に強く刺さる気がした。
冒頭からラストに繋がるシーン、カット割り、総じて画の撮り方は素晴らしかった。自然に見えて不自然な。イエス様の動きも、最後に姿を見せるところ含め、その展開が最高だと思う。
前半と後半をつなぐ神社とサッカー、人生ゲームのゴール、主人公の願いごと、の意味を考え続けている。あの部分は敢えて放置したんだろうけど、若干の中途半端さというか、もやもやは感じた。
後は、大人をもうちょっと複雑に描けたら奥行きは出たかな、という気がする。まあそれも敢えてだろうけど...良くも悪くもステレオタイプ...まあでも子ども主人公の映画の大人って必然、そんなものかとも思うけれど。
淡々と。嫌いではない映画
淡々とした映画。自分は、嫌いではないです。
主張するのではなく、事実を描いていく。音楽も賛美歌のみを用いており、音楽で感情表現を補完しようという思いがないのも好ましい。とにかく、観た人が、自分で感じてね、という姿勢に徹していると感じた。
では自分はどう感じたか? 自分は、宗教は、苦しい人の心を救うものだと思っている。苦しくない、普通に生活できている際には、不要だと思っている。
だから、ユラの、宗教との出会い方は、ちょうど逆になっちゃったんだなあと感じた。友達ができたこと、お金がもらえたことは、神様のおかげではなく偶然。一方、終盤のやるせない気持ち、どうしようもない悲しみや怒り、それらを自分一人では乗り越えられない瞬間が来たら、その時こそ、宗教が、神様がユラの役に立つときが来るのだと思う。
かつ、少年の心は柔らかく深いので、いくら悲しみや怒りが深くても、宗教に頼るところまで行くことはないのだと思う。そういう意味で、少年たちに、真の意味での宗教は不要だと思う。
静かな落ち着いた絵、こどもたちの自然な演技。見事。監督・脚本だけでなく、撮影・編集まで一人でやったからこその完成度だと思う。今後もこのスタイルで、時間をかけて一作ずつ撮っていくのか、チームで作ることを学んでそれなりの頻度で作品を見せてくれるのか、いずれの方向に行くにせよ、次回作が楽しみだ。
ところで、オープニングとエンディングを構成する “障子の穴” って、何だったのだろう… これについて「こういうことじゃないか」って気づきを得たら、また追記します。ここがわからないって、監督の狙いに対して、おそらく何か大きく欠落してると思うので。
2021/3/26 追記
以下、引用ですが、監督本人が語る内容がありました。
----- ここから引用
劇中には穴の開いた障子が登場。その意味について奥山は「僕のおじいちゃんが障子に穴を開けていたと、亡くなったあとにおばあちゃんから聞いて。こじつけではあるかもしれないんですけど、亡くなる前にこれから自分が行くところをのぞいていたのかなって。今いる場所から外の世界や現世ではないところを見ようとすること。それが宗教すべてに通じることのような気がして、メタファーとして映画に取り込めないかなと考えました」と実体験を交えて説明する。「映画には余白が大事。観たときに『こういうことを意味してるのかな』と考える余地があることで『私の映画だ』『私が考えていることを言ってくれている』と思っていただける。実際僕はそういったことを考えながら映画を観ています」と映画作りにおける心構えも明かした。
----- ここまで引用
手紙と祈りと
演出は最高だったけれど映像が物足りない
小さな奇跡と、大きな悲しみ
子供の瞳に映る美しくも不条理な世界
ほんのささやかなファンタジーが、現実の裏に優しく寄り添うようなフィクション作品が好きだ。
美しい雪国の気色、友達とのかけがえない時間、不思議な出来事、事件を経過して少し大人になっていく心。
【子供の目線になって】ではなく、本当に子供が見て感じた気色や想いを写したようで、良質な児童文学を読んでいる心持ちだった。
ミッションスクールが舞台の物語だが、宗教について、子供らしい無邪気さと、いい意味で日本人らしい曖昧さを持って描いているような気がして、肌に馴染む。
「神様ってホントにいるの?」と尋ねた少年が、願い事を叶えてくれる小さなイエス様に会って、祖母と並んで仏壇の祖父に線香をあげ、神社ではお賽銭を納め、手を合わせる。由来は柏手を2度打ち、和馬は指を組んでいる。賽銭箱の上には小さなイエス様がうろついている。「何をお願いしたの?」と笑い合い、食前の祈りでふざけて母親にたしなめられる。
向かい合う神の名は違えども、子供の柔らかで初々しい心の中では、祈りの対象に明確な区分けは無いように思える。
また、宗教と信仰というデリケートな主題でありながら、主張は極めて控えめに感じる。
感覚も、感情も、静かに圧倒的に押し寄せてくる。けれど、解りやすい正否や主義を強く押しつける事がない。
それ故、受け取り手は他人事のように眺めるのではなく、追体験するように自分の中で咀嚼出来る。
私には心地良い感覚だった。
他愛もないお願いを叶えてくれた小さなイエス様は、本当に叶えたい願いを、心から必死に祈った時には、姿を現さず、叶えてもくれなかった。
祭壇に響いた衝撃が、現実の不条理に「何故!」と問わずにいられない人々の、悲痛な叫びに重なる。
大人になって、現実はままならないのよ、と理解して生きようとしている私の中の、割り切れずにいる子供が、由来と一緒に拳を叩きつけた。
逃げ出した鶏、祖母の見つけたへそくり、見た振りをした流星群。
何でも叶えてくれる神様がいない事を少年は知った。
それでもいつか、遠い空から見守る何かの存在を、彼は感じるだろうか。
一面の雪景色、俯瞰で捉えられた子供達、ブランコ、もの思う由来の斜め横顔、いつも同じアングルで撮られた食事風景、色褪せたトーン。
映像も独特の雰囲気を醸して美しく、一枚一枚のポスターのようだ。
何処を切り取っても絵になる。
宗教がテーマではなく
映像から溢れ出るピュアさとみずみずしさ
サンセバスチャン映画祭 新人監督賞を受賞した作品。
奥山大史監督は22歳で、これがデビュー作
なるほど、とてもみずみずしい作品だった
小学生のユラは、おじいちゃんが亡くなって、一人になってしまったおばあちゃんと同居するために、お父さんの実家に引っ越してきた
ユラが転校した学校はクリスチャンの学校で、お祈りというものを、ユラはそこで始めて知る
友達が一人もいないユラだったが、やがて、ユラにしか見えない神様が現れ、神様はユラにクラスメートのカズキを紹介する
その物語は
「神様は本当にいるのか」
「お祈りは何のためにするのか」
という、大人でも答えづらい疑問について、小学生の目線で描いている作品
たしかに
悲しいことがあったとき
人は「祈りましょう」と言うけれど
祈っても、どうにもならないことはたくさんあるわけで
それを子供に説明しなければならないとなったら
ますます難しくなる
そんな時、大人たちは
「神に祈りなさい」と言ったとしても
それに従順に従うのではなくて
「僕はイエス様が嫌いです」
と言っても良いと思った
むしろ、それが子供ならではの素直さであって、そうやって彼らは成長していく
窓の外の景色を、障子に穴を開けて覗くように
ユラにとっては、ちょっと大人の世界を覗くような
そんな経験になったのではと思う
面白かったのは、その時、監督は映像を少し斜めにしたこと
それは子供の気持ちをよく表していて
これまで真っ直ぐに見ていた社会を
少し斜めから見るようになったということではないのか
映画を観る前に、出演者たちによる
舞台挨拶があって
登壇した佐伯日菜子さんは「監督は子供の感性をお持ちの方」だと話されていた
この映画を観ていて、その言葉が何度も頭の中で繰り返された
景色が斜めなのも、
障子に穴を開けて外を覗くのも
真っ白な雪の上に残る足跡も
ピュアだからこその映像
その感性で、今後、世界をどう観ていくのかが、とても楽しみな監督だと思った
全55件中、41~55件目を表示