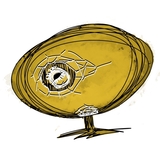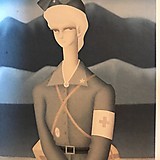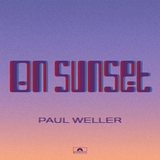斬、のレビュー・感想・評価
全71件中、41~60件目を表示
80分の作品なのに寝落ちしそう。
途中何度か寝落ちしそうになる度に、蒼井優の絶叫演技でびっくりして目が覚めました。(ファンの人、すいません…)
監督自身が演じる古強者の浪人の佇まいや、刀を抜く時の効果音なんかはリアルでいいんだけど、時代劇の魅力である殺陣は手ブレ映像で何が映ってるかよく分からず、主人公たちも何がしたいのか不明瞭。何かのメタファーなら時代劇じゃなくてもよくない?
一度好きになった監督を嫌いになるのは難しい
監督の「鉄男」からファンになった身としては、年々パワーダウンしていく作品群に
(あくまで自分の主観です)少々寂しさを感じてしまう。
自身の思想や主題も人間生きてりゃ本人も気付かぬうちに変わって行くものだろうが、やはり「TOKYO FIST」迄がピークだったように思う。
本作も音響や音楽に塚本晋也監督らしいこだわりは感じられ、それがまた格好よく「海獣シアター作品観てるぜえ」と云う感じにさせてくれるが、満足感はそこ迄だった。
前作「野火」も流石に市川崑監督のオリジナルには及ばない感じだったし、何故あの作品を塚本監督がリメイクしたのか謎だった。
やはり、監督の中に色々な変化が有ったのだろう。「鉄男Ⅱ」を観たらこの監督が将来反戦映画を撮るとは思えないもんなあ。
それでも、塚本監督が時代劇を撮るとなれば観に行かないわけにいかないのは、一度ファンなってしまった性か。そしていい加減監督出演止めた方がいいんじゃね?と思うのも毎作品の事か。
もう塚本晋也作品から初期の頃のようなパワーやスピードを感じる事は無いのかねえ。
しっかし公開館数が少ない。これがジャニタレ使わない時代劇の実情か。
矛盾だらけの時代劇
何と恐ろしい映画だろうか。冒頭の木刀での激しい稽古と勇ましいまでの音楽に一抹の高揚感を覚えてしまったのであれば最後。映画が終わる頃には切られた腕から流れ出る血のように、その高揚感はドボドボと音を立てて流れ落ちるに違いない。何故ならこの作品、時代劇の最大の見せ場であろうチャンバラシーンさえもいとも容易く斬りつけるからである。
矛盾しているように聞こえるだろうか。いや、事実本作は矛盾だらけだ。人を斬るために稽古をする。しかし人を斬ることはできない。人を守るために剣を抜く。しかし人を守ることなどできない。では何のために稽古をするのか?何のために刀を持つのか?
尽きぬ恨み、晴らせぬ思い、やがてそれらが報復の連鎖となって身に降りかかる。自分にだけではない、家族、愛する人、村の人々、果てには己の精神さえもその刃は斬りつけていく。その怖さ、その恐ろしさは何たるものか。ラストシーンは決して後味の良いものではない。しかし、血に染まってしまったその手を洗うことなどできない。たとえそれが自分が斬った相手の血であろうと、斬られて流れた己の血であろうと…。
深い森の中を彷徨う主人公のように、私もこの作品に溢れる矛盾だらけの疑問の答をまだ見つけられていない。
斬って終わりのチャンバラではないからタイトルに読点がある
なるほど。斬って終わりのチャンバラではなく、人を斬るという暴力行為の意味、その行く末をも描く作品だからタイトルが読点で終わるのか(ってことで合ってます?)。変則的ではあるけど、和製『シェーン』『マッドマックス 』『許されざる者』とでも称されるべき暴力映画の新たな傑作
オープニングの鉄を打つ音から音への拘りをビンビンに感じる、この拘りは終始貫かれている。「斬」という時の一画目の刀身を想起させるタイポグラフィにも感心した。死を描くなら、生も然り。池松壮亮のオナニー、蒼井優との戯れも抜かりなく描く。やけにエロい。やっぱり映画はエロくないとな
和製『シェーン』と言ったが、本作のラストで彼もまた去っていく。しかし、彼女は『シェーン』のように「カムバック」と言うことはなく(日本映画だから当然だ)、声にならない声を絞り出すのみ。暴力が全てを変えてしまった。彼は彼岸に行ってしまった(常人ではなくなってしまった)。此岸から「カムバック」と言ったところで届かない
俺が愛して止まないNWRの『ドライヴ』のようでもあって『斬、』マジで素晴らしいよ
観客までも斬りつける
凄い迫力ある映画❗
人を斬れるようになりたい
先ず最初の音で驚かされる。当方も少し飛び上がった。効果音は全編を通してかなり大きく、重低音である。大太鼓やバスの男声合唱もあり、作品に重々しさを与えていると同時に、観客にとっては重苦しさも感じさせる。狙い通りなのだろうか。台詞回しも大仰ではない平易な言い方が日常感を強調し、芝居がかった言い方よりもリアリティがある。これは塚本監督の意図であろう。
テーマはわかりやすく、人を斬れるか斬れないかの分かれ目はどこにあるかということである。天下泰平の江戸時代にあって、人を斬る機会はあまりなかったはずだ。しかしそれでも武士は毎日稽古に励み、いざとなったときに戦えるように備えていた。今も昔も、人は他人に勝つために強くなりたいと思う生き物らしい。空手や柔道などの格闘技は、実際に人を相手に技を使うと傷害罪になってしまうにもかかわらず練習に励む人が多いのは、必ずしも大会で優勝するためばかりとは限らない。
しかしそうやって練習を重ねても、実際に人を相手に刀で斬りつけたり、または人中(じんちゅう)みたいな顔の真ん中の急所に正拳を叩き込んだりすることができるようになる訳ではない。人を斬ったり殴ったりできるようになるには、精神的な堰を超えなければならないのだ。
池松壮亮は、恒常性バイアスによってかろうじて守られている我々の日常が、如何に脆く崩れやすいものであるかを見せてくれるような俳優である。この作品はそういう点では彼にぴったりの映画である。腕は立つが人を斬ったことがない武士は、一生人を斬らないで生きていくか、どこかで一線を越えて人を斬るかのどちらかしかない。人を斬るためには、斬られた側の痛みとか、人生を終えることの後悔の念とか、そういった思念を全部捨て去らなければならない。甘っちょろい良心などは、ハナから捨て去るべきものだ。平穏無事を願う夢は失せなくてはならない。
一切合財を捨てて人を斬ることができるかを、塚本監督は池松壮亮演じる都筑杢之進だけでなく、観客全員に問いかける。人を斬れない杢之進を、映画は必ずしも否定していない。原始時代の人間は、欲望と本能のままに人を殺していたはずだ。想像力や罪悪感が生じて人を殺しづらくなったのは、文明の証である。人を殺せないのが文明人であり、人を簡単に殺せるのは野蛮人に他ならない。
理性ではそのように理解していても、人を殺したい衝動は誰しもが持っている。しかし殺したら自分もただでは済まない。その恐怖が衝動を押し留めているだけだ。デスノートのようなものがあって証拠が何も残らなかったら、誰もが自由に人を殺してしまうだろう。自分が殺したことを社会に知られることが恐ろしいのだ。
世の中には、人を簡単に殴る人間がいる。そういう人間は人を殴れない人間よりもずっと、人殺しに近いだろう。この頃はスポーツの団体をはじめとしてそういう人間がコーチや監督の中に大量に存在していることが次々に明らかになっているが、スポーツ界だけではないだろう。政界にも財界にも、あるいは官僚の中にも、人を殴っても屁とも思わない人間がいて、そういう人間たちがそれぞれの共同体の中で監督やコーチの立場にあるとすれば、人を殴れない、人を斬れない人間たちは一生スポイルされたままである。
どうだ、この辺で人を斬れるようになってみないか。塚本監督の皮肉な笑みが脳裏に浮かぶ。
ガッカリ感満載
耳で楽しむ。
冥土の土産
自慰映画
斬る理由
静寂も、そして怒号も斬り裂く甲高い金属音が、頭の中に波打って消えない。
人を斬る理由とは何か。
生きるため、家族のため、大義のため、そして、自分自身が生き残るため。
しかし、斬った後に残るのは、悲しみや憎しみ、復讐心や絶望だ。
だが、刀は、これらの残されたものたちを断ち斬って無くすことは出来ないのだ。
武士の世が終わり、新しい時代に変わろうとするなか、多くの命が失われて、悲しみや憎しみも取り残された。
武士道が美化され語られる時代だが、150年ちょっと前の日本には、こんな光景がたくさんあったのかもしれない。
物語は、薄暗く小さな山村で、杢之進や、ゆう、市助、山賊の叫びは、まるで舞台で演じられてるかのように狭い空間に響き渡る。
普通の時代劇映画とは明らかに違う
池松壮亮さんと蒼井優さんが好きなので、見ようか見ないか迷っていましたが、某早朝トーク番組見てやっぱり見てみたいと鑑賞です。
思っていた時代劇映画とはまったく違いました。迫力もスピード感もあって、美しさと狂気と不気味さが伝わりました。特に戦闘シーンは手持ちカメラでスピード感があって、音も良い意味で不快な音で、迫力がありました。
また、キャラの狂気に侵される感じもよく、とこがフランス映画のようなセクシーさもありました。
日本刀で人を斬るということなので、日本刀と美しさと重量感、恐ろしさのようなものが良かったです。
たた、、、終始、演出が過多気味で、こんなシーンも撮れる、こんか役者の演技もあると、胸焼け気味です。どのシーンも全力!となると、観ていると引き込まれるところもありますが、疲れてしまいました。
斬れない苦悩をシンプルかつ力強く描く
塚本晋也監督の初の時代劇とのこと。幕末の農村を舞台に江戸から京へ出てひと花咲かせようとする二人の浪人を描く。
池松壮亮演じる若き浪人は、物腰が柔らかく、用心棒の体で農家に溶け込み、武術は達者だが「人を斬ること」に激しい抵抗がある。塚本晋也演じる壮年の浪人は「人を斬ること」に何の抵抗もない。
塚本との対峙を通じ、人を斬れない池松の苦悩をシンプルに描く。そして池松に想いを寄せる農家の娘(蒼井優)が彼らのすべてを見届ける。
激動の時代にいながら、その中心から遠く離れ、近づくことができない焦燥をもしっかりとらえた。
力強くもピュアで美しい作品。そのシンプルさゆえに物足りなさを感じる方もいると思うが、私は好きだ。
【追記】
上映後に塚本監督の舞台挨拶があった。時代劇との出会いは市川崑監督の「股旅」だったとのこと。黒澤明や小林正樹の作品がもつ様式美とは一線を画す、このカジュアルかつニューウェーブなATG作品が記憶の底にあったのだろう。
偽らざるもの
叫び
全71件中、41~60件目を表示