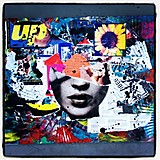来るのレビュー・感想・評価
全555件中、441~460件目を表示
怖くないホラー映画
私はホラー映画は苦手です
ですのでホラー映画絶対に観ないのですが
この作品は予告編を観る限りでは
怖くない感が溢れていました
それに大好きな中島監督なので観ることにしました
結果 やはり怖くなくて
娯楽作品に仕上がっていました
妖怪退治に近いような作品でした
ですので ホラー大好き人間の人には物足りなく
怒りが出ても仕方ないなと思います
余談ですが
私は依然「セブン」(ホラーではないですが)と言う洋画を観て
怖くて怖くて夜も寝られないくらい怖かったのですが
友人が「セブン」は怖くなくてちっとも面白くなかった!と
言うのです。あれには驚きました(笑)
この作品も怖さを期待してはいけない作品です
この作品の中で ばけもの退治をする小松菜奈 松たか子が
かっこよくて 良かったです!!
クライマックスのシーンは大好きでした!!
(怖くないのです)
物語が進むにつれて えーなんで かんで こうなるの!!と
展開がわからなくなり(これをネタバレするのはまずいので)
最後まで目が離せませんでした
しかしこの作品 クズ野郎がごろごろ出てきますが
最後は 救われた感があり少しはほっとしました
中島ワールド全開の作品でしたね
来たのかなぁ…?
中島哲也監督の作品は好きだ。
『下妻物語』から『告白』まで、どれも甲乙付け難い。
世間的には酷評された『渇き。』も、邦画にしてはなかなかのバイオレンス・ハードボイルドで、嫌いじゃない。
その『渇き。』から4年振りとなる待望の新作は、監督初のホラー。
鬼才がどんなホラーを魅せてくれるのか、年末のラインナップでも特に期待し、楽しみにしていた。
もう一度。中島監督の作品は好きだ。
だから、はっきり言ってしまおう。
今回は、来なかった、と。
クソつまんねぇ!…と、バッサリ切り棄てるほどではない。
それなりには面白い。
が、賛否両論レビューも頷ける。
あらすじからオカルト系(と言うか、和独特の心霊系)と思うが、そうでもあり、そうでもないような…。
かなり癖のある怪作であり、ハマる人はハマるし、ハマれない人はハマれない。
そもそも、この鬼才監督がドストレートなホラー映画を作る訳がない。
事実、描かれていたのは、人の心の闇。
結婚生活の失敗、家庭の不和、偽り、見栄、育児や家事のストレス、虐待…。
それらは、人の弱くて脆い心に取り憑き、蝕み、惑わせ、苦しめる、悪しき何かの仕業のように解釈も出来るし、それを具現化した描き方もユニーク。
ブラック・コメディでもあり、シビアで風刺的な人間模様ドラマでもある。
途中までは良かった。が…
クライマックス、遂に“あれ”と対峙。
スペクタクルなお祓いシーンは何だか笑えてくる。
それはまだいいにしても、いざ対峙が始まると、大量の血糊や大袈裟な演出や音響、VFXなどで誤魔化してるようで、こけ脅し感半端ない。
で、結局“あれ”は来たのか…?
来たんだろうけど、よく分からなかった。
“あれ”も何だったのか…?
はっきりとした正体や謎も明かされないまま、観客に丸投げ放り投げ。
何だか、頭がクラクラ疲れただけ。
豪華キャストたちは怪演を披露。
妻夫木のイクメンやってます&幸せアピールは見てて本当にウザイし居る居ると思わせるし、新妻・黒木華の心身衰弱していく様はさすがの名演で、まだ独身の筈なのにリアル。
パンクな小松菜奈はイメチェン、そしてキャストで誰よりも異様さと存在感を放つは、松たか子。
日本最強の霊媒師で、日本のお偉い機関さえ頭を下げる。常に無表情、無感情。この姉さんが一番怖い気がする…。
周りが個性あり過ぎて、一応主役の岡田クンは影が薄かった。
演出も作風も映像も選曲も、中島センスの異色のエンターテイメント。
でも、ラストの岡田クンの台詞が、本作の率直な感想を表していた。
かと言って、これで中島監督の作品が嫌いになった訳じゃない。
中島監督にはまだまだ“来る”事を期待している。
やっぱり原作の方が面白い
中島監督という時点で悪い予感はしていた
原作を読んでからの観賞。
納得できないのは、一切「ぼぎわん」を映像化していないという点。あの灰色の身体で口の大きな化け物は?
最後まで「ぼぎわん」という
恐怖の対象物は姿を現さないのである。
そもそも、ホラー映画は恐れる対象物からの逃避に限る。ジェイソンもジョーズも貞子も、恐れる対象からの逃避があるからこそ、リアリティと恐怖感が生まれる。恐怖の対象がないからオカルトになってしまうのではないか。個人的にはそう感じる。
原作を見ていない人には、何から逃げているのか
余計に分からなかったんじゃないかな?
映画化決定の時から、中島さんが監督というところに悪い予感を感じていた。
餅は餅屋に任せるべきだと思う。
ホラー作品を撮ることに優れた監督はもっとたくさんいるはずだ。
原作は良かったので
出来れば他の監督でリメイクして欲しい。
純粋なエンタメ映画
原作至上主義者ではありませんが、これは原作小説の話の筋の方が面白かったと思いました。
映画はホラーというか「行くぜ!鬼退治!」的なエンタメでした。
わざとらしすぎる派手な演出や音が多くてあまり怖くなかったです。ハリウッド的でした。もう少し抑えた演出と普通の音でジワジワと来る恐怖を見せられるのではないかと思いました。
小説でも書かれていた、「人間の闇」と毎日のちょっとした積み重ねから壊れていく「人間関係」「家族関係」、その歪みに怪異が引き寄せられていくことが描かれているのは良かった。
俳優陣の熱演も素晴らしかったです。
小説の題名は「ぼぎわんが、来る」。
映画は「怪異の正体とかどうでも良し。やっつけるのみ!」ということでした。
しかし小説では「来る」怪異の正体を追って、最強の霊媒師琴子とフリーライター野崎が推理し、ついには真相を暴くというミステリー仕立てにもなってました。
「あんな恐ろしいものは誰かが呼ばなければ来るわけない」
じゃあ誰が呼び寄せたのか?なぜ田原家にまとわりつくのか?怪異は遠くから「来ている」が、どこから来るのか?そこら辺がちゃんと書かれてました。
怪異の正体と関係があるのですが、昔の貧しい農村では、口減らし(食糧確保のため)の姥捨山や赤ん坊を間引いていた忌まわしい歴史があり、そこから派生したであろう怖い民間伝承や民俗学の話しもほどよく書いてあり、絵空事のようなこのホラーに現実味を与えてました。
日本古来の民間伝承と、普遍的かつ現代的な問題がひとつに組み合わさり、謎が解けていく過程は秀逸でした。
これを映画で省略しないで欲しかった!!
と、長々書きましたが、つまり私的には感想は
「映画はホラーとして見ない方がいい」
「原作小説の話の筋の方がしっかりしている。ちゃんと謎が解けてスッキリする」
ということです。
ホラーのふりをした娯楽映画
タイトルなし(ネタバレ)
☆☆☆★★
続『フラレラ』の先に有ったモノ、それは…。
めちゃくちゃでござりまするがな〜(古い)
この監督作品ならば、原作を読んでも意味は無いだろうと思い。原作本を読む気は無かったのだが。
何分にも、通勤時間での手持ちぶたさが何とも…。
結果、原作読了済み。簡単に。
原作の題名は『ぼぎわんが、来る』
しかし、映画版の題名はシンプルに…。
『来る』
確かに、原作未読だと【ぼぎわん】んて何だよ!となってしまう。
ぼぎわん=ブギーマン
キリスト教伝来と共に、海外の悪魔伝承と言うか。人さらいに近い語源が和歌山県の一部地域に根付いている…って話だったのだが。
原作は主に3章から成り立っており。
第1章が夫の秀樹。
第2章が妻の香奈。
第3章が田原家とは部外者の野崎から語られる。
第1章にて描かれるSNSを通した、偽イクメンパパ奮闘記は。この監督が過去に描いた『フラレラ』での傑作短編を思い出さずにはいられない。
イイネ!欲しさからの暴走。その果てに行き着いてしまう炎上の嵐。ネット上で発覚した蜜に群がる魑魅魍魎の魔物達は、この作品では妻の香奈となり示されている。
直ぐ傍にいるからこそ見抜いてしまう、夫の器の小さなところ。
第1章の夫役である妻夫木聡と。第2章で描かれる、子育てに疲れた妻役の黒木華。
この2人の演技は、原作をも上回るくらいのキャラクターになっていて、尚且つかなりの熱演。内容自体も、この監督にしては意外と言うか。原作の主だった筋からははみ出さずに描かれており。ちょっと拍子抜けを感じながらの鑑賞でした。
確かに、幾つかの原作には無い変更箇所は有るには有って。例えば、大量の虫が投入されていたり。やたらと◯ムライ◯が強調されたりと、言ったところは見受けられるのだが。それほどの違和感は感じられなかった。
第3章の最初の方までは!
問題は、最強の霊媒師役の松たか子が本格的に登場してからだった。
やりやがったな!中島哲也〜!
もうめちゃくちゃでござりまするがな〜。このフレーズやっぱり古いけど、2回も言っちゃったわ〜(。-_-。)
おいおい!ひょっとして、大量の血飛沫を使いたかっただけなのか〜!…と、叫びたくなってしまった。
最早、原作はどうでもよくなってしまっている。
いや!別に、原作至上主義では無い(寧ろそれほど良い小説とは思ってはいない)ので、原作通りで無くても構わないのだけれど。
大体《彼奴》は、デカイ口の筈。
それなのに、やって来るのは常に《血だらけの手》なのだ!
そりゃ〜口が襲って来たところで、実写で見たら怖さには繋がらない。との考えたのならば、分からなくは無い。
しかし、妻夫木の同僚役の太賀の傷跡は。原作どころか、映画でも「噛まれた跡」とはっきりと言ってしまっているのに…。
第3章で明らかにされる【ぼぎわん】の秘密。それは、田原家に代々祟られた呪いで有り。古くからの因習を始めとした、日本全国つづ浦々に伝わる伝承だからこその怖さが、その裏には有った筈だったのだけれども。
とは言え、この最後のやり過ぎなスペクタクル。
恐怖と笑いは表裏一体を表すが如く。明らかにコメディーに振った演出もチラホラ。正直なところ、3回程ゲラゲラと笑ってしまったのも事実でした(¬_¬)
…と、此処まで書き込んで、「そうか!」と思った事が!
映画版の題名に何故【ぼぎわん】が無くなっているのか?
まさか?原作者との間に、「やりたい様にやっちゃって良いですか?」とのやり取りが有ったのか?…と。
もしもそうだったならば、題名から【ぼぎわん】が消えた訳も分からなくも無いのだけれど。
まあ、この監督ですからね〜!と言うしか無いですね〜。
2018年12月9日 イオンシネマ市川妙典/スクリーン2
ホラーではなくエンタメ
原作は未読。
物語のテンポがいいし、怖さを演出するシーンもなんかポップで新鮮だった。でも、なんか長い!観終わってから思ったのは、冒頭の親戚の集まりとか結婚式とかもっと短くてもよかったってこと。
妻夫木聡、黒木華と死んだところでもうそろそろ終わりかと思ってたら、そこからのお祓いがメインだったとは!それならばお祓いパートをもっと丁寧に描いてほしかった。これって原作が短編集なのか?
真相が明らかになる中わかるのは、登場してる人間の黒い部分。怖いのはそっちで、怪物?妖怪?はあんまり怖くない。ホラー映画としては評価は低いかもしれないが、エンタメ映画としては及第点ではないか。
来た‼︎
評価低めでビックリ⁈
最近ピンと来ないのばかりで(私の好みですが)
邦画ホラーでは
久々悪く無いのでは⁇と思ってたのですが...
妻夫木聡や黒木華も
もっとぐちゃぐちゃにして
ラストにかけて
もっと切り株シーン増やしてくれたらな
松たか子のグーパンチ
ワロタ‼︎
似てる個所がある
國村隼が出てた「哭声」を思い出しちゃいました。
オムライスの夢に出てた
トマト可愛かった〜
作家性は爆発しているが
見た瞬間に これは中島哲也の映画だ と見た人みんながわかる作品だった
個人的には中島哲也作品の特徴は人間の一枚皮を剥いだ先にある邪悪さを描き出す時の音楽と色の使い方と編集テンポに溢れる 独特のポップセンス もっと言うと それらが醸し出す 邪悪なカラフルさ にあると思うんだけど、今作もそれが随所に散りばめられている
色々な作品(しかも原作付き)を撮りながらも全作に共通してこの作家性がぶち抜かれているのはいつも見ていて凄いなーと思う
(ティムバートンの映画を見た時の感じに似てる)
ただ、その作家性がこの映画にあっていたかと言われると… 個人的には上手くいっていないように感じる箇所もあったりした。
未読ながら調べたところ、原作からは大きな改変が施されているようなのだが、今回の話だと、あの夫婦は色々あったけど結局この映画で語りたかったのは岡田くんの部分だけでした という風に見えてしまいかねない。
改変によって 中島哲也作品 らしい味わいは増えたけど
話の輪郭が歪んでしまった感は否めなかった
積極的に話の全体像をボヤかしに行っているというのは間違いなく意図としてあるんだろうけど、ぼやかしすぎで 夫婦 と その他の人たち の関係がストリーリー上で有機的に結びついてないように感じてしまったのが個人的には一番引っかかってしまった。
妻夫木聡と黒木華の二人が 中島哲也テイスト にバッチリハマっていただけに残念。
終盤の祈祷バトルシーンはエンターテイメント性の追求という意味では個人的には大いにアリな試みだったと思う。 いっぱい人死んだけど結局なんだったこれ… という雰囲気はあったけど、その部分のぼやかしはこの映画にあってたと思う。
あと個人的にはこのシーンの 松たか子のパンチ すばらしかった。 作中最強キャラとして堂々たる右ストレート。
まぁこれだけ作家性爆発させる以上 多少の歪みは 織り込み済みなのだろう。非の打ち所がない映画を作るのではなく 自分が追求する物を作り上げる というスタンスは素晴らしいし、何よりこれだけスター出まくりの日本映画でここまで我を通す作品を作り上げたというのは本当に凄い。噂でも聞いたことあるがこの監督、相当癖が強そうである。
映画は監督のものである という側面を存分に味わった一作だった。
うーん。
……なんだそれ(笑)
これは映画のラストシーンのセリフなのだが、この後、暗転してエンドロールが始まった画面を見ながら、同じセリフを吐いてしまった(笑)
まず致命的なことに、まったく怖くないという、ホラー映画としては致命的な欠点を抱えている。
なんせ、極端にホラー表現が苦手で、あの「貞子3D」ですら映画館で悲鳴をあげてうるさかった私の妻が、本作では一声も発しなかったのだ(笑)
私の妻を怖がらせることができなかった時点で、ホラーとしては0点、というか評価対象外、としか言いようが。
登場人物の設定、ぼぎわんの成り立ちなど、原作からいろいろ変えているが、それら全てが空回りしている。
元々原作でも、視点人物が次々と退場し、特に秀樹編と香奈編では、読者が感情移入していた秀樹を香奈の視点から見た際の落差が激しく、読者の感情を揺さぶる作りになっている。
その構造を映画の脚本に中途半端に持ち込んだため、話の前半が単に冗長になってしまっている。
そして、その香奈をああいう設定にするとは、観客はいったい誰に感情移入して見れば良いわけ?(笑)
あ、でもこの香奈役の黒木華は見事だった。この脚本では才能の無駄遣い感は半端なかったけど(笑)
で、映画の尺を前半にほぼ取られているおかげで、真打ちが登場してから、つまり原作の第三部が駆け足になってしまってるわけで、さらにそこに原作にはない野崎の過去とか"ぼぎわん"の独自解釈などを突っ込み、とどめに観客から笑いを取ろうとしているとしか思えない"霊能者全員集合"イベントにオムライス(笑)
役者は、今回の黒木華は絶品だったが、岡田准一も小松菜奈も妻夫木聡も松たか子も実力確かな人たちで悪いはずもない。
この俳優陣をもって、観客を怖がらせようとしているのか笑わそうとしているのか分からん、という映画ができてしまうのは、200%脚本のせい。
多分これで自分は、中島哲也の映画は見ない。
クソ作品
全555件中、441~460件目を表示