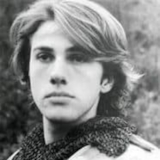万引き家族のレビュー・感想・評価
全935件中、181~200件目を表示
今の日本の縮図
市井の人々を描く是枝作品の中で、今回はとても設定が分かり辛い。この人とあの人はどういう繋がりなのかという、謎解き要素もある。
万引きは生活の一部で、そのベースにはもっと深刻な問題が山積みで、
再就職出来ない元犯罪者、
夫に捨てられた孤独な老女、
留学と偽って日銭を稼ぐ若い女性、
ネグレクトで親の愛情を知らない子ども、
それが寄り添いあって生活している風景には、当たり障り無く生きてきた自分には共感ポイントはゼロ。しかし、放置されていた子どもが感じるモノは、元いた家族のそれとは遥かに違い、その子に目をかける老女や偽夫婦の心情もまた、他人ではあるが惜しみない愛がある。
少なくともここで言う愛とは、世間的な常識とは少し離れたモノであるのは、製作者の意図として理解出来る人が多いだろう。
同じ是枝作品「そして父になる」での台詞、
「一緒に過ごした時間が大切」
が身に染みて理解出来る作品である事は、
是枝作品の一貫性を教えてくれる。
偽りとはいえ、彼らは家族だった。
これだけは言いたい。
松岡茉優の頑張りと池松壮亮の存在感に拍手。
今の年齢だから感じるものがあった
自分は安藤サクラと同世代でいわゆる団地世代の最後の世代として子供時代を過ごした。
私が小学生の頃は集合住宅の団地に住んでいて、その頃は団地にたくさん子供がいたし今思えばネグレクト状態でいた子供も多く見たし、うちも裕福な方ではなかったが当時母が新聞配達をしていて集金に尋ねた市営アパートには子供しかおらず、ご飯もなく母が見兼ねて近くのコンビニでおにぎりを買って与えていた事なども思い出した。
現代では考えられないけれど見兼ねて他人の子供を自分の子供として生活するというおったまげな設定も、ひと昔前の時代に取り残されてひっそりとギリギリを生きる人間がいたならあり得るような気がした。
これはそういう人を描いたテーマの映画だという前提で、割とリアルに素直に受け入れられた。
登場人物たちは根っからの極悪人でもなければ善人でもないし経済的に困窮している人間が目の前に起きる問題を自分の欲望を入り交ぜながらその日暮らしで乗り切っていくとしたら、正にこんな事も起こり得るのかもと思わされた。
日本映画がカンヌで最高賞を取ったと聞いた時点でかなりハードな内容なんだろうなと覚悟して見たが、この年齢になったせいか思ったよりはマイルドだった。
タイトルが万引き「家族」とは言っているが決して家族と見るものではない。
(言っても気まずいシーンはあるので)
ラストの方で(子供が産めない)安藤サクラが子供たちにどう呼ばれていたのか、と警察が問う場面では警察役の池脇さんの芝居がちょっと臭いななんて思いながらも気付いたら涙が出ていた。その涙に対する自分の感情がよくわからないが…
(録画を見直してリンを戻しに行った先で言い争う声「私だって産みたくて産んだわけじゃない」を聞いた安藤サクラが子供を返したくなくなったんだろうというところとか、工事現場の家の中で「ただいま〜おい、翔太…」と妄想を口に出すリリーに泣けた)
そろそろ終盤かなというところから、はっきりすっきりさせないまでもある程度のところまで見せてくれてあとはこの人達はどうなっていくんだろうというところも実在する人間のような終わり方でリアルに感じた。
あとは松岡茉優がおばあちゃんと慕って甘える場面や、色々な事が分かったあと自分が必要とされていたのか疑問を持ってしまうところなんかも樹木希林と同じくらいの祖母がいる自分としては切なかった。
いろんな世代の登場人物が出ているので、見る人の年代、性別、その人の現状によって感じる事は様々だろうなと思う作品だった。
この映画の主人公たちを忘れたくない。
何度も見返したいと思った映画だった。
正直うまく感想を言葉にできない。
その時の自分の置かれた状況や気分で感想がかなり違ってくるような気がする。
今回(2019.12.17)に観た時点では、
社会には、自分よりも、経済的にも世間的にも孤立している人が実際いるということに関心があるため、この映画がとてもリアルに感じた。
この映画のような世界、人生があるということも、この世界の悲しい現実であるということが、これから生きていく上で、かなり悲しく、辛くなる。
一方で、社会的な弱者にも手を差し伸べてくれる優しい映画の中のような人たちもいることを忘れたくない。
リアルと芸術の狭間
一緒に見ていた母は、「作品に共感できない」と、途中眠ってしましまし...
一緒に見ていた母は、「作品に共感できない」と、途中眠ってしましましたが、
私は、この作品は、実際にあった事件をモチーフにして作ったんだろうと感じるほど、とてもリアリティを感じました。特に、おばあさんが亡くなったあと、葬式などの費用がないので、庭を掘って埋めるなど。実際、本物の家族でも、葬式が出せずに、そのままにしている方があとを絶ちません。善悪ではなく、現代の、ある擬似家族の1断面として、良く、描かれていると感じました。
かなり泣けた
やっぱり是枝監督の作品は良いね。しかも知らなかったけど先行上映だったんだね。出演しているキャストみんな演技が上手だった。是枝監督の作品にはとうもろこしを食べるシーンが出て来ることが多いです。特に歩いても歩いてもに出てくるとうもろこしを揚げたシーンは見ているだけで食べたくなる。是枝監督のお母様が作ってくれていた料理なんです。そんな実際の家族の思い出がシーンに込められたりするから見ているこっちまで血が繋がってなくても絆に感動するんだろうな。
以前、他の試写会作品の舞台挨拶なのに阿部寛さんが次の作品「歩いても歩いても」がめちゃくちゃ良い作品だったと絶賛していたのが印象深くて出演しているキャストが感動してるんだから観ているこっちはそれ以上に感動しました。いつもキャストの中に樹木希林さんがいるのも素敵だなと思います。
ひどいと言っている人は何も不自由なく育った方だと思います
こちらの作品を見てただただ泣きました。その後はまずレビューが気になりました。同じ感情の人がいるのが見たくてたまらなかった。普段はレビューなんて投稿もした事は無いけれどとにかく皆んなの感想が知りたかったです。レビューを見れば普通に育って来た方、ネグレクトで育った方の解釈は明らかに違いが出るだろうと…やはりレビューには普通に育って来た方の評価は悪く、何らかの違った育ち方なのかはわかりませんが、人の痛みが分かる方のレビューもあり救われました。この作品は完結ではないし丸く収まる形でも終わってないのがまた泣けるポイントだと思いました。愛が溢れる嘘の家族の中で育つよりも愛のない本当の家族の方が良い環境だと思われてしまっている。戻ったとしてもやはり嘘の家族の時のことを不意に思い出してしまい遠くをみるりん。しょうたに最後嘘を付いたのも愛だと思う。嘘を付いてしまってもバスを追いかけてしまう所。泣けて泣けてしょうがなかった。でもこれは育った環境で感想は違うかな。でも分かって欲しいと心の底から思いました。
この映画は鏡
やられた人しかわからない
虐待を生まれてから何年もされ続けた人にしか分からない痛みがあるし家族に存在を消される痛みも本人にしか分からない
やられた者だけがわかる痛み
その傷を少しでも癒そうと集まって
自然と家族になってしまった万引き家族。
私は生まれてから家出をする17歳まで虐待されていたので泣きながら観ました、痛いほどみんなの気持ちがわかりました
学力や経歴もないので水商売するしか生きていく方法が無いのも理解できます。
夏のシーンでは本当の家族のようにみんなの笑顔が素直で可愛らしくて尊かった
信代がきちんと働いていたので治が真面目に働いていればもう少し家族でいれたのかなと思いました。
この映画は理解出来ない人が多い事を願います
痛感して涙を流した人にはあなただけじゃないよ、よく頑張ったねとお伝えしたいです
酷い経験をしていなくても見事に演じきった製作に関わった全ての方達も凄いの一言に尽きます。
これはひどい・・・・
なぜこんなに話題になったかが理解できなかった。
まずどんな環境であれ犯罪集団に全く感情移入できず、被害者が気の毒で仕方ない。
最後の30分ぐらいで子供がきっかけで警察沙汰になったときは爽快だった。
自分の子供には絶対に貧しい生活を送らせてはいけないということを痛感しただけでも、
見る価値があったから星一つ。
全935件中、181~200件目を表示