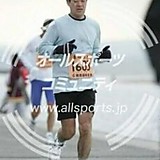運命は踊るのレビュー・感想・評価
全21件中、1~20件目を表示
運命の理不尽さ
イメージで語るのが映像の醍醐味だが、本作はその醍醐味に溢れている。玄関に飾られた抽象絵画、繰り返しのデザインが印象的な床のタイル、検問所を悠々と通貨するラクダ、鳥の大群、車に大きく描かれた金髪の美女など、セリフや人物の行動とともにそれらのイメージが雄弁に作品のテーマを語る。
邦題『運命は踊る』とあるが、運命とは超然的な力だ。個人がよかれと思って行動したことが、予期せぬ結果に収束する。これが運命だ。息子を助けたい親の行動が、息子を追い詰める。世の中はそんな風にままならないことだらけで、人は運命に導かれ結局同じ悲劇を繰り返す。原題はフォックストロットというダンスの一種から取っているが、その繰り返す運命の比喩だという。
これはイスラエルの物語だが、観客に突きつけるものはイスラエルの問題ではない。人間の運命の理不尽さが的確に描かれている。
こんなにも不可思議な構成で運命を描き出した怪作
こんなタイプの映画は初めて観た。宣伝のチラシには本作が並外れた映画であることが記され、現にヴェネツィアでは審査員グランプリを獲得するほど激賞された作品だ。
正直言って、私にはこれが傑作なのかどうかは判断つきかねるところがある。むしろ、評価や満足などの「人の手によるラベリング」の域を超えて、不気味に体内へと侵食してくる映画のように思えてならなかった。
これまでにも「運命」というものを捉えた芸術作品は星の数ほどあったろう。しかしそれをこんなに特殊なカメラワークと構成、リズムとテンポ、語り口で描き出してしまうことに、胸の内側が静かに沸騰させられた。何よりも、眼前に生贄のごとく吊るされた運命を、これほど俯瞰して見つめた作品は他にないと思うのだ。近隣の国や地域と衝突を繰り返すイスラエル。だがこの映画は、宗教や政治、主義、主張、その全てを超えて、世界の共通言語として受け止められる。そう強く思った。
【戦争による死が日常生活の中にある恐ろしさ。戦争の愚かさを戦時場面一切なしにシニカルに描き出すイスラエル映画。】
ー 三幕構成の映画。ー
<第一幕の印象的な場面>
・ミハエルとダフナ夫婦に息子ヨナタンの戦死が突然軍役人から告げられる。呆然とするミハエルと失神するダフナ
・葬儀段取りを事務的に説明する従軍ラビ
・ミハエルの兄、アヴィクトルの訃報の文を推敲する姿
・ミハエルが施設で暮らす母に息子の死を告げに行った際、フォックストロットのステップで踊る男女達
・ヨナタンの死が誤報だったと告げられ、激高するミハエルと落ち着きを取り戻す妻、ダフナ
<第二幕の印象的な場面>
・イスラエル国境付近ののどかな検問所前をゆっくりと歩むラクダ。暇を持て余すヨナタン達若き兵士
・夜中、検問中にある小さな出来事がきっかけで起こる惨事。それを”戦時中には何でもありうる、何もなかったことにする”という上官
<第三幕の印象的な場面>
・冒頭のミハエルと妻ダフナの遣り取りで、ヨナタンの死が仄めかされる。誤報ではなかったのか? そして、真相を語る淡々とした映像
<戦争に起因する死が日常の中にあるイスラエルの現状が、静かなトーンで語られる反戦映画の秀作。>
ミハエルを演じるリオール・アシュケナージー(テルアビブ生まれ)とダフナ演じるサラ・アドナー(パリ生まれのイスラエル人)の演技も印象的であった。
追記:サラ・アドナーはこの作品の少し後に公開された「彼が愛したケーキ職人」でも拝見した。少し、シャルロット・ゲーンズブールを想起させるアンニュイな雰囲気が印象的な素敵な女優さんである。
<2018年9月29日 劇場にて鑑賞>
自主映画こじらせテイスト
「運命は踊る」と言うより「因果は巡る」
どこにも行けない
突然に訪れた悲劇的な状況に翻弄される家族。 緊迫感が滑稽でシュール...
運命は踊る、されど進まず
懐かしいような新しいような、
おかしな国
なんとも皮肉な運命のいたずらを描いている。話の筋としてはそれだけなのだ。後になってから、余計なことをしなければよかったと思うことは、人生の中でままあることだ。
それだけの話を映画がどのように表現しているのかをじっくりと味わいたい作品である。
多用される垂直方向からの俯瞰のショット。懐かしさを掻き立てる音楽。兵士たちの休憩小屋の傾きなどの、寡言にして雄弁な演出。陰陽的な照明。
いつも被写体となっている人物のあずかり知らぬところで、重要な事態が進行する。
そして、いつしか観客はイスラエルという国の滑稽さに辿り着く。事態は当事者にとっては深刻なものだが、それらを引き起こした原因は非常におかしなもので、おそらく世界にこのような国は他にはないだろうと思わせる。
人は踊らされるが
悲しみのステップを踏む
いまこの瞬間に、世界のどこで戦争が起きているだろうか。どれくらいの戦場があって、いくつの戦闘が繰り広げられているだろうか。
本作品はある家族のことを描いているように見えるが、実は立派な反戦映画である。戦場がコミカルに描写され、将校たちは見るからに愚かしいのがその証拠である。
日本国憲法の前文の一節に「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」とある。つまり政治家は戦争が起きないようにするのが仕事なのである。軍備を増強し、日本を再び戦争のできる国にしようとしている現政権は、トチ狂っているとしか思えない。そして本作品にも見られるように、他の国の政治家も、トチ狂っていて、意味なく若者を戦場に送る。
世の中では、親の愛情は人の命の大切さとともに、無条件に肯定される。しかし必ずしもすべての親に子供への愛情があるとは限らない。そして子供は 必ずしも親を尊敬しているとは限らない。というより、子供は意外に親を客観的に見ているものだ。
邦題の「運命は踊る」の意味がよくわからない。原題の「Foxtrot」は踊りの一種で、スロー、スロー、クイック、クイックのステップはあまりにも有名だ。父と息子でこのステップを共有しているところが、この父子の関係性を暗示している。運命というよりも、戦争に翻弄された被害者としての体験を共有しているといった方がいい。戦争体験の闇を抱えながら、父は悲しみのステップを踏むのだ。
運命を描くとは、こういうことか
逆らえない運命の悲しさ
すごく静かな場面が続く映画だったけど、その静けさにグイグイと引き込まれた作品だった
ベネチア国際映画祭 銀獅子賞 受賞作品
イスラエルで暮らす中年夫妻の元に、ある日突然「息子ヨナタンが戦死した」という知らせが入る
ひどくショックを受けた夫妻だったが、やがて、それが誤報だとわかり…
たとえば、
友人に余計な一言を言ってしまった結果、その友人との仲が険悪になってしまい「あの時、あんなことを言わなければ良かった」と、ひどく後悔するが、
少し時間が経ってみると、「遅かれ早かれそうなる間柄だったんだな」と思うようなできごとがおきる
結局、その相手とは「仲たがいする運命」だった
そんな経験はないだろうか?
この映画を観ながら、そんな「逃れることができない運命」を思った
父も母も、息子ヨナタンに起きたことについて自分を責めているけれど、
そもそも、それはヨナタンに定められた運命だったのでは…
それは、何度やっても、最初のポジションに戻ってくるフォックストロットのように
そう考えれば、きっと、ヨナタンの両親も少しは気分が楽になるのではと思った
そんなことを考えながら、夫妻のダンスを観ていたら、涙が溢れてしまった
それが「もう、お互いに責めるのはやめよう」と言っているように見えたからだ
それよりもむしろ、「一日の通行人がラクダしかいないような過酷な環境に、検問所を置く必要性があるのかどうか」ということの方が問題だと思った
いつ沈むか分からないようなコンテナでの生活を強いられている彼らに、事故が起きたのは、必然としか思えない
だから、責められるべきは両親の言動ではなく、無駄が多すぎる軍隊のあり方なのではないだろうか
セリフが少なく、説明が極端に少ない映画がだけれど、そこに描かれる闇はヨナタンの家にあった抽象画のように深く、
「運命は踊る」というよりも「運命に踊らされる人々の話」だと思った
面白い
日常と戦争が隣り合わせのイスラエルの苦悩
マオズ監督に踊らされる
戦場で一人踊るダンス、その姿は運命に翻弄される人間像そのもののようだった
この作品のファーストシーン、行き交う車も無い何処辺境の地を只ひたすらに車が進んで行く。
そしてシーンは一機に変わり、映し出された処は、息子の戦死の報を受ける両親や家族の混乱するシーンが延々と続いて描かれて行く。
そしてこの様子を時にカメラが天井からのショットで描いてゆく。
それは観る者に、今ここで繰り広げられている物語を登場人物と同じ目線の同次元で捉えるのではなく、上から観察する事で、どこかに人の運命を司り操る、人知を超えた神と言う存在がいるとでも言っているようなカメラワークもクールな様であり、しかし逆に観る者の心を物語の細部へと誘ってゆくこの撮り方も迫力があった。
劇中で、息子ヨナタンの訃報を受けた父親のミハエルがその知らせを自分の母に告げにゆくシーンがあった。そのシーンでは自分の孫の死の知らせを受けたにも関わらず狼狽する事も無く、淡々と事実を受け入れる年老いた老婆の様子が映し出される。
その様を認知症の一種と捉え、この老婆の様子を憂い気遣う家族のシーンもあったけれど、これはきっと年老いた老婆にとり、死の世界は余りにも身近で、いつも自分の際にいる友の存在で有るような当たり前の世界と捉えている感覚が有るのだろうと思う。
この作品では一人の人間の生死を巡っても、人それぞれの自己の立場や故人との関係に因っても同じ人間の死で有る筈の事実が、それぞれに違った意味や形を呈していく事の当たり前だけれど、この不思議な世界を描き出してゆく。
昨今の日本を含めた先進諸国では、引き寄せ等が流行り、自己の人生は自己の思い描いた通りに作り替える事も可能かもしれないと言う、人間の人生の質という物は、それぞれ自己の管理責任に因る処が多いと、人の生まれながらに持つ運命の存在を軽視する捉え方も有る一方で、本作のように人の運命の不思議さに切り込んでゆく作品が作られている事は実に面白かった!
私は神だか何だかは知らないけれど、人が存在し生きると言う事には、何らかの力が必ず介在していて、私達を生かしてくれているように感じながら日々を送っているのだが、あなたは本作を鑑賞して、人の運命をどのように捉えるのだろうか?
私はこの映画のラストを観て、人間が生きると言う背景にはきっと必ず、こんな不思議な運命の存在が大きく横たわっているに違いないと感じずにはいられなかった。
全21件中、1~20件目を表示