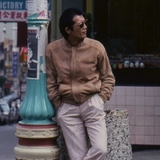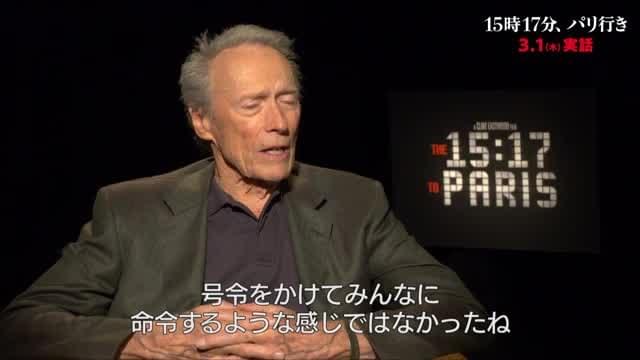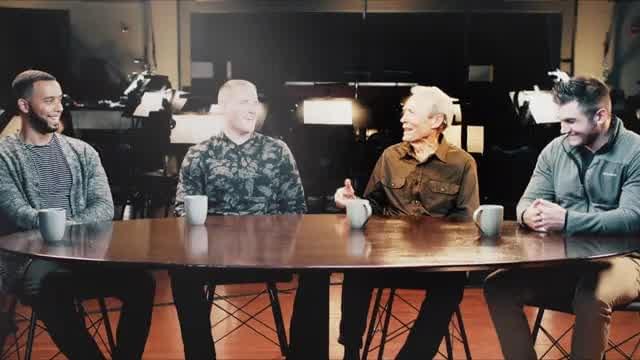15時17分、パリ行きのレビュー・感想・評価
全329件中、1~20件目を表示
当事者起用の狙いは
日本においては押しも押されぬ大巨匠といった扱いのクリント・イーストウッド監督だが、本作でもサラリと良い映画を撮ってしまっている。この時はどう撮れば良いか、ああいう場面ではどうすべきか、骨身に染みて映画の撮り方を知っているという印象を与える。指摘しやすい個性を持った映像ではないが、最後まで釘付けにさせる手腕に衰えは見られない。
本作では、事件の当事者をメインキャストに据える大胆な方法を採用した。こうした手法はメジャーハリウッド映画では珍しいが、しばしば用いられており、古くは映画史上最初のドキュメンタリーフィルム『極北のナヌーク』まで遡れるかもしれない。最近ではダニス・タノヴィッチが『鉄くず拾いの物語』で実践している。
この手法の肝は虚実の境にいかに迫れるかということだ。映像はそこにある様をそのまま切り取れる表現手段だが、映像の演出は嘘をつく技術でもある。キアロスタミの『クローズアップ』はそのことに最も自覚的な作品のひとつだが、本作はそうした先達の作品群と比べれば虚実の境を追求する姿勢は薄い。
なので当事者の起用自体は筆者はあまり大きな意味を感じなかったが、それでも上質に映画に仕上がっているし、等身大の彼らの活躍に胸打たれた。人生の積み重ねに焦点を当てたのも良い狙いだと思う。
異色作とはいえ、巨匠ならではのアウトサイダー的な目線はしっかりと刻印
もしもこの映画を、監督名を伏せた状態で観せられたとしたら、私は「何だこりゃ!」と突っ込んだかもしれないが、その見方は決して正しくない。むしろ本作はきちんと監督名を踏まえた上で臨むべき映画なのだろう。
テロ事件を描いているとはいえ、それは『ユナイテッド93』とは恐ろしくかけ離れた構造を持つ。「当事者たちを起用する」という驚きの決断もさることながら、テロそのものよりも、彼らが幼少期から辿ってきた人生に何一つとして無意味なものなど無かったのだという「運命の導き」に焦点を当てている点もまた、イーストウッドらしいアウトサイダーへの温かい目線だ。
学校にも馴染めず、軍隊生活でも脱落を繰り返し、しかしそのアウトサイダーの彼らが、何かを成し遂げ、脚光をあびる。その姿を描くのに、本作もまた、教科書通りの作りを放棄して、見たこともないようないびつなアウトサイダー的な作りで臨んでいる点こそ非常に興味深い。
正直いうと、面白くはなかったです
歴史とは、英語でhistory 神の計画が語源だそうです
15時17分、パリ行き
2018年公開
2015年8月に起こった実話の映画化
主人公3人は本人が演じています
つまりイーストウッド監督の狙いは、できる限り事実を忠実に再現したいということです
それは、映画的に盛った演出を排した映画を撮るということを意味しています
なので、普通の映画のような構成や感情の盛り上げとか、掘り下げて観客の感動や共感を得るとかという計算は投げ捨てられています
だから、ここをこうすればもっと盛り上がるのにとか、感動するのにとか、カタルシスがあったのにとかついつい思ってしまいますが、それは最初から監督は目指していないと言うことだったと思います
むしろ、そう感じて欲しかったのだろうと思います
そうなってこそ、本作は成功だと、監督は考えていたのだと思います
冒頭の映像からして、YouTubeの素人動画みたいな映像で始まります
もしかしたら、本当にiPhoneで撮影したのかも知れません
劇中の観光シーンなどはYouTubeそのままの映像です
わざと意識して模しているのかもしれません
そのように、普段私達観客が目にしている演出のない世界の中で、異常な事件が起こるその光景をそのまま映画にすることで、神が人を選び動かしていることの人智を超えた運命の不思議さが本当にこの世の中にあるのだと浮かびあがるということを狙ったからだったと思います
そんなこと頭で考えてみても学生の自主制作ならともかく、劇場用映画として成立してしまうのですから、やはりイーストウッド監督の手腕のものすごさを感じ思ました
歴史とは英語でhistory
彼の計画という語源だそうです
いざそのとき、あなたなら動けるでしょうか?
普通の人間なら逃げだすか動けません
しかし、あらかじめ神の計画にそうなっているのなら、何も考えていなくとも勝手に身体が動いているのでしょう
だから本作とは、神が人をえらび奇跡を行ったその瞬間を撮るということなのでしょう
落ちこぼれの三人が小学校から友達になることも、主人公達がナイトツアーで酔いつぶれて二日酔いになってしまうのもすべて、神の奇跡の瞬間だったことにほかなりません
私達の毎日の一瞬一瞬がすべてそうなら?
ありとあらゆることが神の計画による介入なのなら、人間の個人の意思とか、努力とかは全く無意味なのでしょうか?
きっと監督はそこまで観客に考えさせたかったのでないでしょうか?
ラスト間際、車椅子に乗ったスペンサーが次のように独白します
「神よ、私を平和の道具にしてください
憎しみには愛をもたらし
諍いには赦しを
疑いには信仰を
絶望のあるたころに希望を
闇のあるところに光を
悲しみには喜びを
人は与えることで受け
赦すことで赦され
死ぬことで永遠の命に甦るのです」
2018年な本作公開以降
アメリカは世界の警官を辞めアフガンから逃げるように撤退しました
平和の道具になるなど、もうまっぴらだと言っているようです
さらに時は流れて2025年、ガザ紛争にもウクライナ戦争にも米国はもう決して平和の道具にはなりたくないようです
それでも、神の計画がそうであるのなるのなら、より人間一人一人の意思や努力こそが一層神から求められているのかもしれません
ますます暗くなってゆく21世紀の暗闇のなかで光を求めることの意味を監督は普通の人間の私達に考えて欲しかったのではないでしょうか?
そんなことを考えさせられました
前評価、前説を知らず良かった
本人映像で
自分にとっていい映画とは、先の展開が読めない映画だ
やはり自分にとっていい映画とは、先の展開が読めない映画だと確認した一本である。本当の事件を扱った様子なので、映画の最後のシーンに事件の当事者をちょこっと出すだろうと、見ていたら、ずっと出ていた3人組がサングラスをかけてパレードに参加しているシーンがあった。映画のタイトルから調べてみると、イーストウッドが監督で、実際の事件の当事者を映画に起用したことを知った。なぜ普通のアメリカ人3人組の生活やヨーロッパ旅行の描写を見ていて、自分が目を離せないのかが、監督の意図された描写だからだと理解できた。列車内での事件でも、トイレにこもった人物があやしいと気づいた最初の2人の若者の乗客のほうが、状況判断がすぐれていると思う。ぼんくら3人組は事件に巻き込まれて、事件を知り、特に、空軍上等空兵スペンサー•ストーンが、今まで学んでいた軍隊の日常訓練成果が自然に出てしまって、テロリストを制圧し、負傷した乗客の手当てをしたと、意外と淡々と描いている。監督も大げさな映画撮影テクニックを使っているように見えないが、違うところで、つまり、事件の当事者を多く出演させたり、フランスの事件の起こった場所で同じ型の列車を使って撮影したことが、視ている者の無意識に働きかけ、先の展開が読めないと感じる映画にしているのだろうと思う。
神への祈りの言葉や冗談めいた「人生は導かれている方向に進んでいく」という会話がそれとなく繰り返され、事件でケガをし手当されたスペンサーがプラットホームに準備された車椅子に座り、後から出てくる乗客を観ているシーンなどが、なぜか印象に残った。いい映画だ。
普通の善き人々
スペンサーの成長
今作でイーストウッド監督が描きたかったのは、スペンサーの成長なのだと思う。昔から問題を起こしてばかりで、何も成し遂げていない。だが人を助けたいという気持ちだけは人一倍持っていた。そんな彼が偶然列車での事件に遭遇して、勇気を出して犯人を止めた。彼の願いが叶った瞬間だった。そこまでの彼の半生を丁寧に描くことで、ストーリーに単なる事実の再現に留まらない深みが出たように思う。彼は、希望の職種に就けたかどうかは大きな問題ではない、それよりも何をするかが大事なのだということを、学んだのではないか。
途中で出てくるヨーロッパの街並みが綺麗なのも良かった。特にイタリアがピックアップされていて、映画を観ながらローマやベネツィアの美しい観光地を堪能できたのが良かった。ただ、場面がいつ切り替わったのかよく分からない(いつの間にかイタリアからドイツにいるとか)箇所がしばしばあり、そこは気になった。
本人が俳優として出演しているというのは事前に知っていたが、自然な演技で違和感は全くなかったところも良かった。
究極のリアリティの追求
ストーリーは考えさせられるが?分かりすぎ。
BSで録画視聴。
この映画はまさかのクリント・イーストウッド監督に驚き。気に
なったので観た。
ストーリーは確かにテロ事件を防いだ三人の若者の話。内容的にも
色々考えさせられた。
しかし、ストーリーがはっきりしすぎているし、分かってしまった。
消化不良で残念な作品だった。
軍が劣等生を育てた
淡々と過ぎる日常が
憎しみには、愛を。赦すことで、赦される。
この3人だから、映画にしたのだ。
劇映画の説得性を高めるため、衝撃的な実話の映像化にリアリティを付与するため、事件の当事者である3人の若者を本人役として起用した。
というのは完全なる間違いである、事態は全く逆であり、
“この3人を主演にするために、3人にまつわる劇的な事件を題材として取り上げた”のだ。
そんな出鱈目を吹聴したくなるほどに、スペンサー・ストーン、アンソニー・サドラー、アレク・スカラトスの3人の若者は、個々の持つ被写体としての魅力、そして3人の関係性によって、同世代としての羨望と共感の雨を心にさめざめと降らせてくれた。
3人は幼馴染だった。
キリスト教系のスクールで、教師に目の敵にされていた3人。
大学生になり、軍隊に入り、遠く世界の果てにいながら、オンラインで近況を報告しつつ旅行の予定を立てる。
旧友との久しぶりの再会、かつて共有した時間に裏付けられた気楽さを享受しつつ、お互いの少し真剣な思いを交換する。
劇的でも何でもないシーン、アムステルダムのクラブの翌日、昼のカフェで遅い朝食を食べる3人がパリ行きを決める会話の場面に、深い感動を覚えたのは、彼らが今の若者の実直さ、堅実さ、素直さを、いささか理想的な形で代表していることに対する羨望と共感によってである。
映画を観る自分は、白人でも黒人でも、軍人でも、パリの旅行者でも、仏大統領に名誉勲章を授与される英雄でもない。
しかし間違いなく、彼らと同じ、現代を生きる若者の一人である。
彼らが僕たちを代表してくれた。
そしてイーストウッドが、彼らの実直で、堅実で、素直な姿勢を敏感にキャッチし、それをありのまま画面に乗せるという、大胆かつ繊細な決断をしてくれた。
そのような繊細な感覚によって人物を見ることができる者のみに、映画を観、語り、撮る資格があるはずなのだ。
と同時に、それは至極当たり前のことであると信じたい。
素人のくせに良い雰囲気
全329件中、1~20件目を表示