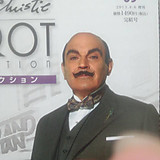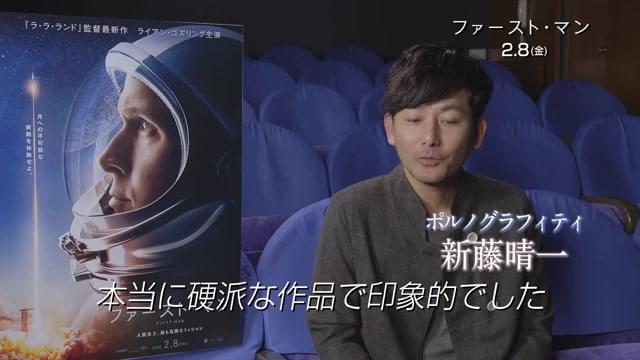ファースト・マンのレビュー・感想・評価
全372件中、341~360件目を表示
地味。でもそれが「人」というもの。
宇宙空間で起こる様々なトラブルを乗り越えて偉業を果たし、奇跡の生還…といった、いわゆるSFモノとは違う。
キャラクターの体温さえ感じる距離感で、人間の姿を上品に、穏やかに、そして切なく描いたヒューマンドラマだった。
派手な演出は少ない。
「ゼロ・グラヴィティ」とか「アポロ13」みたいなモノを期待すると物足りなく感じるかも。
宇宙でのシーンについても、『神の視点』とも言える「引き」の画はほとんどなく、観客に与えられる「画面の揺れ」と「計器に現れる数字の動き」「小さな窓からわずかに見える外の景色」といった情報から何が起きているかを感じる、つまり搭乗員と同じ『人間の目線』で事態を乗り越える、というのがこの映画のスタンス。
そして「音」。
音楽の良さはデイミアン・チャゼル監督作品である以上もちろん言うまでもないが、今回も、小さな音、その距離や方向に至るまでこだわり抜いた感じは否めない。
鑑賞中、音の発生元を求めて振り向きたくなったのは私だけではないのでは?
主人公のニール・アームストロングは決してスーパーヒーローではない。過酷な訓練に耐え、社会の批判の矢面に立たされながら、それでも口数は少なく、感情的になることもない。だからこそ観客は「変人」にさえ見えてしまう彼の内面を覗きたくなる。彼の見ているモノを、彼の視点で、彼と同じコクピットに搭乗することで感じ…たい。
ラスト、(月面着陸は史実だからネタバレではないよね)大切な人を失いながらついに月面に辿り着いた彼が何を思い、何をしたのか。
世界の歴史に名を残した偉人の物語ではなく、一人の職業人であり、一人の夫、一人の父親としての彼の姿を描いている。
極端に言うと、ある男性に焦点を当ててドラマを作ったら、たまたまそれが人類で初めて月に降り立った人物だった…と言ってもいい。
『人間を描く』
鑑賞直後よりも、家に帰って思い出し、噛み締めるほどにその作り手の想いが伝わってくる気がしている。
観た方なら分かるはず。
あのラストシーンの二人が、何と可愛らしく、優しく、何と美しく、愛おしいことか。
奥さんのクレア・フォイの演技も素晴らしい。この人、ホントに役によって別人に見える。
とっても大人な映画。
今までの監督作品は皆好きだが、中でも本作が一番好きかも…というか、時間が経ってどんどん好きになっていく自分がいる。
ぜひ、あの「月」を大きなスクリーンで感じて頂きたい。
不覚にも泣けてしまいました。
一歩そしてこれから
アメリカ本国公開してから3カ月あまり公開を待っていました。
デミアン・チャゼル監督作品。前作の『LALALAND』で主演を果たしたライアン・ゴズリングが今作では月に初めて行ったニール・アームストロング船長を演じた。
アームストロング船長の事は月に初めて行った人として記憶されているがその人となりは知るべくもなく今に至っていた。
オープニングから映画『ライトスタッフ』でのX1での飛行シーンの場面が思い出された。
X15の試験飛行。
その間たくさんのパイロットが亡くなっていた。
そしてニールの娘も病気で失っている。
その喪失感が彼に重い影を残している。
その喪失感から逃れるようにNASAのジェミニ計画へ応募する。
当時ソビエトとアメリカの覇権争いが激化。
そしてジェミニ計画を進めていく中でもたくさんの仲間たちが散っていった。
新天地でもニールの喪失感は埋められない。
それでも彼は宇宙への道に何か救いがあるのではないかと突き進んでいく。
映画はゴズリングの憂いを帯びた演技が光る。
そしてニールの妻役には先日見た『蜘蛛の巣を払う女』で主演をしていたクレア・フォイ彼女も死と隣合わせの宇宙飛行士の妻役を見事に演じていた。
『蜘蛛の巣を払う女』のリスベット役よりこちらの方がしっくりきた感じがする。
映画はニールの喪失感や葛藤を淡々と描いている。
映画的には静かに進むが途中ここのシーンにはこの効果音はかえって安っぽく感じさせるところもあったが概ね評価したいと思う。
この映画見終わって『アポロ13』が見たくなった。
エンドロールにはスピルバーグの名前もあり何故か納得。
今や宇宙競争はアメリカNASAだけでは進まなくなった。
月から次は火星へとターゲットを変えてるが近い将来にはそれも達成する事だろうがその過程でまたたくさんの人が散っていくだろう。
その周りにはニールと同じ気持ちを抱くだろう。
4DXで見るべき
着陸直前の”1202”アラーム”に、感動は倍増。
物事を最初に成し遂げるということは、どれほど偉大なことなのか。多くの人がたどったあとでは、それは、"あたりまえ"になってしまう。
けっして例えが適切だとは思わないが、それは"妊娠・出産"に似ている。たいへん喜ばしいことで、周囲の家族からすると、"いつ生まれるのか"と待ちどおしく、"男の子か、女の子か"で気をもんだりする。まさか現代で"命の危険と隣り合わせ"ということはすっかり忘れている。
この映画を観て、"なんてことないロケット映画"とか、"「アポロ13」(1995)のほうがドラマティックだ"という感想を持つとしたら、すでに麻痺している。
多くのアニメや映画で、地球と宇宙を行き来するシーンを観すぎていて、"産みの苦しみ"を忘れているだけ。もとより出産の痛みなんて、オトコには分からないが…。
約50年前のロケット性能は、今から考えればオモチャ以下である。コンピューターの性能を表わす単位、FLOPS(毎秒浮動小数点演算)でいうなら、月に到達したアポロの誘導コンピューターは初代ファミコン2個分程度である。いま手元にあるスマホと比べたら、100億倍でも足りない。
デミアン・チャゼル監督と脚本家のジョシュ・シンガーは、"常に死と隣り合わせ"のミッションであることを描くためだけに全力を尽くしている。
映画冒頭、ニール・アームストロングが宇宙飛行士になる直前、幼くして病死した娘・カレンの話は単なる家族エピソードではない。子どもが普通に成長することも、"あたりまえ"ではないことを表わしている。アポロ計画で亡くなった多くの宇宙飛行士の失敗や、何度も描かれる葬儀のシーンもそうだ。
一方でアームストロングの家族との団らんや、子供と遊ぶシーンは手持ちカメラで撮影することで、家庭用ビデオの雰囲気を出し、"生きていること"と"死んでしまうこと"の対比を強調している。
この映画は、アームストロング船長の伝記でありながら、ことさら月面着陸をサクセスストーリーとすることなく静かなエンディングを迎える。
失敗に次ぐ失敗に、"命と税金の無駄遣い"と反対運動をしていた世論も、結果として月面着陸のテレビ中継に歓喜する様子は、"出産"を喜んでいる第三者と同じである。
本作はIMAXカメラで撮影されているので、IMAX上映を選択するのもいい。しかし個人的に心からおススメしたいのは、4D系で観ることだ。
4D上映自体が、多くの作品を経て進化しつづけた結果、とても細かなモーション効果を表現できるようになっている。本作の冒頭から繰り返される、"飛行訓練シーン"や"ロケット実験"が、まさに飛行士の目線で"体験できる"。ともすると、"絶対に宇宙飛行士になんかなりたくない"と思わせるほどの疑似体験だ。
チャゼル監督の意図した、静と動のコントラスト比もより大きくなる。"アトラクション効果なんていらない"、なんて決めつけないで。映画「アポロ13」(1995年) の頃は、4D上映がなかったのだ。
最後に、知っている人と知らない人では感動がまったく違ってしまう重要なシーンがある。
月着陸船イーグルが、月面へのアプローチ中に出てくる[1202アラーム]だ。劇中では全く説明されない。アームストロング船長も、1202なんて知らない。「1202アラームの意味を教えてくれ」となる。
これは32歳の女性プログラマー、マーガレット・ハミルトンの開発した、偉大なるソフトウェアなのである。ヒューマンエラーを回避するためにひそかに作られた。万が一、何らかの原因でコンピューターがフリーズしそうになると、宇宙飛行士の生死に関わる重要なプログラムだけを再起動させる。そしてそれを知らせるのが[1202アラーム]なのだ。
この時点で、宇宙飛行士が何らかのミスを冒しているという意味でもあるのだが、この画期的なプログラムがなければ、アポロは月面着陸できなかった。
だから[1202アラーム]が何度鳴っても、オートパイロットは正常に作動し続けているという意味であり、「問題ない。着陸任務続行!」なのである。
このエピソードを知っているだけで感動は倍増する。NASAで働いた女性技術者・科学者たちの貢献は「ドリーム」(2017)でも描かれていたが、ほんとうに多くの科学者のバックアップがアポロを月面に導いていた。
(2019/2/8/ユナイテッドシネマ豊洲/シネスコ/字幕:松浦美奈・字幕監修:毛利衛)
家族の不安がクッキリ
顔芸すごい
実にいい映画。
名作と言えます。
初めて月面に辿りついた、ニール・アームストロングを描いた作品。
(「黒人ミュージシャンとして初めて月で演奏した人・サッチモ」って話じゃないから)
ニールの視点で家族や同僚への想いや、ミッションへの義務感と恐怖との間で苦しむ心の葛藤を中心に描写していました。
ストイックで真面目に仕事へ打ち込む「プロ」と、子どもに心を寄せる「父親」、二つの姿がどちらもニール。
ただし、その映画テーマゆえ、宣伝で見せていた宇宙開発的な描写が少ない。
マーキュリーもアポロも、開発シーンはほとんどなく、打ち上げなどだけの最小限のシーンしかない。
象徴的なのは、打ち上げより難しく、技術的なドラマ満載なはずの、各ミッションにおける帰路~着陸のシークエンスがないですのよ。
そこに期待して行っちゃうと、肩透かしを食らうはず。
小説で言えば一人称の映画ゆえ、ニールの視線に同化できれば、月へ向かう男の感情や思考をトレスできるといった指向であり、実体験のような錯覚を覚えるかもしれません。
ただ、心を描くのに、目や表情を追うので、ニール(ライアン・ゴズリング)の顔のアップばかりって印象を受けました。
いや、奥さんや同僚、政治家も顔のアップだらけ。
生活を圧迫して税金を戦争と宇宙開発に回す政府へのデモやってる、黒人すらアップ。
是非ともこの映画の前後どちらかで『七つの会議』を連続で観て、「日米顔アップ顔芸大会」を味わっていただきたい(七つ~はコメディですけど)。
一足お先に、月旅行!
臨場感たっぷりのIMAXで鑑賞しました。
有名すぎる実話なので、もちろん結果はわかっています。
その結果に至る過程を描いた映画です。
原作は「ファースト・マン 初めて月に降り立った男、
ニール・アームストロングの人生」です。
ドラマ性やエンターテイメント性はなく、ドキュメンタリー
映画です。
主人公の性格は控えめで、音楽も控えめで、セリフより
映像で伝えようという演出を理解しておく必要があります。
「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、
人類にとっては偉大な飛躍である」という有名な
セリフを、米国を前面に出さないことで、映像化
できているところに良い印象を受けました。
なぜ、米国がアポロ計画を遂行したのかは、ケネディ米国
大統領の以下の演説を知っておくと良いです。
「我々が10年以内に月に行こうなどと決めたのは、
それが容易だからではありません。
むしろ困難だからです。
この目標が、我々のもつ行動力や技術の最善といえるものを
集結しそれがどれほどのものかを知るのに役立つこととなるからです。
その挑戦こそ、我々が受けて立つことを望み、先延ばしする
ことを望まないものだからです。
そして、これこそが、我々が勝ち取ろうと志すものであり、
我々以外にとってもそうだからです」
「アポロ13」、「ライトスタッフ」や「ドリーム」
を鑑賞して、良かったと思う人にはお勧めできます。
登場人物は、宇宙飛行士、家族と地上スタッフです。
アポロ計画は、40万人もの人々が関わった国家プロジェクトで、
映画で描かれているのはその一部です。
ディーク・スレイトン(カイル・チャンドラー)は、
元宇宙飛行士で、心臓に病気が見つかったために、
米国航空宇宙局の宇宙飛行士育成部門の責任者になり、
宇宙飛行士達にアポロ計画の説明を行い、
誰をどの宇宙ロケットに搭乗させ、誰を船長にするか
も伝えます。
ボブ・ギルルース(キアラン・ハインズ)は、米国有人
宇宙船計画の責任者です。
X-15は、母機であるNB-52の主翼下に吊るされた状態で
高度13kmまで上昇した後に空中発進するジェット
エンジンではなく、ロケットエンジンにより高高度まで
上昇出来る能力を持つロケットプレーンです。
X-15で得られた極超音速下での空力特性や熱力学的影響
などの研究結果は、後の宇宙開発に貢献しました。
14万フィートは、42kmです。
米国の有人宇宙飛行計画は、マーキュリー計画、
ジェミニ計画、アポロ計画という3段階で構成されています。
マーキュリー計画は、1人乗り宇宙船で地球を回る技術を
確立する計画です。
ジェミニ計画は、2人乗り宇宙船で最大2週間宇宙飛行し、
宇宙空間で2機の宇宙船が接近し、ランデブー(連結)
する技術を確立する計画です。
アポロ計画は、3人乗り宇宙船で、月周回ランデブー方式で、
月面着陸し、帰還するという計画です。
月周回ランデブー方式は、司令船と機械船が月周回軌道で
待機し、月着陸船が月面に降下し、着陸し、月周回軌道へ
帰還し、司令船と機械船とランデブーし、司令船だけが
宇宙飛行士を乗せて地球に帰還します。
月周回ランデブー方式は、月着陸船を軽量化し、地球から
の発射総重量を最小限に抑えることができるために採用され
した。
宇宙船は、司令船、機械船と月着陸船で構成されています。
司令船は、円錐形で、3人の宇宙飛行士を月軌道に乗せ、
宇宙から帰還させ海上に着水します。
機械船は、メイン・ロケットや姿勢制御用ロケットおよび
その燃料、燃料電池、通信用アンテナ、水や酸素のタンク
などを搭載しています。
月着陸船は、月面に降下し、着陸し、月周回軌道へ帰還し、
司令船と機械船にランデブーします。
この宇宙船を打ちあげるロケットがサターンVです。
サターンVは、全高110.6m、直径10.1m、重量 3,038トンです。
フォン・ブラウン博士が、サターンVを開発しました。
ニール・アームストロング船長達が降り立った場所は
「静かの海」で、機動戦士ガンダムでは「フォン・ブラウン市」
となっている場所です。
アポロ11号が、地球を飛び立ち、月に着陸し、地球に帰還
するまでに要した時間は、8日と3時間18分35秒です。
月着陸船の航法・誘導コンピュータが予期しない警報
"1202" と "1201" を発生します。
月面着陸の際には使用しない司令船とのランデブー用の
レーダーが、緊急脱出する事態に備えて入っていたためです。
航法・誘導コンピュータが月面着陸に使用する高度測定用
レーダーとランデブー用レーダーのデータを処理しきれずに、
警告を発し、月面着陸に使用する高度測定用レーダーのデータ
を優先処理しました。
このおかげで、無事に月面着陸できたということです。
ニール・アームストロング船長達が月面で過ごした時間は
2時間15分ほどです。
突き動かすもの
ニールを突き動かすもの、それは、家族のもとに生還するという、生への執着、信念だ。
冒頭のシーン、ジェミニ計画のドッキング後のアクシデント、多くの友人が亡くなった後のテスト飛行…、国家の威信や、科学の進歩など様々な思惑やモチベーションが渦巻くなか、全編を通じて、ニールは感情を抑制しながらも、確実に生を掴みとっていく。
ただ、アポロ11号計画で月面に降り立ち、娘を回想するシーンで、もしかしたら彼は亡くなった娘に会うために、死んでも構わないと思っていたのではないかと考えさせられる。
旅立つ前に、ジャネットに促されて対峙した二人の息子が、彼を死への欲望から生に引き戻したのではないか。
そして、娘に対して、そっちに行けなくてゴメンねと。
家族は勇気をもってニールを送り出し、ニールは再び家族の待つ地球に立つ。
そう、これは、家族の物語なのだ。
胸が痛む、辛い道のり
私は感動しました。丁寧に描いていると思う。
【人類の、いや男のロマンだね。大きな犠牲と引き換えに・・・】
初日に観てきました。
1969年人類初の月面着陸を成し遂げたニール・アームストロングの話。
誤解を恐れずにあえて言うと…
男って、すごいな、と。
こんなこと、やっぱり男にしかできないよね?
命がけの、国の威信を背負っての、当時の科学技術から言うと無謀と言っていいチャレンジに賭ける男たち。
どんどんミッション途中で殉職していく同僚たちの後に、続けますか?
実際アームストロング自身も何度か死にかけてます。
厳しい訓練に、求められる高い頭脳、何かあれば一斉にマスコミに叩かれ、国からは半端ないプレッシャーをかけられ。世間は反対運動まで。
隊員は精神的にも参って、家族まで巻き込む。
並大抵の身体能力と精神力では決して耐えられない任務ですよね。
当時は米ソ冷戦時代真っ只中。宇宙開発が国力の象徴だった。
まだようやくコンピューターの元祖みたいな機械の時代に、よくぞ月に行けたものです。
(この映画に興味のある方は是非『ドリーム』も観てほしいな〜NASAの偉業を陰で支えた天才数学者の黒人女性の実話映画)
つくづく人間とは、飽くなきチャレンジをしたがる生き物なのですね?
劇中でケネディが演説していました。
「困難だからこそ、挑むのです」と。
IMAXで観たから、まるでアトラクション並みの迫力。
リアルに月に行ってきた気分。宇宙船に酔う〜
いやでも、いい映画だと私は思う。
レヴュー読んだらけっこう賛否両論ですが。
事実は事実としてしっかり受けとめたいし、ライアンの演技がやっぱり好きだから!
大好きな「ララランド」と「セッション」のチャゼル監督だから。
奥さん役のクレア・フォイも良かった。
この映画を作った意味が分からない
月面着陸した初の人類
月面着陸に成功した初の人類、
ニール・アームストロング船長の偉業を描く作品。
題材からきっと困難な末のサクセス感動物語だろうと
思って見に行かれる方が多いと予想される中、
「ララランド」のチャゼル監督作品という前提を知り
見に行かれる方とで覚悟の度合いが変わるであろう作品。
冒頭、葬儀で棺が土に埋まるのを見つめる
ニールを描くシーンがあるが、この映画の本質はそこにある。
画面構成がニール視線で常に進み、
テスト飛行や訓練、初のドッキングを行うジェミニ8号でも
椅子に座った状態から見える視点で画が進む。
数10センチの小さな窓からの風景しか見えない。
火が出ていると大気圏に突入しているのか
事故による火災なのかもわからない状態。
まさに乗員目線での鑑賞を強いられることとなる。
すでに鑑賞されている方の指摘として
ニールが多くを語らないため、何を考えてるかわかりにくい
という意見が多く見られたが、
彼の心理状態は「死人」状態であると推測する。
ジェミニに乗った時、ハッチを閉じられる視点は
まさに棺の蓋を閉じられた状態。
事故があれば死に直結する宇宙において
宇宙船は言うなれば棺桶に他ならない。
この作品の宇宙飛行士は死を受け入れた人物であるという
チャゼル監督のアプローチ手法だったのかと。
一時期、子供たちの憧れる職業の代名詞でもあった
宇宙飛行士の心理的な重圧や過酷さを重点にしていた。
また宇宙飛行士然り潜水艇などの外界と長期にわたり
隔離される環境に置かれる乗務員はストレスやパニックの
耐性が高い人物しか選ばれないと聞く。
いかなるトラブルがあっても現状を瞬時に把握し
今ある環境で問題解決できる冷静な能力を要求されるという。
そういう側面から言えば今作のニールの冷静さは
リアリティを持って描いていると言える。
またニール本人も寡黙で表情を変えないことで
有名であり、実の息子が映画の監修に関わっているため
きっとライアンが演じるニールと近しい感じだったのでしょう。
以上でまとめた箇所を添え本作品を未鑑賞の方は
ご覧頂けると監督の描きたい部分が少しは見えるのではないでしょうか。
英雄も一人の人間。
アームストロングを英雄ではなく、一人の人間として描いている映画。全体的にとても静かな映画でした。ミッションを成功した時、月に辿り着いた時も喜びを大袈裟に表現することは無い人です。そんな彼が娘のことに関してだけ感情を大きく出します。英雄も一人の人間なんだなと思わされた瞬間でした。Ryanの繊細な演技に引き込まれます。
狭いコックピットの中の映像、音がとても繊細で、恐怖がこちらにも伝わってきます。未知な宇宙はとても怖く、美しいと思いました。
静かな海に降り立った彼に相応しい静かな映画でした。
ニール
デミアン・チャゼル監督作品、現在までハズレなし。
「セッション」「ラ・ラ・ランド」と違って、今度は現実の人物が題材ということで、少しチャレンジではないかと危惧していたが、不安払拭。
英雄として、半ば神格化されているアームストロング船長を、ひとりの人間ニールとして、夫、父親として描いていて、とても好感が持てた。
1960年代の事だけに、今からすればポンコツと言うべきロケットで宇宙を目指すわけだが、ロケット噴射というより爆発、金属の軋む音がすごい船内、メーターはほとんどアナログメーターなど、よくこれで…という設備が臨場感があって感激した。
設備テストの事故などで、次々と仲間の命が失われる中、必死に不安と戦う心情が、観ているこちらに浸み込んで来る。家族を前にしながら、死と向き合わなければならない仕事というのは、とてもハードだったろうとよくわかる。偉業は成し遂げたのは確かだが、決してスーパーマンではなく、悩んだり迷ったりウンザリしながら、準備を淡々と進めていったのだ。
ヒーローを描いたり、愛国心を煽る描写は一切なく、月面に立っても国旗を立てるシーンは無く、家族に思いを馳せるシーンが描かれる。このメッセージが、逆に熱く感じる。
決して派手な映画ではないが、ものすごく清々しく、心に浸透してくる内容で、共感が持てた。
全372件中、341~360件目を表示