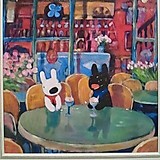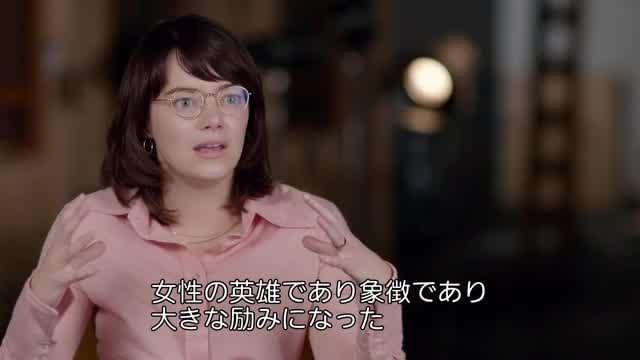バトル・オブ・ザ・セクシーズのレビュー・感想・評価
全134件中、1~20件目を表示
誰もが輝きながらクライマックスへと突き進む高揚感は相変わらず
最初はダニー・ボイルが監督を務める予定だったとという。だが新作で多忙となり『リトル・ミス・サンシャイン』の夫婦監督が代打を務めることになった。この仕切り直しをきっかけに、本作はなんとも夫婦監督らしい方向へ舵を切り、夫婦や恋人といった複雑な関係性にもスポットを当て、さらにはキングとボビー、両陣営が狂騒的なまでに一丸となって“伝説のエキシビジョン・マッチ”へとなだれ込んでいく描写にも弾みがついた。この辺りの構築力はまさに『リトル・ミス・サンシャイン』の作り手らしいところだ。
ストーンといい、カレルといい、決してモノマネにならない演技で物語の両極を担うキャラクターを全力で演じきってみせる。そこにアラン・カミングなどの芸達者が添えるささやかな存在感も旨味を最大限に引き立てる。結果、自らの個性で牽引するボイル作とは全く異なり、誰もが全員野球で精一杯輝きながら猪突猛進していく快作へ仕上がったのだ。
ラストの余韻が後からじわじわくる。
女性の地位向上を願う女子テニス選手と、女性蔑視のクソ野郎とのエキシビジョンマッチの物語……と、単純化して説明したくなるが、実際に観てみるとそんな簡単な話ではない。
例えば女性の恋人ができた主人公ビリーに対して、誰よりも先に事情を察して警告しようとするのはアラン・カミング演じるゲイのファッションコーディネーター。なぜなら彼は、女性の地位向上以上に、同性愛への差別と偏見の根深さを身に沁みて知っているから。
対戦相手のボビー・リッグスも、本気で女性蔑視なわけではない。悪ふざけで話題を集めて、注目とカネを引き寄せようとしているだけだ。
この映画を観ていて、ボビーが戦っている相手は実はボビーではないと思わせられる瞬間がいくつもある。女子テニス選手が解説員としてテレビに出演して、終始オッサンの司会者が片腕を彼女に回している気持ち悪さなど、解決されないが明示されている要素も多い。
最後にアラン・カミングが粋に〆てくれる台詞も、ジーンたち女性の戦いがまだまだこれからであることを示唆している。つまりこれは昔話ではないのだなあ。
ソフトなタッチで描く#MeToo運動の分岐点
1973年の"性差を超えた"エキシビション・マッチで対決したビリー・ジーン・キングとボビー・リッグスは、各々切実な事情を抱えていた。
ビリー・ジーンは当時のテニス界に蔓延していた露骨な性差別と、彼女自身のセクシュアリティとどう向き合い、どんな結論を導き出すべきなのか?リッグスは自らの身を滅ぼしかねないギャンブル依存症からどう脱却するのか?そして、双方にとってあるべき着地点へと向かうプロセスを、ファッションやメディア等、'70年代テイストを満タンにして描く映画は、今に続く#MeToo運動の歴史的分岐点を検証する。でも、そのタッチはあくまでもソフト。ビリー・ジーンと夫のラリー・キング、リッグスと妻のプリシラがそれぞれ悩み抜いた末に紡ぎ出す結論の、何と優しく、思いやりがあることか!?これは、社会的ムーブメントの陰で、夫婦とは?愛とは?そして、セクシュアリティとは?という普遍的な問いかけを観客に投げかけてくる、やっぱり「リトル・ミス・サンシャイン」の夫婦監督が作った最新作。流行や時代の風潮には惑わされない映画作家としての個性が際立つ1作なのだ。
ちゃんとガチのテニスシーンを撮っていてすげぇーってなった。
“Don't go around breaking young girls' hearts“ ウーマン・リブvsミソジニーはいつの時代も変わらず…。
1973年、女子テニス・プレイヤーのビリー・ジーン・キングと、男子テニス・プレイヤーのボビー・リッグスが行った男女対抗試合“バトル・オブ・ザ・セクシーズ“の顛末を描いたフェミニズム・スポーツ映画。
主人公ビリー・ジーン・キングを演じるのは『アメイジング・スパイダーマン』シリーズや『ラ・ラ・ランド』の、オスカー女優エマ・ストーン。
ギャンブル中毒の元テニス世界王者、ボビー・リッグスを演じるのは『リトル・ミス・サンシャイン』や『怪盗グルー』シリーズの、名優スティーヴ・カレル。
女子テニスウェアのデザイナー、テッド・ティンリングを演じるのは『バーレスク』『チョコレートドーナツ』の、名優アラン・カミング,FRSE。
製作は『トレインスポッティング』シリーズや『スラムドッグ$ミリオネア』で知られる映画監督、ダニー・ボイル。
「なぬ!“セクシー“だとっ!?」と思って鑑賞したあなた。残念ながらこれはそう言う映画ではございません。
女性初の10万ドルプレイヤーであるビリー・ジーンと、40年代を代表する伝説的選手ボビー・リッグス。性別も年齢も異なる2人の、意地とプライドと金を賭けたガチンコテニスバトルを描いた作品であります。
ちなみに、3万人を超える観客と、9000万人の視聴者を釘付けにした歴史的一戦のようなのですが、自分はこの試合の事を一切知りませんでした。と言うか、ビリー・ジーン・キングもボビー・リッグスも完全に初耳。以下は圧倒的なテニス弱者の感想となります。
ボクシングのモハメド・アリや野球のジャッキー・ロビンソンなど、社会運動の象徴として語り継がれる偉大なスポーツ選手が存在していますが、ビリー・ジーン・キングもその1人。女性やレズビアンの地位を向上させたとして、テニス界を越えて尊敬を集める人物なのです。
ちなみに、マイケル・ジャクソンの「ビリー・ジーン」(1983)と何か関係があるのか?と思って調べてみたが、どうやら全くの無関係の様です。…今まで意識した事なかったけど、これすげー歌詞だな💦
女性解放運動のシンボルとして世間をリードするビリーに対するのは、どうしようもないギャンブル親父ボビー・リッグス。映画を観るだけではただの中年ミソジニストなオッさんなのだが、実はウィンブルドンと全米選手権を制した事もある超凄腕。「母の日の虐殺」と呼ばれるマーガレット・コートとの試合だが、55歳のオヤジが年間グランドスラムを達成した名実ともに最強の女性選手を完膚なきまでに叩きのめしたと言うのは普通に強すぎる。ダメオヤジだからあまりそうは見えないが、これが『ロッキー4』(1985)のイワン・ドラゴみたいな見た目だったら映画のトーン自体がガラッと変わっていた事だろう。
50年以上前の出来事ではあるが、大言壮語と派手なパフォーマンス、人をおちょくる態度など、リッグスの描き方は完全に某アメリカ大統領そのもの。ユニークなキャラクターで大衆を惹きつけ、彼らを差別的な発言で扇動する事によって自らを教祖化していくというやり口、ついこの間の大統領選挙で見たぞっ!!
リッグスの描き方がどれだけ史実に忠実なのかはわからないが、本作が公開されたのは第1期トランプ政権の真っ只中。リッグスにトランプを投影しているのはまず間違いないだろう。本作で描かれている“性差の戦い“は今この時の政治情勢の暗喩であり、ただの史劇に終始していないところにこの映画の価値があるように思う。
フェミニズムかつLGBTQを扱った作品ではあるが、「女は善、男は悪」「同性愛者は正義」というような単純化が行われていない点も本作の美点。
ビリー・ジーンが不倫をしているのは紛れもない事実だし、ボビーの性格や家族への接し方には、むしろ好人物の風格さえ漂っている。作中随一の聖人、ビリーの夫ラリー・キングは男性な訳だし、ただ男を貶めて女性の素晴らしさを語るミサンドリーな作品ではない。
社会的に偉大な人物が家庭内でも清廉潔白とは限らないし、世間を騒がせるダメオヤジにもそうなった背景がある。そんな人間の悲喜交々が時にコメディとして、時に悲劇として描かれる。人生のままならなさがジワッと胸に沁みる事請け合いな映画である。
もちろんビリー・ジーンさんはとても立派な人物である。当時リアルタイムでこの試合を観ていれば、きっと彼女の事を応援していただろう。
だが、映画的には生真面目すぎるビリーよりも破天荒なボビーの方が面白い。事実、彼が積極的に絡む様になってから物語に拍車がかかる。逆に言えば、彼があまり活躍しない前半部分はテンポ感がゆっくりで、どこかスリリングさにかける。WTA設立の過程やそれが軌道に乗るまでの様子が丁寧に描かれてはいるものの、再現VTRを観ているかのような緩慢さがある。WTAの件はサッと流して、前半からビリーとボビーのライバル関係を軸に物語をガンガン進めるのも一つの手だった様に思う。
ひとつ気になったのは、ラリーがビリーの不倫に勘づくシーン。ビリーの洗濯物から彼女以外の女物の下着が出てきた事でピーンと来るのだが、冷静に考えて女所帯でツアーをしているのだから、下着が他人の物と混ざってしまう可能性も十分にある。それなのに「あっ!あのマリリンって美容師とデキてんな…」と察するのは展開としてあまりに性急すぎないだろうか。それだけラリーの勘が冴えていたのだろうが、そんな事ってあるかなぁ…。
知られざる歴史を知る事が出来たし、テーマ性やキャラクターの描き込みは良いものの、今ひとつパンチが弱かった。興行的にもイマイチだったようだが、もう少し思い切りの良いコメディに振り切っていたら結果は変わっていたのかも。
ただ、エマ・ストーンの演技は今回も見事。『ラ・ラ・ランド』(2016)でオスカーを獲得したすぐ後の出演作という事もあり、とにかく脂が乗り切っている。興行はともかく、演技面では彼女のハイライトと言っても良いのではないか。スティーヴ・カレルとの相性もよく、もっと2人が同じ画面に収まっているシーンを見てみたかった。
激しく火花を散らしたビリーとボビーだが、実はこの2人の仲は良かったのだとか。1995年にボビーが亡くなるまで、この友情関係は続いた。もしかすると、この“男女の闘い“は映画で描かれている様なウーマン・リヴvsミソジニーという単純な対立関係ではなかったのかもしれない。それとも、不良漫画みたいに「殴り合ったら俺たちダチ」という感じで絆が結ばれたのだろうか。
いずれにしろ、対立するイデオロギーの2人が手を取り合う事が出来たというのは寿ぐべき事態である。その未来を生きる我々も、彼らの柔軟さを見習わなければならない。
カラフルdays
男女不平等を打破したテニスプレイヤー!!
この公に男尊女卑を掛けた試合があったからこそ、少しは男尊女卑が解消してきているのかも。最後の字幕と写真で実話と知りました。スティーブカレルは本人に似せていてビックリ!!男尊女卑という言葉が死語になるのは、いつかなぁ。
メモ
マイケル・ジャクソンの歌にあるビリージーンは、この人からのインスパイアなのだろうか?(歌詞からしたら違うのかもだけど)
向き合うことの大切さ
予告からして、面白そうな雰囲気ビンビンの「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」。
期待に違わず面白かった!
でも、意外なことにボビーに感情移入した方が面白い映画なんじゃないかと、そんな気がする。
もちろん主人公は女性の地位向上を懸けてテニスコート上でも偉業を成し遂げたビリー・ジーンなんだけど。
やはり彼女がまだ活躍中の人であることが、一歩踏み出せない表現になっちゃってるのかな、という気がする。
対するボビーは自らを「差別主義の豚」と標榜し、過激なパフォーマンスを繰り広げてやりたい放題。
なのに、何だかお茶目で、ちょっと哀愁があって、ままならない自分のことをもて余すような含みがたまらなく人間的なのです。
地位の向上を望む女性にとって本当に厄介なのは、ちゃんと向き合おうとしない相手。
話をすり替えて煙に巻こうとする卑怯者より、差別的なことを隠そうともせず堂々と勝負してくれるボビーの方が、よっぽど素敵。
いつも女性の登場人物にシンクロして観ていることが多いけど、今回一番心に残ったのは勝負師ボビーの表情。
素材が素材なだけに意外。でも、男性にもきっと楽しんでもらえる映画だと思う。
結末を知っている人も知らない人も、最後のテニスシーンには興奮すること受け合い。良いところだけを圧縮した分、実際の試合より格段に面白い。
パイオニアの信念だな、二つの戦い
男女間の格差を解消していく、この道筋は整った。でも、男性アナウンサーが女性プレイヤーの首に手をかけ続けるTV放送に違和感と嫌な感じが拭えず、まだ道半ばを感じさせる。さらに、アラン・カミングとの抱擁で、もう一つの戦いの始まりを示唆させるエンディング。ということで、この作品ではM」主人公の戦いは一つの区切りをつけただけもしれない。
主人公は性別間の違和感を感じ続け、先頭に立って活動し続ける。テニスを通して、きちんと鍛錬して実現する姿が美しい。エマ・ストーンが良かったな。本当はもっとドロドロした葛藤もあったはずだけど、さらっと明るく検討的に仕上げたスタッフにもあっぱれ。
今見れば、間違った格差意識なんだけど、1972年当時はそれが世界的な常識だったのではないかな。学校でも親からも「男の子だから女の子をいじめちゃいけない」「男の子は女の子を守らなくては」とさんざん性別の違いを言われ続けて育った世代。自分より強い女の子を守るという???はあったけど、それから抜けられないのもまた事実。
彼女は自分の「素」と向き合うことができたのでは?
<映画のことば>
「どうしたの。」
「運命よ。避けられないと悟ったの。」
NHKのダイバーシティ映画特集とかで、数本まとめて放送になった作品のうちの一本になります。
テレビ放送から録画したまま久しく「お蔵入り」(汗)となっていましたが、ようやく鑑賞することができました。
自分自身の心情として、のめり込んで行かざるを得なかったのだと思います。
本作のビリー・ジーン・キングはこの途に。
結局は自分の家庭まで犠牲にしてまで。
そして、その中で、本当の自分の性的指向に気づくことができたのは、「殻」を割って、彼女自身が「素の自分」と向き合うことができたからではないでしょうか。夫がいて、夫との間に子どもまでいた彼女としても。
テニスの優勝賞金の金額の不平等をめぐる男尊女卑「だけ」の作品と本作を捉えるのは、いささか視野が狭いように思います。評論子は。
いずれにしても、自分が不条理だと思う世の中の仕組みを変えていくことは、こんなにも自分自身の「重荷」となり、自分自身をもこんなに深く傷つけるものだと知ると、ずしりと重たい気分になります。
再観するには、いささか勇気が要りそうですけれども。
佳作であったと思います。評論子は。
タイトルがむしろ皮肉
実際の選手達についての知識は全くなく、
予告で面白そうだと観に行った。
タイトルは性差別の戦い的なものだけども、
映画を見ていると、むしろそれは
試合の名目としてキャッチコピー的に掲げられており、
実際にはビリージーンは賞金アップのための意地、
ボビーは妻子にもテニス界からも見切られそうな状態からの脱却狙い。
つまり2人とも這い上がるための、
そして己のアイデンティティのテニスの価値を高める試合だった。
なのに周囲が、男女のガチンコと捉えて
気色ばむのはなんとも皮肉とも言える。
それ故に、試合後彼女の流した涙は
緊張感からの解放と共に、
果たして今後自分はいったいどう流されてしまうのか、
それを抱える覚悟があるのか、と
不安もあったに違いない。
それにしても実際の人物への寄せ方凄かった。
そして同性で泊まってたら、普通は
あ、友達も泊まってったんだね、くらいにしか
思わないのかしら。
ずいぶん察しのいい夫だな。
タイトルなし(ネタバレ)
男女差別に立ち向かい道を切り拓いた話としては勇敢に感じるけどLGBTQが絡みだしてからはなんかいけ好かん
主人公がいつから性的指向について悩みがあったのかは分からないけど普通に不倫だし、それを試合への不安などでナーバスになってるからといって容認するような描写は素敵じゃないでしょ
LGBTQだからとか重圧の多いチャンピオンだからとか
男女差別を是正したからといって道徳的に不倫が彼女を支えて真の自分を見出しハッピーエンド!って綺麗にまとめすぎちゃう?
実際マリリンとは別れる際裁判沙汰になり自殺未遂したマリリンは下半身付随
元旦那とは円満らしいけど
単純に男女差別について描きたかったのであればもっと違う視点があったのでは?
世界を変えるために一番になる
興味本位ながらですが
ボルグ・マッケンローに続き2017の実話テニスものをもう一本。 女...
笑える戦いが石頭を懐柔させました・・・
テニス界で有名なキング夫人のウーマンリブ運動の映画、当時、優勝賞金が男子の12.5%しか与えられない保守的な全米テニス協会に反旗をかかげ女子テニス協会を設立、白が基本のウェアをカラフル、ファッショナブルに一変、独自にスポンサー集めにも奔走した点ではプロスポーツ界の改革の旗手と言った方が良いかもしれない。
後に自身でもカミングアウトしているが劇中でも美容師との同性愛に悩む一面が描写されている、製作陣は男女平等ばかりでなくLGBTにも間口を拡げたかったのだろうが雑味に思えた。
肝心のテニスの方はおまけのような描き方、元チャンピオンとは言えボビー・リッグスは55才、前後左右に揺さぶられては体が持たなかった。キング夫人とリッグスは心底敵対している訳でもなくプロスポーツのショーアップと言う点では両者ともに抜きんでた才能を発揮したと言えよう。
試合に負けたリッグスだが愛想尽かしされた妻と復縁、それに反してキング夫人は離婚してレスビアンの道を歩むのだから振り回された旦那が不憫に思えてきた。
むしろ男女差別との闘いなら「ビリーブ 未来への大逆転」、「RBG 最強の85才」のルース・ベイダー・ギンズバーグさんの方がシリアス、彼女は男性社会に向け、「女性を敬って欲しいのではなく、踏んでいる足をどけて欲しいだけです・・」と名言を放っています。
ただ、このテニスマッチの偉大な功績は北風と太陽の寓話のようにイデオロギー対決をユーモアで処理したことで頭の固いお偉いさんたちを懐柔させたところなのでしょう。
テニスフォームがとても美しい
なぜテニス界にITFやらATP、WTAやらと団体がいっぱいあるのかが少し理解できた。試合のシーンは1ポイントのプロセスを詳しく描いており結果を知ってても手に汗握ってしまう。迫力は今のテニスには及ばないがフラットのフォアや流れるようなスライスなど、ああ昔はこうだったなあと往年のテニスの美しさを堪能。やはり歳いったらこのテニスだな…。キングのドロップショットに追いつこうと必死で走るリッグスの足がつりそうで人ごとと思えない…。それはともかく、全体に声高にジェンダー撤廃のようなメッセージを叫ぶのでなく、主人公達が悩み、行動し、勝ちとるところを淡々と描くことで、より胸に多くの物を響かせてくれるのはさすが。有り体だが、男女は権勢を競ってぶつかり合うものではなく、互いを補い合うものなのだと実感させてくれました。なんかどっかで見た人が多いと思ったら、J.クレーマーはインデペンデンスデイの名演説の大統領、ボビーの奥さんはBTF2で気絶ばかりしてるマーティの彼女だった。まあみんな歳とっちゃって…
でもいつの日か互いの能力をリスペクトしあえている日がきっと来て、その時代が待ち遠しい
三浦瑠璃さん推薦以降、注目してた映画。1991年米軍がイラク侵攻の際、多数の女性志願兵を映像で見たときにときの彼女に『日本もこういう時代が早く来るべき!』と力説したのに対して烈火のごとく『そんなのは男の仕事で役割でしょ!!』と猛反論されたことに強い違和感を感じたのが鮮明な記憶。
この物語、今で例えれば大坂なおみさんが時のヒーローだったベッカー選手やアガシ選手、マイケルチャン選手と今、真剣勝負するようなもの、勝敗予想は聞くまでもないけど大金の掛金が投じられてた信じられない時代。
偉大な女性先駆者が切り開いてのいま。男女が未だ対立軸が残るのはほんとにナンセンス、でもいつの日か互いの能力をリスペクトしあえている日がきっと来て、その時代が待ち遠しい。
単なる「男対女」の構図に当てはめない巧みな演出に脱帽
1973年、女子テニス選手ビリー・ジーン・キングと、当時55歳になっていた往年の男子テニス選手ボビー・リッグスの間で行われた「男女対抗試合」を描いた本作。
『リトル・ミス・サンシャイン』『ルビー・スパークス』のジョナサン・デイトン&ヴァレリー・ファリス監督は、この物語を単純な「男対女」という構図に当てはめず、女性達が平等を求めて奮闘する様子をみずみずしく描いてみせました。夫婦監督だからこその公平な視点とバランス感覚が素晴らしく、当にこの企画にはうってつけの人材でした。
「女性は重圧に弱く、競争には向かない」と決めつける男達に真っ向から反論し、自分の試合が世界を変えることを信じて黙々と練習を積み重ねるビリー・ジーンとは対照的に、試合に向けてまともに練習せず、大勢の女性を使って「男性至上主義」をアピールするボビーの姿は本当に悪趣味なのですが、彼自身の憎めない人柄を見事に体現するスティーブ・カレルのユーモアも相まって爆笑させられてしまいます。
もちろんその行動自体は褒められたものではないものの、シニアになって試合で稼げなくなり、ギャンブル中毒で妻からも見放された彼が、父としての威厳、妻からの信頼を取り戻すために奮闘する姿には、感情移入せざるを得ません。
試合の結果についてはご自分の目で確かめていただきたいのですが、テニスという世界的に人気のあるスポーツだからこその、この試合をする意味、そしてそれらの活動が現在の女性プレイヤーの活躍に繋がっていると思うと、彼女達の貢献には大きな賞賛と感謝を送りたくなります。
エマ・ストーン演じるビリー・ジーンと美容師のマリリンが、出会った瞬間に惹かれ合ってしまうシーンの美しさ、彼女達の関係を知りながら、ビリー・ジーンを思いやり、彼女の選手生命を優先する夫ラリーなど、語りたいことはたくさんあるのですが、最後にもう一つ取り上げたいのは、ゲイの男性でテニスウェアデザイナーのテッドが、ビリー・ジーンと二人で向かい合うEDシーン。
彼を演じるのは、『チョコレート・ドーナツ』にて、1人の少年を必死に守ろうとするゲイの男性を演じたアラン・カミングですが、彼の「いつか、自由に人を愛せる日が来る」と言い聞かせるように語る姿には思わず涙腺が緩んでしまいます。未だそのような時代が来たとは言い難い現代の私達も、彼の夢が叶う日を願わずにはいられないはずです。
全134件中、1~20件目を表示