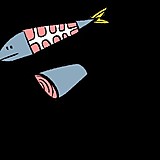モリのいる場所のレビュー・感想・評価
全88件中、21~40件目を表示
観衆はきっといい人。
映画を観る際、映画館という環境も含めて考えていました。
もしも 1人で観るならば、この映画はつまらないかもしれません。
しかし、映画を観る環境条件が自分の直感とリンクすれば、これはユジクで見れて良かったと思う作品です。
1人で映画を観れば、映画の情報を自分1人だけで処理してしまいますが、映画館という場であれば情報の共有が可能です。
私がこの作品を観た時、オーディエンスは殆ど高齢者でした。高齢者をバカにする訳ではありませんが、この人達は最近の映画のセンスについて来られるのか心配になりました。
しかし、この作品はむしろ彼らのセンスに合う作品のようでした。作中の散りばめられた 小さな笑いは会場の雰囲気も作り出しました。
そうか!そういう映画の見方もあるのか!
私は映画を単純な娯楽だと考えていた故に、映画論や技術論にあるような 方程式でもって映画を観ようとしていたきらいがありました。
映画を観る環境を作る映画 という考えはありませんでした。映画はひとつのモノとして、完全に独立する必要があると。
しかし、ユジクの会場で観た和やかな雰囲気はこの作品とマッチングしており、観衆のささやかな笑い声は 映画を観る私のスタンスそのものに彩りを与えました。
つまり、映画 は一概に映画そのものの中で行われる効果だけで完結されるものではなく、周辺環境の在り方が 演出 としてプラスされるのです。
映画の鑑賞の仕方にアクセントもつき、なかなか良い体験をさせていただきました。
なんか、いい。
母ちゃんが疲れちゃいますから、それが一番困る
映画「モリのいる場所」(沖田修一監督)から。
30年以上も、自分の家の敷地から出ないという、
伝説の画家・熊谷守一とその妻の生活を描いた作品であるが、
どうして、そんな気持ちになれるのか、とメモしていたら、
面白い台詞にぶつかった。
文化勲章を受けて欲しい、と電話連絡があった時、
受話器を持っている妻に「いい」とボソッと言いながら
「そんなもん貰ったら人がいっぱい来ちゃうよ」と付け加えた。
妻も「それもそうやね、いらないそうです、はい」とあっさり。
さらに、もっと広い土地に移ったらどうかと誘う人にも、
「私、ここにいます。この庭は私には広すぎます、ここで充分。
それに、そんなことになったら、
また母ちゃんが疲れちゃいますから、それが一番困る」
とにかく、愛する妻と一緒に、のんびり過ごすことが望みで、
あまり有名になって、多くの人が訪れることになり、
大切にしてきた今の生活が変わることが一番困ってしまう、
そういうことなのかな、と思ってメモをした。
監督が伝えたかったことは、守一の好きな言葉「無一物」。
禅語「無一物中無尽蔵(むいちもつちゅうむじんぞう)」の一節、
「無一物」とは何も存在しないということであるが、
何ものにも執着しない境地に達することができると、
大いなる世界が開ける、という意味らしい。
「何もないからこそ、そこに豊かさを見出せる」ってこと。
静かだけど、素敵な作品だったなぁ。
静かな、笑い。
確かに、あのドリフのシーンはびっくりしました。
あの直前の、電話を切ってからの二人の会話と周りの様子だけで充分笑えたのに…とは思ったけど、あれはアレで私は好きです。
だって、えっ!?っていう驚きがあったから。
宇宙人も、いい。
最初は誰だかわからないうちにすぐにどっかに行ってしまって、またそれが可笑しい。
で、あぁそうだったんだ(あんまり納得はできないけど)ってなるし、それが三上博史って(笑)
オープニングの木々の中にうっすら浮かぶモリを無視するかのようなパン、道具を使っての朝食のシーン、無一物…
あとから思うと小ネタの連発。ただ、観てる間は間延びした感じでいろんな虫が必要以上に登場したり、少しのんびりしすぎてイライラしたり。
でも、とても気持ちのいい、もっとずっと観続けていたい映画でした。
さすが、沖田監督ですね。
でも、とにかく樹木希林が、いい。
静かな、いい映画
無一物
本作はまるで本当の守一のドキュメンタリーを観ているような世界観で素晴らしかった!
我が国を代表する画家、熊谷守一画伯の晩年の或る一日の物語をコミカルに描いた秀作。
先の昭和天皇陛下も美術館で熊谷守一の作品を観賞し、文化勲章を受章すると来客が増えるので生活が乱される事が迷惑であるとの理由で、文化勲章の受章を辞退してしまう程の、根っからの天才芸術家。しかし、30年以上も自宅から出た事すら無いと言う、世間の一般のしがらみを全く気にする事無く、自由に画を描く為にだけ生きた仙人画家の晩年の風景物語。だが私にはとても心地良かった。守一独特の世界感へと誘ってくれる本作はこれと言った事件も無い、年老いた画家の只庭を観察するだけで日が暮れると言う日常なのだが、本当にそれはそれは心地良い。
熊谷は明治の初期の生まれで、今から40年以上も前に亡くなっているので、この映画の時代は今から半世紀近くも前の物語だろう。
守一の広い庭には多くの木々が生い茂り、森のように青々と木々が生息し、虫や野鳥の生態を30年以上に渡り観察し続ける事で、独自の世界感を持ち、作品を描き続ける孤高の天才の生き様には心を洗われるような素晴らしさが有る。
勿論半世紀も前の事なので、今とは比較にならない程のんびりとしていた時代の筈だ。高度経済成長期になっているので、戦前を生きた守一達から見れば、気せわしい世の中で、暮らし難い時代になっていたと感じていたのだろう。
守一を取材しに来たフォトグラファーの若い助手は、最初は変人としか感じなかった守一の行動を観察するうちに、その素晴らしさに魅了されて続けて取材をしていく様になるのだった。その様子が何だか私にも分かるような気がした。
それにしても、山崎努と樹木希林が2人並んで座っているだけで、2人とも本当に数十年を共に生きて来た夫婦の様にみえてしまうから、芝居の達人とは本当に不思議なものだ。
ところで、樹木希林の出演する映画やTVドラマには食事をするシーンが凄く多く出てくるが、本作でも、カレーうどんや、すき焼きを囲みながら人々が集うシーンがある。彼女自身も料理上手な方だったらしいけれど、どの作品でもこの食を囲むシーンにそれぞれの家庭の独特生活感が浮き彫りにされ、一つとして同じ様な食べ方をしていないのも、希林さんの演技力の見せ処ではないだろうか?惜しい役者を亡くして残念な限りだ。
それから守一に、子供が書いた画を見せる親を見て、その画を下手な絵だと褒める守一の言葉がまた素晴らしかった。確かに芸術は巧い下手ではなくて、作品を創作する情熱を持ち続けると言う事の方が大切な事なのだろう。下手な方が伸びしろが有って良いとは、素晴らしい含蓄が有る言葉だ。
何も特別な事件も無い平凡な守一と妻の生活を軸に描かれる日常がこれ程豊かで有るとは思いもしなかった。ドラマと言うよりは、本当の守一のドキュメンタリー映画を観ているような安らぎがここにはあった。
幸せのある場所
熊谷守一。
日本画の大先生。
いつもながら恥ずかしい事に、名前を聞くのは初めて。
画の事はよく分からないが、数々の名作を残し、その功績を称えた美術館もある。
氏がひと度一筆取れば、それだけで大変な価値や名誉であり、遥々遠方からの訪問者も後を絶たない。
“画壇の仙人”とも呼ばれ、色んな意味でその名の通り。
偉人ではあるが、かなりの変人。
遠方から訪ねてきた人の為に看板に文字を書くが、全然違う文字を書いてしまう。朦朧してんのかい!
金や名声に無関心。
世の中の事にも無頓着。
服に食べ物を落としても、一人で拭けないくらい何も出来ない。
固いものを食べる時は必ず潰し、相手に汁がかかろうがお構いナシ。
髪はボサボサ、髭はボウボウ。
本当にその名の通り仙人のような世捨て人。
さらに驚きなのは、日々の生活ぶり。
毎日必ず出掛ける。
「行ってきます」と出掛けたその先は…
何と、自宅の庭!
氏は、晩年の約30年間、自宅の庭から一歩も外へ出なかった事で有名らしい。
変人で、今で言う引きこもり…?
勿論、ただそうではない。
庭は、草木が生い茂り、多くの小動物や昆虫が住み付いている。
そんな自然に触れ、小動物や昆虫の観察をするのが日課。
池に行こうとして辿り着けなかったり(極度の方向音痴…?)、蟻は真ん中の足から歩き出すというどーでもいい事を発見したりと、やはりの変人だが、それらを見つめる表情や眼差しは、真剣で穏やかで純真。
創作の源でもあり、自分の全て。
住宅街の中の自然の園とでも言うべき庭は風景も音も美しく、小さいが生命に満ち溢れている。
そんな大先生と、妻。連れ添いはもう50年以上!
老後を二人で仲良く…って感じではなく、我が道を行く夫を、妻が世話してる感じ。
奥さん、大変そう…。
でも、二人共、面と向かって言葉や態度には出さないが、相手の事を心底思いやっている。
妻は、この庭が夫の全てである事を誰よりも理解している。
夫は、これ以上外へ足を踏み出せば、またそれだけ妻に苦労をかけさせる。
何も語らずとも…。
夫婦の歩み、50年。
山﨑努と樹木希林。
共に長いキャリアを誇る大ベテランだが、意外にも共演はこれが初めて!
それだけでも一見の価値あり!
山﨑努は存在感と威厳たっぷりというより、お茶目でユーモラスで愛嬌あって、何処か可愛いらしい。
そして、未だに亡くなった事が信じられない樹木希林。今年遺した3本の作品の一つである本作は、これぞ樹木希林!と言うべき十八番の役柄。
最初で最後の共演。惜しくもあるが、巡り巡って初共演した唯一無二の作品に相応しい。
夫婦の家には、毎日のように誰かしら訪ねてくる。
ご近所さん、依頼者、先生を写真に撮るカメラマン、見ず知らずの人まで。
加瀬亮、光石研、青木祟高、吹越満、きたろう、三上博史ら実力派/個性派集う。
一見人付き合いも苦手そうな先生だが、風変わりでほっこりと、人と人の交流を描いている。
描かれるのは半生ではなく、晩年のとある1日。
なので、劇的な出来事は何も起こらない。唯一、自宅前のマンション建設問題だけ。
ゆったりと時が流れていく。
それだけでも人物像と営みを感じられるのは見事。
沖田修一監督らしいユルさや惚けた笑いも。
本当に何も起こらず、淡々と、最後も呆気ないくらい静かに終わる。
人によっては退屈な作風かもしれないが、この雰囲気、嫌いじゃない。
温かく、心地よく、しみじみと。
不器用で下手でもいい生き方、人々との交流、阿吽の夫婦関係…。
その営みに、幸あり。
豊かな世界の見え方
結構ケラケラ笑える楽しい作品でした。
本作は山崎努アイドル映画ですね。主人公のモリおじいちゃんがとにかくキュート!ジッと虫とかメダカとかを眺める姿とか、杖を2本つきながらも意外とスピーディな身のこなしとか、なぜか小学生と目があって逃げるとか、絵描き部屋に行くのを嫌がるとか、いちいちカワユイです。
勲章を固辞した理由が「人がいっぱい来ちゃう」でしたが、モリの家にはすでにいっぱい来てますよ!それがまた賑やかで楽しそう。だからモリも本気で嫌がってはいないような印象。
勲章を受けたら、きっと卑しい心根の人たちがいっぱい来ちゃうので、それが嫌なんでしょうね。
言うまでもないですが、樹木希林がスゲーですね。本作で気付いたことは、顔がスゲー。片目が義眼だからか、結構激しい斜視で、それが特別なトボけた凄みを生み出しているように感じました。
(追記・義眼ではないとのことでした。間違いスマンカッタ)
宇宙人とかやってくる荒唐無稽さはやや微妙に感じましたが、モリが宇宙に興味を示さない理由はよくわかります。モリの庭は立派な宇宙で、モリにとっては永遠のワンダーランドですから。
また、そのことを樹木希林が理解しているのも素敵です。本当にあたたかで良いです。
個人的に一番ハッとした場面は、モリが現場監督の息子の絵を下手と評し、「それがいい、上手いと先が見える」的なことを述べたシーンです。これは妙に腑に落ちました。我々は下手だからこそ先が見えず、だからこそ新たなる出会いに胸を躍らせるのでしょう。
モリはまだ生きたいと言っています。まだまだ新しい出会いが待っているからウキウキするのでしょう。アリは二番目の足から歩き出すことに気付いたモリですが、また新たなる発見があるかもしれません。
モリの豊かな世界の見え方を体験できる、贅沢な逸品でした。
それでも見てよかった!
演出で賛否両論があったので迷っていたのですが、樹木希林さんが亡くなったことにもきっかけをもらい吉祥寺のちいさな映画館へ。
見てよかった!
虫や木の葉、そしてその中に溶け込む熊谷氏本人。すごーーーくミクロな視点で丹念に撮影されています。
草木に覆われたちいさな庭が大宇宙に見えてきます。子供の視点といえばちかいでしようか。(何箇所か撮影を違う時にやったのか、カットで日差しが変わってしまってるのがもどかしかった。。。と思うくらい庭の空気感が心地良いので。)
かと言ってそれだけでもなく、熊谷氏と対照的な、近隣から訪れる人々の騒がしさや会話のおもしろさにもあふれています。
音楽も映像お共演してるみたいに軽やかで最高でした。
ちなみに
絵を描くシーンはありません、、、。絵も全然出てきません。敢えてなんだと思いました。
突然の非現実的シーンは、仙人のように生きるこの画家に、安易に共感されて映画を解釈されるのを回避していますよね。。。
ちゃんと最後の最後まで あっ!といわされますよ。
好きとか嫌いとか
もっと淡々とした記録映画的なものかと思ってました
冒頭。まかさにあの有名な「この絵は…」のエピソードの再現に、思わずうめき声ともつかぬ声を挙げ、お隣の席の方もつられたのか忍び笑いをされてました。それからみみずく、庭の木々に埋もれるようにしている姿、表札、来客の絶えない居間、池、マンション、カメラマン…沢山のエピソードがありました。途中文化勲章を断ったシーンでは場内こらえきれずに笑いもおき、その後のシーンは…あの演出の意味をちょっと考えさせられたり、意外と仕掛けのある映画でした。モリとカメラマンがお互いを撮りあってるシーン、モリが撮った写真を見たかったですね。映画の撮影協力をされてる柳ケ瀬画廊さんが映画館から歩いて2分なのも、映画を観る立地としてベストでした。来週監督が来られるそうなので、また行きたいと思います。
同じ岐阜人として
映画「モリのいる場所」を、またまた名古屋で見逃したので、岐阜の懐かしの映画館での公開初日に行ってきました。
結果的にこないだの「おだやかな革命」もだけど、岐阜人としてどちらも岐阜の劇場で観れたことは感慨深い。
モリとは、言わずと知れた熊谷守一さんのこと。
尊敬してやまない大好きな画家の、画集や展覧会などで見聞きする作家のエピソードなどで勝手にイメージはしていたものの、長い生涯の中のほんの一瞬である晩年の日常をさらりと描くことで、それまでどんな人生であったかも超越した、あるがままの守一像を映し出した秀作である。
監督がだれであれ 、被写体がいいからいい作品に仕上がったというのも違う。
沖田修一監督だからこそのモリのいる場所へ、観るものを誘ってくれたように思う。
樹木希林さんは演じることなく、「万引き家族」よりさらに自然体でそこにいてくれました。
山崎努さんの奥西死刑囚役だった「約束」もすごかったけど、モリ役はさすがすぎて言葉にならない。
近年、こうした自然に還るライフスタイルを題材にした映画がロングランとなるほど時代は変わったのはよいことだけど、あの「人生フルーツ」より、わたしにはこっちの生き方や暮らしの方が自然で好きだ。
どっちがいいかを比較してるわけではない。
自分もこうなりたいという気持ちにさせるのがフルーツなら、モリは自分もそうなっちゃいそうな非常に近い感覚が、魂なのか血なのか身体の奥から、迷ってないでなっちゃいな、今すぐやればいいじゃんと後押しするワクワク感。
今この時代に映画化してくれたことにも感謝だけど、この偉大な画家が本当に評価されるのはもっともっと先の50年後100年後なんじゃないかと思うほど、まだまだ知らない魅力に満ちた存在なのです。
映画についてもあれこれ書きたいことは山ほどあるけど、ネタバレ暴走しそうなんでやめときます。
そして、ここで観た理由がもう一つあります。
映画館シネックスを出てすぐのところにある、柳ヶ瀬画廊へ初めて訪れることができました。
ここは昔から熊谷守一の魅力を発信しつづけてきた老舗画廊。
展示されてる絵や書を見せてもらったり、オーナーさんたちとモリ話に花が咲きました。
全88件中、21~40件目を表示