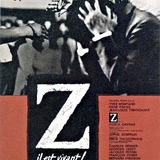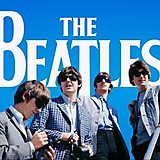デトロイトのレビュー・感想・評価
全202件中、101~120件目を表示
理不尽極まりない
現時点での女性で唯一のオスカー監督賞保持者、キャスティンビグローに...
現時点での女性で唯一のオスカー監督賞保持者、キャスティンビグローにより、我々観客は1967年のデトロイトという1つの箱庭に凝縮された煉獄へ2時間半に及ぶ地獄巡りへと誘われる
白人と黒人の間の根っこにある差別意識から小さな渦が生じて、日に日に双方の生活面を中心としたフラストレーションと憎悪の蓄積によりデトロイトは秩序が破壊された地獄へと変貌を果たす
この炎の絶えない憎しみの蔓延る世界には、遥か遠い銀河のレジスタンスも、アベンジャーズも抗う事は出来ない
この振り子のように憤怒が日々増幅し、秩序が完全に破壊された世界は、また、人の形を模した怪物を生み出してしまう。いや、この映画は、生活の不満を始まりとした怒りの連鎖によって生まれてくる、自らの倫理観で何かを成し遂げようとする化物の誕生プロセス、これは、アメリカのみならず日本やほかの国でも歴史上通ずるような”人間”の根底において極めて普遍的な事ではないか
デトロイトが生み出した怪物たちによる一夜の凶行により3人が命を落とし、また、生きて生還したものたちを傷を負い、苦しめられていく。その傷を負い、輝かしい夢を砕かれた1人の”人間”にが歌い上げる聖歌はまるで我々観客に、あの一夜は何だったのか、を問いかけているように聞こえた
それにしてもキャスティンビグローは監督として、1つ線を超えた監督だなぁーと改めて認識せざるをえない、いや、慣れてる人でもかなりしんどい映画ですよ、コレ
時代なのか?人間の性なのか? 追い込まれた人間の、私利私欲な描写に...
アメリカの闇
「だれが踊ろうと自由だ」って本当は言いたかったろうに
実話系もむなくそ系も映画として好きなんだけど、これはどちらもあまりに具体的であまりに実話で、これを観たら最後、事件の目撃者として責任を持って生きていかなければならない。
実際に証言台に立たされることはないかもしれないが、決して観なかったことには出来ない映画。
あまりに実話であると感じるところは、ハートロッカーもゼロダークサーティもそうだったように、登場人物に起きているシチュエーションからこっちが逃げられない、誤魔化せない、「いやいや映画だし」と思わせてくれない感覚。この監督の凄いところ。
監督が感じた使命感や怒りや悲しみを突きつけるような、不安定な手持ちの超接近カメラが見せる汗とか擦れとか嗚咽とか、今回はそれが40分間。
このリアリティが最後までシラけないのが凄い。英語だから演技がどうとかはよくわからないけどプロットとかメッセージを伝えるセリフを超我慢して減らしてる?ありのままこの状況なら口から出そうな言葉しか発せられていないからか。
警官役の俳優の人下手したらこの映画終わってもめっちゃ嫌われそうだけど下手な尋問も嫌味な笑顔も上司への無垢な報告もピカイチだった。若いのかな?
2回は観たくないけど人に説明される前に映画館で観られて良かった。
暴力
暴力は駄目、差別は絶対駄目。
でも差別という言葉が存在する限り差別はなくならない気がする。差別をしない人間なんていないと思うし。自分がしていないと思っていても。
自覚があってもなくても、その心の中の差別を表に出したり蔑む気持ちを暴力に変えたり、そういうのをやめなきゃ。我慢くらい誰にだってできる、人間なんだから。
人間であることを自覚しなくなって、こころの戸締りを忘れた時に暴言や暴力が飛び出してしまう。
この映画の中で語られるデトロイトの暴動が起きた時、彼らのこころの扉は完全に壊れてた。
映画は出来事を伝えるのに最も適したメディアかも知れない。
観たあとはこのことを考える訳でもなく、じわじわ涙が出てきた。考えてなくても考えていたみたい。傷口から血が出るみたいに、何もしなくても涙が出てきた。とてもこわかった。
67年からの宿題
スゲー腹が立つし、モヤッとする
警官が悪魔に見える
1960年代に実際にあった黒人の暴動事件をテーマに描いた作品
初めは黒人の暴動の様子をドキュメンタリータッチで描いていくのかな?なんて観ていたのが、とんでもない方向に
黒人がおもちゃのピストルを発砲したのをきっかけに
警察官の恐ろしい尋問が始まる
この尋問シーン。とにかく怖かった。観ていてこちらが席をはずして逃げ出したい衝動にかられた
こんなこといつまで続くのか どうしてこう人間は残酷になれるのか、怖くて怖くてたまらなかった
警察官を演じるウィル・ポールターとにかく怖い
白人至上主義の若くて恐ろしい警官
あんなやつにつかまった黒人は逃げられない
逃げたり反抗するものなら殺される
彼の怪演ぶりが今も蘇り夜うなされそうだ
怖くて恐ろしく爽快感もなく喪失感が残る作品だ
アメリカに連れてこられ今でも差別に苦しむ黒人たち
子どもの頃「リンカーン」を読んで
南北戦争で黒人にも自由が与えられたと思い幼きながらも
良かったと思ってものだが とんでもない
今でもかわらない
アメリカだけでなく人種 宗教の違いで争いはどこにでもある
人はいつまで この愚かなことを繰り返すのか
観た後今も心がずしりと重くて苦しいが
すごく 見応えがあり よく出来た作品だと思う
ウィル・ポールター
アルジェ・モーテル事件の全貌
突き付けられる『闇』
これはもう『感想』ってレベルじゃない気がする。
理不尽で執拗な暴行の場に放り込まれて、自分はただ立ち尽くしているしか出来なかった…そんな気分だよ。
それはドキュメント映像を見た時の感覚とは違う。
『世界の何処かで起きている目を背けちゃいけないこと』ではなく『いま目の前』の恐怖に震えたんだ。
そのくせ『自分はその現場にはいない・自分がその被害に遭うことはない』ってどこかで解っている、ムズ痒いような矛盾。
現実と映像との境界を乱された。
ビグロー監督の技量にやられた…感服するのみだよ。
50年前、1000人を超える死傷者を出した史上最悪ともいわれる暴動の最中、混乱の中心部からは少し離れた場所にあるモーテルでの一夜を切り取ったこの作品。
何が怖いって、暴力そのものもさることながら、それを起こしたクラウス達白人警官の意識なんだよね。
他人の生命を弄びながら卑劣な暴力を繰り返す彼等は、それを享楽とする、いわゆる異常者やサイコパスじゃなくて、
『当然のことでしょ?』『何が悪い?』とでも言いたげにフッツーに己の正義を振りかざしてるんだ。
あと保身ね。
『拳銃出てこねぇじゃん!』
『マジで撃っちゃったわけ?』
『取り敢えずまたドヤされんのかよ〜』
『うっぜ〜!やっべぇ〜!』
『お前らが喋らなきゃバレねぇんだから黙ってろよ!』
ってなもんで。
そんな人間を形成する社会・環境があるんだと思うと、その闇の深さが恐ろしくて堪らなかった。
見かねて黒人青年を逃がしてあげた白人兵士がいたのが救いではあったけど、
それだってコソッと逃がしたのであって、不当な尋問を止めようと立ち上がった人は1人もいないんだよね。
決してその兵士を気弱だと責めるつもりはないんだ…ただ『そこにも闇がある』と感じざるを得ず、これがまた苦しかった。
『この夜を生き抜け』と警備員ディスミュークスが言ったように、尋問を受け続けた彼らは自力で堪えて生き抜いた。
…ただ堪えるしかなかった。最後まで助けは来なかったんだよ。
中立に近い立場にあった唯一の黒人ディスミュークスの冷静さと機転は、彼らの生命を繋ぐ要素に確かになっていたかもしれないけど、
あの戦慄の中でも解放された後も、彼にはもう少し闘って欲しかった。闘えたはずなんじゃないかと思ってしまう。
守ることは出来ても挑むことはできない…これも『闇』か。
暴動勃発直後のシーンで
『自分たちの故郷を荒らすな』との政治家の呼びかけに対して、間髪おかず一人の男性が『焼き払え!』と叫んだのを聞いた時、涙が溢れた。
その一言で、黒人達の鬱積した苦悩と怒り・遣る瀬なさがどれほどのものか、突き付けられた気がした。
そして拡大化していく暴動…アルジェモーテルのような事件。負の連鎖だ。
人気歌手への道が開きかけていたのに、尋問のトラウマから人前で歌えなくなってしまったラリー。
あんな体験をした彼が歌うからこそ訴えられることがあるはず…と言う人もいるかもしれない。
でも、それはあまりにも酷だよ…苦しいよ。
染み付いた差別意識によって絶たれた生命・奪われた人生があった事実を、より多くが知らなければならないと思った。
とてもよかった
空気の読めない警官が本当に黒人を殺してしまうのが痛ましかった。殺した方も殺された方もたまらない。警官の横暴ぶりがひどすぎて、それに比べると今は、他の問題があるもののとても丁寧になっていい世の中になったものだ。
意地悪顔の黒人を殺してばっかりいる白人警官にもっとバチが当たって欲しかった。
デビューをふいにしてしまったロマンチックスのボーカルが気の毒だった。
暴動が起こると、それに乗じて商店からの略奪が行われるが、それは暴動とは別問題で単なる窃盗や強盗だと思う。でも実際にそんな場面に遭遇したらオレも興奮してついやってしまうかもしれない。その場の雰囲気でそんな気分になるものなのかもしれないが、居合わせたことがないから分からない。
救いがない映画。
キツ過ぎ
闘わないフィンとファルコン
140分という長さ、上映前は「お手洗いに行きたくなったらどうしよう…」という杞憂で半ば緊張していたのが、開始して15分も経つ頃にはその緊張は全く別の緊張感に切り替わって拳を握っていた。これ程重いテーマの作品に全く長さを感じさせない。ビグロー監督作品では『ゼロ・ダーク・サーティ』が記憶に新しいが、その時も同じようにあっという間に時間が過ぎた。すぐ側で聞こえる鳴き声や怒鳴り声、銃を突き付けられ耳元に聞こえる相手の息遣いにスクリーンを通してひきつけられる。微塵も爽快ではない話と映像なのに味わう臨場感。結論から言えば「観て良かった!!面白かったね~!」と言えるような作品ではない。違ったテンションで「観て良かった…いやあ、凄かったね…;」とこぼしてしまうような映画だった。
冒頭に当時の実際の写真が要所要所に映し出され、資料映像を基に再現して作られたムービーを観ているかのよう。この冒頭部分がこの映画のキモのように思う。
デトロイトに密集して住まわされる黒人の生活が貧困と悲惨さを極め一方的に白人警察に虐められる立場に撮られていたら、全く違った感情をもって観ることになっただろう。差別行為から抜け出さない白人の姿のみならず、黒人達が違法酒場で騒ぎ暴動を起こすことを開き直り、非暴力的だったこれまでが間違いであったと言わんばかりに振る舞う姿も撮られているからこそ、この映画があくまで中立的な視点で描かれている事が伝わってきた。
モーテルでの事件に出てくる名誉除隊軍人役がキャプテンアメリカのファルコン役だし、そもそもディスミュークス君はスター・ウォーズのフィン役だし。ま、まさかここでドンパチ闘っちゃうのでは…?!とか一瞬期待したものの(この事件について事前に学習したわけではなかったので本気の期待込め)、彼らは驚くほどに無力で無抵抗。事件後の裁判シーンでも判決に対して特に誰かが声を上げるわけでもない。常日頃からこういった理不尽さを目に焼き付けられてきたのだろう。この時代に勇気を出して発言をしたり抵抗を見せたりすることがいかに無意味な事であったかが見て取れる。悔しく胸糞悪い思いでいっぱいになるシーンばかりだったけれど、とても「何してんだよ!頑張れよ~」とは思えない。
暴動により狂気に溢れたデトロイトでは、誇りを全うするより1日を生き延びる事を求められる時代であった事を学び取れる140分間だった。
憎悪が駆り立てる負の連鎖
キャスリン・ビグロー監督の作品ということで鑑賞。人種差別や当時の時代背景について考えさせられたとともに、映画の構成や描写についても深く考えてしまった。
ストーリーは1960年代のデトロイトにおける暴動や、不当な黒人差別を描いたもの。テーマが重いだけに、鑑賞していて楽しいものでもなく、見ていて非常に心痛むものである。
演出という面では、本作は今まで見てきた黒人差別をテーマにした映画の中で一番私の印象に残るものとなる気がする。
一つ目にこの映画は主人公が誰かはっきりしない。これはあえてはっきりさせなかったのか、各キャラクター全体をまんべんなく描写しているように思えた。その点、どれか一人のキャラに感情移入するということはしづらいが、全キャラの感情を汲み取りながらも事件全体を俯瞰的に見ることができる。
二つ目にアーティストが登場人物であることから歌を歌ったり、曲が流れることが多く、描写の重さの緩和にはなっているように感じた。
テーマが重い映画は全体を通して鬱屈した描写が続いてしまうと案外鑑賞者は疲れるし、見る気が失せる。特に人種差別をテーマにした場合、ちょっとした鑑賞者を引きつける演出が不可欠になる。本作の場合、張り詰めた空気観から感じられる緊張感がスリルへと転換し、上記の歌や曲が1つの希望へと繋がり、鑑賞していて退屈することは無かった。本作はそのバランスが絶妙で、重いテーマは一貫して露呈していたのにも関わらず、鑑賞者がのめり込む工夫が施されているように感じた。
個人的に好きだったウィル・ポールターの演技もかなり良かったように思える。彼は悪役もこなせるのだなと感服。
キャスリン・ビグロー監督はストレートにこの事件の真相を伝えたかったようには思えない。今の現代に生きる我々の解釈で、どのように過去を見つめるべきかの道標を本作で示したように感じた。
弱い犬ほど吠える
4年くらい前に上映されていた「フルートベール駅で」でも目の当りにしたが、昔も今も警官が黒人を締め付ける構図は大きくは変らない。
そんな衝撃的な時間の中に投げ込まれる中盤からの展開は、息苦しさを感じつつも目を背けられずに見入ってしまった。
人種差別が酷いのはよくわかっている。でもどうにもならないのもアメリカのサガとしてわかっているからやるせない。(あんな大統領が選ばれるんだから)
平和な日本に暮らしてこの物語のどこに共感を得れば良いのかわからない、辛さと後味の悪さに包まれる重い作品でした。
キャスリン・ビグロー監督のいつもながらの問題提起は素晴らしいけど、やはり結論は見た人任せ。出してはくれないんですよね。
職人芸とも思える硬派な作品に仕上がった
これもまた『ダンケルク』と同様の体験型と言えるが、当時のデトロイトの空気感と白人と黒人の関係性、そして白人同士、黒人同士の思想の違いなど多様性も感じられて、すでに職人芸とも思える硬派な作品に仕上がった。
冒頭にアニメーションで前提を説明する手法はよくある形すぎたし、そのクオリティもあまり良くないのはまず残念だったが、そのあとの2時間強は圧巻で、ときおり挿入される当時の映像が編集の確かさと相まって違和感なく繋がっていたのは、本編の迫力ある映像とサウンドのなせる技。
そうして徐々に醸成される没入感の先にあるアルジェ・モーテルでの描写は本当につらいものだった。アフリカ系のベトナム帰還兵があのモーテルで理不尽な迫害を受けるが極めて理性的だった。それは彼の地での経験がそうさせたのだろう。 偶然ながら今作を鑑賞後に録り溜めていた『プラトーン』を観た。こちらも馬鹿をやるのは差別主義者の白人だという描かれ方だが、その背景を観た後では全く頷ける描写だと思った。北軍と無関係の村人に対して出来るはずのない供述を強制する、という構図もまたまったく重なる。
今作は当事者たちへのリサーチをもとに一部は脚色されているが事実に近いものになっているという。 『否定と肯定』でも触れられていたが、被害者側に当時のことを語らせるのは望ましいことではない。しかし語り継ぐべきこともある。記憶のすり替え、曖昧さは常につきまとうことではあれ、そこにいた人たちの証言はより多くの人の耳に届くべきだろう。
アルジー・スミスは特筆されるべき存在感だったと思う。またラリーが聖歌隊にやんわり拒否されてたのは、彼らの世代と背景にあるモータウンが、コアな層からは嫌われていたってことだよね。同じ人種であれ。でもラリーはオールドスクールも敬愛していたし、そういう彼がまた同年代からは浮いていたことがあのモーテルの一室で描かれるのも良い。 Youtubeでは「Algee Smith & Larry Reed - Grow (from DETROIT) 」で今のラリーと演じたアルジーのデュエットが聴ける。素晴らしい。
全202件中、101~120件目を表示