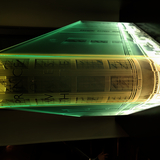博士と狂人のレビュー・感想・評価
全21件中、1~20件目を表示
ショーン・ペンが演じたマイナーの魅力
辞書作りといえば三浦しをん原作の「舟を編む」が思い浮かぶ。本作の中で「舟を編む」のように博士と狂人の二人で用例採集するのかななんてワクワクしてしまったが、そんなお気楽な感じではなくシリアスなドラマ作品だった。
辞書作りとは言葉を伝えることだ。言葉の存在とその意味だ。
何世紀にもわたり使用例を記すことで、言葉の歴史と用法も伝えようとした一大プロジェクトが本作の内容である。
しかしメインとなる物語はショーン・ペン演じるマイナーの過去から現在で、特に未亡人との交流の比率が大きい。
この未亡人との交流を要らないと感じているレビューアーが多いようだが、むしろ非常に重要だ。
先に書いたように辞書作りとは言葉を伝えることだ。しかしその辞書も文字を読めない人間にとっては何の意味もない。
つまりマイナーは、言葉を伝えるということについて一番下から一番上まで助けようとしたのだ。
今の罪だけではなく過去の罪の贖罪としてマイナーが選んだことが、言葉を伝える手伝いだったのである。
統合失調症となり自分がおかしくなっていることを自覚しているマイナーはできる限り全てをかけて言葉を伝える手伝いをしようとした。
彼は間違いを犯したが、その純粋で崇高な魂に応えようとするマレーたちの行動は、人として当然のことのように思えた。
善き人であろうとしたマイナーを見捨ててはそれこそ人でなしなのである。
穏やかなとき半狂乱のとき、かなりギャップのあるキャラクターであったが、名優ショーン・ペンは軽々とこなし、にじみ出る人間性まで表現したように思う。
刑務官のマンシーが作品序盤で同僚を助けてもらったという直接的な理由があるとはいえ、やけにいい人だったのも頷ける。マイナーを見て悪意が芽生えるならば、やはりそれは人でなしだ。
それだけ、ショーン・ペンが演じたマイナーという男は魅力的だったのである。
アメリカに帰ってからは?
最初は狂人と博士が、どんなふうに繋がるのか不思議だったけど、徐々に繋がってきて楽しくなる。
ただ、狂人の帰国後の様子が分かりづらかったので、終わり方が好ましくないなと…
それと、夫の職場に行って妻がスピーチする時代じゃないし…理解に苦しむシーンも。
だけど、この映画で私が得たものは狂人の言葉…
言葉の翼を持てば世界の果てまで飛べる
私たちの頭の中は空より広い
殺してしまった男の妻が、文盲だと分かったと同時に、狂人が妻に伝えた言葉である。
本当にそうだなぁと感じます。
言葉を大切に、生きて行かねばと感じた映画でした。
テーマ曲が良い
・マレー博士は無事に辞書編纂を成し遂げられるのか?
・マイナー氏は罪や病から立ち直れるのか?
という2つの主軸が絡み合うストーリー展開は、新鮮な面白さを感じた。
中盤まではやや退屈ではあるものの地味に丁寧に話が進むのだが、対照的?に、終盤、若干演出が安っぽくなる(例→手を握ると目に光が戻る、看守が院長に反抗する、博士夫人が理事会でよく分からない演説をぶつ)のがちょっと気になった。
最後のシーン、時間の経過を感じさせるような演出はジーンと来た。そこで流れるテーマ曲もメロディアスで大変良いです。
オックスフォード英語辞典誕生秘話
19世紀、オックスフォード英語辞典誕生秘話。オックスフォードならさぞ大学の権威筋が編纂したものと思っていたが独学で言語学をマスターしたジェームズ・マレーが編集主幹というだけでも意外なのに精神を病んだ殺人犯ウィリアム・マイナーが協力というのも驚きでした。もっとも彼はエール大学の医大生だったころアルバイトでウェブスター辞書の改訂版製作に関わっていたので辞書に関して造詣が深かったと思われます。
邦画の「舟を編む」も辞書編纂の話だったが、冒頭の右の定義がユニークで惹きこまれてしまったが本作は英語だし、出典や用例に拘るのであまりピンとこなかった。
何故マレーらが過去に遡って語彙を追っているかというと、1066年のノルマン人によるイングランド征服後1362年までフランス語を公用語にされていた、16世紀の後半になると、さらにラテン語、ギリシア語をはじめ、ヘブライ語、アラビア語などの流入も進んだ。母国語の再定義はまさに英国人のアイデンティを復活させるための偉業だった訳である。
それでも、どこの国でも権威を笠に足を引っ張る輩はいるから編纂作業は順風満帆と言う訳では無いし、スキャンダルが絡んでも不思議はない。
ウィリアム・マイナーの精神錯乱は南北戦争従軍時の今でいうPTSDが原因だから同情の余地はあるものの罪もない人を撃つなんて悩んで当然、看守は嘔吐していたが自身の陰茎を斬り落とすなんて酷いシーンに付き合わされた。
総じて、編纂の背景や苦労はわかったものの感傷的に描き過ぎているし、観ていて愉しい映画ではありませんでした。
「言葉」の重みを見せつけられる2時間
私の好きなYoutubeチャンネルに「ゆる言語学ラジオ」という言語学を取り扱った教養系のチャンネルがあるのですが、そのチャンネル内で「オックスフォード英語大辞典(以下、OED)」の編纂には殺人犯が関わっていたという話が出てきたことがあります。その際に紹介されていたのが本作『博士と狂人』です。
ざっくりですが事前に映画の内容については知っていたため普通に観ることができましたが、これってタイトルだけ見ると『ジキルとハイド』と勘違いしてしまいそうですよね。間違って鑑賞した方もいらっしゃるかもしれません。多分。
本作を鑑賞した感想ですが、非常に面白かったです。「全ての言葉を収録した辞典を作る」という前代未聞の辞書編纂プロジェクトに参加することになったアマチュア言語学者であるマレーと、彼の辞書編纂に協力していた収容所に収監された殺人犯マイナーの、何とも奇妙な友情と情熱の物語。若干説明不足に感じる部分もないわけじゃないけど、それでも十分に楽しめました。私は事前に内容を知った状態で鑑賞したので、事前知識なしで鑑賞した方の感想も聞いていみたいですね。
・・・・・・・・・・
貧しい家庭環境故に学歴は無いものの、卓越した言語の知識を独学で獲得した異端の言語学者であるジェームズ・マレー(メル・ギブソン)は、「全ての英単語を収録する」という前代未聞の辞書「オックスフォード英語大辞典(OED)」の編纂に携わることとなる。膨大な仕事量と不足する人員で先の見えない作業、マレーのアイディアで一般人ボランティアに協力を仰ぐことで人員不足はある程度解消されたように見えたが、言語学者でない協力者から送られてきた単語カードは使えないクオリティのものばかり。そんな中で、クオリティの高い単語カードを大量に送ってくれる協力者が現れる。それが、元アメリカ軍医で戦争のトラウマによって精神病を患い、殺人の罪で投獄されていたウィリアム・チェスター・マイナー(ショーン・ペン)であった。
・・・・・・・・・・
本作を観ていると、エニグマ暗号の解読に成功した天才数学者アラン・チューリングを描いた名作映画『イミテーション・ゲーム』を思い出します。ネタバレになるので詳細は伏せますが、ストーリーにかなり似ていますね。どちらも第一次世界大戦あたりに活躍した実在の人物の偉業を描いた実話を基にした作品ですし、ラストの展開がかなり似ているように見えました。本作を観て楽しめた方は、『イミテーション・ゲーム』もハマると思いますのでオススメです。
本作は、アマチュア言語学者のマレーと元軍医で知的な殺人犯のマイナーの友情物語と観ることもできますし、彼らの偉業を理解できずに圧力を掛けたりプロジェクトから外そうとする権力に対する反逆の物語と観ることもできます。
私はマレーとマイナーの関係性が凄く好きですね。特にマレーが最初にマイナーに会いに行くシーン。最初はマイナーが受刑者だったことを知り驚くマレーでしたが、話をしているうちにお互いの言語への情熱や知識量に関心し、どんどんと心を開いていく。そして最終的には面会時間が終わるまで、ひたすら二人で言語に関するクイズを出し合ったりして大盛り上がり。「言語」という共通の関心があったことで、あっという間に距離が近づいていくのが上手く描写されていました。
そしてラストシーン、マレーは生涯にわたってOED編纂に携わり、その一生を終えたことが描写されます。しかしマイナーに関してはあまり詳細な描写がありません。というのも、精神病の悪化などが原因で故郷のアメリカに送還されたマイナーですが、OEDに大きな貢献をした彼の偉業は周囲の人にはほとんど知られていなかった故に、孤独に寂しく余生を過ごしたとのこと。ラストに若干の哀愁を残して終わる本作の締めは、個人的には結構刺さりましたね。
非常に面白い映画でした。オススメです!!
辞書の編纂は狂人出なければできない
本当にそのとおりだと思う。
あって当たり前の辞書。
最初にどうやって作ったのかなんて想像もしたことがなかった。
最初は学士も持っていない人が編纂人だったこと(独学でどうやってあれだけの知識を身につけたのか、驚愕するしかない)。
編纂に殺人犯が関わっていたこと。
当時でもあり得ないことだったのだろうが、実現した。
現代で同じことが起きる可能性は、ゼロな気がする。
フレデリックにナイスアシスト賞をあげたい。
罪悪感が人を狂わせ、愛が人を救う。
これもこの映画のテーマのひとつだったと感じる。
いろいろあってへこたれてたけど、自分がやるべきことを貫くべきだと、意を新たにした。
これはもう
役者陣がすごい。ショーンペンはもちろんメルギブソンもそして他の人たちも俳優が演じているという気がしなかった。オックスフォード大辞典ができるまでのこれは実話を基にしているのかな?基盤となるものがあればそれを直したり追加したりするのは簡単だけどその基盤を作るのが大変なんだよね。
気が遠くなるような…
編纂に70年もの月日が掛かったとは。。言葉は時代とともにを変化する。それを過去の文献から、文例も載せ、意味の変化を記していく。ストーリーはその辞書の編纂の大変さもさることながら、博士と狂人という二人の人生にスポットを当てている。冒頭、この二人がどこでどうやって交じるのか謎だったが、互いに出会えたことが、その後の人生を大きく変えた。キリスト教の赦しも大きく影響を与えている。マイナー博士はその後彼女と会ったのだろうか。
始めたら信念を持ってやり遂げて
映画「博士と狂人」(P・B・シェムラン監督)から。
映画(英語版)「舟を編む」の表現がピッタリだったし、
もちろん、私の「お気に入り」に仲間入りした作品。
邦画「舟を編む」と違い、やや重たいストーリーだけど、
久しぶりに、重厚な作品と出会い、メモも溢れた。
貧しい家庭に生まれ、学士号を持たない異端の学者マレーが、
豊富な知識と根気が認められ、編集責任者を任される。
彼は、その時の喜びを家族に、こう伝えた。
「今までやってきたことを全て生かせる。
完成させるには気力がいる。
私はすべての言葉を調べて、定義する責任者になる」と。
それに対し妻は、しばらくしてこう励ます。
「迷いと恐れを捨てると約束して欲しいの。
始めたら信念を持ってやり遂げて」と。
あなたがこの仕事を受けるということは、
家族と過ごす時間を減らすことに他ならない。
その大切な時間を使うのだから、中途半端は許さないし、
それを認めた私たちに後悔をさせないで・・
そんな切実な気持ちが込められていて、胸を打った。
一生に一度の人生だからこそ、このフレーズは重かったし、
24時間、365日、そして数十年をかけて挑む大きな仕事って、
それを支える人たち(特に家族)の理解が必要だよなぁ。
言葉に救われた者にしか分からない、が
作中に登場したように「言葉は生きている」し、「脳は空よりも広い」し、「読書をしている時間は何者にも追われない。自らを追う」と思う。
この作品は二人の博士を中心に紡がれている。しかし私は、その二人を献身的に支える女性に魅了された。初めは文語を持たずただパートナーの死にうちひしがれていたものの、時の流れと共にマイナーによって言葉を教えられたことで、強く美しい女性へと変わっていったイライザ。「愛が呼ぶものは愛」失ったものをいつまでも追い続けない強さが見られる言葉となった。ロンドンでの安定した生活を捨てる勇気をパートナーと共にし、辞書編纂を始める際は「今から迷いを捨てて」と言葉をかけるエイダ。この二人の存在はとても大きかったように思えた。
評価を2.5にしている理由は、終わり方でたる。最後まで完成させて終わるのかと思いきや、Aの完成の時点で盛り上がる編纂者たち。最後にはマレーとマイナーの別れやマイナーの釈放を持ってきていた。今作品を人間ドラマだと考えるのであれば良いが、言葉の存在や歴史について着目していたと思っていた私としては疑問が残るものとなった。
前半はよかったが…
辞書作りに励む博士と用例収集を手伝う狂人の話。ふたりに友情が芽生えて狂人の狂気が薄れ始めたまではよかった。それ以降の展開は、頭に疑問符が躍るばかりでよくわからなかった。事実に基づいて作った結果なんだろうけど。
なぜ未亡人は夫を殺した狂人への「愛」が目覚めたのか?院長の治療の目的は何なのか?よくわからないが結果として狂人は壊れ切ってしまい、同時期に博士が狂人を組んでいたことが偉い人にバレてしまい、なんやかんやでとりあえずふたりが救われたところで劇終。
同じ辞書作りの映画でいえば舟を編むはとても面白かった。何が合わなかったのだろう。
タイトルなし(ネタバレ)
博士がメル・ギブソン、狂人がショーン・ペン
なかなかお二人ともイイお年になられたようで
最近のショーン・コネリーが亡くなって以来
私の好きだった人たちも歳をとるんだと勝手にショックを受けてる
物語はオックスフォード辞典を作る事になる博士と
その編纂に協力する事になる狂人のアメリカ人との関係を描いている
テーマとしては法的な罪の償い
被害者の家族が許してるのに贖罪は必要か?
一見狂人でも人の役に立つ事もあるのに
人を有効利用できない社会の有り様は
本当に考えなきゃいけない問題だろうな
能力を社会の為に役立たせるという目標を除いたら
何の為に社会的な制裁があるんだろうね
狂人でも社会の為になる事もあれば
まともでも社会の役に立たない人も居ると思う
考えさせられた一本だった
もし愛なら、そのあとに続くものは・・・
世界最高峰の辞書といわれる「オックスフォード英語大辞典(OED)」誕生にまつわる驚きの真実の物語の映画化。
19世紀半ば、英国オックスフォード大学で進められていた新たな辞書編纂作業。
しかしながら、膨大な単語の量に作業は頓挫しかけていた。
これまでの言語学者だけでなく、新たな視点を盛り込んで作業に拍車をかけるべく選ばれたのが、独学で多数の言語を極めたジェームズ・マレー(メル・ギブソン)。
彼の編纂方針でカギとなるのが、用例採取。
過去の文学・文献の中から、その単語の用例を抜粋し、語意の変遷を明らかにしようというものだった。
しかし、用例採取は容易ではなく、マレーは民間人の助けを借りることにした。
そんな中、マレーのもとに多数の稀少用例を届け出るものがいた。
その彼は、米国南北戦争で精神を病み、妄想による精神錯乱から殺人を犯して英国の精神病院に収監されている米国元軍医ウィリアム・チェスター・マイナー(ショーン・ペン)だった・・・
といった内容で、辞書編纂の中心を担うマレーと、塀の中から協力するマイナーのそれぞれの物語が交差していくさまが描かれていきます。
マレーは、辞書編纂の中心作業を担うが、在野の言語学者であり、貧しい家の出であることから大学などの高等教育を受けていない。
さらには、イングランド人で占められる言語学者のなかにおいて、彼のスコットランド育ち、スコットランド訛りは蔑みの対象になっている。
マレーにはそのようなハンディキャップがあるが、映画ではもう一方のマイナーに比重が置かれて描かれます。
映画の巻頭は、マイナーの殺人とその裁判の顛末であり、この時点では、彼の特異な言語能力(読書力と記憶力)は明示されていません。
精神病院に収監されてから、看守のマンシー(エディ・マーサン)から、本を贈られ、その本の間に辞書編纂の協力者を求める案内が挟み込まれたあとに、マイナーの秘めたる能力がわかることになります。
殺人を犯したマイナーですが、誤殺であるがゆえにそのことを深く後悔しており、被害者の遺された妻イライザ(ナタリー・ドーマー)と遺児たちのことが気になり、自身の米軍退役後の年金を彼女たちに贈ろうと決めるわけですが、その仲立ちをするのが看守のマンシー。
マンシー役のエディ・マーサンは『おみおくりの作法』の主役のひとですが、ここでも味のある演技をしています。
当初、マイナーの援助をかたくなに拒否していたイライザですが、マンシーの仲介でマイナーと面会。
やはり最初は拒絶の態度ですが、次第に軟化。
マイナーから字を教えてもらうまでに至り、心が絆されていきます。
絆されたイライザが、マイナーに贈る短い文が、この映画の肝です。
「If love....Then what?」 もし愛なら、そのあとに続くものは何?
イライザから赦しを得ることなど許されるはずもない、そんなことは自分自身を許せない、と考えていたマイナーは、こののち苦悩と狂気のどん底へと落ちていきます。
心身共に衰弱したマイナーのもとを訪れるマレーの言葉が、マイナーを救います。
「If love....Then...LOVE」 もし愛なら、そのあとに続くものは、やはり愛だよ。
辞書づくりの映画と思わておいて、帰着点は愛。
かなり、じーんと胸に来るものがありました。
髭が、鬱陶しい!(笑)
ようやく観ました。
英語も出来なきゃ、原作も知らない、
英和辞典作った学者の話としか。
正直、話と言うかストーリーがかなり散漫
に感じました。後、編集で調整していると感じるシーンがあり、感想としては「普通」
先入観として、辞典作りに焦点を充てていると思っていたので、マレーとマイナーが出会うまでが長いと感じました。
個人的にメル・ギブソンとショーン・ペンの人物像を同じくらいに扱っている為、辞典作りと精神疾患の患者のストーリーが同時進行で話が散漫に感じたのかと。
そもそも、マレーがいきなり辞典作りの責任者に抜擢されて話が進むので、辞典作りへの情熱に対する描写が弱く感じ、(言語学に強い一般人てだけ。)また、何故マイナーが辞典作りに協力する気になったかが唐突でした。
後、未亡人がマイナーに愛情を持ってしまうのですが、旦那殺した相手に、同情や境遇を赦してしまう感情はあってもあそこまで一途な感じになるかな?
仮に持ったとしてもあからさまに態度に出さないのでは?(原作通りと言われればそれまでですが。)
まあ、典型的な感想で、思ってたの違う印象。いい意味で裏切られたと言う事もなく、かと言って悪かったと言う程酷くも無い。なので「普通」です。
美術、演技などは、言うまでもなく素晴らしいです。
観れてよかった!
あまり下調べをせずにOED編纂のノンフィクションということだけを念頭に観たので、戦争や精神病の要素など心が痛くなる描写もあったことに驚きましたが、かなり印象に残りましたし鑑賞後も深く考えさせられました。
夫を殺害した犯人に恋に落ちるということが私には想像し難かったのですが、これは宗教による考え方の違いでしょうか。他の方のレビューをチラッと拝見して「赦すこと」と「赦されること」にそれぞれ壁があること、神に対する思いなど、なるほどと後々思いました。
大学の授業でOEDの素晴らしさを語ってくれた教授がいましたが当時は理解できず、OEDを使って英単語の 起源を調べる課題も中途半端に嫌々ながら仕上げてしまいましたが、鑑賞後は居ても立っても居られず”art”など調べてしまいました。
大好きな英語の奥深さ感銘し、戦争の恐ろしさを痛感した、そんな映画でした。出会えてよかったです。
直近では一番
109系が邦画に肩入れしているので、大概キノシネマにお世話になってます。で、ショーン・ペンのならず者が好きではないし、メル・ギブソンの自傷チックなとこも好きではないので全く期待せずに行ったら、良い映画でした…
ナタリードーマーって何かで見たことある顔ですが観たことなかったです。彼女がムサイダブル主演に一服の清涼で、博士の取り巻くが良くって、あの人はホーンブロアーかな?良いですね。看守も良い。お薦めできます。
精神病患者のリアル
過去の精神病患者に対する誤った治療や、精神病患者が辿る不安定がよく描かれています。
とくに、正常を保っているときの状態。
精神病患者は、ずっと異常な世界にいるわけではないという描写が素晴らしい。
ショーン・ペンの演技も凄い。
言葉のルーツを紐解くという作業が二人を近づけ、友情からリスペクトに発展し。
博士を取り巻く人々も、芯からの理解者。
考えに相違はあっても、折り合おうとする姿勢が、それを説明する言葉たちが美しい。
何が彼女の心を打ったのか、なぜ赦しを超える愛に発展したのかは、本人にしかわからない感情でしょうが、これが小説以上に観る者を圧倒するわけです。
最後までハラハラしながらも、エンドロールの最後まで余韻を楽しめる作品でした。
魂の演技に震えた。見事。そして奥深い映画。
メル・ギブソンとショーン・ペンがダブル主演なら、観ないわけにはいかない!
予想以上に良かった。。。
やっぱりショーン・ペンが圧倒的な存在感。
この人の、昔の死刑囚の話で「デッドマン・ウォーキング」を観て「この人はタダ者ではない」と震えた記憶がありますが、今回も同じくらい衝撃的な演技でした。
誤って人を殺してしまった罪を悔い続けながら、その遺族に許されることでさらに苦しむ様。
人間とは本当に繊細で複雑な生き物なのですね。
精神を患ってもなお、彼は良心を失わなかった。
・・・文盲だった彼女が文字を覚え、彼にシンプルなメモをそっと渡す。
I can because of you
言葉を知ることで、書物を読めるようになることで、どれほど世界が広がるか。
言葉の大切さ、尊さ。生きる力になること。
作品自体は世界最高峰「オックスフォード英語大辞典」の完成秘話がストーリーの軸ですが、メル・ギブソンとショーン・ペンの友情ものとして観ても良し。
宗教的に「赦しとは」「罪とは」という視点から観ても考えさせられ、奥深い作品だと思いました。
うん、観てよかった〜!
【”言葉の翼”を持ち、英語圏に貴重な足跡を残した”交わる筈のない”二人の男の物語。二人と関わる二人の女性の振舞いと、19世紀の意匠が印象的な作品でもある。】
ーある晩、PTSDに依る狂気に取り付かれた男:元アメリカ軍医師マイナー(ショーン・ペン)は、誤って罪のない男を射殺してしまう。その男には妻メレットと幼き子供が6人居た・・。
一方、スコットランドの貧しい仕立て屋の息子マレー(メル・ギブソン)が、その豊富過ぎる言語知識故に、夢叶い、オックスフォード英語大辞典(OED)の編纂責任者に抜擢される所から、物語は始まる。-
■印象的なシーン
・マイナーは精神病院に収監されるが、守衛の一人が大怪我をしたときに戦時を思い出し、正気に返りその男を救うシーン。
ーマイナーの姿を見ていた別の守衛マンシー(エディ・マーサン)は、その後、マイナーとメレットとのやり取りを取り持つようになる・・。ー
最初は拒絶していたメレットだが、マイナーからの謝罪の意を込めた援助の数々に徐々に心を開いていくシーン。
特にクリスマスのシーンが良い。マイナーが戦火で心を病んではいるが、元々は健全な心の持ち主であることが分かる。-
・マレーの辞典編纂過程で、17,18世紀の言葉のデータが決定的に足りない時に、マイナーから送られてくる膨大なデータ(紙片に記されている)。
そして、会う筈のない二人が初めて会うシーンと、その後の二人の間に育まれていく行く絆の幾つかのシーン。
ーマレーもそうだが、マイナーの驚愕の語彙力と読書量には、脱帽する。知的好奇心が擽られるが、残念ながら私には、概ね分からない・・。-
・マイナーとメレットが初めて会うシーンから、徐々に距離を縮めて行く過程。文盲だったメレットに少しづつ言葉を教えていくマイナー。
だが、彼女からの2通目の手紙を読んだ彼は・・・
-”あわわわ・・” 男だったら、物凄くイタイシーン。だが、マイナーの人間性と狂気性が分かる。現れるメレットの夫の亡霊・・。-
・マイナーがメレットの子供たちの名前を一人一人言いながら挨拶するシーンで、長女だけが、マイナーの頬を引っぱたくシーン。そして、その後マイナーが裁判にかけられた際に、メレットが彼を擁護する言葉を述べる際に、頷く姿。
ー”マイナーを時間がかかったが、漸く赦せたんだね・・。”
ここでの、韓国や日本に根付く”恨(ハン)”の文化とキリスト正教に基づく”赦し”の文化の違いを受け入れるかどうかで、今作への受け止め方は違って来ると思われる。-
・マレーの辞書編纂に犯罪者マイナーが関わっている事が分かり、任を解かれるシーンでマレーの妻エイダ(ジェニファー・イーリー)がオックスフォード大の関係者たちに ”特にマレーの出自、人種に偏見を持つ人物二人に向け” 話す言葉。
ーこのシーン、とても良い。怒りを込めた言葉を静かに笑顔を浮かべ話す姿。沁みる。ー
<二人に対する様々な横槍の中、妻の進言もあり、オックスフォード英語大辞典編纂の仕事に戻ったマレー。
そして、病院長の無理な治療により、強固症になってしまっていたマイナーが”ある人物”の行為で、正気に戻るシーン。
夫を殺されたメレット・イライザとマレーを支える妻エイダの言動がこの作品を、より感慨深く、見応えの有る作品にしている。
重厚で、見応えある作品であると思います。>
言葉の重み、進化
英単語に詳しく単語が持つ複数の意味合いなどの知識があればこの作品への理解が深まるように思える。
残念ながら英語に詳しく豊富な知識があるわけではない為所々理解ができないシーンや台詞はあったが、マレーとマイナーの各々の人生にフォーカスを当てながら作品を観るスタンスでも非常に楽しめる。
日本語は世界的にも最難関の語学だなんてよく言われるがこういう作品を見ていると英語も中々複雑で非常に難しさを感じる。当初は作中でも5年以内にはとマレーは発言してたが、完成させるまで次代の者に引継ぎ含め70年。この数字だけでも言葉の重み、歴史の深さを感じさせられる。
マレーのパートは比較的見易いのだがマイナーのパートは中々複雑。戦争で心のバランスを失い人を殺めてしまう。その被害者家族を自身の生涯を捧げることを誓いサポートすることで被害者の妻と互いに恋に落ちてしまう。マイナーだけで一つの作品を作れるのではないかと興味を惹かれる人物背景である。
マレーとマイナーという2人の偉大な人物を一つの作品で描かれている為とても展開も早く見応えのある作品と個人的には感じた。
全21件中、1~20件目を表示