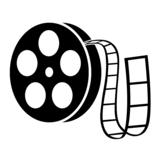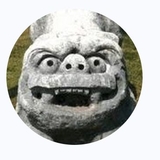ローサは密告されたのレビュー・感想・評価
全22件中、1~20件目を表示
欧米メディアの報道ではうかがい知れないフィリピンの闇
麻薬のはびこり、警官の腐敗が状態化したフィリピンのスラムの実態をリアルに切り取る作品。フィリピンで麻薬と言えば、ドゥテルテ大統領が、撲滅のための過激な政策が、欧米諸国から問題視されているが、この作品はドゥテルテ政権誕生以前のスラムの現実を描いている。
雑貨屋を営む、ごく普通の貧しい家庭が生活費のために麻薬を売っている。ある日妻のローサが逮捕され、釈放に高額の保釈金か他の売人を密告するよう強要される。そうして密告が連鎖していき、地域の信頼は崩壊。警官は押収した麻薬を横流し。この人々に救いはあるのか。一筋縄ではいきそうになり、社会が腐敗していく連鎖がドキュメンタリータッチで紡がれる。
主役のジャクリン・ホセがフィリピン人として初のカンヌ女優賞に輝いたが、そのリアルな佇まいが素晴らしい。ケン・ローやダルデンヌ監督などの作品が好きな人にオススメ。
ローサの最後の涙がすべてを物語る
<映画のことば>
「あっ、ローサおばさんだ。
アイスある?
0.5グラム売ってもらえない?」
ラストシーンで。おそらく、あれが彼女の初めての食事だったのでしょう。
ほんの粗末なものだったとしても。
警察署から外に出て以来の。
そして、そのときに、彼女の胸に去来し想いは、どんなだったでしょうか。
長く空腹だったことの惨めさ
最後の金策にも成功して、なんとか急場を乗り切ることができたことの安堵
「アイス」の販売に手を染めてしまったことへの悔悟
誰かが密告したのだろうか、その不安と密告者に対する恨み
自らの無思慮についての怒り
もともとの貧乏の辛さ、悲しさ
そのどれだったのか、はたまた、まったく別の思惑だったのか。
まだまだ観賞眼の乏しい評論子には、いずれとも断定はしかねるのではありますけれども。
おそらくは、貧乏から抜け出すために、方便として手を出しただけのはずだった「アイス」の販売ー。
よもや、それが、まさか自分や家族の生活をいっそう苦しくさせることになろうとは。
その矛盾に思いが至ると、観終わって、本当に切ない一本だったと思います。
内容的には劇映画で、登場人物も場面設定もフィクションのようですけれども。
しかし、淡々と進むストーリーは、まったくをもって、一編のドキュメンタリー作品を観ているかのようでした。
監督インタビューでは「本作で描かれているのは完全な社会ではないかも知れませんが、人間性についての物語です。助けを求めていたり、チャンスを与えられれば、自らの人生を変えることのできる人たちの物語です。サバイバルの物語でもあります。最も重要なのは、家族の物語だということです」と語られていましたけれども。
その製作意図のとおり、申し分のないヒューマンドラマにも仕上がっており、文句なく佳作の評価が適切な一本だったと思います。
(追記)
本作を警察関係者にも観てもらったか、というインタビュアーの問いに、警察にもDVDを送ったとした上で、監督は次のように答えています。
「一部の警察官が不正を働いているのは事実ですが、すべての警察官が同様な訳ではありません。この映画は警察の暗部を描いていますが、それは実際に起きていることでもあります。もし、この映画を観た警察官が不正を働いていないのであれば、恥だと思う必要はないのです。それは、世の中と同じです。よい人もいれば、悪い人もいる。社会の悪い面を映画で描くことが、普通の観客にとって必要な時もあります。映画を観た人が、何か行動を起こす、社会を変えようとする、という作用をもたらすことがあります。」
この監督のコメントを聞いて、評論子の脳裏には『日本で一番悪い奴ら』(実は、評論子もエキストラとして映っていたかもしれなかった・汗。エキストラでけっこうな協力したので、エンドロールには、確か評論子らが入っている映画サークルの名前が入れてもらえていたと記憶しています。)が思い浮かびましたけれども。
翻(ひるがえ)って考えて、日本の警察も、同じように腹は太いのでしょうか。
気になってしまったのは、独り評論子だけではなかったことと思います。
ドゥテルテ大統領就任前でもこれだから・・・
マニラのスラム街で小さな雑貨店を営むローサと夫ネストール。四輪自動車が通れないほどの小路にひしめく露店や小売業。どことなく戦争直後の日本の闇市にも似た雰囲気で、人々の絆も深そうな賑わいを見せている。ローサには4人の子供たちがおり、雑貨、駄菓子を売るだけでは家計を支えられず、本業に加えて少量の麻薬を扱っていた。ある日、密告によりローサ夫婦は逮捕される。「刑務所に入るわけにはいきません。貧しいんです」・・・
売人の密告をするか、保釈金として20万ペソ(日本円で40万強)を払えと言われ、しぶしぶ麻薬を彼らに売っていたジョマールの名前を挙げる。電話をさせられ、売人ジョマールを捕まえた警察。巡査たちはジョマールにも金を要求するが、ジョマールが上級警部へ携帯メールしたために袋叩きにする。何とか15万ペソを手に入れた巡査たちだったが、足りない5万ペソをローサ夫婦に要求する。保釈金とは名ばかりで、金を山分けし、彼らのふところへと消えていくかねなのだ。
ローサの子供たち女子高生のラルケ、長男ジャクソン、次男アーウィンが警察を訪れて、なんとか両親を解放しようと懇願するが、5万ペソの要求は変わらない。ラルケは親せきから金を工面しようと頭を下げまくり、ジャクソンは家のテレビをなんとか売ろうと頑張り、アーウィンは男色のおっさんを捕まえて体を売るという悲しくなるほど惨めな行為で金を集める。ようやく貯まった4万6千ペソを持って警察へと向かうが、足りない分はラルケの携帯を質に入れるしか道がなかった・・・
ラストのローサの涙には少なからず心を揺さぶられるが、最も悲惨だったのはやはり次男アーウィンの行為。映画はずっとハンディカメラで彼らを追い、リアルな貧困層を映し出していたのですが、警察署の周りをぐるぐる歩くシーンは何か意味があったのだろうか。ローサたちを尋問する取調室には制服の巡査がいなかったし、オネエ野郎と呼ばれる子どもまでいた。アットホームな対応をするものの、巻き上げた金を着服するという特別室みたいなものだったのかもしれない。
映画としてはラストに大きな展開もなく、驚愕のエンディングを期待していたのに裏切られた感じもする。訴えたい内容も伝わってくるのですが、まだまだ甘いようにも感じるのは、ドゥテルテ大統領が就任してからは映画以上の凄惨な現場が溢れているだろうから。麻薬の売人たちは銃殺してもかまわない。刑務所に自ら入る売人たちといったニュースも記憶に新しい。ただし、この出来事を他人事のように捉えてはいけないのだろう。日本だって共謀罪が成立したのだから、ちょっとした政治的言動によってテロリストとして扱われ、密告も日常茶飯事になる可能性があるのだから。
【2017年10月映画館にて】
【”密告の負の連鎖”】
ー 愚かしき男:フィリピン大統領に民衆からの圧倒的支持を受け1988年から国を統べるロドリゴ・ドゥテルテである。トランプが、まさかの米大統領に就任した際には、チャッカリお祝いをし、ミニトランプとも言われた男である。
今作では、無能だが悪智恵だけは働く男が、国のトップになってしまった前の市井の人々が足掻く姿、及び愚かしき警察と称するチンピラの姿を、ブリランテ・メンドーサ監督が痛烈な批判の視線で描いている。ー
◆感想
・国のトップを統べるモノには知性、器、教養、リーガルマインド、等々人間として最小限必要な事が身に備わってる必要性を改めて、思い知る。
尚、この作品にはロドリゴ・ドゥテルテは一切登場しない。彼が就任する前であるからである。でも、この混沌状態・。
・描かれるのは、マニラの混沌とした街で、必死に小さな雑貨屋で生計を立てているローサ及びその家族の姿である。
その雑貨屋では、家計を維持するために少量の麻薬も売っている。
・ある日、その事実を密告する者が出たために、ローサと、夫ネストールは警察と称する連中に摘発される。
ー この、警察と称する連中は公権力を衣に仮り、ローサ達から法外な金を引き出そうとする。そして、そこで巻き上げた金を警察に上納する・・。暴対法施工前の、どこやらの国と同じである。ー
・街中では、少年たちが、シンナーを吸っている・・。
・劇中流れる、グリッジノイズが気に障る音響も印象的である。
<鑑賞当時、この作品はドキュメンタリー作品かと思って観ていたのだが、ナント、ローサを演じたジャクリン・ホセは第69回カンヌ国際映画祭でシャーリーズ姉さんやイザベル・ユペール姉さんとクリスティン・スチュワートを制し、フィリピン初の主演女優賞を受賞しているのである。
ラスト、マニラの混沌とした夜の街を見ながら、涙するジャクリン・ホセの姿は、久方振りに鑑賞すると、受賞は納得してしまった作品でもある。>
<2017年9月23日頃、京都シネマにて鑑賞>
<2021年8月8日 別媒体にて再鑑賞>
フィリピンのスラム街お母さん
これが実態(ドゥテルテ政権以前)か
手持ちカメラで後をついていくスタイル
照明なし
サリサリストアを営む。でかいスーパーが仕入先。
アイス(覚醒剤)も売ってる
子沢山
20万ペソの賄賂要求
ローサが売人ジョマールを密告した
売人にも20万ペソ
署長にも上納金
上級警部にご注進したら殺された⁉かと思ったやん。
てか売人も警官?
奥さん読んで賄賂請求
あと5万
息子2人と娘来た
正規逮捕じゃないから記録がねえ
やばい、売った売人が怒ってる
子供らが金集めに奔走
次男はおっさんに体売る
ティルデ伯母さんも文句言いながら金出してくれた
ローサはボンボンに密告された
長男のTV危うく
体売っても、と思ったら前からの付き合い?
3人で一日集めてなんぼになったかな
46,000
惜しい
残り稼ぐためローサが出ていく
パキスタン人みたいな質屋
小銭まで取るのか!
屋台の串もの
移動屋台の物売りは家が無いって事なんだろうか
またそこからやり直さなきゃ、って終わり方なんだろうか
ぐっとくるラスト
こんなにぐっとくるラストシーンを見たのは久しぶり。
麻薬密売を密告された夫婦とその子供達が、保釈の金策に奔走するというごくシンプルな内容。とくにどんでん返しやサスペンス要素があるわけでもない。
麻薬が蔓延する都市、汚職が常態化している警察を描いているのが、テーマはそこではないような気がする。もちろん、重要な要素ではあると思うが、この映画、本質は違うところにある。
言葉にするのが難しいが、生きている実感、普段気付けないありふれた日常にこそある幸福感、それを映しているような気がする。
雑多な町の風景は生きていることを感じさせる。
なによりラスト。涙を流しながらお団子を頬張るローサ。視線の先には、小さな店の片付けをする家族の姿。いつも食べてる平凡なお団子の味。
犯罪に手を染め捕まってはじめて大事なものに気づく。遠くなってしまった平凡な日常が輝いて見えてしまう。犯罪に限らず、誰かを亡くしたり、病気になったり、何か絶望的な状況になったことがある人ならば理解できる心境だと思う。なにもかもが輝いて見えてしまう、あの感じ。
スラム街の現実
黒ブラ
フィリピンもグローバリズムの犠牲者
麻薬に汚染されたフィリピンの現状をドキュメンタリー的な手法を用いて描いた映画である。
まず何よりフィリピンのスラム街の小さな雑貨屋であまりにも簡単に覚醒剤などの麻薬が手に入ることに驚く。
また、それを売る側にも買う側にも全く罪悪感のようなものが感じられない、いたって日常なことにさらに驚く。
もはやこの手のマグマのような力強さを放つ映画は日本では作り得ないことを感じさせる。
発展していない社会は自分たちの目を背けたくなるような暗部を暴こうと果敢に挑戦できる。
日本にも厳然として暗部はあり、それをテーマにした作品は制作されているのだが、独居老人の問題であったり、ニートであったり、ある一定の世代間でしか共有できない問題をテーマにした場合が多く、社会全体として共有しうる大きなうねりに発展するものは少ない。
北朝鮮問題がタイムリーな話題であるので安全保障などは本来は日本国民全体に関わる大きな問題だが、実際に核爆弾でも落とされない限りどこか遠いことのように感じている国民は多いだろうし、そもそも日々の生活に直結しない。
表面的には日本は発展して安定した社会になったということの現れなのだろうが、現在の日本映画からこの手のパワーを感じることはまずない。
この映画のコンセプトはドゥテルテ大統領が当選する前に作られたようだが、なるほどドゥテルテが密売人は殺して構わないと発言して麻薬撲滅戦争に突き進んでいったのはこういう社会だったからかと妙に納得させられた。
それぐらい庶民の日常に麻薬があふれている。
作品中、セブンイレブンの前で小学生ぐらいのこどもが2人、地べたに座り込んでふくらんだビニール袋から何かを吸い込んでいるシーンが登場する。
シンナーを吸い込んでいるように見えるが、警察署で雑用係のようなことをしているこどもはそれを見かけても全く気に留めない。
また一方で取り締まる側の警察が麻薬関係者に保釈金をふっかけてそれを横領するという問題も描かれている。
この映画を観るとドゥテルテが厳しく取り締まってもフィリピンの麻薬問題は解決できないのではないかと危惧してしまう。
逮捕されたローサと夫のネストールは自分たちが釈放してもらうために麻薬の売人をさらに密告していく。
だがそこにも後悔の色は全く感じられない。あっさり警察に売ってしまうのだ。
どんなに普段仲良くしていても家族以外は全く信用しない社会が描かれているのだ。
この映画はタガログ語の会話が90%以上を占めて、英語の会話はほとんど登場しない。
両親の保釈金を工面するために次男がカフェで人を待つシーンがあるが、次男の横には漢民族系だろうか上流階級と思しき若者たちがPCについての会話をしている。
彼らの会話がまさに英語なのである。次男はそんな彼らをうらやましそうに眺める。
本作の監督はインタビューの中で「20%の裕福な階級はこの国を代表しない」と言っているがまさに言語の断絶も意識して描かれているのである。
また、筆者はこの映画を観て現在の日本に住んでいる幸運を感じたが、「先進国でも不正はあり、もっと上層部で行われるため、人の眼に触れることがないだけ」という監督の言葉を知ってそんな思いも吹き飛ばされてしまった。
ドキュメンタリー的な手持ちカメラの長回しは作品の性質上絶大な効果をあげている。
フィリピンの気候を反映してか土砂降りになり、道路などが水溜りになり場合によってはぬかるむシーンがあるが、撮影陣は大変だったろうことが推察される。
またローサ役のジャクリン・ホセは本作の演技が高く評価されてカンヌ映画祭で主演女優賞を受賞したようだが、その他の出演者も真に迫っていて素晴らしい。
監督は出演者たちに脚本も与えず台詞はある程度自由にさせたようだ。
そのせいか出演者の演技に全くもって不自然さがなく見事だ。
発展途上国においても裕福な20%とそれ以外の80%の貧困家庭、世界はどこも似たような状況であることをあらためて認識させられた。
1000本に1本の価値あり
ちとオーバーに書き過ぎたが、年50本映画館で映画を見るとして、2年に1本出合えるかどうかというレベルの作品だ。
こんな作品を見ると、日本映画の99.9%、ハリウッド映画の90%は見る価値のない、地球資源の無駄遣いと思えてくる。
映画の根底にあるのは「貧困」以外の何物でもないのだが、日本含め、先進国に目に見える貧困がないからといって、描ける素材がないわけではないだろう。
確かに60年以上前の日本にも、この映画と同じような状況はごろごろあり、日本映画もそうしたものを素材にするなどして、すごかったとは思う。
豊かになり、平和になったことで、簡単にそういう素材が見つからないというのは分かりはするけれど…。
今の日本映画、少なくとも実写ものには見るべきものはほとんどない。
昭和20年代、戦争直後の日本は確か、当時のフィリピンよりGDPは少ない時代があった。
フィリピンは60年たっても人口だけ増えて、社会は成長してないんだ…。みんな日本に来たがるのはわかる。
ラストシーンの絶品さ
フィリピンの肝っ玉母さん
フィリピン映画が一般の劇場で公開され、結構人も入っているというのは、私たちアジア映画ファンにとってはうれしいことだ。近年の大阪アジアン映画祭ではフィリピン映画が毎年結構たくさん上映され、そのレベルの高さには目を見張る。
さて、この「ローサは密告された」だが、どこまでが事実を基にしているかは、私たちには推し量ることも難しいが、ある程度は現実のフィリピン社会を反映していると考えていいのだろう。この厳しいフィリピン社会を生きる人たちと、苦境を生き延びる力強さが感じられる作品だ。
スラム街で雑貨屋を営むローサ。夫は麻薬を扱い、自分もときどき手を出しているようだ。このスラム街の中では比較的裕福な方の部類に入るのであろうローサ一家だが、それでも生活はかつかつだ。(もちろん、社会全体、ましてや世界を基準とすれば超貧困家庭だが。)
そんなローサ一家の生活を映画は時系列に沿って淡々と描いていく。何のけれんもなく、トリックやどんでんもなく、本当にストレートな表現だけが使われている。ドキュメンタリータッチと言ってもいいかもしれないが、ちょっと違う。
ある日、ローサの店に警察の手入れが入った。彼らはローサ夫婦を連れ去るが留置所に入れるわけではなく、自分たちの部屋に閉じ込める。もちろん、賄賂が目的だ。20万ペソ(50万円くらい)出せば解放するという。そこからがこの一家のしたたかなところ。さまざまな交渉術と家族の金策でこの危機を乗り越えようとするのだ。
この作品で「正義」が声たかだかにうたわれることは一度もない。この映画にも、フィリピン社会にも正義など存在しないのだ。警察が「悪」を非難することもないし、正しい道を歩むよう説得することもない。捕まった夫婦は裁判や服役などということはいっさい考えていない。はじめから金で解決することしか頭にないのだ。映画もいわゆる「社会派」の態度をとらない。
警察は減額の代わりにたれこみを要求し、(そもそもローサ夫婦も密告されたのだが)それで捕まった売人はさらに別の警察幹部に連絡をとろうとする。誰も「法律」による解決など望んでいない。
ローサ夫婦は4人の子どもたちの必死の金策により何とか解放されるのだが、それで何かが解決されたわけではない。さらなる密告の連鎖は続いていくだろうし、彼ら夫婦には大きな借金が残る。
しかし、映画はとことん暗い印象を残すかというと、決してそうではない。金策に走り回る一家のしたたかさ。また、悪態をつきながらも彼らを助ける親戚やコミュニティ。それはそれで何とか回っていくフィリピン社会の不思議さみたいなものも描かれる。
我々の目から見ればとんでもなく絶望的な社会を描きながら、なぜか暗くはない。そこがフィリピン社会の面白さでもあり、この映画の良さでもある。
ローサは密告された 私は吐きそうになった
実話でなくても、この映画が造られた現実に、気が滅入ります。
「ボーダーライン」のセリフで、メキシコ警察は信用するな。麻薬カルテルに買収されてるぞ。ってありましたけど、買収されない道を選択した国も、大変ですね。腰にぶら下げた硬いもの使って、副業に余念がない姿は、給料だけで生活できない現実なのでしょう。腹が減っては、正義はできぬってことですかね。フライドチキンで、お腹いっぱいになってましたけど。結果、弱い者がさらに弱い者を叩く、ブルースは加速してゆくようです。
世界を支配するのは、明らかに、セックス、ドラッグ、バイオレンス。ここに、お金が潤滑油となって回転してゆくと云う、知りたくもない現実を、手振れ補正のない映像で、興行するあたり、ほとんど鬼畜の所業ですね。映画観て吐きそうになったのは、「ハートロッカー」以来です。
穴の開いたパンドラの箱みたいな作品ですが、家族愛と、悪態つきながらも、手を差し伸べる人がいるだけ、救いのある話です。
重たい作品ですが、観て損はないと思います。観て気分が悪くなった時は、おばちゃ~ん、アイス0.5ちょうだ~いって、呼んでみましょう。きっと…手が後に回りますね。
予告、タイトルのまんま
ドキュメンタリーのようにうまく作られていたと思います。
ただ警察の腐敗やローサの生活などすべて想定の範囲内での出来事。
ニュースなどで見聞きするまんまでした。
クスリを売って、捕まって、残された子供達のドタバタ、それだけです。
この臨場感と緊張感!僕らの世界とは全然違う!
全22件中、1~20件目を表示