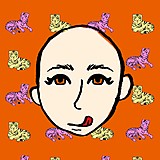セザンヌと過ごした時間のレビュー・感想・評価
全20件を表示
セザンヌ没後110年記念
セザンヌの人となりを、ゾラとの関係を軸に描き出した作品。二人が幼馴染だったと知らなかったので、それなりに面白く観た。
ゾラが画家を主人公にした不幸な小説を書いてセザンヌが激昂し喧嘩になったが、その後も二人は距離を置きながらもやり取りをしていたとのストーリー。
登場人物がおじさん主体でひげもじゃの方が多いため、印象派の面々だなとは分かるのだが誰が誰だか判別が難しく、少々混乱した。笑
エクスの風景が美しく、セザンヌの家や山など、彼の絵画になっている場が再現されているのが良かった。
天才芸術家のことが理解出来ないゾラ、世間、そして自分
ダニエル・トンプソン監督による2016年製作のフランス映画
原題:Cezanne et moi 「セザンヌと私」、配給:セテラ・インターナショナル。
最初のタイトルバックの映像がとても美しく芸術的で、大いなる期待を抱かせたのだが、
・・・。
天才は理解されにくいというが、実際に幼馴染ゾラの友情を踏みにじるばかりの嫌な奴。ゾラはセザンヌのことを天才と評価するが、何をもってそう断言しているのか分からず、共感を覚えなかった。
落選ばかりと映画の中でも語られていたが、セザンヌの初期の作品を調べてみると、暗い画調で独自性も無く魅力を感じなかった。それが、映画でも目標とするところと語られていたが、最後に紹介される作品群で示されていた様に、空気の動きを感じさせる画期的な画調に進化していく。
何がこの進化を生み出したのか?それを映画で明らかとされることが私の期待するところであるが、妻を邪険に扱う等、狂気的なところだけが見せられてかなり不満を覚えた。
まあ、この映画は天才を理解できず、自分の才能の平凡さに絶望し、自覚的には売文行為に邁進するゾラ自身を主題とする映画かもしれない。フレイア・メーバー演ずる美しい家政婦ジャンヌ(実際綺麗だった)に、年甲斐もなく恋心を抱き悶え苦しむゾラ。最後、天才なのにセザンヌの才能は開花しなかったと結論付けるが、画商の活躍で遅咲きながら評価され始めているセザンヌ。結局、芸術家としては敵わなかったゾラの姿が印象つけられる。
最後、サント・ヴィクトワール山の実映像に、セザンヌのこの山を描いた数々の傑作を重ねる映像は、天才性を示していて素晴らしかった。
製作アルベール・コスキ、脚本ダニエル・トンプソン、撮影ジャン=マリー・ドルージュ、
美術ミシェル・アベ=バニエ、衣装カトリーヌ・ルテリエ、編集シルビ・ランドラ、音楽
エリック・ヌブー。
ギョーム・ガリエンヌ(ポール・セザンヌ)、ギョーム・カネ(エミール・ゾラ)、アリス・ポル(アレクサンドリーヌ・ゾラ)、アリス・ポルデボラ・フランソワ(オルタンス・セザンヌ)、フレイア・メーバー(ジャンヌ)、サビーヌ・アゼマ(アンヌ=エリザベート・セザンヌ)、イザベル・カンディエ(エミリー・ゾラ)。
絵はやめない、描きながら死ぬ
売れない画家の、早く世に出た幼なじみに対するやっかみが凄まじい。しかし物書きなら自分のことを書かねばならない現実において、画家の私生活は絶好のネタだ。
それを晒さすしかないジレンマの繰り返し。
セザンヌはよくケンカしたという逸話は読み知っていたが、これほど激しやすい人とは思わなかった。嫉妬が憎悪になり物を投げるは壊すは。
ゾラとセザンヌが互いを傷つけ合いながら認めてくれないアカデミーやサロンに悪態をつき創作に苦悩する姿が凄まじくも愛おしい。
「絵はやめない、描きながら死ぬ」
見かねたモデルを務める妻から「絵を辞めて!」と言われてセザンヌの人生はどうなったのか、物語としても出色だ。
男同士の友情の微妙なバランス
映画に出てくる画家はだいたい言動についていけないが、このセザンヌもそう。
男同士の友情ってこんな感じなのだろうか。心が通じ合っていると思っていたら、そうではないような、微妙なバランスで成り立っているのかも。
セザンヌは喧嘩したつもりはなくても、ゾラには許せないところに触れてしまったのだろうか。
最後のゾラに合わず帰ってゆくシーンは印象的だった。ゾラは自分のことを評価してくれている、そして会いに来てくれると心の底では思っていたのかもしれない。
色彩がきれい。フランスっぽくもあり、また特に子供の頃のシーンなどイタリアっぽい。独特の美しい色彩。
セザンヌとゾラが同時代に生きていたなんて知らなかった
男の友情も女同士も友情なんてものに縛られながら生きるなんてまっぴらだと思ってしまった。方や小説家。しかも早々と流行作家で画家は人生の終焉近くまで注目されない。そして小説家は孤児で貧乏。画家は裕福家庭に育って世間を嘗めきってしまっている。どちらともに創作に七転八倒。創ることに苦痛が伴うことを感じ、妬み・嫉みの発露をお互いに求めてしまう。
生身の生き物だから人間だから仕方がないはずなのに会えばどちらかが聴かなくてはならなくなる。ゾラが大概はその役割だったんだ。セザンヌは育ちがお坊ちゃまが故にゾラに甘え倒している。決裂は時間の問題。
「心がない奴には何も表現できない。」~当たり前だろう。
モノを作る者の原点は哀しみなのだから・・・・。
人の心を読める・・・そんなことは嘘バチなのだ。
自分の心さえ読めぬ者には人の心は動かせないのだ。
映画のセリフにはなかったが、エンディングロールが流れる間にそんなことを感じたんだ。
愛しすぎたがゆえの
家族でも恋人でも友達でも、愛しすぎは破滅のもと。
人間の感情の話だからコントロールも難しいのだけど。
別れは穏やかなものではなかったけれども、それでもここまで想えた友人がいたということは、かげがえのない思い出となる。
しかしセザンヌってこんなエモーショナルでアグレッシブな人だったとは、知らなかった。
マネさんやルノアール、モネあたりの絵が好きだったけれど、バックグラウンドを知った今、セザンヌ作品も順を追って見直してみようと思います。
歪な友情物語
セザンヌとエミール・ゾラは若い頃からの友人、ゾラが小説にセザンヌの暗部を描写したことで絶交したと伝えられるエピソードを軸に二人の真の心の内を探ろうとするダニエル・トンプソン脚色の歪な友情物語。諍いを中心に話が前後するので分かりにくい、まるで監督の仮説の検証を見せられている様です。もっとも後年(2014)、交友が続いていた書簡が発見され映画の信憑性が裏付けられた形です。
昔、美術館で観たセザンヌの静物画は薄い絵の具が何層にも塗り重ねられていて、厚さはコインが挟めるほどだった、陰影や色彩を超えた光の魔術師の印象が強く残っていたので彼の作風の秘密に触れられるかと期待したのだがあまりにかけ離れた人物描写に失望を禁じ得なかった。
もっともセザンヌ自身の人柄の問題だろうから監督を責めても仕方ない、むしろ女性を見る卑しさや下劣な描写は女性監督であることで免罪されているのかもしれない。
ランボーやゴッホ、ゴーギャンなど当時の芸術家の乱行振りや醜聞事件は多いから驚くほどのエピソードではないにしても終始、毒のある言葉が飛び交うドラマは良い気がしない、セリフに頼らず演技で語って欲しかった。貧困時代、雨の中、飛べない小鳥を捕まえて羽をむしるゾラの描写は見ていて辛い、豪邸にペットと住むゾラの変貌ぶりは人間の本質なのか、セザンヌに「お前の絵には心が無い」とはゾラもよく言えたものだ。
この種の伝記ものを観る方が悪いのだがセザンヌ鑑賞に無用なバイアスがかかるとしたら悔やまれる、作品の価値は作者の人格と無縁ではないが善い人の絵が優れているわけでもなく、逆もまた真であるところが芸術性だと思う・・。
タイトルなし
セザンヌファンは、打ちのめされるのを覚悟して!
学生の頃からずっと好きだったセザンヌ。画集を通じて、それなりに思い描いてきた彼のイメージが、この映画で塗り替えられた。
社交性に欠けた頑固者ながら、禁欲的な画風は信心深い孤高の画家ならではと勝手に思っていた。
世間の無理解に背を向け、自分が信じる自然の輝きを表現する方法を追求し絵に没頭した頑固者、そう信じ込んでいた。
小さなエピソードや登場人物が交わす会話、インテリアや衣裳に至るまで、資料に裏打ちされたものだろう。
映画の中の晩年のセザンヌは卑屈だ。成功したマネの名声を妬み、批判し嘲笑する。ゾラの作品を恨み、ゆすりまがいの言いがかりをつける。
最も友達になりたくない種類の人物。
印象派の旗揚げになった落選展や、仲間たちの口論の場面は臨場感いっぱいで、目をみはるほど新鮮。
マネやモリゾ、タンギー爺さんの姿にも、時代の空気を感じる。
「セザンヌとゾラの40年に渡る友情物語」だが、セザンヌの良いところはなくファンには辛い。
彼の死後、絵を世間に売り込んだのは、遺族の生活を心配した昔の仲間だったのではないだろうか。仲間たちの尽力でセザンヌは天才になれたのだと思う。
最大のギャップはセザンヌの女癖の悪さ。女性に関心がない朴訥人だと思っていたので真逆!
家庭では息子ポールを産んだ夫人を、自分の自由を阻む「錨を付けた女」と疎んじ、母や妹が入籍を勧めても彼女を妻と認めず冷淡だった。
没落した元資産家出身のプライドが許さなかったと言うより、女性に人格を認めていなかったのではないか。
セザンヌの冷え切った家庭とは対照的に、純情なゾラは初恋のピンク帽の娘の面影を忘れられず、若いメイドに恋をする。
エクスプロヴァンスの赤い岩肌、「水浴図」やマネの「草上の昼食」の舞台を連想させる美しい川辺の光景が眩しい。
エンドロールに重なる「サント・ビクトワール山」のきらめきに、セザンヌの生活臭が浄化されていくようで救われる。
自分の思い込みと作品世界とのギャップを差し引いても、やはり美しく上質な映画だといえる。
セザンヌの静物画が好きだ
変わりゆく関係
性格破綻者のセザンヌと、寛大で理性的なゾラの友情物語
直訳すると、"セザンヌと私"。いわゆる歴史人物モノだが、画家ポール・セザンヌと文豪エミール・ゾラという2人の有名人の知られざる友情物語という切り口に、が然、興味が湧くはずだ。
原作はなく、オリジナルなので、よくぞここまで調べあげたというべき、ダニエル・トンプソン監督(女性)取材の勝利である。
近代絵画において、ピカソに"我々の父"、マティスに"絵の神様"とまで評されるセザンヌだが、本格的に評価されたのはその死後で、実際には先に成功を収めた、幼馴染みのゾラだけが、セザンヌを"天才"と呼び、生活費を工面したり、公私にわたる擁護をしていた。
ストーリーは、ゾラの発表した小説「作品」(本作字幕では「制作」)のモデルとなった画家が、"セザンヌである"ことについて、2人が口論になり、関係に致命的な亀裂が入ってしまうエピソードを描いている。
登場するセザンヌは、ホントここまで性格破綻者だったのかと思うほど、コミュニケーション能力が絶望的に欠如している。それでもゾラは、40年間も"親友"でありつづけたのは凄い。
むしろ、絶交は信じられないほど呆気なく、"ブチ切れた"状態に近い。劇中でゾラは、"彼は天才です。しかし、その才能は花開かなかった"と断じている。
トンプソン監督は、小説「作品」はもちろんのこと、それぞれの伝記、幼馴染みだった2人の子供から大人になるまでの往復書簡、周囲の人々の日記やメモなど、あらゆる素材を元に創作している。
また第10回アカデミー作品賞を受賞した、「ゾラの生涯」(1937)を併せて見ると、セザンヌが出ている。また"ドレフュス事件"の詳細や、やはり画家マネを評価するゾラもクリアになる。セザンヌは、マネを嫉妬の対象として、ゾラを取られまいと気を揉んでいたのだろうか(amazonビデオで観られます)。
映画としては、2人の友情をやさしく包み込んでいるが、実際は100年以上も前のこと。真実は知るべくもない・・・そこで、女性遍歴も重大な要素という説を盛り込んでいる。他人事だが、あまりにもセザンヌは変わりすぎていて、いろいろ面白い。
(2017/9/17 /Bunkamura ル・シネマ1/シネスコ/字幕:齊藤敦子)
全20件を表示