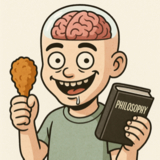ハクソー・リッジのレビュー・感想・評価
全420件中、21~40件目を表示
1番リアルだったかも、、
戦争映画は割とみている方だが、1番リアルだったかも、、
しかも実話なの知らなかったからびっくり。さらに敵が日本人だったとは。。
第二次世界大戦の話で、舞台はハクソーリッジ(沖縄の前田高地)での戦い。
銃を持たずに戦場に行くとはどんな度胸なんだ、、
最初怖かった大将も、ドスがみんなからボコられたと知ったあとは優しかった。
ラストの大将を助ける場面では、絶対大将デッドエンドかと思ったらちゃんと生きのびててよかった。無駄な悲しみは味わいたくない。このエピソードはちゃんと実話らしい。
「あともう1人助けさせて」かっこよかった。
あと序盤でドスだけ見捨てなかった両足吹き飛ばされた人が生き残ってたのもよかった。
日本兵が手榴弾握りしめて米兵とくっついたシーン鳥肌たった。自分が死ぬとわかってる時どんな気持ちなんだろう、、
お父さんの方はPTSDに苦しんだっぽいけどドスはどうだったんだろう
信仰と狂気
宗教的欺瞞にあふれた作品。
メル・ギブソンの監督復帰作品として大いに期待しての鑑賞だったが、なんとも微妙な作品。
実話に基づく作品だが、それを前提にしても正直この物語には素直に感動できない。
主人公は敬虔なキリスト教徒。幼少の頃の経験から、人の命を誰よりも重んじる青年。そんな彼が戦場で敵味方を問わず人命救助に命をかける様を見れば感動するでしょという作り手の思いが常に透けて見える演出がまず無理。
子供向けと考えれば納得はできるが、本作は結構な残酷シーンもあり、あくまで大人向けであろう。
そもそも主人公が人命を何よりも尊重する人間であるならば、戦場に行くよりも人命軽視の極致である戦争に対して反戦運動をするのが筋ではないのか。にもかかわらず、彼は自ら志願して戦場へ向かう。
彼は戦場で仲間を命がけで救うが、その救われた仲間は治療を受けて再度敵を殺すために戦場に出ることになる。つまり主人公は間接的に敵の命を奪うことに加担しているのだ。たとえ敵兵の命をも救ったとはいえ、やはり人命を重んじるはずの主人公のこの行動には矛盾を感じざるを得ない。どうしてもその辺が引っかかって本作を楽しむことは出来なかった。
同じく敬虔なクリスチャンであるメル・ギブソンがこの物語に飛びついたのは容易に想像がつくが、宗教的欺瞞にあふれた作品としか思えなかった。
本当に人の命を一番に思うのなら人の命を食らう戦争という怪物と戦わなければならない。けして敵は相手国ではなく、敵は人の命を奪う戦争そのものなのだ。戦争という安易な方法で国際問題を解決しようとする体制と戦う、それには反戦運動しかない。そして平時から戦争に向かわせないよう権力を監視する。これが本当の正しい道なんだろう。
メル・ギブソン監督には過去作のアポカリプトやブレイブハートで圧倒的に魅了されたのだが、今作の演出はやたらと仰々しかったりと、いまいちの印象だった。やはりブランクが尾を引いているのだろうか。
テリーサ・パーマー
信仰が狂気に勝った瞬間
1945年3月26日から始まった沖縄戦は6月23日に終結。浦添城跡は戦争中、日本軍からは「前田高地」、米軍からは「ハクソーリッジ」と呼ばれた。
ドスが銃を持たない理由は信仰心よりも、父を苦しめた戦争の象徴そのものであることと、そんな父を更に打ちのめした自分の行為を畏れ、また、恥じたからでもあるのだろうと思う。
心を守るために信仰するのか、信仰が心を守るのか、どちらが先かはわからないけれど、それが戦場において彼がパニックにならず、やるべきことが明確になった大きな要因なのだろう。
自分だけ安全圏にいて戦場にいかないことは国民として公平ではない、しかし銃を持って人を殺すより、傷を負った者を助けたい。彼の中では矛盾せず愛国心と博愛心が同居している。
それは他人にはなかなか理解しがたく、敵を殺めることのできない臆病者だと勘違いされるが、そもそも銃も持たずに戦場にいること自体がとても勇気の要ることなのでは?と思う。
実際、戦場においては人を殺すより、人を助ける方がずっと難しい。
ドスの祈りが皆に与えたものは、束の間の心の平穏。それはまさしく、信仰が狂気に勝った瞬間でもある。
きっとドスの助けた日本兵は他の米軍人には見捨てられたのだと思うけど、彼の行いは決して無駄ではない。きっとその行為を見て、改心した人もいるだろうから。こういう信念のある人が生き延びてくれて、本当に救われた気持ちになった。
武器を持たずに戦線へ…。 最高です。実話です。
デスモンド・ドスという男の実話が描かれている。
しかも身近な沖縄戦。前田高地戦線。
日本とアメリカの太平洋戦争での出来事。
旧日本軍の徹底した富国強兵の軍国主義が徹底された日本にアメリカ軍が日本国土の最後の白兵戦を繰り広げた。
クリント・イーストウッド監督「硫黄島からの手紙」、「父親達の星条旗」の延長線上にあるとても悲しい映画です。
沖縄戦というのは、歴史上日本の完全負け戦で時間稼ぎの戦争でした。
その中でアメリカ軍から見た戦線の映画です。しかも武器を持たずに戦線に出兵するデスモンド・ドスという衛生兵の話。
感動しました。
戦争反対!改めて思わせてくれる内容でした。
戦争映画の中でも優れた映画。
参考資料
YouTubeの「地獄の戦場と化した沖縄…悲惨な戦争の爪痕」で紹介されてます。
銃を拒み、衛生兵となって活躍した兵士の実話。 沖縄戦を描いているた...
信念は銃や爆弾よりも強い。75点
銃も持たず、戦場を駆け回る主人公の姿には感動を禁じ得ない。
徹底して信念を貫く不器用な主人公にはいくら映画にしてもやり過ぎだろと思ったが、実話だというからおったまげる。
話は自体は面白かったけど、戦場で引きの絵が極端に少なくややチープに見えるので迫力に欠ける。
凄惨な戦場
特に前情報無く鑑賞。
戦争映画なのに主人公が「銃には触らない」と言い出してびっくりした。
主人公「人を傷つける銃には触れない」と主張するが、もちろん許されるはずがなく、命令違反で軍法会議にかけられるも、何とか自分の主義主張を通した主人公はついに戦場へ赴く。
舞台は沖縄・前田高地へ。
前田高地は激戦地であり、死屍累々、阿鼻叫喚、屍山血河、、、どの言葉もこの戦場を表すには生ぬるく感じるほどだ。
主人公は血と腐肉の舞い散る戦場を丸腰の状態で駆けまわり、負傷兵を救い出す。
もちろん勇気がないと出来ないことだし、常人には無理だと思うが、「アメリカンスナイパー」のように仲間のために敵を殺し、精神がズタボロになった兵士もいるわけで、、、
結局、自分が殺さなかった分、他の誰かにその重荷を背負わせているのでは、と思ってしまった。
どうしてもライフルに触らなくて他人に迷惑かけてしまうところも、良く言えば「確固たる信念がある」のかもしれないが、自分の生き方を優先し、絶対に譲歩しない「かなり自分本位な人間」ともいえる。
この映画の見どころはリアルな戦場の描写にあり、戦場での活躍譚や友情物語を期待する人には物足りないだろう
深く考えさせられる戦争映画
(2017年7月に劇場鑑賞した直後の感想です。ご参考までに)
世評の評判が良く、一見の価値ありと感じて、劇場に足を運んできました。
デズモンド・ドスという青年が、第二次大戦に志願兵として参戦するも、自らの信念から、武器を持たずに、負傷した兵士を救うということに力を注ぐという実話。
ここでは、彼を動かした「信仰」と、戦場となった「沖縄戦」に分けて感想を述べたいと思います。
【信仰について】
デズモンド・ドスの信仰するキリスト教には、「汝、殺すなかれ」という教えがあります。彼は、これに従い、戦場でも武器を持たない衛生兵として、負傷した兵士の救助に尽力します。
「人を殺してはいけない」というのは、別にキリスト教に限ったことではなく、全人類共通の道徳観だと思います。
それが、戦争という国が下した決断により、人を殺すことが当たり前になってしまう。
彼が、志願するまでの苦悩というのは、あまり描写されなかったけれども、人を殺すことが認められてしまった以上、せめて助かる命は救ってあげたい、という苦渋の選択だったのでしょう。
私は、こうした人間が現れ、武器を持たずに戦場に赴かせ、最後には勲章を与えて英雄とする、米国の懐の深さに感銘しました。
もちろん、日本人だって人を殺さないという信念は誰しも持っていると思います。
でも、それをこのような形で実現することが、日本人には国民性からか、なかなか難しいような気がします。
【沖縄戦について】
本作品では、宣伝の中でも、特別に沖縄戦が舞台だということは強調されていません。
だから、本作品が上映されていることは知っていても、沖縄戦のことを描いているということを知らない人は案外多いのではないでしょうか。
もっとも、本作品の主眼は、沖縄戦ではなく、上記の武器を持たずに戦場で兵士を救ったということなので、それでよいとは思います。
しかし、日本人である以上、沖縄戦ということに着目せずにはいられませんでした。
沖縄戦というと、民間人や年少者に多くの死傷者が出たことで、その悲劇性がしばしば取り上げられます。
今回は、期せずして、アメリカ目線で、沖縄戦を観ることになりましたが、日本だけでなく、アメリカにとってもいかに熾烈な戦いであったかが、臨場感溢れる戦闘シーンでよく分かりました。
本作品は、反戦映画ではないけれど、このような戦争のない平和な日常というものを、とても有り難く感じた次第です。
だんだん良くなる
戦争は悲惨
信念を貫く兵士の壮絶な生き様
本作は、“汝、殺すことなかれ”という宗教の信条を信じながらも、第2次世界大戦の戦場に赴き、信念を決して曲げることなく、自らの方法で戦い抜いた兵士の生き様を描いた作品である。本作は、信仰を取り扱っている。この手の作品は宗教が根付いている洋画の得意技であり期待して鑑賞したが、期待を遥かに超えた傑作だった。
主人公デスモンド・ドス(アンドリュー・ガーフィールド)は、幼い頃の体験から、“汝、殺すなかれ”という宗教の信条を強く信じるようになる。そして、第2次世界大戦中、彼は、信念を曲げずに、志願兵として軍隊に入る。軍隊の中では、武器を持たない彼の信念は全く理解されず、迫害を受けるが、それでも彼は信念を曲げず、ついには、衛生兵として沖縄戦に赴くことを許される。しかし、そこは、彼の想像を遥かに超えた、阿鼻叫喚の生き地獄だった・・・。
入隊するまでの主人公は、特に信心深いところは見受けられず、好きな女性(テリーサ・パーマー)に夢中になる有り触れた青年として描かれる。青春映画を観ているような雰囲気である。いきなり、信仰、信念という題材にフォーカスせず、自然で静かなプロローグとなっているので、作品に素直に入っていける。
物語は、軍隊への入隊から、本題である彼の信念を貫く闘いに突入する。主人公の信念を軍隊が看過するわけもなく、上官、同僚から、除隊を迫られる。しかし、どんな目にあっても、宗教家然とせず、理屈っぽく説明をせず、自然体で、決して信念を曲げない主人公を観て、主人公の信念は主人公の中に根付いていると納得できる。
そして、クライマックスの沖縄戦。今まで多くの戦争映画を観てきたが、その中でも屈指の壮絶な激戦描写である。戦場が画面から溢れ出してくるような臨場感、凄惨で生々しい戦場描写に圧倒される。主人公は、あまりの惨状に、自分に何ができるか苦悩し神に問い掛ける。ここは、今年観た“沈黙”を彷彿とさせる展開であり、主人公も“沈黙”と同じアンドリュー・ガーフィールドだったので、その後も、“沈黙”と同様に、信仰と現実のなかでの激しい葛藤が再現されると思いきや、全く違っていた。主人公は、戦場のなかで自分の使命に気付く。ここは、主人公の信念が、神の教えを守るというものから、神の教えではなく自らの信念に昇華した、自己覚醒、自立の瞬間だったと感じた。もう彼は迷わない。自らの意志で行動して、決死の覚悟で戦場から多くの負傷兵を救出する献身的な姿は、感動的であり、涙が止め処もなく溢れてきた。
本作は、信仰と現実の矛盾に葛藤する主人公を描いているが、最終的には、信念を貫くことの意味、大切さを教えてくれる作品である。エンディングで、実在した本人が紹介され、信念は自分自身であるので、決して曲げてはならないと語る。信念を貫いて生きることの大切さを教えてくれる名言である。
タイトルなし(ネタバレ)
実話と知らずに観たので、実話だと知った時に生きて帰れたことが本当に「良かった」と思えた。
信仰心を持っていない身としては、なんでそこまで強い信念を持てるのかが不思議で仕方がないけど、武器を持たずにあの戦場で70人以上もの負傷兵を救い出して自分も帰還出来たことは、信じた人に与えられた所謂"神のご加護"なのかな。
戦争映画を見ると、不況の世の中ではあるものの、つくづく戦争のない時代に生きていて良かったなと思える。
信念
「信念を持って生きる」とは
こう言うことなんだと。
本当にすごい。
これが実話なのかと思うと、心底人間捨てたもんじゃないと思う。
そして、戦争の描き方が今までみた、どの戦争映画よりリアルに感じた。
足が吹き飛び、内臓が飛び散り、地面が人の肉塊でどす黒く染まっている様が、本当に恐ろしいと思った。
私の祖父も第二次世界大戦のガダルカナル島というところに陸軍兵として出兵した。
仲間が大勢亡くなり、祖父も4箇所銃弾をあび
命からがら生き延びた話を聞いた。
隣にさっきまでいた仲間が次の瞬間撃たれて亡くなった話や、泥水を飲んでしのいだ話をよく聞いた。
もう祖父は5年前に92歳で亡くなったけど、毎年お盆には戦死者の慰霊碑に訪れ私も度々一緒に行った。
20年ほど前。
祖父が参加したあるパーティーにアメリカの方がいて、酒を飲みながら話したそうだ。
なんとそのアメリカの方は第二次世界大戦で祖父と同じガダルカナル島に出兵していたのだそうだ。
祖父は少し涙ぐみながら、
元敵同士だか、今はこうしてお酒を酌み交わせる。
本当に平和はいいな。
と言っていた。
戦争で戦った兵士たちは、みんな誰かの息子だったり父親だったり、恋人だったりする。
戦争は二度と繰り返してほしくないなと、この作品を観て本当にそう思った。
とてもいい作品でした。
傷口が超痛そう..
勝者目線の英雄譚
信念を曲げたら僕は生きていけない
あんな近距離で戦うなんて、実際、想像を絶する恐怖だったろうな。映画の中とは言え多くの日本人とアメリカ人の戦死者を出した戦いは凄まじいのひとこと。
デズモンド(主人公)が、「汝、殺すことなかれ」とのキリスト教の教え(モーセの十戒の一つ)を守るという点では、一見キリスト教の物語とも言えるが、根底に流れているのは、自分の信念を貫くことの大切さである。
なお、入隊直後の訓練時、銃を持たないので上官に呼び出され時の尋問で、僕の宗派では土曜が安息日で、というセリフがある。日本語字幕では省略されてしまっているが、英語のセリフではその前に、確か、I'm a seventhday ・・・と言っている。これは、彼がちょっと特殊なキリスト教の一つである、セブンスデーアドベンチスト教会という宗派に属していることがわかる。
※印象に残ったセリフ
(主人公が銃を持てという上官の命令に背いたため軍法会議にかけられ、牢屋で面会に来た婚約者に言ったセリフ)
デズモンド:
プライドのせい?そうかもしれない。でも信念を曲げたら僕は生きていけない。君だって失望する。
全420件中、21~40件目を表示