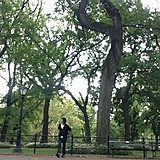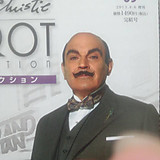幸せなひとりぼっちのレビュー・感想・評価
全168件中、141~160件目を表示
ひとりぼっちとは
見当違いの感想ですが…
この邦題を採用したのは、今の日本には、リタイア後の人生や配偶者に先立たれた後の人生を、現実的に切迫感を持って考えている人が団塊世代を中心にたくさんいるからなのでしょうね。
ささやかながらも、一定のコミュニティーの中で相応の責任感を持って取り組める仕事(無報酬でも)があるのは、幸せなことだと思いました。オーヴェだって文句を言いながらも墓前であれこれ報告するのが(たぶん)楽しかったはずです。
普段は誰も気付いてくれないけれど、たまには、やっぱり俺でなきゃダメなんだなと、たとえ独りよがりだとしても思えることがあるのは、その人にとっての支えになります。
この映画の主題は、今述べたようなことではなくて、本当はもっとオーヴェ個人の人生にスポットを当てているのだと思いますが、個人的には人生における黄昏時(君の名は。の誰そ彼時のような哀切とは程遠い平凡な人生の黄昏時)以降をどう生きていくか、考えるヒントとなる作品でした。
※車を巡るこだわりが、とても愉快でした。
私の場合はビールですね。
晩酌は、専ら首の長い動物か、ふくよかな太鼓腹です。
強さを持つこと…優しさに触れること…生きる事の難しさ…
いろんなレビューに書いてあるとおり、偏屈な老人が引っ越してきた一家との触れ合いの中で、閉ざした心を開いていくヒューマンドラマ…なのですが、本当に深くて、笑えて…悲しい映画でした。
早くから母を亡くし、無口で昔気質の父の愛で育った青年は、父をも失い、父にもらった形見の時計を守るため、自分を信じて闘う決意をし、父の残した家に住み続ける。
それから数十年が経ち、唯一の理解者であり光であった妻を亡くし、生きる希望を失った老人が、相変わらず自他共に厳しく、規律を守り、住宅地を勝手に管理しながら、妻を追いかけ自殺を試みたが、隣人に引っ越してきたのは、ポジティブで外連味無く誰とでも平等に接する家庭の妻だった。
こんな偏屈なおじいさんに何故にそんなに構うのか…?という疑問も最初はもったものの、本当に誰にも明るく接して、裏が全く感じられない人ってたまにいますよね。
そんな姿は、おそらく亡くした妻ソーニャがもっていたもの。
その無垢で誰にも屈託がなく、未来を信じる姿にオーべが両親以外で唯一本当に心を開いたのがソーニャだということが嫌というほどわかるエピソードが盛りだくさん。
家も失い、自分しか信じられるものがなくなってしまったオーべ青年の心を見事に開き、その愛情を注ぎ続けたソーニャが亡くなり、オーべ老人は、他人の正しくないことを厳正にただして、規律を保ち続けることでしか自己の存在意義を見出せなかったのでしょう。
絶望にかられ、愛する妻と後生で会うことを決め、自殺を図るオーべの前に、現れたパルバネ。その屈託のない性格とポジティブな生き方に、オーべも徐々に心を開いていく。
で、些細なことで許せなかった友人と心を通わせはじめ、パルバネの娘達に心を開き、妻の教え子の友人を家に泊めるようになり…順調に周りとの調和を取り戻して、そのことに「人が生きること=一人ではない」ということを感じ始めたラストは…。
人が生きるということは、自分には理解できない他人を排除して、いかに自分というものを保っていくか…孤高の人という生き方もあるものの、そんな生き方ができるのは本当にごく僅か…。孤高と思い込んでも、自分が気持ちを許した人がでた瞬間にその箍が一気にはずれたり、なんだかんだで他人に頼っていたり…いろんなケースはあるものの、オーべに生きる光を与えたソーニャ、その死によって再び閉ざした心を開いたパルバネとの出会いを経て、ようやく気付いた時には…。
人生の残酷さも同時に物語っている気がして…。悲しかったです。
あの世があるなら、幸せな生活の続きを送ると共に、きっと仲間との生活も楽しめるはず。
コミカルな部分もあり、笑いも誘う映画ですが、本当に深くて悲しいお話でした。
幸せな気分になれるはず
Ove 寡夫 無職 59歳
正直日本人目線だと79歳でもいいくらいの外見です。
どんなことでも筋を通さずにはいられない、融通がきかない、曲がったことは大嫌い。規則を守らない輩には容赦なく罵声を浴びせる。真っ向から正論を振りかざす。こういうオジサンは線なら定規を当てて引くだろうし、円ならコンパスで精確に描くだのだろう。
頑固オヤジには頑固になるだけの理由がある(から理解してあげないとダメなのよ)と聞いたことがあります。劇中では、理由というより主人公Oveのこれまでの人生を振り返る過程で、人格形成と元来の素質も見えてきます。
一人ずつ大切な人達に先立たれてしまう悲しさ。かなり不運の連続です。「一人で何でも出来ると思うな」と隣人に叱られるシーンがありますが、自分で何とか乗り越えていかねばと思わざるを得ない境遇だった感じがしました。車の進入禁止に特別やかましいのも、過去の事故が原因なのかな?と思いました。
後に妻となるSonjaがレストランで十分食事が出来るようにと、財布が淋しい自分はデート前に腹ごしらえ。初デートではカッコつけたがる男性が殆どだと思いますが、そんなことより彼女が美味しい食事をたらふく楽しめることを一番に考える優しさ。彼女の夢を叶える為に雨の中、学校に車椅子用のスロープを自作するOve。妻へのまっすぐで一途な深い愛情が伝わってきました。
妻の後を追うために、あの手この手で自殺を試みるのですが、その度に「邪魔」が入る所が面白いです。自分の血で家が汚れないようにビニールを張る細やかさ(^。^)。隣人達が彼を放っておかないのは、無愛想ながらも何だかんだ彼が常に正しいことをすると知っているからなのでしょう。Oveの性格なら自殺こそ許されない気もしましたが…。
コミュニティの大切さもそうですが、血の通っていないようなお役所的仕事も万国共通なのかなと思いました。
大笑いと涙、両方持っていかれた良作でした。それこそ人生なのかも知れません。オススメです。
コミカルだけどシビアで、とても公正な佳作
いきなり、割引の方法でクレームをつけるおじさんの姿に一瞬ひるむ気がするものの、物語が進めば進むほど、このおじさんが憎めないどころか愛おしくなってくる。店員に対するクレームには頂けない部分もあるものの、基本的には「筋の通らないこと」が嫌いなだけの男。ただの偏屈オヤジではない部分に安堵する。
物語は、亡くなった妻を追って自殺しようとする現在と、少年時代からの回想シーンの往復で成り立っている。この回想シーンが、決して偏屈に見える現在の主人公の言い訳ではなく、一人の男の人生の歴史として描かれているのにとても好感を持った。ともすれば嫌われてしまいそうな主人公から観客を引かせないための言い訳みたいな回想だったら、印象は違ったはず。一人の男が愛した父親の存在と最愛の妻の存在を浮かび上がらせ、それによって現在の主人公がいかに形成されたかがそっと縁取られるようなエピソードが積み重なっていく。
現在の物語は、ユーモアがあってとてもいい。自殺しようとする度に「他人」がこぞってそれを邪魔しにくる。その都度腹を立てて怒鳴り散らしたりするのだけれど、他人の介入によって少しずつ少しずつ救われていく様子が、時にコミカルでかつ繊細に描かれて、向かいに引っ越してきた家族の奥さんの「あなたって死ぬのが本当に下手ね?」と笑い飛ばすような明るさや、いい意味での厚かましさが否応なく主人公を変えていくことろなんか、見ていて清々しい気分。その様子には、ユーモアがあり、スパイスもあり、ウィットに富み、それでいてとてもフェアだと思った。
とても観後感がよくて、ついうっかり「ほっこりと心が温まる」なんて言葉を使いたくなってしまうくらいにやさしい気持ちで映画を見終えることが出来た。これは掘り出し物。身近な人に積極的に薦めたくなる作品だった。
あなたの周りには優しい人がたくさんいましたよ。
不器用で頑固で、共同住宅の規律に守らない隣近所にうるさいおじさん。あんな人と付き合いたくないし、話したくもない。そんな彼の子供時代から今に至る話を彼自身が淡々と話すとき、彼という人間にもそれなりの人生があったんだなぁと目頭が熱くなった。なぜあんなに何度も何度も妻の所に行くのか。他人のやることにがなり立てるのか…。彼は、人が面倒臭いことを率先してやる男だ。
自分のことより他人のことを進んでやる男。もう少し人と人の付き合い器用であれば好かれたのに。妻の死後、そんな男に話しかける2人の娘をもつ女性が現れるしだいに、彼女と大笑いをするまでにもなる一人の男。最後は、心臓肥大が影響したのか、自分の寝室で死に至るわけだが。その女性に遺言めいたものを残す。泣けた。
嫌味のない難解でもない単純な心温まる映画であった。
しかし、男のキャラが、若干ぶれてしまっている。近隣の女性からもらったペルシャ料理のタッパーに感謝のメモ。公道での運転教習等。
邦題あるあるに汚染されています。
本国スウェーデンでは、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』を抑えてトップに躍り出た作品。結局、動員数は160万人を越え、スウェーデン映画史上歴代3位となる興行成績を収め、第89回アカデミー賞では、外国語映画賞のスウェーデン代表作品に選ばれています。(2016/12/23現在、アカデミー賞外国語映画賞へのノミネートはTBD)
もともとは、原作者のフレドリック・バックマンが自身の父親との出来事をブログに書き込んた事が話題を呼び、その後小説化されたものが原作になっているそうですが・・・、まぁ、こう言う偏屈な人は日本にも居ますよね。特に男性は、年をとると偏屈になる人が多いとも言われていて・・・。でもなぁ、極端ではありますが、間違ってはいないんですよねぇ。なんか、世の中いい加減すぎ。
もっとも、オーべの場合、もともとキッチリしすぎていたきらいはありますが、それが“ある事故”をきっかけに、過激化というか、より極端になっていった気がします。その“ある事故”は作品を見て確認してほしいんですが、微妙にあれ?とも思いました。だってねぇ、その事故でって思うじゃないですか。少なくとも私は思ったんですが、その事故はある意味では“切り抜けた”んですね。日本人が描いていたら、あの事故で全てを決してしまうと思います。そうで無い所が、スウェーデン映画なんでしょうか?ただ、その事故後の話があったがゆえに、社会の問題点がよりクリアになったと思います。
この作品も邦題あるあるですね~(苦笑)。この邦題はいけません。原題の意味は『オーべと呼ばれた男』なんですが、そっちの方がスッキリしていますし、オーべと言う一人の男を描いた作品としては、適切だと思います。
あたたかい
素敵なラブストーリー
オーヴェとソーニャの素晴らしいラブストーリーでした。
さまざまな場面で挿入される2人の歴史がとにかく素敵です。ソーニャのためにスロープを作ったり、最高です。
ソーニャはチャーミングで人格的にも完ぺき。ちょっと出来過ぎかなとも思ったのですが、ソーニャの負の面はオーヴェが背負っていたのかも、と大胆に推測してみます。
事故のことは、ソーニャの代わりにオーヴェがめちゃくちゃ怒ってくれたから、ソーニャは怒りに囚われることなく、エネルギーを未来に向けられて、改めて自分の人生にチャレンジできたのではないかな。
ソーニャの怒り・嘆きをオーヴェが図らずとも背負ってくれた。確証はないけれど、2人のパートナーシップを見ているとなぜかそんな気がしました。
若いころからオーヴェはぶっきらぼうで不器用。なので、序盤はなんとなくオーヴェにソーニャは不釣り合いかな、と思っていました。しかし…いやいや互いを補い合うベストカップルでした。
オーヴェはちょっとアスペ入ってますが、火事場に飛び込み人を救うような優しくて勇敢な男ですしね。聡明なソーニャはすぐに彼の魅力を見抜いたのかな。
ソーニャを失い、一時的に腐ってしまったオーヴェですが、隣人パルヴァネと子どもたちのと出会いで、図らずとも再生していきます。
パルヴァネの子どもたちとの触れ合いなどを見ていると、ソーニャとの間で不運にもできなかった子育てをしているよう。なんとなくオーヴェの中にソーニャが生きているように感じました。
再生していく晩年のオーヴェを見ていると、ソーニャとの間で培った愛を、周りの人たちに配り直しているようなイメージを抱きました。愛が2人だけで完結せず、世界に還元されているようで、なんとも豊かな気持ちになりました。
しかし、オーヴェは最後まできちっと生きれてよかった。自殺が成功していたらあの世でソーニャに振られるからね。
いい人生を観させて頂きました。オーヴェのおっさん、マジ幸せです!
人生とは
全168件中、141~160件目を表示