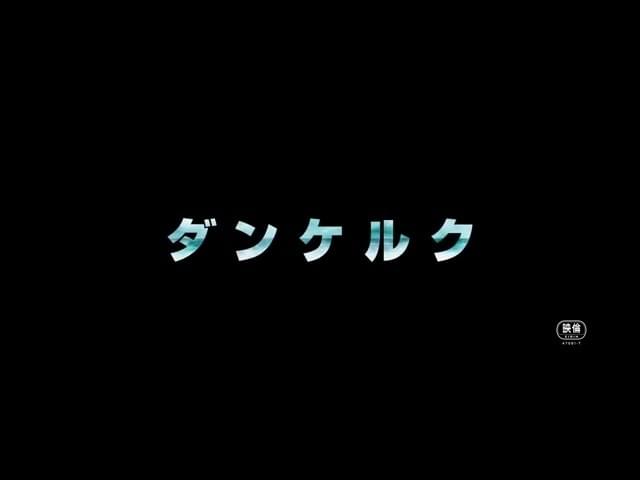ダンケルクのレビュー・感想・評価
全745件中、141~160件目を表示
相反するあらゆる人間性が収斂され、ここにある
どうしてもIMAXで見たくて、難儀した。
日本はIMAXシアターが無さすぎる。 で、結果。IMAXで観てよかった。
でも大いに酔った(笑)。
いい映画だったか?と問われれば見た価値はある、と答える。だが他人に「いい映画だったよ」という軽いレベルで勧める映画ではない。誰かの人生を軸にし、感情移入を前提にした悲劇やヒロイズムを描いたものではないから。
極端に少ない台詞、極端に少ない説明。 陸空海それぞれの時間軸と視点で進行する戦場に、観客はなんの前触れもなく放り込まれる。助けた兵士に奪われた命。助けられた兵士を見殺しにする命。
連合軍のなかで、突如表面化する人種差別。人間は自分が何に属しているのか、その群れは安全なのかばかり考え、コロコロと掌を返し平気で裏切る。その様子は生存本能に操られた生物として俯瞰的に捕らえれば、何もおかしいものではない。
そのように、戦場では命がちっぽけで個の値がかすれてしまう。
しかし、人間は考える生き物だから、一人一人果てしなく苦しみ続けてしまう。 混乱の中で人知れず己の葛藤と戦いながら、誰かを救った挙げ句死んでしまった人たちに、それぞれ積み重ねた時間と人生があったことに思いを馳せずにはいられない。
なんにせよ、ノーランは陳腐な台詞とヒロイズムで大義名分を振りかざす大国を代弁しているような陳腐な表現は一切しなかった。精一杯生き延びること、生き延びたいと思うこと、突き動かされる助けたいという思い、いろんなものが収斂して人間の善さと悪どさを描いた。
誤って民間人の少年を殺してしまったがそれを知らぬ兵士に、「彼は大丈夫」と嘘をついた民間船の船員が、男前すぎる。きっと大丈夫じゃないことは、兵士も察したはず。だがそれを伝えて何になろう。悲しみは少ない方がいい。
後日、少年が望んだ「新聞に英雄として掲載されたい」というちっぽけな(でも純粋な)夢も叶えてあげた船員は、その後きっと志願兵になって散っていくのだろうと想像したら、胸が詰まった。
苦しみがあるから人間が輝くのだろうか。苦しみを取り除いたら人間性は薄れていくのだろうか。
戦争は人間性を再確認させるために繰り返し行われる必要悪なのだろうか。
そうだとしたらなんて皮肉なんだろう。
そんなことを考えながら劇場を後にした。重い足取りで。
現実的戦場体験と映画的カタルシスの両立
ダンケルクからの撤退作戦を描いている作品ですが、状況説明が全くと言っていいほどされないので、事前に歴史的背景を予習しておいた方が入りやすいかと思います。
また、冒頭のテロップで「海岸の一週間」「海の一日」「空の一時間」と出ているように、それぞれで時間の流れる速さが異なることにも注意。海岸は長い時間を短く、空は短い時間を長く描いています。
ノーラン監督らしい時間軸のズレ。私はこの意味がわからないまま観てしまいました。それでも大きな問題はなかったですが、知った後だとこの3つが交差する点がより感動的に思えます。
本作は、登場人物の内面描写を静かで内に秘めたものにすることで、鑑賞者自身が戦場を体験しやすいようにしていると感じました。インタビューのないドキュメンタリーのような。空爆や魚雷だけでなく、水の怖さもよく伝わりました。映画館映えする作品ですね。
主人公にも活躍らしい活躍は見られず、戦争映画によくある戦友との友情なども薄く、兵士の間で名前を呼び合うことも数回。悪く言えば特に前半は盛り上がりに欠け、地味です。ですが戦場では個が許されないということの表現にも思えました。主人公もいわゆる勇者のような選ばれた主人公ではなく、ただ1人の兵士としての描写だったのだと思います。
セリフも少なく、演者からすれば表情や仕草に感情を込めるのは難しかったのではないかと思います。
私はテレビでの鑑賞でしたが、映像もさることながら音響もよく、ハンスジマーのbgmも緊迫感を引き立てていました。本作のフィルムの都合上、通常のスクリーンでは上下の40%がカットされてしまっていることもあり、IMAX鑑賞を勧める方が多いのも納得です。
序盤中盤では現実的な苦しい展開が続き、終盤に映画的カタルシスを詰めてありますね。苦しい展開が続く中でカタルシスを感じさせようとしているのは良かったのですが、中盤まで現実的だっただけに、少し娯楽映画っぽく、浮いているようにも思えました。しかしカタルシスの後に辛さやほろ苦さを残す描写を入れているので、バランスの取り方が上手いなと思いました。
空軍の2人が格好良かった。特にトムハーディ演じるファリアは英雄的に描かれていましたね。個人的にはコリンズ役のジャックロウデンがとても好み。イケメン版サイモンペッグとか言っている人がいて笑いました。
好きなシーンを並べておきます。
冒頭のビラが降り注ぐシーン。印象的で美しい始まり方でした。
ドーソンさんがスピットファイアをエンジン音で聞き分けるところと、それができる理由。
そして終盤の「何が見える?」からのファリアの活躍。
ラストの新聞記事、毛布おじさんとビールおじさん。そしてボルトン中佐。
史実における時系列シャッフルという挑戦
4K UHD Blu-rayで鑑賞(吹替)。
クリストファー・ノーラン監督が実話を元にして製作した戦争映画である。監督のCGに極力頼らない映画づくりが大好きだ。本作でも、圧巻の迫力とリアリティを醸し出していた。
戦場から脱出しようとあの手この手を試みる兵士たち。救出に協力する民間船舶の船長と息子。航空支援に向かうメッサーシュミットのパイロット。
様々な視点が時系列を前後しながら絡み合う。
今のシーンはあのシーンの前で⋯と、時に混乱しつつ考えながら鑑賞した。全ての出来事がクライマックスに向けて収斂していく展開が秀逸である。
史実に基づいた戦争映画で時系列は最も大切な要素だと思うが、敢えて時系列をシャッフルし並行させることで陸海空のそれぞれの視点からダイナモ作戦の全貌を浮き彫りにしていく構成だったことに気づき、構成の素晴らしさに痺れた。
[鑑賞記録]
2019/01/26:4K UHD Blu-ray(吹替)
2021/10/08:4K UHD Blu-ray(字幕)
2025/12/21:NHK BS「プレミアムシネマ」(録画)
*修正(2025/12/21)
映像作品として、とても素晴らしい
映像作品として、とても素晴らしい。ただ、そっち寄りのため、ストーリーを丁寧に追うような親切な作りにはなっていない。途中で飽きる人は多いでしょうね。
とくに、三つの視点(浜辺、船、飛行機)が重なり、意図が鮮明になるまでは、拷問のような遅い展開。映像美で我慢。
さすがに幕のおろし方が上手いので、トータルまとまりもあって鑑賞後の印象は良い。正直、中盤あたりで興味なくしかけてたので。
たぶん、戦闘機を撮りたかったんでしょうね。プロペラとまった戦闘機の姿にロマンがあります。
時間軸の妙
1940年、フランス北端の海沿いの町ダンケルク。ドイツ軍に包囲され、逃げ場を失った英仏連合軍40万人が決死の覚悟で撤退する物語。イギリス人兵士トミー(フィオン・ホワイトヘッド)の視点を中心に陸の1週間、パイロットたちの空中戦を1時間で切り取った空、そして彼らを救おうとする民間船の1日を描く海を時系列をバラバラにして、最後には1つに帰結するという作品だ。
トミーは市街戦で仲間を失い、帰還のために兵士たちが集まった海岸へとたどり着く。寡黙な青年と行動を共にし、負傷兵を担架で運んだりして船に乗り込もうと努力する。早く船に乗り込みたいがために桟橋の陰に隠れたりして、姑息な手段も厭わないのだ。
最新鋭スピットファイアのパイロット、ファリアー(トム・ハーディ)は味方の撤退を援護すべく、ドイツ機と空中戦を繰り広げる。一方、民間船の船長ドーソン(マーク・ライアンス)は息子とともに危険を顧みず、ダンケルクを目指す。
時間軸の妙があり、同じ場面を多角的にとらえていたり、どういう風にまとまっていくのかというサスペンス。ドイツ兵がほとんど映らないという恐怖感も相まって、スクリーンの中に引き込まれる臨場感もありました。空以外は撤退劇、救出劇なわけで、こちら側から攻撃することはありません。戦況もさっぱりわからないけど壊滅的な状況ということだけわかるという、観客もほんとに逃げ出したくなる手法で描かれてます。
セリフが極端に少ないのも特徴の一つであり、その効果もあって、どっぷりと映画に浸れました。ようやく傍観者として観ることができたのはイギリス本土にたどり着いた後。逃げ帰ったことがどういう評価になったのかを知ると、ホッとできるはず。
戦場のレクイエム
タイトルなし
いまなぜチャーチル?いまなぜ第二次世界大戦?というのはありながらも。
アメリカ参戦前のヨーロッパ戦線。当然英仏目線の作品だが、撤退だけをひたすら描写するというなかなか渋いチョイス。
連合軍側は基本やられ役で最後に一矢むくいるというか、なんとか最悪の事態は免れる訳だが、それでもあくまで命からがら撤退できたに過ぎないというなんともストイックな作品。
この作品では、ドイツ人を殺害するシーンはほとんど出てこない。それは、敵を殺す高揚感ではなく、戦争の恐怖感を擬似体験させるためだろう。戦争賛美にならぬよう苦心したのがうかがえる。
また3つの異なる時間軸の使用によって、航空戦力の圧倒的重要性がいみじくも表されている。題材は真珠湾攻撃の一年以上前だ。
この後5年間戦争は続く訳だが、脱出できたうちの何割が戦後を見られたのだろう。気が遠くなる話だ。
当時の戦わなければならない過酷な時代
感想を書くのが難しいです。。
他の人を見捨てず守りながら国に帰ることをただひたすら願う者。
戦って取り残されている兵士達を迎えに行くために船でひたすら危険な地ダンケルクへ向かう者。
戦闘機で守るために攻防しながら打ち落としひたすら最後まで戦う者。
どの立場の者も必死で決して諦めない姿は胸が締め付けられます。
たくさんの故国の船を見たときは歓喜で涙し、列車で戻った時も国民の反応に涙しました。
でも、「降伏しない、戦い続ける」と言う言葉には、賛成できませんでした。
日本は白旗を掲げ、敗けを認めたところから平和になったことを考えると、違うかな、と思いました。(恥ずかしながら、戦争のことはほぼ知識がないに等しいです)
過去の事なので、その当時の思いで描かれている言葉であるのはもちろん理解していますが…犠牲になった人がたくさんいて、「こんな辛いことは嫌だ、もうやめよう」とはその時点で思わなかったのだろうか…と感じたので・・(簡単でないことは承知で発言してます)。
うーん、、やっぱり感想難しいですね!
言葉が乏しくて上手く伝えられません。。
すみません。。
うーん、IMAXですか。
IMAXのデモンストレーション映画?
戦況や、英仏の関係についての説明どころか、登場人物の背景説明はほとんどなく、IMAXの画面効果によって、砂浜、海、空で一人ひとりが感じたこと(特に閉塞状況の恐怖)を表現しようとしたものと思われる。
私はIMAXではなくごくごく普通の画面で見たためその映像効果について云々することはできない。
だが、機上の人と船内に閉じ込められた人との間で時間の感覚が違うとはいえ、同じ地理的なエリアを描いた映画の中で流れる時間があまりにも食い違っていると、頭が混乱しついていけなくなる。
特にひどいと感じたのは編集。連続した場面なのに快晴下の輝く海面と曇天下の荒れた海面のカットが頻繁に切り替わる。
天候の変化が、大規模な撮影に味方しなかったのか。なぜこのちぐはぐなのが平気なのか、理解に苦しむ。
題材をダイナモ作戦から借りてきた、IMAXのデモンストレーション映画ではないかと感じた。
視点の違いが「時間」を生む
2020年8月2日追記
★現在形の視点が目撃した客体が、別の視点の主体であるという気づきが発生することで、「時間」の考え方がうまれる。それは「同時性」や「事象の前後関係(発生順序)」だ。
すべてを現在形として語りながら、視点の違いに気づかせることで、回想という形式を用いずに時間の前後関係を整理させようとした。
出来るだけ人間の原(現)体験をそのまま映像にしながら、時間の経過を観客の中に生み出そうとした
オモテ(表面的なこと=映像)
裏(私たちの中で起こること)
オモテの楽しみ方→アクション、現在起こっている危機に対処すること
裏の楽しみ方→現在形で提示された映像を整序すること
★他人事(と自分ごと)
過去のことを回想としてではなく現在形で語る
視点の違いに登場する時、「過去」という着想が生まれる
現在形で提示された事ごとのあいだに前後関係を見出し、過去と現在の関係を正しく見出すこと
・・・
ダンケルクという映画を構成するのは、「陸」「海」「空」の3つの主観だ。
「陸」「海」「空」それぞれの視点の持ち主である主人公どうしは、基本的にはそれぞれ異なる場所にいるけれども、しばし同じ場所・時間を共有し、助けたり、助けられたりという相互作用(この「相互作用」が命のやり取りに限定されている点が、「単に生存すること」をテーマに、余分なものを切り詰めて『ダンケルク』が作られたことを分からせてくれる。)を及ぼしあう。
ここで大事なのは、命の相互作用をし合う人々は、赤の他人どうしのまま映画が終わるということ。そして、「主人公たちが同じ時間・同じ場所を共有している」という我々の判断は、あくまで主人公たちの主観を通して行われるのであり、俯瞰的な映像を通してではない、ということだ。
娯楽映画に対して観客が期待するのは、様々にすぐれた能力を持った人間が、知り合い、仲間意識を持って共闘することだ。顔を合わせ、言葉を交わし、自己紹介をし会った登場人物たちは、共闘を深めるにつれて互いを知り合い、話題はしばしば彼らの過去に及ぶ。
そこには登場人物の過去という設定があり、設定に従って、登場人物たちの行動が帰結する。これは過去のノーラン作品の全てのストーリー作りのやり方である。
特に『インセプション』『インターステラー』において、「帰りたい」「我が子に会いたい」という動機からシンプルに「だからミッションを達成する」という登場人物の動機を単純に帰結するというやり方が明確になった。
『ダンケルク』にはそれがない。誰もが生存したいと願う。生存したいと願えば、みなやることは同じだ。だから登場人物には、過去の設定の必要がない。みな無個性に捨象されている。ダンケルクは、『プライベート・ライアン』のような、能力と過去によって兵士たちがキャラ付けされた部隊のロードムービーではない。
わずかに「ムーンストーン号」の船長には、「戦争で息子を亡くした」「だから若者を助けるんだ」という動機があると示唆される程度だ。
「過去を設定するかどうか」を変えることで、登場人物の知り合い・共闘の有無が変わる。これはノーランが『インセプション』で我々に見せたのとは異なる。3つのミッションがありそれぞれに主人公がいる点は共通している。それぞれ平等に上映時間が割り当てられているけれど、「実際」の時間の長さは異なるという点も、共通している。けれど3つのミッションがより大きな1つの目的の達成のもとで統合されるかどうかは異なっている。ダンケルクにおいては、3つのミッションを統合するより大きな目的はなく、それぞれがそれぞれの目的に向かい、個人で動いている。
この「統合の不在」が、観客の期待にそぐうものではないという場合もありえる。特に映画に娯楽を、派手さ、豪快さを求める観客にとっては。しかし戦争というのはそういうものだ。現実の経験というのはそういうものだ。人々は互いの過去を深く知り合うことがないし、少人数の戦闘力で反撃に出て大逆転が起こることもない。『イングロリアス・バスターズ』のような少数精鋭部隊による戦局の大転換は存在しない。サッカーの試合のテレビ中継の視界を、芝生に立つ当のプレイヤーたちが持つことはない。
我々は「陸」「海」「空」の各主人公が、どのような順序でイベントを経験し、どのイベントにおいて他の主人公と同じ場所・時間を共有したか,1つのt-xグラフに表すことができる。しかしそのような俯瞰的な図は、映画の中で示されるものではない。
映画の中で示されるのは、あくまで主観のみである。 劇中で主観が提示される順序は、そのような主観が実際に体験されたであろう順序-ニュートン力学的絶対時間における順序-とは異なる。したがって観客は、このような俯瞰図を作成するにあたって、まず異なる複数の主観による複数の報告が実は共通の同じ事象についての報告であると確認する「同定」作業を行わなければいけないし、また実際とは異なる順序で提示される複数の事象を、発生順に並べ替える「整序」作業を行わなければならない。
これまでのノーラン作品の中でも特に『プレステージ』は、整序作業が観客に要求される映画だった。『バットマン・ビギンズ』も、前半部は過去と現在を交互に行き来する作品だった。だが同定作業は要求されなかったように思う。新たに同定作業(同定作業にかんしては、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の得意であるように思う。『灼熱の魂』に始まり、『プリズナーズ』『複製された男』『メッセージ』『ブレードランナー2049』のいずれもが、同定に関する映画であった。)を要求した点が、『ダンケルク』の持つ新規性ではないか。
これらの主観は、いわばある事件の目撃証言である。観客はいわば事件を捜査する刑事であり、刑事の仕事は、複数の目撃証言から、事件を、1つの無矛盾な物語として語ることだ。この点において、ダンケルクは戦争映画でありながらじゅうぶんにミステリ映画でもある。
普通のミステリであれば、この作業を行うのは劇中の登場人物である刑事、探偵、教授、医者であったりするのだが、ノーランはこの作業を観客に行わせる。この映画は物語というよりも、物語を作る素材なのだ。
このような同定-整序作業を、巻き戻しの効かない映画館の上映中にやらせるというのは観客は認知能力を試されるし、観客をテストするような作品の製作-上映の承諾を映画会社から取り付けてくるところにはノーラン監督の持つ知名度、宣伝効果が見込まれているのだろう。
俯瞰的映像を減らし、視界の狭い主観的映像を多用したのには別の効果もある。それは閉塞感の表現であり、また戦争において兵士が大局観を得ることのできないことの強調だ。
前者を利用した映画としてはネメシュ・ラースロー監督『サウルの息子』を挙げたい。
クリストファーノーランはおもしろいなあ。 戦争モノはカッコ良くする...
タイトルなし
全745件中、141~160件目を表示