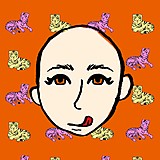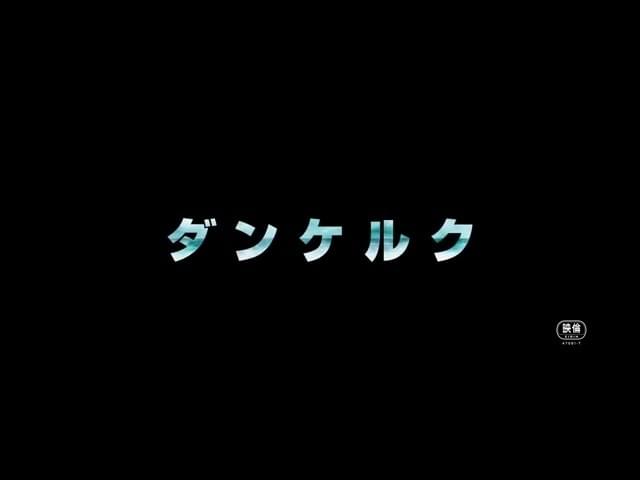ダンケルクのレビュー・感想・評価
全745件中、481~500件目を表示
臨場
1940年5月、ナチス対英仏の開戦直後に英仏精鋭軍は大敗を喫する。
負け戦の果てに追い詰められたダンケルクから、英軍はドーバーを渡る撤退作戦を実行。
その様子を、撤退する兵隊の1週間、軍の要請に応えて救援に向かう遊覧船の1日、援護に向かうスピットファイアの1時間という3つの時間軸で見せる作品。
撃たれ、沈められ、命までもっていかれる襲撃の恐怖。
目の前で同胞が虫けらのように死んでいく恐怖。
その恐怖に打ち勝つ精神と冷静な計算。
言葉は最小限と思えるほど少ないが、映像と音で、十二分にその時の体験を伝えてくる。
経験の乏しい若い兵隊たちのシーンはとても苦しい。
時に感情的になり、エゴをむき出しにしてくる。
(( 1DのH・スタイルズが起用されているが、ただの一兵卒。兵隊という没個性が要求される集団にあって、あの顔が、観客にとって目印になる、という程度の。))
対象的に救援に向かう遊覧船をあやつるライランスは老練だ。
無口で無骨ながら優しい人物だが、戦闘機に詳しく胆力も強い。
死の淵まで追い詰められた恐怖で、感情的で利己的になっている兵士に決して無理をさせず、でも自分の意思は貫く。
長男を戦争で失っていると設定だが、たぶん自分自身も従軍経験があるのだろう、という同行者の意見に「なぜダンケルクに向かったのか?」が腑に落ちる。
凄みがあるのが、スピットファイアのパイロット。
僚機の景気故障のために、つねに帰路の燃料を気にしながら飛んでいるのだが、目の前で大量の兵士を乗せた僚艦に敵機が迫るのを見て、ガス欠をおそれずに追走に入る。
その時には「伸るか反るか」に見えるのだけれど、だれもいない敵陣内の砂浜に不時着させ捕虜になるシーンまで見ると、あの時に、そこまで計算したんだとわかる。
あれが、軍人の決断力というやつでしょうか。
実際にダイナモ作戦を経験した人たち(ほぼ90代)がプレミアに呼ばれたそうで、映像はおどろくほど事実に忠実、爆撃音はあれほど大きくなかったという感想だったらしい。
飢えや渇き、水の冷たさ、砂の不快さなどは客席で体感することはないが、その部分を音で補ったのだろうか。
素晴らしい音だったし、怖かった。
さて、 imdb では 8.4/10のスコアだが 映画.com の反応は3.7/5.0 とやや熱量に乏しい。
米国にはイランやアフガニスタンなど最近の従軍経験者が多い。その家族や友人も含めると、この映画を「わがことのように」体感する観客が多かったのではないだろうか?
それがいいとか悪いとかいう話ではないが、作戦に至る経過や成功の理由を知って観るのはずいぶん理解の助けになる。
session22 2017.9.14(木)放送分の音声配信も、よかった。
IMAX用の映画
自分的には惜しかった
軍人といえども英国紳士
盛り上がらない映画
酔った
すごい映像でした
戦場の音、大多数の本能の群れ、砂粒の英雄
IMAXにて観賞。初体験だったのですが、凄いですね。とりあえず見終わった後にものすごくお尻が痛くなったw、と言うことは、こころだけでなく身体も消耗していたのです。飛び交う弾丸の音や爆撃の音、何かが軋む音、破壊された音など、この世であまり頻繁には聴きたくない音のオンパレードかつ、終始不穏なBGM。いちいち身体が反応してしまうほどでしたので、戦場で魚籠ついている二等兵の如しでした。
あれで、PTSDにならない方がおかしいですよね。
ストーリーやキャラクターについては、割愛w、史実通りの所も有るでしょうし、誇張した点や創作した点もあると思われます。
個人的には、ストーリーが解らないのが面白い所だと思いますし(と、言ってもキチンと最期には集約されてます)、主要キャラクターが例え全員戦死していたとしても、憤りやドラマの無さを責めることは無かったと思われます。本来、古来より戦争でドラマが生まれるのは、生き残った者がいるからだと思います。しかし、特に近代に入ってから国家が、国民国家の概念が成立してから、ドラマがないと戦いを始めることすらできなくなってしまいました。また戦争が、国民とゆう膨大な人間を基にしているが故に数字に囚われすぎたからとも云えますが。
つまり、この作品の肝や裏のメッセージは、戦争でのドラマなんて、フィクションか後付けなものであり、数字なんて、さらに不気味なものに過ぎない~ということではないでしょうか。英雄的行為は、萌芽にすぎず兵士はただただ死んでいくばかりー特に撤退戦ですからね。
星を4つとさせて頂いたのは、僕みたいに、近現代の戦場を実際に参加してる雰囲気を味わいたい変態は少なく、一般的な受けがどうか?という点と、制限がかかっているとは言え、子供には見せられないかな?という点を引かせて頂いただけで、僕にとっては満点の映画体験でした。ただ、身体が痛くなるので、もう一度映画館で見るとなると、、、今度はぎっくり腰になるかも知れないww
お粗末な空戦の展開するパニック映画
筆者はクリストファー・ノーラン監督作品を『バットマン ビギンズ』以降全て映画館で鑑賞しているが本作はその中では一番凡作に思えた。
ノーランの最大の特徴は彼の紡ぎ出す世界観にあると思う。
『インセプション』しかり『インターステラー』しかり、細部を見ると実は強引な展開や論理的にあやしい部分もあるのだが、提示する世界観が魅力的なために観客を納得させる、そういう種類の監督に思える。
新バットマン3部作もバットマンの新しい世界観を提示し、それが熱狂的に受け入れられたのではないだろうか。
裏を返すと、彼の提示する世界観に入り込めない人は彼への評価は低いだろう。
さて本作だが、監督のノーランが「戦争映画」ではなく「人々が生き残ろうとする姿を描くスリラー」にしたかったと話している通り、敵兵(ドイツ兵)の姿は一切出て来ず、沈没や爆発など危機的状況から人々がただひたすら逃れようともがく。
魚雷攻撃で船が沈没する際もUボートは言葉として登場人物たちの口から発せられるだけで実物は登場しない。
さすがにドッグファイトや空爆のシーンではメッサーシュミットやハインケルのドイツ軍機を登場させないわけにはいかないが、スピットファイア側とは違って搭乗員などの細かい描写も一切されない。
物語は、砂浜からの帰還兵、、救助に出る民間船、イギリス軍戦闘機スーパーマリンスピットファイアの3つの視点で進められ、最後に民間船に収束する。
本編の始めに「防波堤:1週間」「海:1日」「空:1時間」と、それぞれの視点の始まりで字幕の説明が入るが初見では何を指しているのかわかりづらい。
また海上に不時着したスピットファイア搭乗員が民間船に救助される下りがあるが、以前にも不時着したシーンがあるにも関わらず、別視点でもう一度不時着シーンを繰り返してから救助シーンへと移行する。
本作は全般的に会話も少なくあえて説明的な場面や台詞も省いているが、別視点であれ同じシーンを繰り返したことで、観客に頭の中でシーンを整理する時間が必要になるので物語全体の緊迫感は薄れるのではないか。
他にも繰り返しのシーンがあったと思うが、筆者にはどこを繰り返しているのか頭の中で整理がついていない。
スピットファイアの残燃料を計器類の隙間に書くシーンも緊迫感を出す仕掛けの1つだとは思うが、正直わかりづらい。
またノーランは「時間との戦いを描くサスペンス」にしたいとも話しているが、こちらは逆に敵兵の姿を描かなかったことで刻一刻と追いつめられていく印象は持てなかった。
攻撃する側の顔が見えず、逃げ惑う人々に焦点が当てて描かれるという意味では、たしかに戦争映画というよりもむしろ天災や事故によるパニック映画を観るようであった。
海上脱出の物語であり水のシーンが多いせいか、筆者は『ポセイドン・アドベンチャー』を懐かしく想った。
第二次大戦を舞台にしたパニック映画といったところだろうか。
また救助船として民間船が数多く浜辺に到着するシーンやイギリス国民が敗残兵を暖かく迎えるシーンは、まさにパニック映画の大団円である。
CGの使用を避け実物にこだわったことは素晴らしいが、スピットファイアが画面上に3機同時に飛ぶのに対してメッサーシュミットが1機しか登場しない。
ダンケルクの戦いは1940年5月24日から6月4日までであるが、この当時ドイツではメッサーシュミットが量産されているのに対してスピットファイアはわずかしか生産されていない。
実際に本土防衛に使用を限っていたスピットファイアがこの戦いに投入されて初めてメッサーシュミットと互角の戦いのできる性能を証明することになる。
スピットファイアに比べてメッサーシュミットの方が数が少ないことはないだろうし、そもそも両軍ともに戦闘機の参加総数が少な過ぎる。本作の空戦はまるでちゃっちい。
また、この時期の両機を比較すると、上昇や降下などの縦方向の動きではメッサーシュミットが、旋回能力など運動性能に関してはスピットファイアが優れている。
本作では、メッサーシュミットの後ろに付いたスピットファイアがメッサーシュミットの上昇時に距離をつめる場面があった。これは可能なのだろうか?と考えてしまった。
余談だが、ゼロ戦もスピットファイアと戦っているが、格闘戦においてスピットファイアはゼロ戦に全く敵わなかった。
カラーリングと形状、エンジン音の問題もある。
例えば日本の零式艦上戦闘機、いわゆるゼロ戦に関してだが、最初期の真珠湾攻撃をした無敵の時代は二一型だが、アメリカで高性能機が多数を占め劣勢となった後期は五二型というものになり、同一機種とは思えないくらい形状が全く異なる。
エンジンも「栄一二型」から「栄二一型」に変更されている。
またカラーリングも当初は灰色だったものが濃緑黒色へと変化していく。
ゼロ戦に限らず、メッサーシュミットもスピットファイアも、中身も形状もマイナーチェンジも含めて大戦中にどんどん変化する。
外色に関しては時代だけではなく運用地域や部隊で違う場合もある。
実物を使用する場合、現存している機体が厳密には当時にそぐわない可能性がある。
筆者はそこまで詳しくないので自信はないが、もしかすると見る人が見たら本作の戦闘機のカラーリングや形状がこの時代とは違うのを見破ってしまうのではないか?
またエンジン音も聞く人が聞いたら微妙に違うのかもしれない。
特にドイツは敗戦国であるため、保存状態の良いメッサーシュミットがどのくらい残っているか疑問である。本作に登場する同機の機首部分がオレンジ色だったのが気にかかる。
形状もあんなだったろうか?
本作冒頭の浜辺のシーンで遠くに近代的な建物が見えたことなども細かいところだが指摘しておきたい。
神は細部に宿る!
主役を演じた俳優も含めて当時の兵隊と同年齢の18、19、20歳をオーディションで選んだようだ。ワンダイレクションのメンバー1人を抜擢しているとはいえいやらしい役であり、いきなり主演俳優というわけではない。
事務所の後押しなのか全く見当違いな配役、俳優ありきの年齢などの設定変更が横行する日本の映画業界にも学んでほしい姿勢である。
黒澤明や宮崎駿にも駄作はある。
これだけの大エキストラを使用してパニック映画を制作できるところはさすがはクリストファー・ノーランだが、この監督は良くも悪しくも大上段に構えて世界観を創造することで本領を発揮するのではないだろうか?
ヤバいかも。
IMAXにて観賞、なのだが、あのスクリーンの大きさでIMAXを標榜するのはいかがなものか。ただ音響効果は只事ではなかった。
クリストファー・ノーランの演出力が取り沙汰されていることが多いが、この人は生粋のストーリーテラーだと僕は思う。
監督作にはすべて脚本に参画していて、なにを物語るのかということを、いつも考えている。
本作もそのストーリーテラーぶりが発揮されている。
だが、それを戦争映画に持ち込んだのはどうだったのだろうか。
観た直後は、不思議な時系列をもつ脚本と効果絶大な音響とに幻惑されていたが、帰りの電車で9年前のキネマ旬報に載っていた「チェチェンへ アレクサンドラの旅」(アレクサンドル・ソクーロフ監督)の大場正明の作品評を読んでハッと目が覚めた。
「ダンケルク」には反戦の視点がないと、僕は感じた。
あの「スターシップ・トゥルーパーズ」(ポール・バーホーベン監督)でさえ反戦メッセージを受け取ったのに。
ダンケルクの戦いは、確かに史実なのだろうが、もっと違う切り口があったのではないか。
クリストファー・ノーランはヤバい作家かもしれない。
音楽最高!IMAXで二回目
もっとストーリーを!
共感ポイントがない
ノーランらしく実写を追及した迫力はあった。
が、共感できるドラマがない。
ドラマ性を極力無くした体験型映画を目指したのかもしれないが、映画的には入りこめない結果になった。ただ逃げ、ただ戦い、ただ駆けつける。感情移入が出来ない。
時間軸を前後させた構成も混乱させるだけでうまく機能していないし、テーマが見えてこない。
ハリウッドエンディングではない
戦争映画ではあるのですが、舞台は違うもののオデッセイ、グラビティ等に近い、主人公の青年達が生き残るためのサバイバル劇が中心となっております。
時系列や場面がいったり来たりするのでわかりづらい印象で、また爽快感のあるハリウッドエンディング(目出度目出度)ではないため、鑑賞後の爽快感は期待できないでしょう。緊迫感を煽る飛行音や射撃音、そしてBGMが(過剰と思うくらい)効果的で、(精神的に)けっこうこたえましたが、戦争のリアル、恐怖感は十分感じとれる作品だと思いました。
サイドストーリーとしてこの作戦を支えた桟橋の中将、民間船の船長、飛行士達も印象的でした。
全745件中、481~500件目を表示