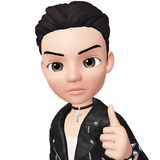アイ・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場のレビュー・感想・評価
全110件中、41~60件目を表示
PSP phone!?
現代戦を描いた映画として素晴らしい
「ゼロ」グラビティ同様に、作品の内容を理解していないとしか思えない副題、付けた奴は本当に見たのか?
現代の戦争は対テロ戦争かつ非対称戦争
ドローンで対象をピンポイントに絞り戦う米国
自爆テロにより無差別に民間人を虐殺するテロリスト
命がけで現地工作員が情報を入手し、数年掛けて追跡、絶好の機会が訪れても法律上外交上政治上問題のない事が確認出来るまで攻撃できない
シン・ゴジラの序盤とデジャブするほどお役所仕事的でアメリカ的英雄行為とはほど遠い本作
印象的なのはあまりに小さいドローンと、その操作にまさかのPSP phoneを使っていることだ。数年前の超ニッチなデバイスの登場にあまりに意外すぎてびっくりした。
空の目
ヘレン
サクサクしてて、おもしろい。イギリスとケニアが友好国で、イギリス籍とアメリカ籍がいる特殊な状況だから凄く丁寧な攻撃だけど、きっと本当はもっとずさんで、日々バンバンやってるだろうし、承認プロセスも、データ照合ももっと雑だろうし、そこにほパトリオット精神絡むと、もう短絡的で機械的でワンクリックな結論に毎回落ち着くんだろう。
で、そんな感じは別に戦争というか、これは戦争とは言わないで、テロとの戦いとかいうのかもしれないけど、それに限った話ではなくて、決断の責任が現場から会議室に順繰りにたらい回しにされるのはどこにでも一般化されてて、皆んな良くない結果になった時に、自分に降りかかる火の粉を払うのは、当たり前にやってる。だから、むしろ一般社会とおんなじことを、こういうミサイル撃つとか撃たないとかいう時にやってるのが、本当かしら?って不思議。
虫カメラ操作してたケニア人の彼だけが、リアルな危険に直面させられてる。で、狂信者じゃなかったお父さんはこれをきっかけに次の自爆ベストを着る。
意図的にテロリスト側の実態は描かず、攻撃する側に絞ってて、でもテロリストはちゃんと台座外して、少女を搬送してくれたりして、そういう描き方は良い感じ。
パン売りの少女の話は、パンと植木鉢をちょっと思い出した。まぁ全然違うけど。
本当によく出来てる。
選択
最後は政治判断しかない
凄さまじい作品!!
伏線も背景描写も無く、ただただ単一の軍事オペレーションを100分間でひたすら描いている、この約100分が徹頭徹尾 緊迫の連続で兎に角重く、 でも目を離せない
コブラ中枢の激しい議論が為されるけど、
皆、各々の立場でポジショントークに徹していて結論を導けない、
けど 最後は やはり 政治判断しかない、だってこれは戦争だから
人道派のように映るアンジェラも、
責任回避しつつ宣伝戦勝利オプションを訴求しているし、突き詰めると人道判断じゃない
ラストのアンジェラによる糾弾への中将のカウンター、
これも本質的だった
戦争の代償(コスト)を誰よりも知っているのは文民じゃなくて
軍人であるってこと
感情で叫ぶアンジェラ(人道派文民の象徴だと思う)こそ コストを実感できてないっと感じた
しかし、荒唐無稽かもしれないけど
こんなシーンはこの世から無くなれ!!って純粋にそう思うばかり
経済的困窮が 危険思想を喚起し テロル等の破滅を導く
これが問題の核心のはず
ソリューションの多くは マクロ経済政策に依存するから
世界の指導者達は 頑張ってほしい
重い
世界各地で勃発している紛争の多さに、また大きな戦争が起きるのではと...
神の視点を得たとて
ドローン攻撃にてテロリストを抹殺する話
作戦本部とコントロール室と会議室を舞台にドローン攻撃の是非を問うのだが、凄い緊張感と臨場感でピリピリした雰囲気を上手く描いていた。
少女の命かこれから起きるテロ被害者の命かを天秤にかける選択は誰もが避けたくなる。
戦争ではそんな非情な出来事が多発していると突きつけられる映画だった。
圧倒的優位に立ちながらも攻撃の出来ないじれったさや、少女を救う方法を模索するも解決策が上手くいかない歯がゆさなど、ドローン攻撃のリアルが知ることができた。
また、判断を下す人間の苦悩が伝わってくる。
ドローン攻撃は卑怯だ、安全圏からゲーム感覚で爆弾を落とすなど、いいイメージが無いが、操縦する兵士、指令を出す大佐、許可する官僚などだれもが命と向き合っていた。
卑怯だとかの話の前に戦争を起こさないようにしなければと思った。
いくらハイテク装備を駆使しても、救えない命、神の視点で物語は進むが人間の無力さも叩き付けられたように思う。
もしかしたら、神様もこんな風にもどかしく思いながら地上を見ているのかも知れない。
自分がこの状況ならばどうするだろう、どちらにしても後悔する選択を前にして引き金を引けるだろうか。
多分、引くだろう、そして一生言い訳を考えて無理やり納得して悩み続けるだろうなと想像してしまった。
アランリックマンが「決して言ってはならない、彼らに戦争の代償を知らないなどと」と最後に言う。
戦争は悲劇しか生まない、軍人は悲劇の数を減らすのが仕事なのかも知れないと思った。
この映画に似て非なる作品「ドローン・オブ・ウォー」もおすすめ
ドローンパイロットの苦悩とCIAの非道さが見れる。
こちらの作品は民間人だろうが標的の近くに居ればかまわず爆撃する。
判断はしないし命令のままに引き金を引くのだが、段々すり減っていくパイロット役をイーサン・ホークが熱演している。
二つの映画は米国と英国で立場が違うので何とも言えないが、「アイ・イン・ザ・スカイ」は責任を取るのは誰か、法律は犯してないかを気にして作戦の苦悩を表し、「ドローン・オブ・ウォー」は責任がない事に苦悩する。
二つ合わせて見ることで、ドローン戦の今が見えてくるかも知れない。
劇中セリフより
「待てるが、待つ必要はない」
時間が有るなら最後まで粘りたいと思った。
今まで見たことがない新しい戦争映画
今まで、たくさんの戦争映画を見てきた。
中でも印象に残ってるのは、戦場の兵士の視点から描いた、プラトーン、プライべートライアン。
これらは、兵士の息遣いまで聞こえ、弾丸が耳元をかすめ、自分も戦場にいるかのような感覚になり、衝撃を受けた映画。
見た後、すごく疲れたという記憶がある、
一方、この映画は戦場から遠く離れた安全な場所から現場を眺めている映画だ。
見る前は、ゲーム感覚の映画だろうと思っていたけれど、確かに会議室で戦争は行なわれているが、目標の近くに少女がいることがわかってから、戦争は緊迫してきた。
攻撃に賛成、反対の立場から、上司への協議、作戦の見直しなどを瞬時に行なわなければならなくなった。
自分も会議室にいるようで、一緒にハラハラしながら、現場の様子を見ていた。
判断に時間がないという状況が、一層、ドキドキさせられた。
遠く離れた安全な場所でも、痛みや生命の危険はないけれど、戦争はある。そう思った。
そして、見た後、すごく疲れた。
描き方は今までと違うけれど、新しい戦争映画である。
最後に、攻撃することはやむを得ない判断だと思うけれど、あどけない少女が犠牲になるのは痛ましい。
戦争もテロも嫌だ。心からそう思った!
解釈によっては微妙…
戦争もここまで来たか、という感じ。
「殺す方にも心はあるのよ~」みたいなメッセージが含まれているようにも見え、戦争を正当化している風に解釈することもできる。
映画としてはスリリングで中だるみもなく、面白い。
現代の戦争
ドキドキはらはら
戦争反対。
戦争の形態が時代とともに変わりつつある。軍事用ドローンで敵のアジトをピンポイントで攻撃できる。ドローンどころかもっと上から攻撃できる。
テロリストが自爆テロの準備をしているところをキャッチ、捕縛が目的だった当初の作戦は殺害に変更。ドローンによる攻撃が指示される。
その標的のそばにひとりの女の子が。
彼女もろとも攻撃するのか。
イギリス、アメリカと離れた場所で同時刻にケニア ナイロビの映像を見ながら攻撃の是非を議論する。なんとも不可思議な光景である。
攻撃の意思決定は誰に委ねられるのか。そんなところから、女の子はどうなる?というところまで、ギャビン・フッド監督の演出は的確に映し出す。
サスペンスフルでもあり、また、群像劇にもなっていて、今の時代を映す好編になっている。
本作を見逃さないで、本当によかった。
個人の命に代えはない
クールにしてハード。ホントに考えさせられる!
なかなかハードな映画。
ずっと緊張し続けで席に固まっていた。
誰も悪くないし、誰も間違ってない。だが、現実にひとりの少女の命は奪われてしまう。
撃つか撃たないかという緊迫感がほぼ全編に渡って続くという構成はすごい。そしてそれを全く冗長にしない脚本と演出、アカデミー脚本賞、演出賞、監督賞の候補になるのだろう。
無関係な少女の命を奪うかもしれない作戦を実行する決断は、上へ上へと持ち上げられ、または横へ広げられ続ける。当事者の気持ちもわかる。結局、最終的な判断は、大佐と軍曹という強烈な上下関係がある中での無言の圧力というか、軍人としての阿吽の呼吸というか、共感というかに基づくデータの改竄によって決定している。
目の前の比較的小さな悲劇を防ぐか、ごく近い将来に起きると予想される大きな悲劇を防ぐか、といった判断を、軍人は戦場で都度しているわけだが、それを技術の力によって机上に持って来ることはできても、その判断の質が向上するものではないことを示していて、ほろ苦い映画だ。
究極場面では、民間人を一人でも巻き込む危険があり甚大な被害の確率が50%以上の場合はどんな作戦も実行しないという暗黙のルールを出来上がり、確率計算をする人に負荷が寄るだけで、「確率は65%だが、作戦を優先しよう」といった上位の「犠牲があってもやるんだ」という責任を背負った意思決定が行われるわけではない。これは、射手の「撃っても良いのか?」という疑問や要望に、指示命令系統はどこまで応える必要があるのか、という点も含めて難しい問題そうだ。
戦場という状況の恐ろしさを改めて気付かされつつ、戦場と遠く離れた場所で意思決定と実行が行なわれようとも、関わる人たちの苦悩と悲劇はなんら変わらないのだということ、巷で言われているような「ゲーム感覚での戦争」になっているわけではないんだということを教えてもらった。
民間大臣の「あなたは遠くから決定しただけ」という非難に対して軍人大臣は言う。「私は自爆テロ現場の処理で多くを見てきた。どんな軍人に対しても『お前は参加していない』と言ってはならない」このセリフも重かった。
軍人とは、ほんとうに非日常の極限を要求される職だ。そうした職業が必要という状況は、やはり、理想の姿ではないのだろう。
観ている間はひたすら緊張感、後でいろいろ考えさせられるクールな映画でした。ぜひ、機会を見つけて、鑑賞してみてください。
全110件中、41~60件目を表示