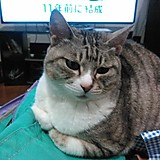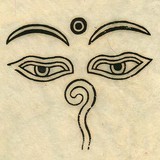サウルの息子のレビュー・感想・評価
全86件中、61~80件目を表示
ユダヤ人の悲劇
立派な映画だが・・・
人間にとって戦争程憎むべきものはないだろう。
世界中の何処の国に暮らす国民の誰に聞いても、戦争を好む人間はいないだろう。
しかし、人類史始まって以来、それ程誰もが嫌いで、望まない筈の戦争が終結した事はない。
必ずと言ってよい程、この地球の何処かのエリアでは戦争や内戦が起きている。
そんな状況下で、この「サウルの息子」もカンヌでグランプリを受賞し、オスカーの外国語映画賞も受賞した作品なので立派な作品なのだろう。
監督や制作者が意図するように、戦争の悲劇を描く事は後世の人々に、この愚かな行いを繰り返させない様に語り継ぐ為のツールとして、映画と言う素材を使って戦争の惨禍を伝えてゆく事は一番適した素材であり、効率の良い方法なのかも知れない。
それだからこそ、戦争映画の存在は必要不可欠として考えられ、制作されているのだろう。
だが、現在の私にはこう言う映画に感動し、高評価を付けると言う事は有り得ないだろう。昔なら星5でも喜んで付けたかも知れない。
今では私の心が石の様に堅くなってしまったのだろうか?全く感動はしないどころか、その逆で拒否反応しか起こらなくなってしまったのだ。
3度の飯より映画好きを自負する自分としては、一応話題作なので観たが、前半少し睡魔に襲われ意識が遠のいた。
多分、冒頭サウルが子供の遺体に纏わるシーンを見せ付けられたのと、次々とガス室に送り込まれるユダヤの人達へのナチスの「スープが冷めるから急げ」「コーヒーが~」と言うセリフが聴きたくなかった為か異常に眠かったのだ。
ゾンダーコマンドとして僅かでも生き延びなければならなかった人々がいたのは悲劇的史実であるし、そんな彼ら苦しみなど今更知らされてどうなるのだろうと思ってしまうからだ。
特に日本人の観客などは、ユダヤ教に詳しくないし、この作品の状況を正確に理解する事は一般人には難しい。そしてその事を真面目な日本人は不勉強と思ってしまう。その事を理解する事にどれ程の重要性が有るのだろうか?
カメラの使い方を駆使し、色々な撮影方法を例え試みたところで、虐殺されたユダヤ人の悲劇を観客は頭では理解しても、その苦しみを知る事は出来ないだろう。
そして殺す側に立たされてしまったナチスの苦しみも理解する事は出来ない筈だ。
戦争映画は戦争の悲劇的なエピソードを幾つも幾つも手を変え、品を変え延々と作り続けているが、戦争になってしまった背景や、その当時の世界の政治が戦争を勃発する様になるまでにはどのような道筋が有り、その時代に生きていた人々がどのような心の葛藤を抱いていたか描いている作品は非常に少ない。
世界経済の不均衡であるとか、エネルギー資源供給の不均衡等の様々な事情に因り、戦争が始まりに至る迄の理由や過程を詳細に描き、反省や過ち見つけ出し、その悲劇を繰り返さない為、未来に建設的なメッセージを描いている作品は極めて少ないと思う。本作も立派な作品かも知れないが、戦争は、勝っても負けても、どちらも被害者で有る。戦争を始める国も悲劇!売られた戦争を交戦しなくてはならない方もどちらも同じように悲劇には相異がないのだ。この映画を観て貴方は何を理解し、今後に生かすのだろうか?とても興味深い。
好むと好まざるに関わらず、観ておきたい作品
勉強不足を痛感
サウルが見た世界
あるいは、地獄と云う名のテーマパーク
教科書の゙虐殺"の文字。ひどく無味乾燥ですが、冒頭いきなりその現場に、立ち合うことに。ご見物(観客のことです)一同、固まってしまいました。スパルタ式、歴史授業の始まりです。全てを失ったパパの、さまよう魂と共に、地獄巡りするわけです。POV方式(主観映像ってやつです)で撮影せざるを得ない情景。見たくもない映像が、画面を埋め尽くしているからです。おまけに、4DX方式なしで、恐怖と狂気が放出します。映画観てるのか、鬼畜なアトラクションに、参加してるのか、判らない状態に。終盤に、パパが見せる穏やかな笑み。息子さんの御霊は、天に召されたのでしょうか。余談ですが、収容所の彼らが、解放者として期待したのが、当時のソ連。その後のハンガリーと、ソ連の関係を描いた「君の涙ドナウに流れ」も、観ないと損です。悲し過ぎて、涙も出ない大河ドラマが、完成します。
せめて人間として死ぬための努力
アウシュビッツでユダヤ人が虐殺されたということについては、事柄として知ってはいたものの、映画という形で見たのは初めて。
シンドラーのリストや、ライフイズビューティフルで見た程度で、これほどまでに生々しく見せた映画は見たことなかった。そんな自分にはものすごい衝撃的であった。全編通じて主人公しか映らない映像とピンボケした世界。しかし、それが、映画の世界で主人公と一緒に見ている感覚にさせる。映画は疑似体験的な要素があるものだが、この映画ではまさに疑似体験レベルが未だかつてない。本当にその場にいる怖さと緊張感がある。ドイツ兵が本当に怖い。実際はこの何百倍も、何万倍も恐ろしいはすだ。それでもその片鱗に触れられることは大事なことだと思う。
そういう意味で、この映画にはネタバレなんていうものは存在しない。全ては見なくては理解できないからだ。
まず、何が始まるんだろう、と見ていたら、何やら多くの人が集められている。収容所の中かな、と思ったら、多くの人が服を脱いでいる。そして密室に押し込められる。扉が閉まると、壁に掛けてある服を主人公サウルたちは回収していく。ここで、ああガス室か!と分かるのだ。ここで、彼らは死ぬのだ。暫くすると密室から、叫び声ともなんとも言えない声と、扉を叩く音が聞こえてくる。次第に扉を叩く音は大きくなっていか。しかしサウルは表情を変えない。彼の心はとうの昔に死んでしまったかのようだ。
そんな心理状況を説明するかのごとく、周囲はピントボケ、ぼんやりとしかわからない。しかし確実にそこでは虐殺が行われているのだ。肌色の死体の山と思われるものも見える。
そんな中で、ある時死にきれなかった少年を見る。彼はその少年を埋葬することで、自身の人間としての尊厳を、それは無くしてしまったものなのかもしれないものを、再び思い出すための行為であった。
彼はその少年を息子だと言うが、彼の息子ではないことは映画の中盤で分かる。彼自身も恐らく分かってはいるが、彼は自分の尊厳のためにも、少年は彼の息子、つまり自分自身を投影した人間であったときの自分である必要があったのだ。ゾンダーコマンドとして死んでいくしかない彼だが、彼自身あるいは彼らを人間として死なせる唯一の希望が少年の埋葬であったのだ。
ゾンダーコマンドの反乱は実際にあった出来事だそうだ。この映画でもそれは描かれるが、主人公サウルはそれに組みしようとしない。反乱は死を覚悟しながらも生きることを目指す行為であるが、サウルは逆に尊厳的な死を目指すことでそれまでの生を肯定しようと試みているからだ。
最後に死体が川に流されてから絶望したが、その後の死んだ少年が成仏したかのような、尊厳のある死を与えられたかのような人物に出会えて、彼は彼の生と死に満足するのだ。
胸に突き刺さる作品
何とも言えない重い空気が・・
ゾンダーコマンドという仕事…ナチスによる強制収容所でユダヤ人の死体処理をするユダヤ人。表情はありません。淡々と仕事をしている…そんな中で……
延々と続く残虐・残酷な描写。
主人公サウルの視点と傍観者である私たち観客よりの視点みたいな感じでカメラワークが随時変わっていく。それが何ともいえない重苦しさを伝えてくる。
鑑賞後心が落ち着きを取り戻すまで時間がかかりました。そしてしばらくして、ゆっくり思い返してみると…涙がとまらなくなりました。劇中泣くことは多々あるのですが、鑑賞後に、こんな思いになるのは久しぶりです。それだけ鑑賞中は衝撃と重苦しさで脳がショートしてたんだと思います。
万人におすすめは出来ませんが、万人に観てほしい作品。
息子云々というより、サウルのラストの表情が胸に突き刺さる。
胸が痛い
死者を葬る
この監督の次回作が早く見たい
ホロコーストがテーマなので、当初はあまり気乗りしていなかったんですが、オスカーの外国語映画賞最有力ってのと、やはりユダヤ人研究は自分の生涯のテーマなので、意を決して見ることにしました。
そしたら、これがとんでもない代物だった。去年のカンヌでグランプリ取ってます。ゴールデングローブでも外国語映画賞受賞。見れば納得ですよ。
何が凄いかって、とにかく画面設計が斬新なんです。それを実現する撮影も凄い。画面は3:4というスタンダードの画角で、カメラは主人公の背後30センチあたりが定位置。いわゆる三人称視点です。ピントは常に浅く、主人公の背中に記された赤い大きなバッテンにフォーカスされます。だから背中越しに見える風景は、いつもピンぼけています。舞台はアウシュビッツの収容所。その中で繰り広げられる陰惨な出来事は、狭い画角とピンぼけ状態で描かれます。つまり、肝心の場面は「見えそうで見えない」。そして、主人公はある使命に取り憑かれていて「あちこち目まぐるしく移動する」。……ワンカットが20〜30秒というのはザラ。1分以上の長回しもたくさん出てきます。
監督は弱冠38歳。ハンガリー出身のユダヤ人ネメシュ・ラースロー。長編1作目だそうです。ゲーマー世代ですよね。そうじゃなかったら、こんな映画の撮り方思いつかないでしょ。
終盤、カメラは収容所を飛び出し、森を抜けて川を渡ります。映像は観客に若干の開放感を感じさせながら、実に複雑なフィナーレを提示します。
久々に「ヨーロッパ映画」を見たなという感じ。早くこの監督の次回作が見たい。
自己中をテーマにした映画
他の方が書かれているのであらすじは省くが、重い背景が下地になっているので正直、泣ける映画だとは思わないし、良い映画か悪い映画かも難しいところだと思う。
感情や目線を強調した撮影技法が素晴らしいとか、ピックアップされた「1944年のある日」がノンフィクションで救いようのないストーリーになるってネタバレなト予告編が良いのか悪いのか僕には分からない。
ただ、僕は登場する能動的なユダヤ人全てに有り余る人間らしさ、もっと言えば「生」に対する執着を感じた。勿論、その執着が側から見れば自己中であったり、周りの人の運命を大きく変えてしまう大ポカであったりするワケなのだが、場面場面で考えて行動した人たちを誰も責められはしない。
作中、ナチはユダヤ人を部品と呼ぶ描写があるが、彼らは間違いなく人間であったのだ。
ラストシーンの笑顔が印象的
正直ちょっと難しい。少なくとも私には。この作品に込める監督の想いが、どこまで自分に理解できたのかなと思ってしまった。
セリフも会話も少ない。最低限の知識は必要。たとえば「ラビ」とはどんな人たちを指すのか?とか。
印象的だったのはラストシーン。サウルが一回だけ見せた笑顔。その裏にはどんな意味が隠されていたのか。。。。
同化への仕掛け
ナチスのユダヤ人収容所では、労働力として生かされるユダヤ人たちがいた。ゾンダーコマンドと呼ばれるその人々は、各地から運ばれてくるユダヤの同胞を「処理」することをその使命とされている。
そのゾンダーコマンドの中の一人、サウルがガス室で息絶えなかった少年を見つける。しかし、すぐにナチスはこの少年を殺してしまうのだ。
この後、サウルはこの少年は自分の息子なのだと言って、ユダヤ式の埋葬をしようと、閉ざされた収容所の中を奔走する。
「処理」されるユダヤ人たちには、映画の冒頭からレンズの焦点が合わない。35ミリの狭い画面はサウルの姿でほぼ占められている。観客は、彼の周囲の状況をそのごく限られた余白でしか窺い知ることができない。
このサウルの捉え方も、大部分が彼の背中からのショットである。観客はサウルのあとをついて歩いているかのような錯覚を抱く。そして、その錯覚がサウルの抱えるストレスと同じ恐怖や焦燥につながっていくのだ。
サウルが抱えている遺体の少年は、本当にサウルの息子なのか。
死者を葬るために、生きている者たちが命を危険にさらす意味があるのだろうか。
収容所内で反乱を起こし、果たしてドイツ軍やナチス親衛隊相手にどこまで戦えるのだろうか。首尾よく収容所を抜け出したとして、どこまで逃亡すれば安全が確保できるのか。
それらの疑問もまた観客にストレスを与え、憔悴したサウルその人へと同化させる。
映画はこのように、カメラワークとシナリオによって、観客に主人公そのものを疑似体験させる。
サウルの身に起こったことの追体験は、われわれに早くこの状況が終わって欲しいと願わせる。ことの成否よりも、尊厳を失うことなく早急に生を終えることのほうが重要であり、そこにこそ当事者のその絶望的な感情を理解させる仕掛けがあるのだ。
全86件中、61~80件目を表示