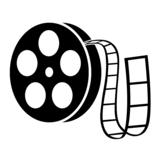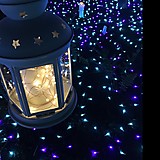君はひとりじゃないのレビュー・感想・評価
全19件を表示
ブラックユーモアあふれる人間ドラマ
感動ものとして宣伝されているが、どちらかと言うとブラック・コメディ。首をつっていた男が、まだ生きていて突然あるきだしたり、霊を感知できるというセラピストが奇妙なセラピーを展開したりと、不条理劇的要素も強い。
原題は「BODY」とあるが、肉体とはなんなのかについての作品であるのは明白だ。翻って肉体以外の存在とは何なのかをも逆説的に問うている。
死体を見慣れた心が麻痺した刑事。拒食症のその娘。変わったセラピーを実施して異端扱いのセラピスト。3者の肉体と精神の関係が丹念に描かれる。
ポーランド映画というと、クシシュトフ・キェシロフスキが有名だが、監督はその影響を認めつつ脱構築するような気持ちで製作に望んでいるらしい。難解な面もあるが、ユーモアで上手く緩和している秀作。
君は ひとり じゃない
ブラックジョークで始まるハートフル・ストーリー
途中、伏線ばら撒きっぱなしで回収ナシなんじゃないかと思ったが、見事な着地点を見つけた風変わりな脚本。検察官のヤヌシュ、娘のオルガ、そして心理療法士兼霊媒師のアンナという3人の視点での物語は、最終的に3人が手を繋ぐところでまとまるのだ。
ヤヌシュの職業も、最初は警察官なのか医師なのかわからず、ひょうひょうとした態度で仕事をこなす太ったオヤジといったイメージ。そんな父親が大嫌いな娘のオルガ。ただ、一緒に暮らしているだけの存在なのだが、その存在自体が鬱陶しく思える思春期を過ぎた娘。
エピソードが上手く繋がるのかわからに上に、誰一人として笑顔を見せないという無表情演技が多い。BODYというタイトルからもわかるように、肉体と精神は一つじゃないことを意味しているように感じるし、霊媒師を否定もしないが、笑えるようなイメージでとらえたりもする。
墓場が水道管破裂によって困ってることを言い当てたアンナ。ちょっとは霊の存在も信じる気になったヤヌシュが彼女に相談するのだが、そろそろ自分でも霊を呼べるからと、机の引き出しに手紙を書けるように準備するよう助言するのだった。
最後には全然能力を発揮できずにイビキまでかいてしまうアンナだったが、そのおかげで父と娘は心を打ちとけることができた。この最後のシーンで思わず評価が上がってしまうのですが、笑いの無かった中盤から一気に表情まで氷解する展開が素敵。ほっこり。こんな可愛い子だっけ?とびっくり。
何気ないことが人生
シュールな入り方
窓から入る光が
ヨーロッパではオカルト流行?
拒食症とスピリチュアルを扱ったポーランドの奇妙な映画である。
死体を見慣れて何も感じない検死官の父、拒食症の娘、霊的能力を使用するセラピスト、この三人を中心に物語は進んで行く。
やはり今年『パーソナル・ショッパー』という主人公が霊的能力の持ち主という映画があったが、テロが頻発するヨーロッパではキリスト教に根ざした精神世界の無力感の代替として霊的なものが流行しているのだろうか?
ポーランドでテロはほとんど起きていないと思うが、監督のインタビューを読むと、共産主義から脱却後、経済格差が増大し、不安定な社会で教会の権威は失墜し、目的なく生きる人々が増えているらしい。
前述した『パーソナル・ショッパー』もカンヌ映画祭で監督賞を受賞したが、この作品も第65回ベルリン映画祭で銀熊賞(監督賞)を受賞している。
筆者から見ると両作品ともにオカルト的だなと思える場面が時折あるのだが、ヨーロッパではキリスト教に替わって台頭しているのだろうか?
あの世の人間がこの世の人間を導くような映画は日本にも腐るほどあるのだが、日本はもう少しさわやか路線だ。
しかし両作品ではホラー映画を観ているような感覚になる時がある。淡々と描かれるからそう感じるのだろうか?
また日本のこの手の映画がカンヌやベルリンで絶賛されることはないんだろうな、というのも両作品を観ているとよくわかる。
日本はどこまでも霊が人に寄り添ってくるが、両作品ではほとんど寄り添って来ない。何か示唆を与える、もしくは与えるように見えるだけである。
そこには欧米の個人主義と日本の集団で協調を重んじる感覚の違いがあるのかもしれないが、とにかく違う。その分不気味に感じてしまう。
またこの映画は軋んだ音をたてて蛇口から流れる水道水や雨などとにかく水がよく描かれる。また全体的に色調も暗い。
水道水の音や雨音に限らず、ヘリコプターの音など外界の音が効果的に使われている。
最後の場面での主要登場人物三人がテーブルを囲むところなど会話以外無音のシーンがあるが、ヘリコプターの音が聞こえてきたりする。
マウゴシュカ・シュモフスカという女性監督だが、カメラ映りの良くない普通の人々の日常を描きたかったという。
音においても日常に強くこだわったのかもしれない。
戦前日本がシベリア残留孤児を救出して以来、ポーランドは親日的な国だが、日本はあまりポーランドを知らないように思える。
かくいう筆者もポーランドの映画監督はアンジェイ・ワイダしか知らない。
しかし、この作品で光の当たらない所で生きるポーランド人の現状を垣間みたように思える。
この映画で霊的能力の持つセラピストを演じるマヤ・オシュタシェフスカは40代半ばの女優だが、ポーランドでも日本と同じように40歳を過ぎると重要な役はもらえなくなるらしい。
同年代の監督がわざわざこの役を当て書きして彼女を起用したようだ。
また、このオシュタシェフスカはワイダ監督作品の『カティンの森』の主役も演じていたが、その映画から数年経過し、髪型もショートヘアになり、眼鏡をかけるとまるで別人である。
作品中若い男女が濃厚にいちゃつき、それをオシュタシェフスカが影からうかがうシーンがあり、筆者はそのシーンを唐突に感じたのだが、前述したような映画界での女優起用の現状に対する監督の不満を現したと見ることも可能である。
どんなに暗い生活でも人はそこに慣れ、視点を変えることで幸せを見いだすことは可能だ。
日本人も戦前までは本来そういった死生観を当たり前のように持って生きていたように思えるが、今あらためてその重要さを教えてくれる作品である。
笑えるけれどシュール過ぎる
現実と虚構の狭間をリアルに描いていたと捉えるべきなのだろうか。オカルトの類も決して劇場的に見せるのではなく、現代において誰もが体験していそうな事柄として提示していたところが、何気に斬新だと感じた。
血と恐怖を笑いでうまい具合に丸めようとしている意図は感じるけれど、あまりにシュール過ぎて、決して大笑いできる内容ではなかった。
見る人によっては、かなりホラー的要素を盛り込まれたと思えるだろうし、そのように見えてしまうと最後はかなり肩すかしのように感じるかもしれない。かたや、単に日常をリアルに淡々と描いた退屈な映画と感じる人もいただろう。そんな人にとっては、最後は相当に笑えるに違いない。自分はどうかというと、前者と後者の狭間で、眠気と笑いが去来していた。
内容はあくまでヒューマンドラマなんだろうけど、今までにない斬新なものというか難しさというか、一風変わったものを感じる作品であった。
不思議な作品
母を亡くした喪失感から、心が壊れうまく距離感がとれなくなった父娘の話。セラピーや霊媒、超常現象とか出てくるから途中まで〝スピリチュアル系?ちょっと苦手な作品かも…〟って思ってたが、予想を裏切るラストで驚き。感動✨
心の病気という摂食障害が結構詳しく描かれていて、なかなか深い部分も。拒食もそうだけど味覚障害も心の病からくるのね。
ちょっと難しい作品だったけど、でもその難解さもラストシーンの2人の笑顔、そこに流れるBGM、部屋に差し込む朝の光の美しさで、ふと湧いた疑問もどうでも良くなって一瞬でかき消されるかな。記憶に残るラストシーンだな〜。とても不思議な作品でした。
私の中にも見えない〝何か〟を信じる気持ちも無いわけではないけれど、そればかりに捕らわれてしまっては自分を見失うよな〜と。心で寄り添うくらいで良いのかなと。うまく言えないけど…^^; 心を見失った時は、時には他人からのちょっとした事で救われる事もある。そんな事を観終わった後にふと考えたかな。
原題が『BODY』。なかなか興味深い作品でした
霊っているのかいないのか、ま、どっちでもいいのか
ポーランドの中年検察官ヤヌシュ(ヤヌシュ・ガイオス)の仕事は、来る日も来る日も凄惨な死体の検証をするというもの。
心は疲弊している。
家庭でその心が癒されることはない。
というのも、妻を亡くしてからは、娘のオルガ(ユスティナ・スワラ)との仲も上手くいっていないからだ。
そんなある日、娘オルガは摂食障害の末に自宅トイレで倒れてしまう。
ヤヌシュはオルガを精神病院に入院させ、グループセラピーに参加させるが、そこのセラピストであるマオ(マヤ・オスタシェフスカ)にはもうひとつの顔があった。
それは、8か月の息子を突然死で喪って以来、霊と交信する能力が芽生え、その能力を使って残された遺族を救うというものだった・・・
といったところから始まる物語で、まぁ、その後は、マオの不思議な力によって(か、よらずか)ヤヌシュとオルガの心が再び通い合う展開になる。
いやぁ、どういっていいのかよくわからない感じの映画で、ストレートなヒューマンドラマとは趣を異にしており、コメディに分類しているサイトもあるくらい。
先ごろ特別上映で観たイザベル・ユペールとジェラルド・ドパルデュー主演の『愛と死の谷』もそうだったが、近年、ヨーロッパでは霊的なものが題材に撮られていることが多いのではなかろうか。
未見だが、オリヴィエ・アサイヤス監督の『パーソナル・ショッパー』もその手の話らしいし。
とすれば、かなりヨーロッパ全体が疲弊しているのかもしれない。
そんなことを観終わってから考えたが、映画のラストはどう捉えればいいのか、よくわからない。
心に深い溝のあるヤヌシュとオルガが、マオを交えて、亡き妻の降霊会を行う。
霊が降りてくると、マオは自動書記を行う。
が、いつまで経っても霊は降りてこない。
そのうち、深夜になり、夜明けになり、マオはテーブルを前にして大きな鼾をかいて眠ってしまう・・・
これは、陽気な亡き妻の霊が降りてきてグースカと寝たようになっているとも受け取れるし、単にマオが眠ってしまったともともとれる。
個人的には後者だと思うのだが、まぁ、どちらでもいいのかもしれない。
いずれにせよ、父娘の心の溝は埋まったのだから・・・
って、やっぱり、よくわからないなぁ。
独特な展開、セラピーと霊媒の組み合わせか〜
嘲笑
父親の仕事が精神的にキツいのはわかるけれど、親を亡くしてっていうのはちょっといただけないし、結局のところセラピストよりも親子のコミュニケーションが大切ってことね。
霊能者なんてインチキでバカバカしいということで。
壮大なる前フリ
説明過剰でない各シーン
しかし、全体通して雄弁なストーリー
感心しながら観ました
タイトルに付けました前フリ
それは、
ご覧になった方だけはわかるでしょう。
ラストシーン。
今までのストーリーなら、
ヒアアフター的でも十分なカタルシス。
それをアチラへ振る。
それもまた真実。
癒されました。
家族との対話が深い悲しみから救う
全19件を表示