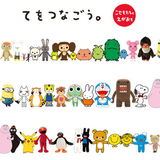この世界の片隅にのレビュー・感想・評価
全159件中、61~80件目を表示
生きることの暖かさ
戦時中が舞台ということで重いのかな、と思ったけど、たまに笑いもあり、当時の日本人のありのままの生活が垣間見れた気がした。ただ、戦争が平凡な日常を変えてしまうのは事実。それはひしひしと感じた。
すずは、ちょっとおっとりで天然でそんなに目立つタイプではない。だけど、絵を描くのが大好きでしっかり芯がある女性。嫁ぎ先の住所もわからないところとか、道に迷っちゃうところとか、こちらとしてもついつい応援したくなってしまう。周作は、そんなおっちょこちょいで、でもしっかり芯が通った彼女に惹かれたんだろう。幼馴染の哲が泊まりにきたときはドキっとした。何が何だかわからないまま北条家に嫁ぎ、でもずっと哲のことはどこかにあったんだろう。久々の哲との再会で彼への恋愛としての気持ちを断ち切ったシーンはちょっとせつなかったな。でも周作とより一層強い絆で結ばれていって嬉しかった。姪が亡くなったところは辛くて涙が止まらなかった。この映画が今までの戦争ものと違うと感じるのは、戦争が主体ではなく、すずという女性の日常を主体として描いている点だとおもう。その日常に忍び寄る戦争が、よりリアルに、自分の今の世界で起きたら…と想像できるから人々の胸に刺さるのだろう。戦争がなければ…本当にその一言に尽きると思う。戦争の悲惨さは伝わってくるのに暗くなりすぎず、生きることを楽しもうと思えた。
みぎてのうた
話だけ見ると、特に何が起きる訳でもない退屈なはずの前半だが何故か観入ってしまうのは、のん演じるすずさんの愛らしさが非常に大きかった。
「あまちゃん」でも思ったが彼女は演じるというより、そのキャラのまま画面の中で生きている感がある非常に稀な才能を持った女優さんだと思う。彼女が演じなければこの作品がこんなにも素晴らしく心に残るものにはならなかっただろう。
やがて、どこでどうしちょるかと思っていた戦争がすぐ目の前にやってきた。ほのぼのした絵の中に突然襲いかかる現実。それまでとはあまりにもギャップのあるスピードや音、残酷な破壊の世界にあの愛らしいすずさん達が晒される。
我慢して我慢して、あるものだけで生きていく。それがうちらの戦争ですけ。
こんなに失った、それでも表には出さずに耐えてきた。終戦の日、すずさんの感情が爆発したあのシーンにどれだけの思いが詰まっているか計り知れない。素晴らしいシーンだった。
そして、すでに感情の高まりがピークを迎えた我々に、壊滅した広島で物語のラストへ向かうあのエピソードが描かれる。コトリンゴの「みぎてのうた」と共に描かれた映画史に残るといっても過言ではない本当に心に残る演出だった。
片渕監督、こうの史代、のん、コトリンゴ
この組み合わせもまた一つの奇跡的なマッチングだったんだろうと思う本当に素晴らしい作品。
私はボーとした子供だったから心を捕まれました
小柄で若い女性すずが戦争と倹約・貧困という時代の中で「破綻」と闘っている姿が胸を打つ。「私はボーとした子供だった」という出だしで心を捕まれました。義姉の娘の晴美を死なせてしまう瞬間の破綻が、すずの小さな世界の崩壊が物凄く上手く描かれていると思う。ボーとした子供だったすずの崩壊。でも破綻はしない。支えあう中で再生していく。座敷わらしで女郎になった彼女に寄り添う夢が儚いが、そんな夢を見るボーとした少女が「破綻」と闘う本当に強い人間なんだと思いました。
この世界の片隅に
この世界の片隅に映画鑑賞し私自身戦争と言うと父方の祖父母から昔話の用に話しを聴いて、生きて来ました今年45歳のおっさんです、祖父母も戦争に巻き込まれたこと、祖父も目黒中隊大17部隊に所属してます。しかも新宿区四ッ谷に曾祖父と祖父母が住んで居ました父は昭和18年に四ッ谷で生まれたことからこの映画悲しいけど、戦争知らない世代で以下に戦火の中で一般人も普通に暮らしていたことの最中で戦争が悪化に成りつつも主人公すずさんが戦火の中でどんなに辛くて悲劇がお気てもと前向きな生き方が良い話しで、祖父母達の話しとリンクして観てました途中途中自然と涙が流れていました。2017年に成って横浜の映画祭典で特別賞を採ったのも納得する。因みに祖父98歳祖母96歳健在です。
誰かれなく見て!と言いたくなる映画。
公式ホームページに「すずさんからのありがとう」の映像がでて、「あんたの街で、会えますねエ」の声を聴いたらまた見たくなって、今日五回目の鑑賞でした。
6月15日現在19回見ました。
アニメなんですけどアニメを見たという気持ちになれない。良い映画を見たという気持ちがあります。
原作も買って読みました。原作のりんさんとすずさんや周作さんとのエピソードは大幅にカットされていますが、原作を読んでから見るとわかるシーンやせりふが散りばめられています。
私たちの父や母、あるいは祖母祖父、曾祖母曾祖父が確かに生きてきた時代、世界を描いています。そしてこの映画の世界の延長に今の自分たちの世界があり、その過去からの繋がりはまた、未来へもつながっていくものなのです。
淡い色調の「この世界」に、リアルに描かれた戦争がどんどん入ってきます。B29から落とされる爆弾がゆらゆら揺れながら落下していくところでぞっとしました。
どのシーンが面白い、どのシーンが悲しいといい難いのですが、見終わった後で毎回涙が流れ落ちています。幸せの涙なのか、悲しみの涙なのか、5回見ても判らない。
玉音放送から後、畑で慟哭してつぶやくセリフは原作の方が良かったと思う。変える必要はなかったと思います。
1番最後の径子さんのセリフの「こまいかねー」に幸せの響きを感じるのはウチだけか?
エンドクレジットは最後まで見てください。途中で帰ったらだめです。すずさん一家の幸せが見れます(でもその幸せがどうなっていくのかも私たちは知っている)。
由緒正しげなまがい物
NHKニュースで取り上げられ、しかもキネマ旬報の第1位ということで、期待感を持って見た。個人的には、良いと思われるところも無くは無かったものの、大部分で、がっかりとさせられた。
まずクライマックスであるはずの、すず号泣のシーンでの涙の絵が良くないと感じた。あの大きな玉が涙なの?液体感が無く、涙の感じがせずに、美しさも無かった。アニメは動画の質感がとても大切だと思うが、あそこではその仕上げレベルが低いと思われた。又、すずの言う言葉も陳腐で、その前の韓国旗の絵との繋がりも悪く、号泣の訳が理性的にも感情的にも十分につくりとして納得させられていない様に思え、ここの部分の原作からの変更は失敗していると自分には思えた。
第2に、登場人物の誰もが良いヒトであることを、とてもつまらないと思った。少しとろく、少女の様に無垢のまま妻となったすずのキャラクターは、監督の理想かもしれないが、アニメ界での宮崎及び庵野両監督の二面性有するヒロイン像からすると、少し、監督の計算?があざとくも感じられ、自分には魅力を感じられなかった。自分で「うちゃはぼーっとしとるもんで」と言ってしまう主人公を2017年の今、女性の蔑視にも思え、自分は見たくないのだろう。原作では習作は遊女リンと関係していて、すずはそれを知って苦しむらしいが、映画ではただただ良い旦那との設定で、視聴者の理解レベルを低く見ている様で、あまり気に入らない。第一面白くもなんとも無くなってしまっていて、勿体無い変更だと思われた。
第3に、リアリティが十分には無いと感じてしまった。確かに、戦争中といえども穏やかな時間や家族団欒や笑いもあっただろう。しかし、呉空襲や自宅に被害受けた後、もちろん笑顔の時間帯もあっただろう。でも、やはりその笑顔には多少の陰やどうなってしまうかという恐れや不安が滲み出ているのが、やはり真実に近かったのではないか?どうせやるなら、そこまでリアリティにこだわって欲しかったとの思いが強い。中途半端による嘘っぱちに思えるリアリティは、自分にはかえって良くないと思われた。
まあ、良いと思えたところも有るには有り、オープニングのコトリンゴさんによる「悲しくてやりきれない」は、その歌声だけで涙が出てしまうほどで、とても良かった。無機的美しさは感じられるまでではないが、戦艦大和の精密さには感心させられたし、何処よりも、対空の高角砲の煙幕が赤青黄と色々で、絵画のキャンバスをすずがイメージするところは、絵作り屋としての製作者の想いもこめられてるせいか、とても気持ちが動かされとても良いシーンに思われた。
そして全体としては、自分の居場所を見つける物語に、きちんとした監督なりの前の戦争に対する解釈が無い中途半端な状態のまあ、なってしまっている様に自分には思えた。というのは、あくまで戦争が表舞台に有るにも関わらず、原作のベースにある反戦的メッセージ性を唯そぎ落とすことにより、異なるメッセージ性、即ち、たとえ戦争になろうと、主婦たるものは、どんな環境でも細部にも工夫を怠らず、些細なところにも楽しみを見い出し、たとえ夫がいなくても家や家族をしっかりと守るべしというのがメインメッセージとも解釈可能に思えるグロテスクなものになっている様に思え、かなり嫌な気分になってしまった。声だけでかい様な反戦表明もひたすら被害者視点的なもの、どちらも自分は嫌いではある。とは言え、主舞台である戦争に対する知的考察が殆ど無い様に感じられるこの映画を、自分は正直とても嫌いであるし、多くの現在の一般的日本人に対して、罪深いものと感じている。
タイトルなし(ネタバレ)
軽い内容ではなかったけど、面白かった。確かにのんちゃんの声はあってた。話として、かなり取材されていて現実に近いという話を聞いていたから勉強になった。空襲警報があんなに多かったこと。時限爆弾があったこと。呉市の方が空襲が多かったこと。日本はあぁいった小さな日常を描く方が得意なんだろうな。最後の繋げ方も綺麗だった。旦那さんがどこで会って、毛むくじゃらの人は誰だったのか。
過度の期待を持ちすぎた…
レビューが高評価ばかりなのと、「キネ旬邦画部門1位」というのを聞いて、今更ながら観てきました。平成生まれの私にとって、戦争はリアリティを全く感じていませんでしたが、夜間であっても警報が鳴り、老若男女が防空壕に身を隠す等、当時の様子を具体的に知ることができ、それを乗り越えた当時の男女の精神力の凄みを感じました。ですが、この物語は、私にとってそれ以上でも以下でもありませんでした。主人公に共感できず、感動することも出来ませんでした。一番最後に主人公が夫に発する言葉、「ありがとう。この世界の片隅に、ウチを見つけてくれて。」が、取って付けたような言葉に聞こえました。伏線があってのその表現なら分かるのですが、なぜその言葉を選んだのかという根拠が私には分かりませんでした。
映画館で観れて良かった
どちらかというと明るい映画が観たい気分だったけれど、これは見逃してはいけない映画だろうなということで。結果、観れて良かった。
こんなにも普通の日常を描いた戦争映画って観たことが無い。戦争映画と呼ぶのも憚られるかな。日常の中にたまたま戦争があった。
とんでもなくツラい思いをしながらも人は笑うし、恋もするし、お腹もすく。空襲警報に飽きたりもする。「普通の日常」はいつも傍にあって、だけど「常に同じ」ではない。前半のほのぼのした雰囲気と後半の雰囲気のギャップに衝撃を受けつつ、それでも最後の一言までほっこりさせてくれて、終わった途端に涙がポロポロとこぼれた。悲しいとか辛いとか、そういうのとは違う涙だったと思う。
自信を持って「いい映画でした」と人に言える作品だった。
あったかもしれない過去、創ってはいけない未来
多層的な作品だ。一見、"多感な女性の視点で見た戦争"といった風だが、それだけではない仕掛けがある。叙事的な場面を繋げながら、時折「これは、すずの夢?」と思わせられる不安定な場面がある。それは、母親を亡くした少女が登場するラストまで、意識的に繰り返される。あたかも選択されなかった別の過去を意識させるように。いや、選択できたかもしれない過去と言ったほうが制作者の意にそうか。ともあれ、私たち戦争にリアリティを持てない世代にとっては、こういった表現が、"選択してはいけない未来"を強く意識させてくれる。力強い創造力を嬉しく思う。
戦時下の日常風景
第二次世界大戦下の広島・呉を舞台に、戦争によって人生を翻弄された、ある女性の視点で描かれたアニメ映画。
戦争を題材に扱ってはいますが、敵と対峙して戦うようなシーンは一切なし。そう、ここで描かれるのは戦時下の日常風景なのです。
暖かな光に包まれた前半部とは打って変わって、国内への攻撃が激化していく中盤以降は、何気ない日常から、空襲や原爆で大切なひとが突然失われる空虚感に侵されていく。そして、ヒロシマに原爆が投下。昭和天皇の玉音放送を聞き、独り慟哭するすずの姿に激しく心を揺さぶられました・・・
感じ方は人それぞれあるだろうけど、先ずは四の五の言わずに、観て感じて欲しいなと思う。そんな作品でした。
皆さんと違う視点で・・・・
皆さんが内容的なことは書かれているので、ちょっと違った視点で投稿します。
福岡県から県境を越えて佐賀市の映画館「SIEMA」にて視聴、上映館少なすぎです。シネコンに慣れたおっさんにはアウェー感ありありのディープな空間でした。去年からの宿題がやっと出来た感じ、カーナビで狭い路地を言われるままに運転しやっと到着。平日の月曜昼間なのに90席の半分くらいが埋まりました。年代は20代から50代が均等、男女比も半々という感じ。
すばらしい映画でした。昭和20年8月6日に向かって話が忠実に進められていて、日本人なら必ず知っている事実ですので飲み込まれます。あっという間の2時間(エンドロールも見ごたえあります)でした。
片淵監督は、夜行バスで広島・呉に通い資料を集める生活を6年間されたそうで、時間軸・風景は非常に正確です。山(灰ケ峰)の頂上にすえられている高射砲は戦艦大和と同じものが流用されており、大砲の音は実際に自衛隊に行って録音されたと。夜間の空襲は呉市街からの電源が途絶え、独自の発電機を用意していなかった(あのことを思い出しました)ため、サーチライトが使えず高射砲は役に立たなかったとのこと。木炭バスが登れなかった坂はここ。遊郭があった13丁目はここ。大和・武蔵が入港した日付はこの日。すずさんのうちは灰ケ峰の中腹で、市内に水を供給する給水所より高台にあって水汲みが必要であったこと。お義父さんが入院していた病院の階段は現在も残っていてこれです。闇市で残飯雑炊食べたのはここです。劇中の理髪店は当時の写真から起こし空襲前は実際に有ったこと。楠公飯・雑草の料理も実際に作り試食されています。楠公飯はそんなに不味くなかったとのこと、すべて事実です。
平成28年は、「君の名は。」、「シンゴジラ」と良作が多かったんですが、考えてみたらこれらは「虚」なんだなと、この作品は「実」を描いているんだと感じました。彗星が落ちたり、怪獣が襲ってきたりしなくて、戦争があって原爆は落とされたのですから・・・・。資料・文献・インタビューで作るのは大変だったろうとお察しします。
私の母は、終戦時10歳で、福岡県の大牟田市にいたのですが、戦争当時に、グラマンに機銃掃射され止っている貨車の下に隠れたとか、島原半島の向こう側(長崎)に大きな雲を見たとか、話を聞いてたので現実の厳しさをひしひし感じました。
出来れば、監督が希望されたカットなしの2時間30分の作品を、最新オーディオの映画館で、おっさんの泣き顔が見られなしように一番後ろの席で観てみたい。
★追記:原作者の「こうの史代」さんは、すずさんのお家周辺の聖地巡礼をご近所にご迷惑がかかるのでご自重くださいとのことです。
戦争のすぐ隣で生き営む人々の生身の姿
戦争をテーマに作品を作る時、その悲劇性や無残さ、残る哀しみと描くことがほとんどだ。一番に伝えたいメッセージがそれだからだ。しかしこの作品が違うのは、メッセージは共通していても、その表現方法が異なっている。一人の少女の日常と成長と半生を見つめ、彼女の生活のすぐ隣にある「戦争」、彼女の生活にふと挿し込まれてくる「戦争」、そして彼女の生活を侵食していく「戦争」の様子を見ている。なので物語の主体はヒロインすず自身であり、すずの日常こそが映画の本体だ。だからこそ、一人の少女の生活を戦争が脅かし、食い蝕まれていく様に感じ入るものが湧いてくる。
淡いタッチの優しい絵、作品全体に振り撒かれたユーモア、すずのふわふわとしたキャラクター。いずれも戦争映画には似つかわしくないものだが、その相反する要素がぶつかり合うことで、より描きたいことが鮮明になったような気がする。
映画の中で「生きる」ことを謳うことは難しくない。しかし「生き営む」様をきちっと捉え表現することは時に難しい。戦争という重大なテーマを扱えば尚更、生きることに傾きすぎて、生き営むことを描き忘れてしまいかねない。しかしこの作品は、戦争の中で、生きて生活を営む人々の「生身」を強く感じた。登場する一人一人に平等に命があり、分け隔てない死が訪れる。それを描くのに泣かせの演出が一切不要だったのも大いに納得。すべての登場人物が、地に足をつけて生き営んでいるのを感じられたのは実に見事なことだった。
その上で、一人の少女の成長と女性としての戸惑いと、そして人生の物語としての充実感も素晴らしかった。現在とは違う価値観を持っていた時代。まるで運命に流されるかのように揺蕩うままに生きるすずが、自分に降りかかる運命も宿命もすべて受け入れ肯定しながら、打たれ叩かれ喜び笑い、そして初めて自分の宿命を否定した時にまた一つ扉が開く。そんな一人の女性の人生の物語としても、良く描けた作品で本当に大切な作品になった。
是非、後世に残したい作品だ。
家族愛
すずは声ののんに丸かぶり。
まるで能年玲奈をみているようだ。
戦争前後の時代背景。
ぼんやりおっとりしたすずにある日縁談が持ち上がる。
広島から呉の周作の元に嫁いだすずの日常は一生懸命ながらも時間を見つけては得意な絵を描いていた。
周作の姉が娘を連れ出戻り、すずをイビるがすずのおっとりした天然キャラで笑いに変わる。
戦争が激しくなり物資も乏しい中、食事を工夫し家族を支えるすずの直向きな姿が良い。
飛行機、母艦…呉の高台からの眺めをすずがスケッチしていると憲兵に見つかり機密漏洩だとか難癖つけられ家族揃って説教された。
帰って来た周作にこの一件を話すと家族中バカ笑いするが1人だけ笑えないすずがいた。
すずの性格を家族みんなが受け入れているシーンでもある。
姪が死んですずは右手を失ったが生き延びたシーンからは流石に辛くせつない。
北條家に居づらくなっているすずは実家に戻ろうとするのだが…周作への気持ちは断ち切れない。
周作もまた家族の一員であるすずを失いたくなかった。
あたたかい北條家の愛に包まれすずは家族の絆を深めた。
戦後の広島…焼野原に孤児が…
周作とすずは孤児を家族に迎い入れた。
鑑賞後も涙が溢れて止まらない。
悲しい訳じゃない。
心にじんわり響く感動の涙…
よくわからないのだが自然と涙が溢れる。
家族ってこう言うことなんだなぁ。
コトリンゴさんの曲が沁み渡る。
良い映画でした。
婆ちゃんがすずの嫁入り前に言っていた「傘を持って来た…」とは?
泣けると思ってたが泣けなかった
いい意味で。
かわいそうな部分とか
経験したことのない恐ろしさ
トラウマになってしまうほどのことがありましたが、
すずの、明るいところとか
家族の思いやり、
あたたかさ
のほうが大きくて
気持ちがほっこりさせられて
見終わりました。
最後の一人取り残されてしまった子供さんを
優しく家族にしていたところとか
その後をエンディングにしていたところとか
なんだか、嬉しく思いました。
何度もみたいですね。
戦争映画でしたが、明るくなれる映画でした。
日々無駄にせず、頑張らなきゃなと
色々と思わせてもらえました。
ありがとうございました。
感想が下手ですいません。
DVDになったら日本語字幕になってますよーに!!
字幕になるアプリのやり方がわからなかったので…
_φ(・_・秀作 見逃してたよ。
先日キネマ旬報の2016年 年間ベストテンで一位にこの作品が出ていましたので視聴してみました。
戦時中の北条すずという絵をかくことが好きな女性の半生を描いた作品です。すずの半生は結婚も衣食住も満たされたものでなく、幸福とは程遠いものでありましたが、そんな中で彼女は力強く淡々と生きていきます。近しい人がなくなったり、自分の右手が空襲の爆風でなくなってしまいますが彼女は悲しみを乗り越えて力強く生きて行きます。現実の場面でも塾に行って勉強できたらとか、家が金持ちだったらとか現実ではないタラレバノ場面を想像し、そうでない自分はついていないとか、不幸とか思ってしまう事が多々あると思いますが、これはナンセンスな話で、与えられた状況でベストを尽くすのが人の素敵な生き方なんだと感じました。一生懸命生きるん事。
私も世界の片隅でチョットは抗って生きてみようと思います。
何が良かったねじゃ!
好きでもない人と一緒になり、知らない土地で暮らし、イビられ、食べるものもなく、着るものもままならない、空襲で家は壊れ、知り合いは死んでいき、自分の腕まで失ってしまう。
しかし、みんな○○で良かったねとポジティブに考え、明るく過ごす。
何が良かったねじゃ!
そう言いたくなるだろう。
しかし、そんな日常も当たり前になれば、当たり前なのである。
そんな当たり前を笑顔で過ごす。
現代において、何が不満だろうか?
今の日常の当たり前を ありがたく思い、笑顔で過ごしたいものですね。
タイトルなし(ネタバレ)
善良で慎ましい日本人像がうまく描かれています。だからこそ、すずが、日本人が他国民を暴力で搾取していることから目を背けていたことを認識した時の、何とも表現しがたいやり切れない気持ちが伝わってきました。
殆どの日本人は、戦争を望んでいたわけでも、自ら戦争をしたわけでもなくて、被害者でもあり、目の前にいる他人に直接暴力を振るったりもしないと思います。しかし、日本が他国を武力で攻撃したことは事実で、受け入れなければならないんでしょうね。
素晴らしい映画です。
全159件中、61~80件目を表示