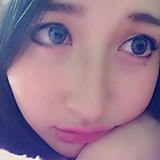Mommy マミーのレビュー・感想・評価
全116件中、81~100件目を表示
や〜、ハハムスコ系作品の中ではメガトン級の重さでしたは。コレ見ちゃ...
や〜、ハハムスコ系作品の中ではメガトン級の重さでしたは。コレ見ちゃうとBoyhoodなんてタダのいい話じゃん!!(号泣)という。 例のインスタ画角の件。その画角で撮られるシーンに共通する「意味」に気づくと、とあるシーンで、もう劇的に”してやられる”のです。。。って幕前のドキュメンタリーでほぼネタバレしちゃってますけどね。それでも、しばらく引きずりましたとも。くっそう、ドランめ・・・ うん、★4っていっても限りなく★5に近い★4かな・・・ぼちぼち全国拡大上映が決まっているらしいので、ぜひ。
つい本気になる。
きつい表現になってるのは承知のうえで言わせてもらいます。
教養ない母親と、その母親から生まれたADHDの息子。この親子の掛け合いは、幼稚な母親と、あまのじゃくな息子が繰り広げるもんだから、お互いに素直になれよって説教したくなるくらいジタバタ。でもそれも監督の狙いなのかもしれないと、まんまと吸い込まれてたと、終わったあとに感じました。
子育てに正解なんてないと思うし、頭が良くてイエスマンな息子だけがいい子なわけでもない。ADHDに限らず思春期とか反抗期の子どもをもつ家庭なら誰でも遭遇する問題。客観的に観せていたようで、実は主観的にも当てはまるのではないかと。
それにしても、母親の愛情とか、息子の愛着とか、奥が深すぎてついていけなかった。24歳独身の私にはまだまだ難しい問題だし、理想でしか語れないとつくづく思う。しかしグザヴィエ・ドラン監督は20代前半でこの作品を映像にして評価されたのだから、どえらい人だと思う。なんといっても映像と音楽に魅了されました。それだけでもお腹いっぱいになります。
切ない
作品価値と好き嫌いは別モノ…
映画的な評価はともかく…「アイアムサム」枠の映画はやはり個人的に好みでは無い…そんな感想が先に立ってしまった一本。
人間の自我に縛られた狭い視野を暗示するような四角な画面の使い方の妙を始め。
演出・演技・音楽全てが良し!
なんだけどなぁ…
ジャラジャラキーホルダーに象徴される、幼稚性の抜けない母親と。
病気(いや、性質か?)とはいえ、活火山のような息子の共依存的な発展も成長もない関係。
そこにやって来る、やはり「自分の物差しでしか世界を計れず、その何処とも距離感を掴めない(のに常識的な旦那子供アリ)」ビジターとの交流の描写。
なんだそう見ればこの作品、ジブンスキーたちの傷の舐め合いか!涙
映画的には、繰り返しになるけれどかなりの良作(しかも監督の才能と、未来の可能性の凄まじさ!)。
だけれど、個人的な感情でシンドイ作品。
若さ溢れる作品
まず、誰もがスクリーンの画角が気になるだろう。そんなことも気にならなくなってきた中盤にハッとさせられる。主人公がスケートボードで道路を滑っていると彼の手の動きと共にスクリーンが開けて行く。その時のBGMがoasisのWonderwallというのが、監督の若さ溢れる表現力を知らしめている。誰もが知っている曲をあのシーンで使うのは若さが成し得る技としか思えない。しかし、曲に負けない演出をしているのが素晴らしい。
他ににもSimpleplanのwelcome to my lifeなどBGMから若さが溢れ出ている。
映画史に刻む
まずは、何と言っても画面構成が綺麗だ。ドラマの中に埋め込まれた芸術性の高い構図は、そこまで意識させないちょうど良い塩梅で、ドラマを形作る重要な要素になっている。
そして、音楽。ドランと言えば選曲が上手くオシャレで有名だが、今作も間違いない、いや、今作こそが、その手腕を最も発揮されているのではないだろうか。
芸術性の高い構図にオシャレな音楽。これだけを聞けば、青臭くわかる人だけわかればいいなんて宣う、逆にクソダサい映画を予想してしまうが、そうならないのがドランが若き天才だといわれる所以だ。
才能あふれる俳優陣を牽引し、解釈が分かれる難しい問題を、親子の普遍の愛にまで引き上げている。ちゃんと物語が、主題が先にある。
スクエアという狭い画角の中で繰り広げられる、狭い世界の物語。スクエアからビスタになった瞬間は永遠に語り継がれるべきだと思う。
その昔、故伊丹十三監督がマルサの女を作る際に、画角をスタンダードにしたのを思い出した。
是非とも映画館で見てもらいたい。
ん〜っ⁈ どう? 別にが後から…
軽やかにスクリーンで遊ぶ
施設入りは、仕方ない。
母親にしてみれば、それが希望なのかもしれないが、鑑賞後の率直な感想。
複雑な心境で、けっこうリアルな気持ちで鑑賞したが、普通の施設で、加害者になっていまって、追い出されたのに、一緒に暮らすのはちょっと無理だろう。母親もセリフで言っていたが。
うまくやっていたかもしれないが、
隣人の協力にも限度があるし。
母親も働かなくてはならないし。
恐らく、かなりの自由が制限されるであろうけど、誰にも迷惑はかからない、命あってのことを考えると、S-14法案を発動させたのは、妥当な判断だと思う。
母親でさえ危なかったシーンもあったから。ましてや、自殺未遂も。賠償請求も脚下されるのだろう。
しかし、あの弁護士?何考えてんだか、あんなカラオケ店に連れて行くのはどうなんだろう。案の定の展開になりやすいことぐらい予想できるだろう。歌っている息子のチョイスした曲をウケないと指摘する前に、あんたのチョイスした店が間違いだろとツッコミ入れてしまった。
ストーリーにあまりにも観入ってしまったので、正方形からの画面の変化は、あまり気にならなかった。深く考えなかった。
出演者は、かなりのリアル熱演!!力作!!
不思議な画法
話題の若手天才監督の作品を、初めて観ることができた。内容としては面白かったけど、監督の素晴らしさはまだわからない。
ストーリーは文句なしに面白い。3人の登場人物の誰ひとり自分とは似ていないけど、全員に感情移入もできる。画のサイズが独特だったのだけれど、これはADHDを抱える息子Steveの(心身両方で)視界の狭さを表現していてのちに広がるんじゃないかなと思ったのだけれど、もしそれが監督の意図であったのなら、一人称で語らない外から見る物語なのには合わない気がした。彼の視界ならば、彼の視点で描いて欲しかった。あとパラレルワールドの意味はどこにあったのか。いまいち活きていた気がしなかった。
ただ前と全然違うという評判だったので過去作も観てからもう一度判断しよう。
グザビエと言えば
多動性なんとか障害の少年とその母親の「奮闘記」。こう言ってしまうとなんだか教育テレビっぽい臭いが漂うのだが、多くの日本の観客にとってはそう見えてしまったのではなかろうか。
ここに出てくる母親の、その人自身の未成熟な姿に、多感すぎる息子を持ったシングルマザーへの同情は沸かない。キーホルダーをじゃらじゃらと必要以上に繋げているその母親の子供じみた姿は、おそらくカナダや他の欧米の観客の目には奇異なものとして映るに違いない。
ともに成熟を拒むこの親子の理解者が吃音に悩む元教師というのも、だからとても自然なことなのだ。この三人は、自分自身が周囲への壁を作っていて、そのために苦しんでいる点で似たもの同士だ。
ところが日本の観客にとっては、さほどに変わったところがあるようには思われないのではないだろうか。なぜなら、「かわいい」小物やアクセサリーで生活を飾り付ける大人は、日本社会ではむしろ普通の存在で、この母親への眼差しはむしろ共感を伴うものになるはずだからだ。携帯電話、バッグ、果てはわが子まで、「かわいい」記号で埋め尽くされた光景を思い出してみれば分かる。
グザビエ・ドランの斬新な映像云々といった評には感心しない。スローモーションで満ち足りた心象を表すことなど、まさにTVドラマ的である。特に近年のフランス語圏において、新たなスター作家の不足に悩む映画界が大きな期待を寄せるのは分かる。
だが、グザビエと言えばロマン・デュリスなのだ。温かみのある表現の中に、個人の力ではどうにもならない現実を描き出したセドリック・クラピッシュの3部作なのだ。
じわじわ映画
ADHDの16才の息子と、そのファンキーな母親、その向かいに住むメ...
「愛」でしかない
辛く苦しい母子愛
グサヴィエ・ドランの才能
全116件中、81~100件目を表示