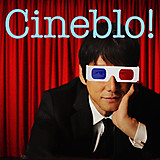この国の空のレビュー・感想・評価
全57件中、21~40件目を表示
切ない・・・
東京で疎開する母 娘を通して戦争の恐ろしさを感じました
そして ご飯が食べられることが何て幸せなことなのだと
さらに空腹がまずしさが 人間のやさしさまでも奪ってしまうということ感じさせられました
あの空襲警報に恐れおののき 振り回される様は観るをつらくさせます。
娘と妻子ある男性の恋に切なさを感じましたが
ラスト 主人公里子の気持ちがスクリーンに文字で現れるところが
とても惜しい気がしました
字で表すのでなく 映像でこのような気持ちを表すことはできなかったのか そして ラストの
私が一番きれいだった時のあの詩も心に響くのですが
これも詩ではなく映画全編で詩の力を借りず描いても良かったかなとも思いました
それを除いては 良かったと思います
二人のラブシーンもドキドキしました
私は好きな作品です
人間の欲望。
予備知識もなく観たので最初は誰だか分からなかったヒロインの母。
そうか工藤夕貴だったか!と気付いたその後、富田靖子演じる伯母
との姉妹小競り合いの妙味ときたら^^;このリアル感にしてやられる。
戦争末期とあり生活は日増しに苦しくなる。ヒロインはまだ19歳で
男性と付き合ったことがない。このまま死ぬのか…?と漠然とした
不安に苛まれた頃、隣家に単身銀行員の男性が越してくる。妻子が
いるとは知りながらどんどん惹かれていく彼への思慕、例え戦時下
であろうと、性欲も食欲も果てはしないことを貪欲に見つめた作品。
昭和時代の日活映画のような汗の質感が随所にエロチシズムを感じ
させ、二階堂と長谷川の大胆には描かれない逢瀬が余計に緊張度を
高めていく。明日をもしれない命が花開く瞬間を決して否定しない
母親の想いが伝わる工藤の演技、茨木のり子の詩に涙する場面など
総てにおいて完璧なところに最後のコメントだけが浮いてしまった。
戦争末期の恋愛物…?
この手の作品はあまり観ることがないので、邦画としてある意味勉強となった作品。設定が太平洋戦争末期という状況下だけであって、普通に不倫的な恋愛物でわ…?と思わずにはいられないのは、少々情緒に欠ける感想か。二階堂ふみがとにかく美しい。だんだんと、美しくなっていく。実は、トマトを食べるのを見つめるシーンが一番綺麗だと思う。
名脚本家=名演出家に非ず
名脚本家・荒井晴彦の18年振りの監督作。
終戦間近の東京、母と暮らす19歳の少女が、妻子を疎開させた隣家の男性の身の回りの世話をする内、“女”を目覚めさせていく。
キネマ旬報ベストテン第7位、映画芸術ベストテン第1位など、高く評価された名作なんだろうけど、う~ん、ちょっと自分には合わなかったかな…。
美術セットにカメラワーク、台詞回しに至るまで、小津映画を彷彿。
往年の名画を見ているようなタッチは悪くない。
直接的な戦争描写は描かず、庶民の姿を通した“反戦映画”である事もいい。
が、如何せん、淡々とし過ぎて、盛り上がりに欠ける。
オマージュを捧げたであろう小津作品はその代表的作品だが、やはり全然違う。
小津映画は静かに染み入るものばかりであった。
往年の邦画のような抑えた演出が仇となり、古臭さを感じてしまう。
台詞なども美しい日本語を念頭に置いたのだろうが、何と言うか、教科書的と言うか、生きた言葉を感じず、どうもぎこちない違和感が残ってしまった。
三人の女優は名演を披露する傍ら、長谷川博己のみ喋り方も含め現代的で浮いてしまっている。
言うまでもなく、二階堂ふみに魅せられる。
おそらくノーメイク、垢抜けない風貌から、男と関係を持ち、徐々に女の色を滲ませる艶かしさと演技力はもう名女優。
ただ、艶かしいというだけなので、「地獄でなぜ悪い」のようなムンムンとしたエロス、「私の男」のような小悪魔的魅力には乏しい。
ここまで昭和の女性が合うとは
「この国の空」を観て・・
久し振りに感動が満点の邦画しかも戦争映画を観た。何と言っても「私の男」で熱演した二階堂ふみの演技がすばらしい。70年前の東京の山の手の言葉や話し方を実によく再現し、19歳の娘役を完璧に演じている。終戦間近の庶民の暮らしを映画化したものに、最近は直木賞作家が原作の「小さいおうち」などがあるが、それとはまた違った味。父親を結核で亡くした母子家庭の母親と娘の些細ないざこざと親子の絆を映像にしている。またB-29の焼夷弾の爆撃の恐怖や、丙種で38歳の銀行員の召集されないかといった不安感を見事に戦争映画にしている。許されない隣人との恋で、男女が結ばれた後の主人公の入浴シーンはドキリとするものがある。長くなったが濡れ場も出来る二階堂ふみの演技とこの映画作品は日本人なら観るべきでしょう。
最後の「わたしが一番きれいだったとき」の詩が感動した。
古さが新鮮な作品
モノは言い様…
なんとも「チグハグ」な印象ばかりが残った1本。
いや「モノは言い様」と言ったら良いのか。
やりたいことも分かるし、言いたいことも分かるのだけれど。
しかしながら。
とにかくメインの男女2人がどうにも最後まで馴染まずブレーキに感じてしまう。
二階堂ふみ氏は雰囲気は抜群なのに。
「あれ?こんなに演技が酷かったかしら?」と思わずにはいられない「台詞回しの酷さ」。
本人は随分と役作りして挑んだらしいけれど…
口を開く度に学芸会レベルに下がり、違和感が気になり作品に集中出来ず。
お隣の市毛さんに至っては、棒読みはさておくとしても…
デカすぎるよ!丙種どころか満場一致で前線送りだよ!
当時の平均身長とか、少しだけでも考慮して欲しかった。
細かい所だけれども、やはり大事な点で作品に酔うことが出来ないのは勿体なかった…
今の時代に今の俳優さんで、1945前後の時代の映画を作るのは。
もう難しいのかなぁ…と思う作品。
ここにも戦争が終わることを望まない人物が
先日TV放映されていた「火垂るの墓」を観て、主人公が戦争の終結を望まなかったことについて考えた。
本作で二階堂ふみ演じる主人公の女性も、愛する隣家の男の妻子が疎開先から還ってくるために、終戦の日を喜びや解放感とは無縁の心境で迎えたのだった。
この作品の中では、戦地へ赴くことのない人々の心情が率直に語られており、終戦を自らの戦いの始まりととらえる二階堂の心情の吐露もこの延長線上にあると言える。
東京に残っている人々の語る言葉には、天皇への忠誠や軍人への敬意などよりも、日々の食料の心配と空襲への恐怖が先に立っている。空襲への恐怖は、自分の街が攻撃目標から外れ、遠くの街が炎に包まれるのを見ることで安心に変わるのである。
これはまるで景気の動向を心配し、台風や地震など災害への恐怖、しかも台風や地震が自分の住む場所に被害をもたらさなければ他所がどうなろうとひとまずは安心していられるという、現代の人々の心情とほとんど変わりないのである。
遠い戦地を慮って禁欲的な生活をしている者は皆無であり、人々は日々のささやかな喜びを求めている。それは、久方ぶりの甘いお菓子であり、田舎の河川敷での水浴びであり、密やかな恋である。
この作品では買い出しや防火活動など、戦時下の最も生活じみた部分を丹念に描いている。戦争映画と言えば、戦闘を題材にしてその勇ましさや凄惨さを伝えようとするものだった気がする。
小津安二郎の戦後の映画は、まさに戦後の家庭が描かれているが、そのパースペクティブにはあの戦争というものがはっきりと映っている。いままた、こうした市井の人々の生活を描く中から、戦争についての人々の思いを描く映画の潮流が始まったのだろうか。それとも戦後70年の一過性のものに終わるのだろうか。
頼むから、蛇足はやめて、監督さん
高井有一さんの、谷崎潤一郎賞を受賞した同名小説(1983年)の映画化。
戦争映画は、人類の記憶として重要だとは思うけれど
自分的にはすでに一生分観た気がするので食傷気味。
でも予告編を見て二階堂ふみさんが出るのを知り、
ああそれなら観てみようか、と思った次第。
「ドクトル・ジバゴ」や「小さいお家」などと同様、
戦争は背景としては重要だが、
軸はあくまで人の――ここでは二階堂さん演ずる里子の――生き方にある。
そして、
茨木のり子さんの詩「私がいちばんきれいだったとき」が
見事に重なる。
少女から女になりつつあるとき、
戦争も末期で、東京はすでに大空襲に見舞われ、
若い成人男性はほとんど応召して周囲にいない、という状況で、
妻子が疎開中の隣家の38歳の男性に心を惹かれてゆく・・・
その情念が、丹念に描かれてゆく。
原節子さんもかくやという
二階堂さんの古風な演技が素晴らしい。
最後の最後(エンドロールの直前)、
痛恨の蛇足がなければ、満点だったのに。
頼むから、世の中の監督さんたち(あるいは製作の方々)、
原作にない余計な説明を付け足して
作品を台無しにするのは、やめてくれ。
市井の人々
悲惨をみせずに写しだす、戦争の悲しさ。
先日観た「日本のいちばん長い日」
と見事にシンメトリーになっていた。
皇室や政治家や軍人が、
混乱の中で戦争を終わらせる話に対して、
こちらは
なかなか終わらない戦争に翻弄される、
平凡な少女の話。
太平洋戦争末期の、東京杉並。
毎日のように空襲警報が鳴り響き、
B29の焼夷弾に怯え、
食料給付も少なくなる。
原子爆弾や本土決戦の恐怖から、
死への覚悟を受け入れる。
そんな絶望的な焦燥感のなかで生きた
母娘のスライスオブライフが、
淡々と描かれていく。
食事のシーンが多いのも、
彼女たちの生命力を、
浮彫りにしている。
悲惨な現場をみせなくても、
戦争の悲しさが、
親子の毎日を通して、
しんしんと伝わってきた。
主人公の里子は、
とにかく戦争に苛ついている。
娯楽なんて何もない。
自分がいちばんきれいな時だろう
結婚適齢期に、
男たちは戦場に行ってしまい、
恋をしたこともない。
そんな里子が
虚弱体質で兵役を免れた
妻子ある男に惹かれていく。
欲望を満たすことで、
不安から逃れようとする二人が、
あまりにも切なすぎる。
全体に静かなトーンが、
映画を上質なものに仕立て上げている。
二階堂ふみさんと長谷川博己さんの台詞回しが、
とにかく美しい。
抑えられながらも情緒を感じる、
会話の内容と声、表情、心情などの、
繊細な描写がうまい。
まるで
小津作品のオマージュのような佇まいに、
思わず息を飲んでしまった。
工藤夕貴さんの母親も、良かった。
自分の過去を娘にさらけ出すシーンは、
女になった娘への愛情にあふれていた。
エンドロールで、
女性詩人・茨木のり子さんの
「わたしが一番きれいだったとき」
という詩の朗読には、
不覚にもぐっときてしまった。
安全保障関連法案を
成立させようとしている時代に、
何も不自由のない現代の女子を見ていると、
戦争の不幸を二度と繰り返さぬようにと、
祈るばかりだ。
日本の黒歴史
綺麗な映画でした
戦争映画とは全く異なる映画
はじめに感じたのは劇中の人々の言葉遣いがとても美しいな、ということです。
男女ともに一つ一つの言葉が丁寧というか堅実?というかで、台詞にひきこまれました。
あとで原作を読んだら、出てくる台詞はほとんど原作のままです。
ただ、現代人にとっては言葉がかなりかしこまっているので演技を意識してしまうというか、違和感を大きく感じる方もいると思いました。
内容は、ありきたりになってしまいますが、二階堂ふみさん演じる里子が女になっていく姿は圧巻の演技だと思います。
戦時中という特殊な環境ゆえか、普通の19歳ではなかなか得ることのできないであろう里子の、神秘的な雰囲気や滲み出てくるような美しさを、とても魅力的に演じられています。
戦時中の話だからこそ、さまざまな面の美しさにとても目がいきます。
この映画には、内容に関係なく、とにかく美しいという印象を持ちました。
ドキドキしました
全57件中、21~40件目を表示