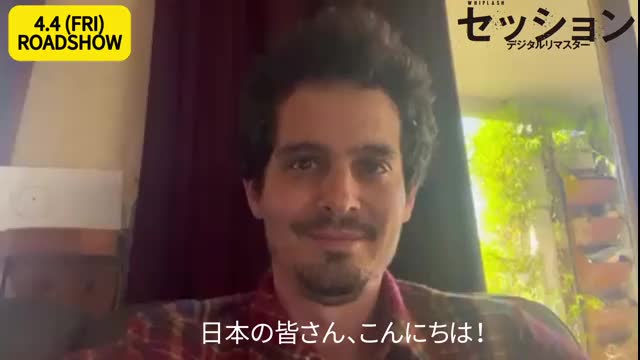「音の戦争」セッション ストレンジラヴさんの映画レビュー(感想・評価)
音の戦争
「目玉をくり抜いてやる」
音楽院を舞台にしたスパルタ教師とドラマー志望の学生による音の戦争。ミュージカルを製作したかったデイミアン・チャゼルが資金集めとアピールのために製作したのが本作にあたる(ご存知の通り、その後チャゼル監督のミュージカル構想はは「ラ・ラ・ランド」として結実する)。
やるじゃねえかチャゼル、というかどうした?こんなに素晴らしい作品を製作したのにその後は一体何だ?「ラ・ラ・ランド」はまあまあ面白かったが「バビロン」はまるで離乳食だ。
魂を揺さぶられた。また私事になるが、僕は奇しくもアンドリュー(演:マイルズ・テラー)とフレッチャー(演:J.K.シモンズ)両方の立場を自分の中で経験した。そしておこがましいことを言えばチャーリー・パーカーも。
僕は10歳の頃同級生からいじめにあった。中学は受験したので中高一貫校に進んだが、小学校時代の同級生を見返したい一心で(「自分はあいつらとは違う」という差別意識もあった)勉強も部活も取り組むようになった。ここまでは聞こえが良いが段々と方向がおかしくなり、気付けば「叩く側」と「叩かれる側」の二面が自分の中に。謂わば「セルフパワハラ」である。「猿でも解ける問題で何故満点が取れないのか?お前の存在は人類第8の大罪だ」といったことを並べたて、ピーク時には真冬に窓全開でシャツ一枚で勉強、試験の成績が思わしくないとズボンのベルトで自分のことを殴りつけるといった始末だった。しかしそうこうしているうちに今度はメンタルがおかしくなり、17歳の頃学校内の試験で失敗したことで完全にグレた。ライブ中にシンバルを投げつけられたチャーリー・パーカーのように、周囲から笑われて完全にやる気をなくした。「お前は無能だ」と吐き棄てて自分を見限ったのである。残念ながら現在でも自己嫌悪の感情はある。
気持ち、僕はフレッチャー寄りだ。僕からすれば「努力」「立派」というワードは人を破滅させる危険なワードだ。英語で言うと"Good Job"といったニュアンスだろうか。だが同時に「一線というものがあるでしょう」とも思う。17歳の自分は、やってもやっても認められない虚しさにやってられなくなって全てを投げた。数年前、電車が遅延した際に「社内会議に遅れる」という理由で勝手に線路を歩き出した会社員が社会問題となった。やはり行き過ぎるとこういうことが起こるし、ここまでくると容認も看過もできない。
でもね、「努力」は結局偽物でしかなく、本物にはなり得ないと個人的には感じる。ここまで来るともう価値観の問題で、要は「天然だろうが養殖だろうがウナギは美味しい」と考えるか、「いや、やっぱりウナギは天然に限る」と考えるかの問題である。別に世の中妥協しても死にやしない、というか、チャーリー・パーカー自体が結局ドラッグに溺れて寿命を縮めたことを考えると、陽キャとして生きたければそこそこのラインで妥協することが必須だ。だから皆「努力が大事」などと不揃いな薄っぺらいことを言う。僕は陽キャにはなれない、故に「努力」とは生涯相容れない。となれば「イカれる」しかなさそうだ。伝えるべきは、狂気。