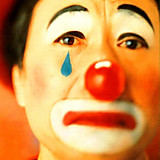蜩ノ記のレビュー・感想・評価
全78件中、41~60件目を表示
クロサワの遺伝子。
小泉堯史監督の新作は腰の落ち着いた時代劇であった。
不義密通のかどで10年後の切腹を命じられたひとりの武士。彼の見張り役として、彼が幽閉された土地に赴く若い侍。
若い侍は武士の家族と接するうちに、また不義密通のからくりを知るに及んで、彼に肩入れするようになる。
他の監督も同じことをしていると思うのだが、人物の配置であるとか、正座する人物の全身を映すショットなどを見ると、黒澤明とそっくりだなと思う。
小泉堯史が黒澤明の弟子筋にあたる、というこちらの先入観も手伝ってのことだと思うが、観ているときは、なんとなく懐かしさをおぼえる。黒澤明の映画は「影武者」以降しかリアルタイムで観ていないが、それでも、本作には黒澤明の遺伝子がみてとれる。
役所広司のたたずまいはただ事ではなく、映画俳優としての矜恃を見た気がした。
男の映画ですね
綺麗だけど。
これでいいのか、と眉間に一本の皺が寄った気分
映像の美しさ、岡田や役所の所作の清々しさ、それはもういい映画です、と言いたいです。
そして、寺島しのぶがいい。「(その人が)この風景と同じ風景をどこかでみているのかと思うだけで心が和むものなのです。それだけで心の支えとなるものです」的な台詞をいう。
ありきたりの台詞が胸に響いてくる。これには参った。
・・・だけど、もうこの設定にどうも納得がいかなくて。
罪人なのに家譜編纂の職を請け負えるものか?、その疑問がずっと引っかかったままで、どうも入り込めない。
編纂をさせるのならば、城内でさせればよかったのでは?
そこになぜ生一本の岡田をさしむけるのか?
まるで頼朝と文覚を野放図にした、平家の手落ちを思い出した。
先日の『石榴坂の仇討』もそうなのだが、現代での常識・モラルを、あの時代に押し付けてくるのもどうも馴染めない。
で、悲しみを秘めた物語なのに、ほぼ悪人が出てこない。ヒール役の家老でさえ実は滅私の人に思えた。だから憎むべき相手がいない。僕の中でその悲しみを慰める発露の先がないのだ。
もしこれが今の時代劇に求められているものだとしたら、僕は間違いだと思う。
藤沢周平的なものを好む人が多いのは知っている。でも僕は池波正太郎的な人間の泥臭さのほうが好きなのだ。
今読みかけの原作も、たぶんもう開くことはないだろう。
美しい映画だった
清らかな水のような
夏の吹き抜ける風のようでした
理不尽なことが多く、悔し涙がでてきました。
その中、主人公や家族は、静かに穏やかにお互いを思いやりながら凛として丁寧に生活しています。
理想の家族です。
丁寧に生きていかなくては、と思わせてくれる作品でした。
日記に映る武士の志
10年後の切腹の日までに藩の歴史をまとめた「家譜」の完成を命じられた戸田秋谷の元に、監視役の若い藩士・檀野庄三郎がやってきます。
気持ちいい映像、ストーリーがとても分かりやすかったです。淡々とした印象でしたが、少し時間が経ってから題名が腑に落ちた気がしました。観て良かったと思いました。
編纂の日々を綴った日記「蜩ノ記」。それは秋谷の志を映しているのでしょう。
事実は曲げず、事柄と言葉を慎重に選び、分かりやすく簡潔に。そして丁寧に読み解けば、言外の真実に迫れるように。
まったく、そんな作品だったなぁと感心しました。
向き合う自然の美しさもさることながら、衣装や道具が出演者の所作と調和してとても美しかったです。
秋谷の襟元が少し乱れていたりして、しっかり働き"生きている"感じが微笑ましく、切なくなりました。
背筋が伸びます!
静かな映画
静かな映画
静かな壮絶
武士ならば弱いものを守りなさい
佇まいの良い作品だなぁ~。監督は小泉堯史氏である。
この人は山本周五郎原作、黒澤明監督の遺稿「雨あがる」を監督した。
僕は原作を読み終えた後、しばらく涙が止まらなかった。
ありふれた「市井の人たち」を映画作品として撮る。
しかし、ありふれたひとたちであっても、人の事を思いやる、弱い人の心に寄り添う。そんな生き方が出来る人は映画を撮る価値がある。
本作を観終わった後、小泉監督が表現したかった事が、自分の腹の奥底の方に、ストンと落ちてゆく。
後味が清々しく、美しい作品である。
どこかの国のエラい人が「美しいニッポン」と言った。
「ゲンパツ」とかいう「ホーシャノー」を垂れ流す「巨大湯沸かし器」は
「コントロールできています」と言いきった。
こういう人たちはきっと、「人の事を思いやる、弱い人の心に寄り添う」よりも「自分の出世を思いやる、そのためには、より強い人に寄り添う」のだろう。
そういう人たちに、この作品を見せてあげたいと思う。
まともな人間なら、きっと自分の生き様に「恥」を感じるだろう。
この映画の主人公のように三年先と言わず、今すぐ
「腹を召されよ!!!」
と厳に申し上げたい。
本作の主人公、戸田秋谷(とだしゅうこく・役所広司)は不祥事を起こし、三年後に切腹する運命を受け入れている。
今は自宅蟄居の身だ。その見張り役として、藩から命を受けたのが岡田准一演じる、壇野庄三郎である。壇野は、戸田の逃亡など、不審な行動がないかを常に監視する。しかし、壇野がそこで見たのは、同じ武士として、戸田が極めて尊敬すべき人物であったことだ。
彼は一つの疑問を抱くのである。
本当にこの戸田が「藩主の側室と一夜を共にした」という、驚嘆すべき大罪を犯した人物なのか?
やがて壇野庄三郎は、藩の根幹を揺るがすような事実を知るのだが………
この作品で特筆すべきは、何よりも美しい絵心だ。端正でしっとりとしている。しかし、決して浮つかず、がっしりとした「絵」をスクリーン上に投影させている。小泉監督は、黒澤明監督によって鍛え上げられた、いわゆる「黒澤組」出身である。本作の絵の美しさは、その黒澤作品を上回るのではないか? とさえ思えるほどだ。
かつて黒澤監督は映画の事を「シャシン」と呼んだ。
映像を、キャメラのレンズを通してフィルムに焼き付けること。その、なんとも手作業の感覚が、大切に大切に、小泉監督に受け継がれている感じがする。
スクリーンに映る、日本の風景。日本の家並み。そしてなにより、質素ではあるが、毎日の暮らしを丁寧に、丁寧に生きていた、江戸時代の「ニッポン人」そして「武士」の姿が印象的だ。
私は決して武士の生き方や、所作を美化しようとか、誉め称えようなどとは、これっぽっちも思わない。
「仏作って魂入れず」と言うたとえがある。
いくら武士として武術が優れようが、その所作が寸分なく完璧であろうが、関係ない。
自分より身分の低いもの、立場的に弱い者。そういった人たちに罪を被せたり、辛い暮らしを負担させたりする者は、すでに武士のココロを失っている。
「美しいニッポン」とか言っているエラい人や、どこかの大都会に「世界の運動会」を呼んだぞ!!と浮かれている人々よ。
武士ならば「弱いものを守ってこそ武士」である事をお忘れなく。
日本人とはかくあるべき
全編静かに流れる如く物語が進行してゆく
日本人の生き様というのがよく表現できていると思います
なかなか現代の日本人にはわかりにくい事柄ではあると思う
こういう映画を世界に発信していく必要が、あるかもしれませんね
全78件中、41~60件目を表示