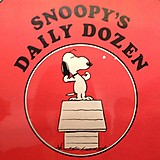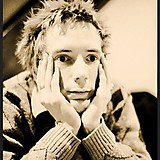かぐや姫の物語のレビュー・感想・評価
全84件中、61~80件目を表示
アメリカよ、これがアニメだ
とか、言いたくなります。
緻密な描写でもなく、リアリティ溢れるCGでもなく、でもため息が出ました。
背景や構図にうっとり。動きやカメラワークに心奪われました。
ストーリーは原作を大きく弄らずにあれで良かったと思います。
押しです!
罰はループ
失踪(疾走)後の炭焼き親父とのやりとりは、実際に体験しないと知り得ない情報を含んでいるのに夢だった。ってことは、同じような人生を何度も繰り返している可能性がある。
愛を得て、無念のうちに失う苦痛を何度も味わわされているのだ。
温もりの記憶
※いつも以上の長文注意です。
僕は昔から文系の授業は好きだったが、
中学の頃に習った古文は、僕からすればシステマチックに
解読するだけの暗号文みたいなもので、ずいぶんと退屈に
感じていたものだった。
『竹取物語』に関してもしかり。せいぜい『地位や名声に
目が眩むと駄目になりますよ』くらいのメッセージしか
受け取れない寓話としか思っていなかった。
ところが本作はどうだ。
導入部は原作と全く同じだし、話の大筋も変わっていない。
なのに、その合間合間を補完するだけで、あんなに味気なく
思えた物語が、ここまで心に迫る物語になるなんて。
* * *
水墨画のような柔らかなタッチで生き生きと描かれる
キャラクター・生き物・風景の数々。画は写実的とは
言い難いのに、どの人物も下手な実写映画以上に
人間臭くて身近な人々に感じられる。
社会的な幸せと娘の幸せを混合して少しずつ歪んでゆく父、
夫に付き従いながらも真に娘の幸せを理解していた母、
かぐや姫を“物”としてしか見られない、
欲深くて情けない男たち、
薙刀を置いて唄を歌ったまんまる侍女。
そしてもちろん、かぐや姫=“竹の子”。
彼女は昔の幸せだった頃を取り戻したかっただけだった。
自然の中を駆け巡り、父や母や友達と
毎日を笑って過ごしたいだけだった。
時代が異なっても、人が何を幸せと思うかに
大きな違いはないのかもしれない。
優しかった父母、不可思議な生き物、きれいな草花 、
共に野を駆けた友人、淡い恋心の記憶。
ラストシーン。
羽衣を着せられてそれら全てを忘れることが、
どうしてこんなにも悲しいのだろう?
僕らは『忘れる』ということを
どうして悲しいと感じるのだろう?
* * *
ここから先は以前『オブリビオン』のレビューで
書いた内容と多少似通ってしまうのだけれど……
『あなたが何を大切と思うか』という質問は
『あなたは何を憶えているか』という質問と
ほぼイコールだと思う。
記憶、記憶、記憶。
古い記憶を漁ってみる。
あなたはこれまでに、
何を醜いと感じ、何を美しいと感じたか。
何に喜びを感じ、何に罪悪感を抱いたか。
何を幸せと感じ、何を不幸せと感じたか。
それらの記憶全てが今のあなたを形作る。
だから、『幸福とは何か』なんて人それぞれ。
幸せに生きたいのなら、
幸せだった頃の記憶を辿って生きればいい。
誰かの押しつける幸せなんかには目もくれず、
自分の幸せだった記憶に従えばいい。
* * *
それだけでいいはず。
それだけでいいはずなのに。
“竹の子”と同じく、
身動きの取れなくなっている自分がいる。
親の期待や、親しい人々の想いや、
社会で生きていく為の決まり事や、
不条理なほどに容赦のない突然の災難や、
そんなこんなの色々なものに縛られて、
いつのまにか身動きが取れなくなっている。
なんだこれは?
重くて動きづらいあの十二単(じゅうにひとえ)
のようじゃないか。いつの間にこんなものを
着せられているんだろう、僕らは?
走っても走ってもしがらみから逃れることはできない。
あなたはこう感じたことはないだろうか。
世の中はいつから、こんなに悲しくて窮屈な場所になってしまったのだろう、と。
記憶の中の世界は、こんなに美しくて自由な場所なのに。
歳を取れば取るほどに、なぜだかこの世界は
擦り切れ色褪せ薄れていくかのようだ。そんな想いは、
かぐや姫の時代の人々から変わらないのだろうか。
* * *
“竹の子”の背負った罪と罰とは何だったのか考えてみる。
予告編から僕は、彼女が何かの罰で
月から地球に堕とされたのかと予想していたが、
実際は地球に降り立ったのは彼女自身の意思で、
月の人々はむしろ幸福になれるのならそれでも
構わないと考えていた様子だった。
思うに、ここでの“罪”とは、誰かから向けられたもの
ではなく、彼女自身の罪悪感を指していたのではないか。
終盤の彼女は「私の身勝手な振る舞いのせいで
皆が不幸になる」という想いに苛まれていた。
彼女にとっては自分の心に従うことが罪だったのだ。
ならばそれに対して自分で下せる罰とは? 自分の心を殺すことだ。
記憶を失って去ることは、周囲の人にとって彼女の死に等しい。
「私はここから逃げ出したいと月に願ってしまった。
すぐに後悔し、連れて帰らないでくれと願ったが、
彼らは聞き入れてくれなかった」
この言葉の意味が今は掴める気がする。
この世から抜け出したいと願うことは死を願うこと。
そして一度死んでしまえば、
いくら後悔しても取り返しは効かない。
罪悪感、そして自罰の意識。
彼女は自分で自分を裁いて、空へ消えてしまった。
* * *
救いがあるとすれば、だ。
死者が後悔するかどうかは分からないが、
“竹の子”には後悔する時間があった。
もう一度、自分の幸福を省みる時間が。
必死にこの場所に残らなければ幸福を再び紡ぐことは
できないし、自分がここに残ることが周囲の人間に
とっての幸福であるということに彼女は気付いたはず。
世の悲しみや怒りにがんじがらめにされながら、
それでも人は生きている。
それはきっと、幸せだった頃の記憶が
こう諭してくるからじゃないだろうか。
ここに踏み留まれ。冬を耐えればいつか春は巡ってくる。
生きるに値すると思えるものが、
この世にはまだ残っているはずじゃないか。
* * *
今一度、古い記憶を漁ってみる。
僕はこれまで何を憶えて生きてきただろう。
あの人、あの生き物、あの音、あの匂い、あの光景。
僕らが憶えている事にはきっと、僕ら自身にとって
憶えるに値するだけの価値があったのだ。
その記憶を大事にしながら生きれば、
世の中はもう少しだけ温かく色づいて見えるかもしれない。
〈2013.11.23鑑賞〉
人として生きる、ということ
この映画が持つ魅力の強さを、どんなに多くの言葉で語ったところで、伝えきれないものがあります。
この映画に触れることで初めて、わかるものがあるとしか言い表せないものが、この映画にあるように思うのです。
かぐや姫は月で居た頃に、命あふれる地球に想いを馳せたことが罪となり、罰として人として生きる事を強要されます。
月は病気、死、喜怒哀楽さえない、安定した世界。無の世界ともいえると思います。
しかし、そんな月の世界から見れば、地球の世界は不安定で穢れた世界だと認識されている。かぐや姫は地球を見てみたいと思った、知りたいと思った。地球で人として生きる事はかぐや姫にとっては罰ではなく願ったり叶ったりの出来事だったんだと思います。
命あふれる地球で人として豊かに育つかぐや姫。土に触れ、虫に触れ、動物に触れ、風を感じ、食べ物の旨さを感じ、人として生きる喜びを感じていく。
しかし、大人になるにつれ、自由は奪われ、思いのままに生きる事は閉ざされます。
かぐや姫はそれに耐えながら生きます。
自分を殺してまで。
それは自分を育ててくれた、翁と媼への感情があるからです。翁はかぐや姫の幸せを願ってそうするのですが、かぐや姫にとってはそれは苦痛でしかない。しかし、翁が自分を想う気持ちも痛いほど、かぐや姫はわかっている。
そんな翁の気持ちを尊重しながらも、誰かの物として、生きる事へは拒絶しつづけます。
それでは本当に死んでいるのと変わりないとかぐや姫は思ったのでしょう。
ただ、そんな姫の健気な生への渇望さえ、自分自身を苦しませる事になってしまう。
そして、とうとうかぐや姫は、地球に失望を覚える。人として生きる事を嫌だと思ってしまう。それが引き金となりかぐや姫の罪は許され、月からの迎えがくる事になる。
しかし、かぐや姫はそこからまた、ここで生きたいと願うのです。地球で生きていたいと。まだ、自分は人として生きたりてないと。
しかし、そんな想いも虚しく月から迎えが来て、人として生きた記憶をなくし月へ帰っていきます。
ただ記憶を失っても、かぐや姫の中にはちゃんと地球での経験がまだ息づいてる。生きた証が残ってるんじゃないのか。そんなふうに最後は感じました。
地球で人として生きた事はかぐや姫にとって、よかったのか悪かったのか、考えを巡らせたところで、無意味なのはわかりますが考えられずにはいられません。
そして、そんな疑問は自分へと返ってくるのです。
いま人として生きている自分へと。
おまえは今、人として生きていて、どうなんだと。
かぐや姫は人として生きる喜びと苦難を体現し、それを全部丸ごと肯定してみせた、肯定してくれた、素晴らしいヒロインでした。
わからないけど泣けた
理由はわかんないけどかぐや姫の赤ちゃんの頃の映像で涙でた。
多分、地井武男が力いっぱい姫ーおいでー姫ーって言ってるところが来たんだと思う。地井さんこれ見たかっただろうなあ、そう思ってなんだか泣けたんだと思う。多分。時間かけすぎた高畑さんは地井さんに謝った方がいいのでは…
でも物語が進むに連れ別にかぐや姫に感情移入できるわけではなかった。やっぱりかぐや姫より翁と媼に感情移入してしまう。子供いないしそもそも結婚してないし20代だけど。
私を物のように扱うなんて!私だって人間よ!誰のものにもならないわ!私は美人で頭良くて器用で完璧だけど誰のものでもないわ!私は私!…って、10代アイドルが中2病発症したような言動は痛々しいだけです。
あと度々つっこみどころあって笑った
おいおい不倫かよまじかよ、とか
月の迎えの音楽隊空気読めなさすぎだろその陽気な音楽聴いただけで笑えてくるわ、とか
帝あご長すぎだろどこの幸せの国の国王だよ、とか
地球は感情あるけど月は感情とかないから平穏でいいよねーとかどこのインキュベーターだよ、とか
まーわれまーわれのあの曲使いまわしすぎだろ飽きだよゲド戦記じゃないんだからさ、とか
ツボに顔突っ込んで死ぬとこおもいこれ笑えってことだよな多分…超すべってるけど、とか
帝に抱かれたとき無表情でスーンてどっかいくのシュールすぎるだろ、とか
媼の乳首の生々しさなんかやだ、とか、いろいろ。
罪とも罰ってなんぞや、どうせキャッチーなコピーつけたかっただけだろうからそれについての言及はなしだろと思ったら、すこーしありました。
姫の犯した罪は地球に憧れることでしょ多分
じゃあ送り込んでやるよ、が罰ですよ、きっと。
地球を見て黄昏てたあのおっさんのエピソードみてみたかったな。まあそれはそれで蛇足になりそうな予感。
富士山のくだりを期待したが何もなしが残念。まあいいけど。
でも、大都会の中にある公園で「あー自然て癒されるーまじロハスー」とか言ってる人間たちに違和感を覚える私にとって、こんなの偽物よー!と激怒するかぐや姫の気持ちはとてもよくわかる。
うーん、あと、
このままでは物語が進まないだろう
とか、現実的に苦しくなってきたなとか、そういうエピソードは全て夢オチで済ませてます。その先描けなくなっちゃったから夢オチにしちゃえーという製作者の声が聞こえてきそうです
そんなもんかな
これで50億か…映画の世界はわしにはよくわからん、わからんほうがいい。
不思議な感じ
古典文学を膨らませた内容なのだが、現代に通じる問題など、色々考えさせられる。親が子供に過度に期待したり、本当の幸せとは何かなど。帝の求婚も断り、地球の生活に絶望したかぐや姫は、月に帰ることを願ってしまう。幼い頃の捨丸との再開も果たし、記憶も失い、月に帰っていく。そのときの音楽が素晴らしかった。捨丸は結婚して子供もいるのに、たけのこ(かぐや姫)と一緒に逃げようとしたのは如何に・・・。
リアルな「いのち」
試写会で観てずいぶん日がたちましたが、
観た時の感触がいっこうに薄れません。
とりつかれたように、いろいろ考えずにはいられませんでした。
この映画そこここで、
「極上の映像の昔話」「話は竹取そのもの。絵が綺麗。」
みたいな称えられ方もされてます。
確かに、ため息がでそうに美しい画面であることが大きな魅力ですが、それだけではこの映画の衝撃十分には語りつくせてないと思ってしまいます。
だってこれほどまでに丁寧に丁寧に
いのちが描かれてるんだから。
ざっくりいうと、
あのわらべうたは「罪と罰」であり、
それがこの映画のすべてなんですよね?
”わらべうた”は、
謎解きができてしまいそうなぐらいに綿密にかつ極限まで無駄な説明描写なしに、物語に織り込まれていて、
リアルな地球を浮き彫りにします。
生きることを鋭く描きだしています。
そして、
「地球に生れ落ちて、とりむしけものくさきはなひとのなさけ…つまり苦しみ悲しみ醜さの中で生きる」これが罰であるならば、
この物語はいよいよただのおとぎ話ではなくて、
今痛みを感じながらこのいのちを生きている、私たちの物語でもあるのかな、と思われてなりません。
最後に…
エンディングの’いのちの記憶’から
「必ずまた会える 懐かしい場所で」
とあるけれど、
姫の出会ったひと(地球で生まれ死に生まれ死にゆくひとたち)と姫とは、もう二度と絶対に会えないんでは?
この歌詞は虚しい慰めなのかな?
と思ってました。
でも、
天人ってそもそも何者なんだろう?と調べてみたら、私はちょっと勘違いをしてたとわかりました。
きっとまた会えるはず。
P.S.私事ですが石作皇子役上川隆也さんが好きで、舞台などいろんなところで上川さんをみてきました。が、こういった形の出演でここまで彼の魅力がひきだされて、作品の確かな一角になるとは!……という驚きもありました。キャストの魅力の引き出し方も、この映画の魅力の一つだと感じました。
美しく静かにどっしり
見終わって余韻の凄さに動揺。最後、2001年宇宙の旅を思い出した。
ジブリ映画でもほとんど宮崎駿監督作品しか見ていなかったが、この作品を見たら、根底にあるのは同じメッセージだと感じた
。引退会見で宮崎駿監督が言ってた、それでもこの世は生きるに値する、という信念を高畑勲監督も共有しているんだなと思った。
と思っていたら、プログラムを読んだらやはりそのように書いてありますね。
この視点や人生観は極めて日本的というか東洋的なのではないかと思うが、日本人の私にはすごく刺さるメッセージ。
アニメは見慣れないタッチだからファンタジー感があり、鑑賞中も入り込むというよりはあくまでも、物語を見ているという感じで、それはこの作品にはとても合っていると思った。
翁がすこしテンション高すぎると思うフシはあったが、他のテンションがかなり低いのであれはあれでよかったのかも。
主題歌もエンドロールですごく効いていたし、冒頭の竹取物語の語りも国語で読んだなぁと懐かしかった。終わり方も、すごく、残酷にあっさりと終わる。
日本最古のお伽話、大人向けの美しい作品だと思います。
親の愛、子の愛
[2回目の感想] 2018.5.22
一度目を見たのは5年前で20代。今は30代になり子持ちになりました。
子供が出来るとガラッと視点が変わりました。翁はお金を手に入れて変わってしまったように見えてましたが、その時代の価値観での最高の幸せを娘にしてあげたかっただけのこと。無理に結婚させようとはしないし、本人の意思も尊重してるいい親だと思うようになりました。
かぐや姫が美しくなく、琴も下手、礼儀作法も出来ないだと諦めもつくんでしょうけど、完璧な姫。
そんな姫なら手に入れて当然の幸せを手に入れて欲しい…と思うのは親心です。
姫が最後に捨丸と再会した時、捨丸は妻子がいるのに姫と逃げようとした。それだけ、特別な存在だったかもしれません。見ていて、このまま逃げれたらいいな…とも思いました。でも、どんな理由であれ、家族を捨てる人。立場が違うだけで捨丸も都の人と変わらないように思います。
それに、捨丸は自分の生活は盗みもすると言っていて、それは貧しい人にとっては当たり前かもしれないけれど、姫が捨丸や田舎での生活を美化してるようにも感じました。
一度目と一番が印象が変わったのは媼です。以前は翁に何も言わないと腹を立ててましたが、男性の意見が絶対の時代だから仕方がないな、と。許される範囲で自分を見失わないように、小屋や畑を作り、自分を保っている所は本当に素晴らしく、生きる上でのヒントになりました。
姫も両親が大好きだったから、反抗出来なかったのが伝わりました。怒りや諦めを自分自身でけじめをつけながら生きていく姿はかわいそうでした。
少しずつの家族のすれ違いで起こった悲劇の結末に、子供の考える幸せ、その幸せのために親がしないといけないこと、それをしっかり考えないといけないという気持ちになり、余韻の残る作品でした。
好みが分かれる絵も、私は味わいがあり、原作の竹取物語の世界観をそのままアニメにしたように感じ、その表現力の凄さを今更ながら理解出来ました。
一般的な今時の受けるような絵にしなかった事に好感を持ちました。
[1回目の感想] ☆3.5
絵が好きではなかったのですが、ケタはずれの製作期間と製作費に驚いて劇場まで足を運びました。
事前にそれらのことやプレスコを使っていると知らなければ、昔話を膨らませた内容にしか思わないと思います。
どこまで深く考えるかによって、映画の評価は分かれると思います。
翁と嫗、二人はとても姫を思っていますが、行動が違います。
才能ある、恵まれた環境に身を置ける子供をそうしてやりたいと思う気持ちは親なら誰でも思うと思います。しかし、それを望まない子供との関係に思えました。
高貴な姫に育てられて行く姫が心の拠り所に場所を作ったのが驚きでした。
捨丸が最後既婚だったことも。姫は知らずに男性を狂わす魅力を持っているのかなと思いました。
姫は自分から何かしなくても、産まれながらの美貌やお金を持っていることで、それに振り回される他人がいて不幸せにしてしまうのが、罪と罰なのかなと感じました。
月へ向かうのは死を連想しました。
姫がここへいたくないと願ってしまい、後戻りが出来なくなったことも死を感じました。
かぐや姫の罪と罰が何なのかを考えながらみると面白いと思います。
見るたびに新しい発見がある映画だと思います。
昔の日本の美しさや赤ん坊のしぐさが忠実に表現されていて、感動しました。
ヤバイ
かぐや姫の話で泣きそうになってしまうなんて…。
娘と一緒に観に行ってたのでちょっとかっこ悪いなぁ…って思ったら、天人界の迎えの音楽に力ずくで幸せ気分にさせられ茫然自失状態になってしまいました。
あの音楽と映像にはドラッグっぽいモノを感じました。中毒性アリ。
これは…
「姫の犯した罪と罰」って文句に釣られたとしか
残念すぎる
ジブリ自体好きじゃないんでその辺の偏見もあるかとは思いますが、こんな風に思ったの私だけじゃないようで安心しています
感想としては、なんで今更(細かいところはともかく)誰もが知ってる物語を改めて2時間もかけて見なきゃいけないんだと
それに尽きます
目新しい設定があるとか、最後に救いがあるとかだったらまだ楽しめたものを…
捨丸兄ちゃんかっこよかったけどね
不倫はよくないよ不倫は
もうちょっと迷え
あと、個人的に帝が不死の薬を捨てるエピソードが好きなので今回なかったのは残念でした
竹取物語は好きになれない…。
幸せを感じるには不幸せを感じなければならない。
小さな幸せで満足できなければ、欲望は拡大する。
欲望はその時代背景上で拡大するが、結局は、何も持たずにこの世を去る身。
生きるだけで、生きているだけで、幸せだったと感じるには、まだ、達観出来ていない自分がいます。
かぐや姫が受けている罪と罰が、全て幸せという幸せを感じられない暮らしは、生きていないと感じたことに対するものなら、
現世に生きているすべての人の罪と罰で、
竹取物語が好きになれないのが、ハッピーエンドじゃないからだと何となく思っていましたが、仏教上修行が足りない自分としては、
輪廻転生への準備が出来ていない、自分と世界との離別への恐怖を感じてしまうからだと、この映画を観て、思いました。
ただ、やはり映画という娯楽のジャンルなので、もう少し既知の物語を裏切ったものにして欲しかったな~。
高畑監督が、かぐや姫の感情が読めずにこの物語を好きになれなく、焼き直したとしたら、かぐや姫に感情移入しやすかったです。
ただ、このテーマで、「今のすべては、過去のすべて」は、お、重い…。
誰もが知っている物語、誰もが深くは知らない物語
高畑勲。
宮崎駿と共に、ジブリの二大巨頭。宮崎の先輩でありながら、一般的にはどうしても宮崎より認知度が落ちる。宮崎ほどのヒット作に恵まれてはいないものの、だからと言って手掛けた作品が劣っている事は決して無い。「火垂るの墓」「おもひでぽろぽろ」の実写のような丁寧な演出、「平成狸合戦ぽんぽこ」のユニークさと社会風刺を見よ!アニメーションの巨匠の名に恥じない。
そんな巨匠の「ホーホケキョ となりの山田くん」以来となる14年振りの新作。おそらく年齢的に見て、高畑監督の最後の作品になるかもしれない。
その感想は…
まず、水彩画風のタッチに目を奪われた。
温もり豊かで味わい深い。
最近のアニメはやたらとリアルな画とか斬新さを求めるが、原点回帰のようなシンプルさ。日本のアニメでしか出来ない表現。
今回の作品にとても合っている。
また、ジブリ作品は主題歌も話題になるが、本作の“いのちの記憶”は秀逸。作品の内容を表しており、エンディングで図らずもウルッとしてしまった。
誰もが知っている“かぐや姫”の物語。どんな話?…と聞かれても、10秒で説明出来る。
改めてこうやって見てみると、深いテーマ性があり、悲しい話だったんだなぁ…と思った。
かぐや姫の幸せの為とは言え、どんどん欲に走ってしまう翁。かぐや姫を我が妻にしようと躍起になる“高貴”な男たち。人間の愚かさを浮き彫りにする。
彼らをそんな行動に走らせてしまったかぐや姫の存在。美しさは罪とは酷な言い方かもしれないが、無理難題を突き付けたり、翻弄させたのも事実。
その罰は余りにも悲しい。
月に帰る。それは即ち、全てを忘れる事。草木、鳥、動物…かぐや姫が好きだった自然、幼馴染みの捨丸への想い、そして育ててくれた父と母への愛。
この地で生きた証し、この地で感じた幸せ、この世は生きるに値する。
先に公開された「風立ちぬ」とどちらが面白い?…と比較されるだろうが、ハッキリ言って愚問。
二大巨匠のメッセージをしかと受け止めたい。
生きる事と、いのちの証し。
監督もお迎えが近いのでは?輪廻転生をロマンチックに語った作品。
高畑勲監督が竹取物語の映画化を思いついたのは、東映アニメ入社時に同作の脚本プロットの公募があったことがきっかけだったそうです。その時は応募しなかったものの以来、ずっとご自身の頭の中には、竹取物語はどう描くべきか、考えてきたそうです。
監督には、かぐや姫が犯した罪と、“昔の契り”~つまり月世界の約束事ということが、いつも引っかかっていて、地上に降ろされたのがその罰ならば、それがなぜ解けたのか。それをなぜ姫は喜ばないのか。そもそも清浄無垢な月世界でいかなる罪があり得るのかそもそもいったいかぐや姫は何のためにこの地上世界にこの地上にやってきたのか。すべてが謎のまま、答えが出せずにいたそうです。
半世紀を経て、その糸口を月での父王とかぐや姫とのやり取りに見いだした監督はいよいよ竹取物語をベースにした本作の製作にかかりました。
しかし映画化に着手した途端、肝心の父王とかぐや姫がやり取りするプロローグシーンをカットして、観客の想像に委ねることになったのです。
その結果、「かぐや姫が犯した罪と罰」は何なのか、テーマ曲で謳われる「今のすべては、過去のすべて」とはどういうことかイマイチ分かりにくくなってしまいました。レビューの後半に、独自の見解を披露したいと思います。
高畑監督が極力説明的な台詞をそぎ落として原作の範囲に留めたのは、主人公の心をとらえることにあったのでしょう。
カットした分、昔話の主人公にすぎなかったかぐや姫を、涙も笑いもある活き活きとしたキャラに仕立て、観客が感情移入し得る主人公として際立たせたのです。
子供の頃から、野の花や動物たちと親しんで育ったかぐや姫は、宮中の雅な世界に閉じ込められた自分をニセモノのといい、自然と一体となって自由に生きることこそホンモノの生き方と希有しました。ときにその渇望は爆発して、洛中の屋敷を抜けだし、野山を荒々しく駆けまわります。その怒りの表現が簡素で荒々しい線大衆だけで表現されるところが新鮮に映ります。
すべての原点となる、前半の山里の描写。まるで「動く水墨画」といっていいほど、話のタッチで花鳥風月を描きだしています。
またかぐや姫の赤ん坊のときの可愛らしさといったら、たまりません。娘の成長を見守る翁と媼の幸福感はさぞかしと共感してしまいました。少女になってからは山を駆けたり、年上の少年に好意を抱いたり、そこに息づいているのは、竹から生まれたという特別な存在ではなく、いたって普通の女の子の姿でした。
だからこそ後半、都に連れて行かれて、姫君になるための教育を受ける退屈な日々が続くシーンとの対比が引き立ちます。姫がなぜ地球での生活に嫌気がさして月に帰りたいと衝動的に思ったのか、納得できる展開でした。
この自然に囲まれた生活と都の生活の対比は単に子供から大人へ成長していくときの喪失感だけではないと思います。
姫のところに帝が忍んできて、姫を抱きしめようとしたとき、姫はそんなこの世の栄華などニセモノだと悟るのです。
これは極めて仏教的な悟りだと思います。月世界の実際が極楽浄土として、この世はあくまで仮の世界。汚れの世界。汚れの世界に住することは、真実の世界の住人からみれば、それ自体が罪なのです。そしてこの世で生きることはいろいろな苦しみを避けて通れないので罰でもあります。そう解釈すれば、姫が負った罪と罰とは何かが見えてくることでしょう。
本当の世界の価値感を知っている姫にとって、この世の快楽や栄華はニセモノで、そんなものに囚われのない清らかな心こそ本物だったのです。だから、この世の権威の象徴である帝からの誘惑は決定的でした。
自分も15歳の時に、生まれる前の世界が恋しくなり、自殺を図ったこともありました。その時は、かぐや姫とは逆にこの世に追い返されてしまいました。だから姫の気持ちもよく分かるのです。
でも、姫は醜い心の人間や、獣たちが暮らすこの世の意義も否定していません。興味深いのは、養父母の体面が必要なときは、豹変して礼儀作法やことの演奏をパーフェクトにこなす雅さを見せつけるのです。桜の花が一面に咲くなかで喜びを爆発させるのも、この世で経験する意義を姫はつかみ取っていたからなのでした。
人は帰天後に天国に赴くと、波動同通の法則に引き寄せれられて、同じ価値観の人達と毎日仲良く生きることになります。それは価値感がぶつかる地上で暮らすよりも楽ちんなことです。しかし、同じ価値観ばかりだといつか飽きが来てしまうでしょう。だから姫のように、地上に生まれ変わって、波乱に満ちた経験を過ごしたいと思うようになるわけです。
なので「今のすべては、過去のすべて」とは、輪廻転生のことを語りたかったのだろうと思います。となるとこの話は、この世に生きる意味を問うなんて生やさしいものではありません。きっと高畑監督の潜在意識には、もうすぐお迎えに来ますからねというサインが来ているのだろうと思います。ラストは高畑監督の潜在意識の願望が色濃く漂っているのではないでしょうか。
姫を迎えにやってくる、お釈迦様を先達としたお迎え集団。「姫神」のようなBGMにのってフワっとした癒される感覚でお迎えが来たらと、誰もが憧れるシーンだと思えませんか?きっと高畑監督自身も、あんな感じの安からな帰天を臨まれているのだろうと思います。
ときに彩度を落としてモノトーンぽくしたり、空中にファ~と舞い上がる質感は、ジブリならではのファンタスティクなシーンでした。そういえばラスト近くで幼なじみと空中を遊泳するシーンも良かったです。
そして多くの観客は、翁や媼との別れのシーンに、結末は分かっていても涙してしまうことでしょう。そこにインターバル取ったのは、高畑監督の憎い演出だと思います。
罪と罰
見方が違うかもしれないのでもう一回見に行くつもりです。
姫の月への願いが罪だったのか?罰としての月への帰り?
背伸びをした現実に抗いながらも何とか生きて行くのか?規律や道徳を無視して何もかもぶん投げて逃げ続けるのか?
それぞれに罪と罰があるように思える。
目の前にある人生、与えられたもの、近くにいる大切な人たち、ありがたみが普段感じられないものが、いかに人生とって重要なのか?
かぐや姫はわずかな記憶と共に月に帰って行くのだけれど、また、恋しくて帰ってくるんでしょうね?
生きるとは
ジブリ全作品を観ているので、今回も観に行きました。
5回ぐらい泣きました。
地井武男さんの声優最後の作品。
立つことができるようになった姫を呼ぶのに一生懸命な翁のシーン、声が枯れ枯れしており亡くなった地井さんとダブらせて泣いてしまいました。
手書きの絵、自然の豊かさが本当に美しく描かれています。
しかし、ストーリー展開が淡々としているため、ハリウッドなどの激しい展開が好きな方はあまり好まないかもしれません。
自分の生まれた意味とは、自分の親を喜ばせたい気持ち、せめて妄想のなかで自由になる自分
自分の本当の気持ちと周りが自分に求めるものとの葛藤、心を閉ざす感じ…けれども心のどこかでは自由を諦めていない感じを描いていました。
個人的にはとても共感できたし、素晴らしいと思いました。
うーん…
試写会で鑑賞しました。正直、お金を払ってまでは見たくないです。
ネタバレしてますし、良い感想ではないので、不愉快に思われる方は読まずに、他の方のレビューを読まれることをお勧めします。
映画の冒頭では、絵のタッチや、幻想的な描写にとても感動しました。そのため、どうストーリーが進んでいくのか、すごく大きな期待をもって見ていたのですが、最後の方で、「これは、やっつけ仕事ですか?」と言いたくなりました。
50億かけたようには思えません。製作にあまりに長く時間をかけ過ぎて、主題を見失って、最後は無理やりまとめてしまったのかしらという感じです。
捨丸との再会では、「え、そんなに簡単に妻子を裏切るの?」と呆然としたまま、どう決着がつくのか心配していたら、まさかの夢落ち…。
せっかく墨絵調の新鮮で素敵な描写だったのに、飛行シーンで水面にCGが使われていて、それがすべてをぶち壊しにしていたと思います。
最後のお迎えのシーンも解せません。
月=別世界っぽさを出したかったのだと思いますが、いくら別世界とはいえ、あの音楽は、日本人の感覚には合わないのではないでしょうか?
もし、外国人のようなイメージを持たせたかったのであれば、なぜ、月の世界の方々の姿をお釈迦様のような見た目にしたのでしょうか?
それに、かぐや姫は、あの方々と同じ人種とは思えない姿をしています。
かぐや姫っていったい誰?
あのお釈迦様のような方の娘なの?
どんな罪があったの?
そして、懐かしい歌を歌ってたのは誰?
もし、地上で生きたいと思ったこと自体が罪であったなら、田舎で辛い畑仕事などさせて、疲れきって後悔するように仕向けてもよかったのでは?
それをわざわざ、大変な財産を送ってよこしたり、美しい絹を送ってよこしたりして、翁をそそのかして、姫が望んでいない方向へ導かせるなんて、月の世界の人は、随分、回りくどくて意地悪な方たちなんですね。
ただ、私自身にも娘がおりますので、他の方々のレビューにあるとおり、親の浅はかさに気づかされました。親が良かれと思って子供にすることは、必ずしも子供のためにはならないのですね。
肝に命じておきたいと思います。
嫗のように、ただ穏やかに、娘のそばについていてやりたいと思いました。
この映画を見て良かったなと思ったのは、その点と、描写の新鮮さでした。
やっつけ仕事?と思わせるような終わり方でなければ、本当によかったのに、大変、残念です。
まさかこんなに感動するとは!
正直、なめてた。
予告では、つまんなそうな映画だったのだが、本編がまさかの濃厚で、シンプルなストーリーの中にしっかりと見応えとジブリの原点が織り込まれた映画。
最近のジブリが忘れた原点回帰の作品だと思う。
まさか、泣くことになるとは。
ストーリーは詳しく書かないが、人生、楽しい思い出も、辛い思い出もすべて日常に詰まっている。辛い辛い、そんな日常の中で、やがてかぐや姫は、自分が月の住人であることを思い出してゆく。そして、月に帰らなければいけない状況を知らず知らずのうちに作ってしまう。
いざ別れの時、自分の生きたすべてが、楽しいことも辛いことも、子供の頃の思い出も、大人になって、親しい友達もそれぞれの人生を歩んで、すべてが変わってしまったことも、何もかもをひっくるめて、それが素晴らしい、そしてかけがえのないものであったことを気がつく。
しかし、月の都の羽衣をまとった瞬間、その全ての記憶がなくなってしまう残酷な定め。
かぐや姫、いや、ひとりひとりの一生をかけて感じるすべてがこの作品に詰まっている。
特に女性には理解しやすい映画かもしれない。
何度も見て噛み締めたくなる昔話。
「かぐや姫の物語」*ややネタバレ
地味。だからこそ素晴らしい。
生きるってなんだろう。
それを、ものすごく控えめに問いかけている。
周囲のいろいろなものに縛られて「こんなのニセモノの私だ!」「もっと自由に生きたい!」と願う気持ちは、誰もが感じることだろう。
フランクフルトに住むことになったハイジが、アルムの自然を恋しがる、あの感覚。
映像が本当にこだわり抜かれていて、動画、ではなく「2時間かけて50万枚の絵画をだぁぁ〜っと見た」感覚になる。
そして、だからこそかぐや姫が満開の桜の下で跳ね回るシーンや、唯一手書き感だけじゃない要素が入ったクライマックスのあのシーンが、ものすごく生き生きと感じられるのだと思う。まさに生きる喜び。
そんな映像を活かす音楽と効果音。そしてキャストの演技。
相変わらず安定の久石譲。ちゃんと高畑カラーの曲になっている。
俳優を使ったアニメ作品で、これまでで一番ハマったと感じたかも。
ヒロインの朝倉あきは素敵な声で、下手な声優さんよりよっぽど上手い。地井武男、宮本信子の翁媼も見事。
あくまでも原作に忠実に、極力脚色しない姿勢は分かるけど、もう少し月での出来事と、捨丸とのやりとりを描きこんでも良かったかも。
そして捨丸は独り身であって欲しかったよね…f^_^;)
たまには炭焼き小屋のお爺さんみたいな人に出会って「必ずまた春が来る。だから冬を我慢するんだ」と教えられることもある。
一緒に見に行った人は「悩みも苦しみもない月の世界の方が良いに決まってんじゃん」って言ってたけど笑
ちょっとスッキリ感に欠けるぶん、大ヒットはないかもしれない。
だけど、そもそも昔話ってつじつまあってなかったりスッキリしない部分も魅力だから、仕方ない笑
そして、77歳の語る「生きる」は、深く重く感じる。
全84件中、61~80件目を表示