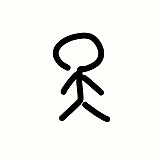小さいおうちのレビュー・感想・評価
全115件中、21~40件目を表示
開戦前夜
山田洋次は寅さんだけじゃないのね。
いい映画でした。
黒木華の出演作は何作か見ましたが、ここでの演技が秀逸ですね。当たり役というのか、はまり役というのか。訛りも良かったですね。温かみあります。
まず戦前や戦時中の事柄はだんだん風化していきます。私も女中の視点から書いた映画なんて初めて見ましたし、戦時中の世相を映像化し、語りついでいく必要性はありますね。
そしていつの時代も恋愛、人のこころは変わらない。不倫とかって事はあるんですが、なかなか自分の好きな人と結ばれにくかった世の中もあいなって、これは純愛以外の何ものでもない恋話でした。
健史とタキ(おばあちゃんと呼ぶ)の関係性がよくわからないまま見てましたが。
健史が、タキ(親類)の自叙伝から、彼女の人生に触れ、最後に彼女が死ぬまで持っていた平井時子の書いた手紙を、平井家の坊っちゃんに手渡す。生きていて良かった。板倉も生きてたら、なお良かったけど。
長い年月をかけたけれど、ひきつがれた、タキの想い。タキを理解し泣く健史、タキの想いをおしはかり泣いた坊っちゃん、私も涙が溢れました。
妻夫木聡は大好きな俳優です。
ほんとに温かみがありましたよ。
脇を固める俳優陣が豪華。
名キャストでした。
山田洋次のムッツリが溢れている。だから良い。
ふしだらな恋も美しく魅せる魔力、昭和と共に移り行く秘密の行方は
恐ろしい雰囲気の映画だと身構えていたのだが、蓋を開ければ、湾曲しているはずの恋が美化され、ありありと山田洋次監督のパワーを見せられた作品だった。
都会に上京したタキは、橙の屋根が特徴的なおうちの女中として働く。時子が起こした恋の事件が60年の時を経て解かれる…。不思議なのが、時子の危険な恋を描いているにもかかわらず、美しく、儚く描かれているのだ。人知れずに同じ人に恋心を抱きながらも、主人を慕うが故の葛藤をしている。離れて観れば、エキセントリックな話であるが、美しく描き出されているのだ。それは、戦争と共鳴するからである。可笑しな関係が、昭和風情の不貞と時代の変化と重なり、クライマックスへと持っていく様は恐ろしい。
赤い屋根の小さな家。
変なストーリーを成立させる山田洋次は恐るべき力技のアンチェインです
ハリウッド流に対する宣戦布告
登場人物はごく少数、美術にもコストは掛かっていない……のですが、なんとなんと少数精鋭の俳優たちの上手いこと上手いこと。
これって、ハリウッド流に対する反骨っていうか、「CG使えばなんだって大作にできちゃうぜウヒヒヒ精神」の対極を行く、本物の映画人による、本物のドラマ、本物の演技の力を心地よく堪能できる映画でした。
ハリウッド流では、エンドロールに出てくる映像って、NG集だったりしますよね。
でもこちらは、エンドロールに出てくる映像こそ、珠玉のように大切で、力を入れて撮影した、まさにストーリーの肝となる、しかも未見のシーンばかりなんですよ。
これを見て、私は確信したわけです。
これは山田監督による、ハリウッド流に対する宣戦布告なんだな、とね。
黒木華さんがエンドロールで初めて2階に登った時の、視線の配り方。
もう、それだけでメッセージが観る側に伝わってくるのです。
これぞ映像の力!
ほんとうにていねいな作りの、素晴らしい作品でした。
小さい秘密に隠された女性の本心
東京のある中流階級の女中の目を通して描かれた、太平洋戦争前の市井の生活。穏やかで幸せな時代と回想する大叔母タキに対して、戦後教育そのままに否定する健史とのやり取りが物語を進める。そこで浮かび上がる奉公先の時子夫人と板倉の不倫劇。山田監督らしからぬ題材をどう描写するか興味深く観ることが出来た。
タキと時子の関係は、ルネ・クレマン監督の「太陽がいっぱい」の女性編になるのか、貧しい生まれから都会生活の安らぎに変わり、若く美しい時子に憧憬と好意を強く抱くタキのたった一度の裏切り。映画としては、些細な出来事だが、一生時子に仕えたいと言っていたタキにとっては許しがたい後悔の念に駆られる。その後独身を通して時子への愛を貫いたと視れば、彼女の純真さが想像できる。
ただ、タキと時子と板倉の三角関係は、曖昧なままで説明不足。時子の幸せを常に願うタキが板倉に対してどう思っていたのかの描写が抜け落ちている。そのためラストの板倉の絵、息子恭一の登場という映画的なクライマックスが最良の効果を生んでいない。
演技面では、主演の松たか子と黒木華が素晴らしい。女盛りの欲望に抗えない時子の感情の行方を丁寧に演じる松たか子に、女中の仕事に献身的に尽くす一途さを体現する黒木華の演技力。このふたりの評価で、この映画の良さの殆どを占める。残念なのは、板倉にキャスティングされた吉岡秀隆の俳優の色が全く合っていないことだ。徴兵検査で丙種合格の後ろめたさを彼なりに演じているものの、松たか子との不貞の相手の危うさのイメージは持ち合わせていない。健史役の妻夫木聡は、「永遠のゼロ」の三浦春馬と同じくステレオタイプの好青年の特徴のない人物像で何の個性も感じられない。脚本の問題だが、教科書通りの歴史観を述べるだけでは教養がない。実際に経験した人間の証言に対しての想像力が欠落した青年で片付けられる。その他男優にも特筆すべき演技がなく、女優優位の作品である。
戦前の幸せな時代を生きた一人の女性の生涯を描く作品の意図は、賠償千恵子が晩年のタキを演じたことで理解できる。戦争がなければタキの一生も全く違うものになっていただろうということに、山田監督の創作意欲が刺激されたのだと想像する。
松たか子と黒木華の演技力が光る!
月並みな言葉ですが
負ではない遺産。
はっきりはわからないくらいの心の動きに感動
【昭和初期を舞台にした気品溢れる作品。】
原作に忠実に再現してほしかったなーと思います。 あのストーリーだと...
昭和初期あたりの暗さと明るさと
全115件中、21~40件目を表示