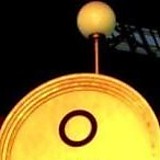マリー・アントワネットに別れをつげてのレビュー・感想・評価
全20件を表示
286人の斬首リスト
ストーリーは1789年7月14日の朝から始まる。あ、パリ祭でもあるフランス革命記念日当日!となると、いきなりバスティーユ牢獄襲撃事件から始まるのか!とワクワクしながらの鑑賞。王妃マリー・アントワネットに本を読み聞かせる朗読係として雇われていた侍女シドニー・ラボルド。うっとりした感じのベルサイユ宮殿の外側ではオスカルとアンドレが・・・とか、あ、シドニーはロザリーやん・・・などと想像力を働かせて革命のスペクタクルを楽しむ準備をしていたら、7月15日になっていた。
革命を全く描かないで、王宮内部の状況、貴族や使用人たちの心理などを描いた珍しい作品だった。普通は革命の荒々しさとか政治情勢とか、宮廷の煌びやかな部分を描いたりするものなのに、これはある意味挑戦的な作品だった。貴族たちの派手な宝石とか潤沢な装飾品とか、そんな明るいイメージは全くなく、むしろベルサイユは暗くて陰湿で噂好きな、みんなローソクを持って談笑するなど、ホラー映画をも思わせる描き方だったのだ。
何しろ情報伝達が遅い。東京ドーム220個分の広さのあるベルサイユ宮殿なのだから、歩いても「革命が起こったよ」と伝えるのに何時間もかかりそう。バスティーユ襲撃事件の噂が広まったのが翌日だったのも当然だったのかもしれない。漫画だと次のコマで「何ですって?!」と王妃が言ってたような気もする。
そんなマリー・アントワネットの当時のお気に入りはレア・セドゥ演ずるシドニー。王妃の間も密室ではなく、侍女たちや他の公爵夫人も隣の部屋にいたりして、個人情報なんて筒抜けだったり、愛人とまで言われたポリニャック公爵夫人の部屋もすぐ近くで、シドニーでさえ簡単に入室できるほど、今の時代には考えられないほど大らかだ。誰と誰が浮気してるとか、宮廷内ではその日のうちに広まってしまう・・・なんて世界だ。
二日目には斬首リストが出回って、民衆によってギロチンにかけられることを恐れた貴族の中には自殺する者まで出た。三日目にはいよいよポリニャックや王妃もスイスに逃亡することになり、シドニーには残酷な命令が下される。「あなたも人を愛したことあるでしょ?」などと、もしや自分のこと?と一瞬感じたのも束の間、ポリニャック夫人の身代わりになれるよう、夫人のドレスを着せられるシドニー。主席侍女であるカンパン夫人からは「断りなさい」と助言されてたのに、身も心も王妃に委ねたシドニーは断れるはずもない。
旅立つ際、王妃からキスされ、自分の役割を再認識するシドニー。すっかり公爵夫人になった気分で沿道の人に手を振る。短いシーンではあったが、彼女にとっては人生の最高潮だったに違いない。スイスに無事に着くまでは私は公爵夫人!そんなシドニーの出自に関する独白で締めくくられるエンディング。何者でもなくなる・・・むしろ首を切られてしまった方が幸せだったとまで思わせてくれた。
片想いの切なさ、届かなさよ…
DVDで鑑賞。
フランス革命時の王宮を描いた内幕劇。
宝塚歌劇「ベルサイユのばら」で慣れ親しんだ名前や出来事がいくつか出て来たので、流れがすんなりと入って来ました。
それはさておき、女優陣が美しい…。
まさに“美の競演”とはこのことだなと思いました。
本作でレア・セドゥの虜になってしまいました。マリー・アントワネットに恋い焦がれる朗読係を熱演。身代りを命じられるも裏切られたような形になり、彼女の女王への“片想い”の切なさが漂うラストが印象的でした。
一方、アントワネット自身はと言えば、側近のポリニャック夫人に片想い…。夫人は女王の危難に際し我先にと逃げたことで有名な人物。それを知っていただけに結末は見えていましたが、やっぱり「最後までお側に…」という返事を期待したアントワネットの心中を慮ると胸が痛かったです。
見どころは、美しい女優陣
片想い
フランス革命勃発時の宮殿内の様子を、Marie Antoinette王妃の朗読係Sidonieの視点で描いた作品。
王妃に焦がれるSidonieは、あえて得意な刺繍係ではなく、謁見できる朗読係に。朗読以外でも出来るだけ王妃に尽くそうとしますが、その想いは到底届かず、王妃はPolignac夫人にぞっこん。この同性愛人関係が事実なのか知りませんが、Polignac夫人というのは、王妃に取り入って階級まで上げたものの、革命時には真っ先に王妃を見捨てた側近。
王妃が夫人に「逃げて」と言った時、本当は「最後までお伴します」とか言ってもらいたかったんですよね。「はい」って即答でしたけど(^^;)。王妃も最後まで片想いでした。
Sidonieの気持ちを際立たせるためか、Polignac夫人とは対照的に、忠実な側近Lamballe公妃は名前だけしか出て来ませんでした。
身代わりを命じた王妃に裏切られたような気持ちだったでしょうが、Polignac夫人の衣装を纏ったSidonieは、「王妃の寵愛を受ける貴婦人」を演じながら、優越感と満足感を妄想しているようでした。
革命時の民衆ではなくて、王族・貴族達と、宮殿で働く人々の反応に焦点を合わせているので興味深かったです。内容的にはFrench大奥の愛憎劇で、登場人物の名前が多くて複雑でした。終わり方がすっきりしませんが、女優さん達と美術が美しいです。
切ない
主人公の心理を追うにつれ深みがます
マリー・アントワネットの姿が、その朗読係の侍女の視点から描かれる。
ゆえに、この断頭台の露と消える運命の王妃が、観客に与える印象の変化は、レア・セドゥー演じる侍女シドニーの王妃への感情の変化を表す。
朝の読み聞かせのシークエンスで姿を現す王妃は、思いつくままに次々と周囲の者へ指示を出す気ままな主人の側面を持つ。しかし、その言葉遣いは丁重で、物腰は柔らかい。そして、臣下に対して思いやり深く、お気に入りの侍女の虫刺されの痕を見て、手ずから精油をなじませるのだ。
シドニー以外の侍女たちは、それでも王妃の顔色を常に窺い、この高貴な女性の大らかさや頭の回転の速さを敬愛しているのが、ここではシドニーだけの特別な感情であることを示している。
ところが、王妃には貴族の女性という同性の愛人が存在する。この愛人と会っているときの王妃は、孤独な一人の女性の弱さを相手にさらけ出す。誰よりも、ありのままの姿を見せることのできる相手がこの愛人であることが、衆人環視のなかで額を寄せ合うショットで痛々しく描かれている。
侍女であるシドニーは、身分というヒエラルキーに加えて愛のヒエラルキーにおいても、自分を王妃から遠ざけるこの女性に激しく嫉妬する。
いよいよバスチーユが陥落し、貴族たちはベルサイユからの逃亡を図り始める。そんな中、王妃は自らの逃亡が王の意思とは相容れないと分ると、最愛の愛人にフランスからの脱出を促す。
そしてシドニーには心外なことに、この愛人は躊躇なくそれを受け入れるのだ。このときこの侍女が知るのは、王妃もまたこの愛人を深く愛しているほどには、彼女からは愛されてはいなかったことである。自分が王妃を愛するほどには、王妃は自分を愛してはいない。それと同じように、王妃は、その愛人に向けている愛に相当するものを、その相手から受けてはいないのだ。侍女シドニーの嫉妬はここで王妃の孤独への共感に代わる。
しかし、いよいよ王妃の愛人がベルサイユを離れるとき、王妃はシドニーに対して残酷なことを命じる。ここで王妃への共感は絶望と憎悪に変化していくかにみえる。ところが、シドニーは死を賭して臨まなければならない役割をむしろ至福の時間を楽しむかのように果たすのである。
レア・セドゥーの控えめな感情表現が、この映画の心理描写にむしろ深みを与えている。王妃を前に感情など表に出せるわけもない状況。パリで何が起きているのか、人の口を介してしか知ることのできない不穏でもどかしい背景には、派手な感情表現は似合わない。
WOWOWオンデマンドで鑑賞
レア・セドゥが素晴らしかった
落ちが残念。役者はとても良かった。
主役のレア・セドゥが特に素晴らしかった。中盤あたりで主人公のマリーに対する厚い忠誠心が窺えたのに対し、マリーに身代わりを命じられてから(もしくはパールを拾わされていたときから)それが少し変わったように思えた。
この物語の起承転結は、主人公の忠誠心の変化そのもののように思う。
ラストは「今日から私は誰でもなくなる」というシドニーの台詞で、投げやりに締めくくられている。
主人公の過去に何かを感じさせておきながら、説明は最後まで無く、とにかく不完全燃焼。
この映画で泣くことも笑うことも出来なかった。
エンドロールが流れたときは思わず「えええええ」と言葉が漏れてしまった。
ただ、役者の演技がよく、映像も終始綺麗で、まるで舞台劇を目の前で観ているような感覚を味わえたのは確かだ。
侍女の視点で描かれるフランス革命
確かに、マリー・アントワネットの侍女である朗読係の少女の視点から描かれたフランス革命という着想は新鮮だし、面白い。
マリー・アントワネットやフランス革命について今更詳しい説明は不要(特にフランス国内の観客を考えれば)と考えたのは分からなくはないが、それでもシドニーとマリー・アントワネット、ポリニャック夫人、この三人の立ち位置はもうちょっと明確にすべきだったかもしれない。
何故、マリー・アントワネットはポリニャック夫人にそれほど執着したのか?
特にシドニー(彼女は架空人物だと思うのだが)が何故それほどマリー・アントワネットに心酔していたのか?はもっと説得力のある描写、シーンが必要だったんじゃないか?
しかし、これが最初から前提になっているので、彼女達のその後の行動がどうも腑に落ちない。
(最初からシドニーが王妃に盲目的に心酔している前提で)シドニーのポリニャック夫人に対する嫉妬とか、最後にポリニャック夫人のドレスを着て彼女の身代わりとなったシドニーの勝ち誇った表情。この辺りのレア・セドゥの表現力はなかなかだが、見所はそれくらいか。
ベルサイユで実際にロケしたという映像はさすがに本物の輝きがあるが、それが作品の質を引き上げたかどうかは疑問。
視点が素晴らしい W座
マリーアントワネットのお話好きで、結構?私にしては見てきたけど、これは、一味違う!主人公がボニノワ?みたいな名前の(絶対間違ってる笑)、王妃の朗読係なのね。だから、マリーアントワネットに仕える一貴族?として映画をみれたことはとっても面白かった。
この映画の特徴は、音楽がほとんど使われてないことにあるなぁ、と。だからとってもミニシアター的で、W座で取り上げられてる意味がすっごくよくわかりました。
そして初めて知ったけれど、マリーアントワネットってレズだったのね(°_°)ボニノワも!!
百合のリアルを読んだばっかってこともあって、とてもフランスらしくていいなぁ、って思うた。。
恋愛の国ね。。
この間のオランド大統領の不倫問題にも国民は寛容な目だった、って。。さすが!日本じゃあ、ありえません。
今の事実婚の奥さんも不倫からのスタートだったわけで、前妻の気持ちがよくわかったんじゃないかな。。
とにかく、私の言うボニノワを演じる、レアセドゥ素敵。
ミッドナイトインパリの雑貨屋さんの女の子だったんだね!!
他のレアセドゥ作品も是非是非みたいです。おっぱいおっきい(°_°)笑
え?
フランス革命前夜の王宮内の出来事を描いた作品。
時代背景としては、今もロードショーしている「レ・ミゼラブル」のちょっと前か。
当時の王宮がどんな感じだったか…というのを知る事が出来るのはいい。
王妃様もあんな感じだろう。
王様の「権力とは王家に与えられた呪いだと思っていた」という台詞など、実際にそうだったのかもと考えてしまう。
…が、正直よくわからない。
おそらくフランスの人達にとっては、フランス革命は歴史の教科書に載っている有名な史実で、解説などなくとも細部まで解るのだろうと思う。
だから、あの事件の裏には実は!的なストーリーなのかもしれない。
しかし、世界史にあまり詳しくない私が見る限りでは、表層しか追えない。
話の展開が淡々と進むのもあり、途中、(おそらく知識がないので)よく解らない描写もあり。
最後も、「え?ここで終わるの?」という感じ。
マリーアントワネットの最後はさすがに知ってはいる。
が、この後、歴史的にどうなるのか、関係者はどうなったのかといった解説が何もないため投げっぱなしに思えてしまい、もやもやが残る結末でした。
ストーリィ展開は後半!
フランスでベストセラーの「王妃に別れを告げて」が原作
マリー・アントワネットの朗読係を務めた少女・シドニーが
フランス革命の勃発で、
心酔する美しい王妃マリー・アントワネットから、突きつけられたのは、
王妃が恋して止まないポリニャック夫人を無事に逃すために、
彼女の身代わりになるということだった・・・
その時の少女の深い悲しみと絶望を
主演の仏若手女優のレア・セドゥーが熱演していました
前半では革命時のベルサイユ宮殿内の人々の思惑と混乱を描き
後半からは、身代わりになったシドニーが
召使いに扮したポリニャック夫人と追われていく
道すがらの様子をサスペンスタッチで描いています
彼女のそれから先はどうなったのか・・・
エンドレスのない絶望の逃亡の先は・・・
いろいろな思いを巡らして映画が終わります・・・
一途な想いで王妃を見つめるシドニーの深い悲しみと
裏切られた思いを断ち切る気高い姿に心を奪われました
ただ革命時の切迫した当時の様子が、この映像を見ている限り
あまり伝わってこないことや貴族達の様子も人ごとのようで
悲しみや絶望感などもあまり感じませんでした
全体的に淡々と描かれた映画だったかなぁ
高評価だったので、期待が大きかった分
少し消化不良で物足りなさを感じました・・
ただ映像は素晴らしかったです
実際に撮影したベルサイユ宮殿内や
貴族達の美しく豪華な衣装は観る価値があります
画は綺麗だが、噺は上っ面を舐めただけ
舞台は1789年7月14日のフランス・ヴェルサイユ。折しもフランス革命の発端となった民衆によるバスティーユ牢獄襲撃事件当日の朝を迎える。
王妃マリー・アントワネットの朗読係・シドニーが主人公で、彼女の視線で激震が走るヴェルサイユの3日間を描く。
シドニーにとって王妃は特別な存在だ。畏敬とともに憧れと恋心を持っている。
このあたりは、出勤に遅れないよう上司から借りている高価な時計で目覚める慌ただしいオープニング、そして一転して王妃の前でかしこまる彼女の内なる高揚ぶりから十分に窺える。
ダイアン・クルーガーる、優雅で気品があるが、思いのままの言動で回りを右往左往させるダイアン・クルーガーによるマリー・アントワネットは文句なしだ。
王妃の世話をするカンパン夫人の心配をよそに、王妃との会話を楽しむシドニーのあどけなさも出ている。
セット、衣装から小物に至るまでよくできていて、豪奢な宮殿内の様子を美しく再現している。
ただ、王妃の寵愛を一身に受けるポリニャック夫人の描写と、シドニーの夫人に対する嫉妬心の描写はともに物足りなさを感じる。
そして、宮殿が不穏な空気に包まれてからは、シドニーを手持ちカメラで背後から追う描写があまりに多く、映画のテンポがどこかへ置き去りにされてしまう。テンポを変えたのならいいが、そうは感じない。おまけに不協和音を使った音楽が安っぽい。絵も音も小手先だけで切迫したものを感じない。
同年代の同僚はメイドやお針子で、王妃に謁見できるのは自分だけという特権意識のようなものがシドニーにあったに違いない。その意識が分不相応の嫉妬を産み、彼女の人生を狂わせる。そうした噺への肉付けが不足している。観客が察するだけでは切なさが出ない類のものだ。見た目の方にだけ気が配われた感がある。
シドニーが同僚に言う。
「刺繍係になったら王妃に会えなくなる」
資料室の老人がシドニーに言う。
「君の王妃への熱い思いは知っている。愛が強すぎ我ままに寛大だ」
シドニーが最後に残す言葉。
「今日から私は誰でもなくなる」
けっきょく、これらの台詞だけで事足り、人生の上っ面を舐めただけの映画で終わってしまった。
p.s. 日比谷のシャンテがデジタル化してから映像が綺麗になり、ヨーロッパの歴史ものを観るのが楽しみになった。
物語の途中で放り出された。
若い朗読係
なんだか悲しい話でした。
主人公はマリー・アントワネットの朗読係です。
主人公は、マリーに対して恋に近い感情を抱いていますが、
映画をみると、マリーは他者を振り回す自己中心的な人物です。
もし会ったこともないなら、
美しいマリーに憧れたかもしれません。
マリーの人柄を知っていて、
「どこにそんな強く惹かれたのだろう…」と思いました。
朗読係の感情にあまり共感できませんでしたが、
とても応援したくなりました。
これ見てマリーアントワネットに興味が湧きました。
レア・セドゥに尽きる!
今まで、数多くのマリー・アントワネットの登場する作品がありましたが
今までとは全く違った視点、全く異なった雰囲気のマリー・アントワネットを取り巻く映画になっています。
バスティーユ陥落の日から始まるこの映画は、煌びやかさや、華やかさはなく、混乱のベルサイユです。
年を重ねたマリー・アントワネット、王妃の寵愛を受けるポリニャック夫人も、今までの描かれ方とは全く異なっています。
しかし最も惹きつけられたのは
王妃に心酔する朗読係のシドニーを演じたレア・セドゥです。
彼女のあどけなさが残る哀愁を帯びた笑顔と美しい肢体。
朗読係から、その場でポリニャック婦人のドレスに着替え、堂々と階段を下りて行くシドニーからは目を離すことができません。
レア・セドゥ自身の演技の幅の広さを、垣間見た感じがしました。
ストーリー的には、期待したほどでもありませんでしたが
レア・セドゥは見応えがありました。
主演女優がとてもよかった
全20件を表示