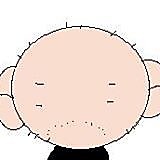ベニスに死すのレビュー・感想・評価
全62件中、21~40件目を表示
【耽美的で、蠱惑的で自己献身な老楽の恋を描いた作品。当時15歳のビョルン・アンドレセンの魅惑的な微笑みと流し目にヤラレタ作品。】
ー 久方振りに鑑賞した。そして、内容を殆ど覚えていない事に驚愕した。
故に、初鑑賞の様に新鮮な気持ちで鑑賞した。
再鑑賞した理由は分かり易く、先日鑑賞した「世界で一番美しい少年」を見たからである。
当時15歳のビョルン・アンドレセンは、矢張り美しかった。-
◆感想
・今作の老作曲家アッシェンバッハ(ダーク・ボガード)が当時50歳であった事に驚く。
- 私も、あと数年すると”老”が付くのか・・。
嫌々、時代の流れであろう。
今観ても、ダーク・ボガードは十二分に若々しい。-
・ルキーノ・ビスコンティ監督が、血眼になってタージオ役(先日の映画の翻訳ではタジオとなっていたが、今作では”タジョ”と聞こえた。)を探した理由が良く分かる。
今作品は、ビョルン・アンドレセンの耽美的で、蠱惑的な美しさ無くしては製作しえなかった事が良く分かるからである。
- 日本で言えば、赤江瀑の小説群に登場する美青年達を想起させる。-
・老作曲家が静養に来ていたベニスから荷物の発送間違えで、足止めされるシーン。
- 抗議をしつつも、明らかに嬉しそうである・・。理由は明白。
自分の命が短くなることも知らずに・・。-
・そして、老作曲家アッシェンバッハは流行していたアジア・コレラに感染しつつも、床屋に行き身なりを整え、タジオの母に、この地を離れた方が良いとアドバイスをするシーン。
ー 老作曲家の不自然な顔色。音楽会での散々の出来。
それでも、彼は息絶えるまで、リドの海岸で戯れるタージオの姿を目で追っているのである。ー
<今作は、間違いなく先日鑑賞した「世界で一番美しい少年」を見ていなければ、印象は変わったであろうと思う。
初見時の記憶が無いのであるから・・。
今作の陰の主演であり、デビュー作でもあったビョルン・アンドレセンが今作出演後、どの様な人生を送ったのかは、「世界で一番美しい少年」で綴られている。
併せて、観賞したいモノである。>
精神性の敗北に美しい形象を付与した稀代の傑作
本作は、初老の芸術家が美に陶酔し、美に殉じ破滅していく姿の美を描いた耽美主義映画である。ことさらストーリーを書くのも気が引けるが、映像が寡黙であるため、ここで原作の内容を紹介しておいたほうがいいだろう。
〈原作のあらすじ〉
主人公の老小説家アシェンバッハは避暑地ヴェニスで14歳くらいの少年に出会う。その印象は、「自然の世界にも芸術の世界にもこれほどまでに巧みな作品をまだ見たことはない」と思わせられる美しさで、彼はその夜、「あとからあとからいろいろのこと」を夢に見る。
次に会った時、今度は「神々しいほどの美しさ」に度肝を抜かれる。
やがて何度も海水浴場で見かけるうちに「小さな肉体の、あらゆる線、あらゆるポーズを知悉し、いくら感嘆してもし足りず、いくらやさしく味わい楽しんでも楽しみ足りぬ」というほどに陶酔しきってしまう。
これはもう、完全に恋愛である。しかし、この頃はまだましだった。「美とは人間が精神に至る道であり、ただの手段に過ぎぬ」と考える余裕があったからだ。美など、アシェンバッハが刻苦勉励して築き上げた精神世界に至る入口程度のものだと。
しかし、出会ってから4週目に入る頃には、彼は少年一家の散策をこそこそ付け回すようになっている。
一方、ヴェニスは滞在当初から「ものの腐ったような匂いのする入江」であり、「不快に蒸し暑く、空気は澱んで」いたのだが、今では町の中心部に消毒剤の臭いが漂い、事情通のドイツ人たちはすっかり引き上げてしまった。
原因を追究したアシェンバッハは、それがコレラの蔓延であると教えられ、ただちに引き揚げるよう勧められる。今ならまだ「自分が再び自分の手に戻ってくるかもしれぬ」と彼は思い惑い、しかし、そうする代わりに留まることを選択してしまうのだ。
今や彼は、美から精神に至る道は「本当に邪道であり、罪の道であって、必ず人を間違った道へ導く。われわれにはただ彷徨することしかできない」と、狂躁した頭脳で思いめぐらす。
美に踏み迷ったアシェンバッハは、もはや精神世界などそっちのけで美を享受することに全精力を傾けるだけであり、彼の芸術はたった一人の少年に敗北したのである。
さらに彼は少年に気に入られようとして、かつて唾棄するほど軽蔑した若作りの老人と同じ化粧を施し、少年一家の後を追って病んだヴェニスを彷徨し、最後には「腰から手を放しながら遠くのほうを指し示して、希望に溢れた、際限のない世界の中に漂い浮かんでいる」少年を追おうとして砂浜に立ち上がったところで、コレラにより絶命してしまう。
〈美学・芸術論について〉
原作でアシェンバッハの内面の葛藤として描かれている美学・芸術論を、映画はアルフレッドなる友人を登場させ、アシェンバッハと議論させる形で表現している。
「美は精神的な営為によって生まれる。感覚への優位を保つことによってのみ英知、真理と人間の尊厳にたどり着ける」というアシェンバッハは原作の通り、自然美より精神性により生まれる美を優位に置いている。
これに対しアルフレッドは、「美は感覚だけに属し、芸術家が創造することなどできない。英知、真理、尊厳――そんなものが何になる」と彼を批判する。
友人の意見は、アシェンバッハが少年に出会った結果、その芸術観を揺るがせていく過程の比喩である。彼が少年に惹かれれば惹かれるほど、その批判は手厳しくなっていく。
「芸術は教育の一要素」と言うアシェンバッハに対し、友人は「芸術は個人道徳と無関係。汚れに身を晒し、道徳から解放されれば、君は最高の芸術家だ」と、彼を堕落と狂気に誘い、その結果、アシェンバッハは醜悪な化粧に手を付けてしまう。
末尾に近くアシェンバッハの公演が失敗に終わるのも、現実というより己の芸術が敗北した自覚の比喩だろう。だから友人の最後の声は死刑宣告の悪夢と化すのである。
〈評価〉
ヴィスコンティ監督は、主人公の職業を小説家から音楽家に代えたこと、美学・芸術論の内容をいくらか変更させていること、主人公の妻子や売春宿シーンを追加したこと等を除き、この映画を原作に忠実に作っている。したがって、上述のストーリーはほぼそのまま映画作品のストーリーと考えてよい。
結局のところ、本作は精神性が美に敗北する耽美主義の映画という結論になるが、ここで何より素晴らしいのは、腐敗臭と消毒剤、汚染物を焼却する煙にまみれたヴェニス、コレラを病む古都の頽廃の美が、見事に映像化されていることである。
ことに醜悪な化粧を施した主人公が、汚染物を焼却する炎と煙に巻かれた迷路のような街並みを、病に侵され弱った足取りで少年一家を付け回す狂躁と徒労に、観客は惹きつけられてしまう。
果実は腐りかけがいちばん美味いという。全編を通して流れるマーラーの第5番は、敗北した芸術家の辿る腐敗した街並みと響き合い、甘美な頽廃とでもいうべきものを伝えてくるのである。精神性の敗北に美しい形象を付与した稀代の傑作だと思う。
監督の罪は消えないが、アッシェンバッハの恋とビョルン君の美貌もまた永久に不滅です。
2月か3月?に、原作を読みました。
(長い上に抽象的だから好みは分かれそうだが、読んでから映画観た方がいいかも)
実は学生の頃に借りて、画像不良かな?冒頭でストップしてずっとそのままだったのを、約15年越しでようやく最後まで鑑賞。
マーラーのアダージェット(シンフォニー5番4楽章)が素晴らしい、、この映画の魅力は、ビョルン・アンドレセンの美貌とアダージェット、そしてダーク・ボガートの好演に尽きると思う。それから、対象をパッと映すのではなく、ゆっくりズームアップしていくクラシカルで貴族的(?)なカメラワーク。
映画でアッシェンバッハは作曲家というテイになっていたが、原作では作家。色んなバリエーションのケンタウロス風のクリーチャーが狂乱の宴といった感じで押し寄せてくる、かなり不気味な悪夢を終盤で(アッシェンバッハが)見るのだが、映画ではお上品に脚色してあった。(原作のヤツはCG使わなかったら相当チャチなものになるし、、ヴィスコンティの美意識に合わなそう)
夕方、空きっ腹にアルコールを流し込んで物語の続きを読み、めくるめく退廃と蠱惑の世界に浸るという愉しみを原作に与えてもらいました。
ただ、いかんせん山場に乏しいというか、、雰囲気を楽しむ作品だから、、正直アダージェットがなかったらこの映画もだいぶ地味だったろうなと。
(映画『さくらん』が、なまじストーリーが平板なだけに、ほぼ椎名林檎のPVと化してしまった事と似ている)
当時まだティーネイジャーだったビョルン君が、修業と称するヴィスコンティの手でパリのゲイコミュニティに放り込まれ、玩具として消費されていたことが最近のドキュメンタリーで明かされたそうな。
世界的な監督&名門貴族だからと誰も逆らえなかったらしい、と。
当時はたぶん今以上に、同性からの性被害は真面目に取り扱ってもらえなかったろうな、、美少年の宿命かミソギぐらいに捉えて黙殺したんだろうな、、
うちの親とほぼ同年だけど、だいぶ年上に見えてしまう現在のビョルンさん。過酷な半生は深い皺として刻まれてるけど、告発は勇気ある行動だし、この映画はビョルン・アンドレセンの美貌なしには有り得なかった。そう思います。
ビョルン・アンドレセンの衝撃
美しい……
少年の美しさと人生の終わりと
生老病死を目の当たりにした老いた作曲家の様子が身につまされる。原作小説はトーマスマンが30才の頃に執筆されたそうだが、既に心の中は老境にあったのだろうか。
主人公のモノローグの代わりに多くがクラッシック曲で語られているのが叙情性を高めている気がした。そして、ビスコンティ監督特有の豪華なエキストラシーン、主人公の心の慰めとなる美少年とその家族の様子がひたすらに眼福な作品だった。
[ビョルン・アンドレセン(2025年10月25日没・70歳)トリビュート]
今年(2025年)10月25日、ルキノ・ヴィスコンティ監督『ベニスに死す』で〈美少年〉タッジオを演じたビョルン・アンドレセンが、70歳で亡くなった。
映画『ベニスに死す』は、全編に流れるマーラーの交響曲第5番 第4楽章〈Adagietto〉を、決定的にポピュラーにした。僕もまた、その耽美的な静謐感に浸るため、50年以上にわたりこの曲を繰り返し聴き続けてきた。だがこの曲は、アンドレセン本人にとっては、長らく“つらい曲”でもあったのだということを、今回の報に接して初めて知った。
映画公開(1971年)から50年後の2021年、本人の証言:サンダンス映画祭で発表されたドキュメンタリー『世界で一番美しい少年(The Most Beautiful Boy in the World)』によって、その背景が明らかになる。
彼がヴィスコンティや周囲の大人たちによって、「美」の名の下に消費され、性的に搾取されてきたと本人が告発する作品だった。
2つの作品を、差し引きの引き算に解消せず、同じ重さとベクトルで丸ごと観たい。それは作品の〈美しさ〉を守るためでも、ヴィスコンティを免罪するためでもない。その美のために差し出された、ビョルン・アンドレセンへのオマージュとして。
| 映画は“美”を浄化した。
| だが、その美に選ばれた少年は、守られなかった。
---- ドキュメンタリー『The Most Beautiful Boy in the World』日本語版キャッチコピー
R.I.P.
美少年の美に耽溺してゆく初老の作曲家
魂の芸術作品
間の使い方が優雅過ぎ、終始音楽が美しいので カフェとかバーで流れて...
間の使い方が優雅過ぎ、終始音楽が美しいので
カフェとかバーで流れてたら丁度ええな
なんで美少年は美少女より儚げで官能的で物憂げなんや…
最高〜 タジオのスタイリング決めた奴は金メダル
腕を後ろに持って歩くのも何からなにまで意味ありげに見え美しさとは罪
めちゃくちゃ影響うけてタジオがかぶってたような白い帽子を買うことを決断
主人公が友人と議論してる場面があるけど
まじで高尚すぎて意味分からず
芸術家とか作家とかそっちの創造者の人達って
身を削り地獄で踠いて傑作を出すみたいな作業あるよね
人生〜
終始 見る側に解釈を考えさせるような雰囲気だなと思う
セリフよりも表情の寄りや変化が多く感じ、
ちゃんと見てたら少し疲れるので
悪魔的美少年のPVだと思ってみると丁度良し
そして主人公にもタジオにもちゃんとモデルがいることがビックリ
そういうのを知っていくとより映画って楽しいね
美に翻弄され醜態を晒し殉死する、老芸術家の最期
トーマス・マンとマーラーとヴィスコンティによる美学と醜悪のデカダンス。原作の設定では小説家のアッシェンバッハを、モデルのマーラーに合わせて作曲家に変更して、全編に渡り交響曲第5番のアダージェットを使用しています。アッシェンバッハの葬送曲なら第9番のアダージョが合理的ではと思うも、水の都ベニスの映像と調和するアダージェットが素晴らしい効果を生んでいます。例えば、ベニスを離れようとして駅に向かう時の重く沈み込んだ表情と、荷物の不備に託けて再びタジオに会える喜びに浸る対照的な両面でアダージェットは、アッシェンバッハに寄り添い同調し、且つ悪魔的な誘惑としての曲のイメージもあります。
映画は原作のベニスを訪れる動機の導入部を省略し、アッシェンバッハを乗せた蒸気船が海を進むシーンをタイトルバックにしました。空と海の境界のない灰色の世界からゆったりと現れる蒸気船と遠浅の海岸線のカットバックが素晴らしいです。音楽と映像の融合はラストショットまで完璧です。砂時計の逸話で語るアッシェンバッハの最期は、すべてが落ち切ってから、つまり誰にも見送られることなく現生を去る事になりました。死と恍惚のなかタジオに手を差し伸べ息絶えるアッシェンバッハの、美に捧げた生涯といえる最期が唯一の救いです。
ヴィスコンティは後期ロマン派音楽のブルックナーを何度か使用しています。「ベニスに死す」から5年後の亡くなった時の記事に、最後はブラームスの交響曲第2番を聴いて静かに眠りについたとありました。マーラーやブルックナーではなくブラームスと知って意外な印象を持ちました。それでも充実した巨匠の生涯を想像させます。
クラシック音楽では制作当時マーラーブームが始まろうとしていた時代でした。私自身もこの映画の関心から、マーラーを知り、ワルターやバーンスタインそしてテンシュテットが指揮するマーラーの音楽の虜になっていきました。
美少年に導かれて亡き娘の元へ…
ヴィスコンティの作品は、映画好きの友人に薦められて「家族の肖像」を観て、内容はあまり覚えてないけど…難しかったと記憶しています。
そしてこの「ベニスに死す」も難しかったです。美学・哲学・芸術学のような…。でも自分なりに解釈できるとスッキリしました。
いろんな解釈があると思いますが私は…
最初の方でアッシェンバッハが娘と奥さんの写真にキスをする場面があり、そのあと過去の回想で3人で仲良く寛ぐ場面も… そして、小さな棺が運ばれ泣いている夫婦。
アッシェンバッハは美少年タージオを初めて見た瞬間に彼が「死の番人」だと感づき、それでも抗えない「死」の魅力にとり憑かれていき、どちらの道を選ぶか悩んでいたアッシェンバッハは、死神タージオに導かれて自ら望んで娘の元へ…
ミュージカルの「エリザベート」のイメージですね♪
最初は恋の病におかされて亡くなった説でしたが、死神説の方がしっくりくるなぁと…(^^)
それにしても、タージオ少年、美しすぎるけど…ママの美しさにも目を奪われました!!
おっさんが美少年をストーキングする映画
美の渇望は生きる活力となるか?
ルキノ・ビスコンティ「ドイツ三部作」第2弾。
Amazon Prime Videoで鑑賞(字幕,レンタル)。
原作は未読。
アッシェンバッハがタージオに抱いた感情とはなんなのだろう。恋なのか憧れなのか崇拝なのか。そんなことを考えながら観ていた。アイドル・ファンの端くれの視点で考えると、推しを愛でる感覚と同じなのかな、などと思ったりしつつ…
生きる気力を失っていたアッシェンバッハはタージオの美しさに心を打たれ、活力を取り戻していった。それと同じかどうかは分からないが、私は推しの頑張る姿から元気をもらっているし、恩返しの意味も込めて応援しようと思っている。
アッシェンバッハが日頃追い求めていた美とは、努力と創造の果てに生み出されるものであった。しかし、老いと共に作曲も思うように行かなくなり、身も心も疲弊していた。そんな時に出会ったタージオは完成された美を持っていた。性別を超越した美しさである。うっとりするような魅力に溢れていた。
アッシェンバッハは、どんなに頑張っても辿り着けなかったものを持っているタージオに夢中になった。恋と云うより憧れに近いかもしれない。タージオに抱く想望が彼に幸せを与えると同時に、己の醜さを実感させられてしまう。タージオの崇高さに声も掛けられない。とてもプラトニックな感情である。
コレラに感染したアッシェンバッハは、キラキラと輝く海に佇むタージオを見つめながら、その生涯を終えた。明るい未来が待っていそうなタージオに対して、若づくりのための白髪染めが溶けて黒い汗になり、白粉がまるでピエロのような物悲しさを漂わせる。対比が印象的なラストシーンだった。
人生と云うものは、対比に満ちているのかもしれない。幸福と不幸。若さと老い。生と死。本作で描かれていたものは、生きている上で逃れられないものばかりだと思った。
どんな形であれ、「好き」は生きる力となる。その結末が幸せだったとしても不幸せだったとしても、愛を求めて命を燃やした日々は人生にかけがえの無いものを与えてくれる。
※修正(2025/05/27)
よく眠れた
ビスコンティの映画は必ず眠くなるのだけど、その中でも特に眠かった。見始めると5分で眠くなるので、見終わるまで10日くらい掛かった。主人公のおじさんが顔を白塗りにしていたのは、笑った。冗談でやっているのかと思ったらそうではなく、真面目でやっていたのでどうかしている。とてもつまらなかった。
けっこう素でキモい
高校生の時トーマスマンの原作を読みこの映画も観たはずなのに本はともかく映画こんなキモかったっけ?!とビックリした
昔観た後はもっと芸術とは…死とは…若さとは…美のもつ悪魔的誘惑とは…みたいなエモい感情が渦巻いたような気がするのだけど今回はおじさん本当気持ち悪いしなのに顔ドアップ多すぎるし長いしで最後の方ちょっと寝てた
映像だとおじさんのいたたまれなさというか哀れさ道化ぷりが激しく顕著 悲劇というよりむしろ喜劇の描き方だと思う
ビョルンアンドレセンの美しさは言わずもがななんですけど本で読んだ時のイメージとやっぱ違うんだよね
まあ 神々が渾身の力を込め贅の限りを凝らして完成させた史上最強最高傑作芸術作品ビョルンアンドレセンを堪能できるので出来はともかく映像的価値は永遠に下がることはないでしょう
砂時計
マーラーの名曲が響く。対比が美しい。
特に最後のシーン。海と陸。黒と白。直立と座位。若さと老い。生と死。いくら努力しようとも決して到達し得ない美しさ。その美は存在そのものが尊い。砂時計はひっくり返した瞬間からゆっくりとしかし確実に落ちていく。生から死へと。砂が減っているのに気づくのは砂がほとんど落ちてからだと言う。自分の力では到達できない美しさを生命という砂をすり減らしながらみた彼。ベニスでの療養のはずが逆に心身を痛ませる結果になった。砂時計の砂は上にはいかない。それは、美を追求する彼がみたものを忘れることができないように。彼もまた椅子から落ちた。広い砂浜へと。
彼は美を追い求め、その中に沈んでいった。彼がかつて愛していた子の死は彼をより観念的な海に身を沈めさせたのかもしれない。現実の悲壮は現実で癒すか、現実とは遠く離れた場所に訪れることでしか癒えないからだ。後者をとった彼はベニスに死す。優美な化身が海の中で踊るのを目にしながら。
芸術家の死
全62件中、21~40件目を表示