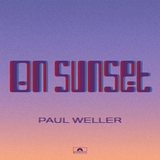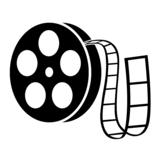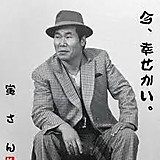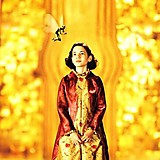未来を生きる君たちへのレビュー・感想・評価
全21件中、1~20件目を表示
憎しみや復讐の連鎖
別居状態の夫婦の子どもでいじめられっ子と、母をガンで失った父子家庭の子どもの2つの家族。いじめられっ子の父はアフリカで医療活動を続け、民族間の争い、殺戮を目の当たりにする一方で、日常生活で言いがかりを付けられた凶暴な男に対して、あくまでも暴力を否定して対応する。
一方、父子家庭の子どもは、母親の病死を経験して父への対応の怒りが心に傷となって残り攻撃的な子どもになっている。
アフリカでの医療活動も殺戮を繰り返すリーダーの怪我をあくまで仕事として治すが、ある一言で切れてしまい、その男を民衆に放り出しリンチに合わされてしまう。非暴力、報復への反対を立場を通しながらも、感情的になり理性を失う。
母を失った子どもは、爆弾を自主製作して、とある大人の車に爆弾を仕掛け復讐しようとするが、巻き添えをくらえそうになる通りがけの親子に注意するために駆け寄ったいじめられっ子が爆発により大怪我をする。
爆発物を使用したことで警察に事情徴収を受ける子どもたち。どうしてこのような事が起きてしまったのか。両親とも精一杯生きているが、子どもにはそれを受け入れられない思いがある。
20131104@WOWOW
難民キャンプでの問題提起
報復と赦しの物語
報復の連鎖をどう断ち切るのか?
深いテーマを背景としながら、スリリングに展開するストーリーに引き込まれました。
破綻した治安やレイシズムといった国際社会の問題と、いじめ、親子の断絶、夫婦の別居といった家族の問題とのオーバーラップ。
それを一つの物語に収束させる作り手の力量。
やられた、って感じです。
現実的な問題であり、かつ哲学的な問題でもある、その問いに
監督なりの一つの思い(いや解答でしょうか)
が示されていたように感じました。
でも、それがこの映画の限界になってしまっているようにも思うのです。
つまり、その思いというか解答というか、それが不正解だとかいうことではなく、
「問いと答え」というとらえ方をされるその形式が
物語の広がりを限定しているような。
道徳的な規範の提示にあやうくなりかけている
その境界線にある映画であるような、そんな気がするのです。
私たちが生きるこの世界に答えはない。
だから私たちは映画を見続けているように思うのです。
でも、いい映画ですよ。
そんなこんなで、評価は4。
親の生き方を子は見て育ついい実例
赦し
どの世界にもある『暴力』それに対して『復讐』するか『赦し』か。
クリスチャンは、理不尽な暴力に暴力で対抗してイジメから逃れる。クリスチャンは、時には暴力が必要だと思わせてしまう。
そんなクリスチャンにアントンは、理不尽な暴力に対して非暴力でいる事で『暴力の連鎖、復讐の連鎖』を教える。
しかしこの映画、決して『非暴力』『赦し』が全て正しい選択と言っている訳ではない。
子供達、そしてアントン自身も選択を迫られるのだ。そしてその選択の結果は正しいのか………
(個人的には、ビッグマンを殺す事は、より良い世界のために必要なのではと思う。)
もっと厳しい現実を見せても良かった。(エリアスの死、ビッグマンを殺した事による報復など)
後で知ったけど子役の2人は、これが初めての演技らしい。凄い
みんな気に入らない邦題タイトルの『未来を生きる君たちへ』聞いた時ダサいなぁと思ったけど観終わった後は、意外にこれで良かったかもしれないと思う。
#映画 #cinema #movie
#未来を生きる君たちへ
#AcademyAwardforBestForeignLanguageFilm #Hævnen #InaBetterWorld
#SusanneBier #スサンネビア
暴力に暴力で応酬してはいけない。そのメッセージを、「いじめ」と「戦...
暴力に暴力で応酬してはいけない。そのメッセージを、「いじめ」と「戦争」という2つの「暴力の現場」から描いた本作。いじめの現場で子供たちは、暴力に暴力でやり返すことで、なめられないようにした。それではいけないと身をもって教えた父も、戦争の現場では愚弄の声に負け、暴力の連鎖に手を貸した。
二つの家族について言えば、すれ違いはあれど愛のある親たちが家族を一つにした。それが紆余曲折を経てハッピーエンドで終わったのはいいことかもしれない。けれど世界の問題はまったく変わらずにそこにある。
変えようとするのは無理なのか?
それはやはり無理なのかもしれないが、やはり諦めてはいけないのだろう。
そういうことを考えさせてくれる良作だった。
映画のラストシーンで流れるアフリカの難民の子供たちの笑顔が印象深い。
医師団の車を追いかけるシーンは映画の冒頭を始め、それ以前にも何度も描かれていたが、そこにどんな意味がわからなかった。ものが欲しいから追いかけているのか。車が珍しいから追いかけているのか。そんな風に思っていた自分が恥ずかしくなる。彼らは感謝していたのだ。自分たちを守ってくれるヒーローに。
手を振る子供たちの笑顔がこの映画のすべてを物語っている。憎しみや暴力は決してなくならずこの世界は悲しみに満ちている。しかし我々はいつだって生きていかなくてはいけない。そうであるなら自分のできる選択をしていくべきなのだ。その揺るぎない信念があればそれがどんな選択であれ、未来は希望に満ちたものになるはずだ。
少しバベル調だけど広く観ていただきたい。
生と死の間には幕がある
近しい人が死ぬ時は、その幕が開く
その幕はスグに下りて、こっちの人間はまたいつも通り生きていく。
この映画には色んな伏線があって、それが意味するのは国際的な情勢の背景や愛だったり。
実は、かれこれ2年前くらいに一度は観てるんですが、たまたま今日また観たんです。
あのときは観た後凹んだんですよね。重くて。
だけど今回また改めて見てみると素晴らしい。
何が素晴らしいって伏線となっている詳細の描き方や風景や景色や空。
ちょいちょい出てくる綺麗な景色など。
それが世界は繋がっているし、どの子供たちも未来を大人として別の環境であれ生きる、そして現大人は、いつか死ぬけれど今の為に何が出来るのか、そして精一杯に今を生きるのだというメッセージが上手に練り込んであります。
多感な少年、バラバラの家族、親と子、友情、大人の事情、貧富の差、挙げたらキリが無い。
兎に角、体系的に捉えることができればポジティブな映画だと思います。
これは何歳に観てほしいかな…
最初に見たときは女性なんで、地球のどこかで残忍かつ悲惨な日常があることに震えあがりましたけどね…
だけど、何処にいても誰でも悪役でも救う側も貧しくても裕福でも愛されたいのは同じなんでしょうね。
親子愛
報復と赦し
アフリカ難民キャンプとデンマークのそれぞれを舞台に、違う世界観の中に垣間見る暴力の存在、それを深い人間像を描き出す中で問題提起してくれるような秀作の一本です。
[暴力の本質は連鎖。振るう方にも痛みはないのか、その痛みは心の痛みでもあるはず] と、以前、違う作品のレビューでも書いたのを覚えています。些細のない口喧嘩でさえ、きっかけはあるし、そのきっかけとは関係ないところで、自身の置かれた環境が心を荒んだものにしてしまうこともあります。
複雑に絡み合っている大人の事情や環境の中で、親は子に重要なことを伝えたいのですが、それが「きれいごと」だとも分かっています。でも、暴力には暴力で!を実行している限り、いつまでもその連鎖は断ち切れないのも知っています。とても難しいことですが、個人レベルならば、(親が、友が、師が、誰かが)包み込んで傷ついた人の心を溶かす機会を与えなければならないのです。温かい一杯のスープを差し出す勇気があればのこと。
この世界は決して生き易くないかもしれません。映像に映し出された、まるでドキュメンタリーの一コマかと思うような冒頭のシーン。「How are you?」と大合唱しながら、南アフリカの子供たちが医療チームのトラックをどこまでも追いかけます。
彼らの笑顔を、今を生きる大人たちが守ってあげなければ、少なくとも、毎朝、目を覚ましてから、その日一日を生きることが苦痛に思えるような子どもを作ってはいけないのだと、ふと、そんなことに思い至った作品でした。 (4.8点)
復讐よりも今を見つめて
言いたい事は分かるけど…
思いを抱え、ぶつかりながら成長する。大人も子供も…
ずっと注目、期待をしていてやっと観れた作品だが期待以上だった。
118分間1秒たりとも無駄な部分が無い。
「赦しと復讐」から始まるドラマ。
それが人間の友情や愛、怒り、全てを形づくる。
何より単純で、何より難しい。
信じられる愛を失い、死と間近に接した少年の目に映る世界、いじめられっ子で心の拠り所を求める少年の目に映る世界、現実、自分と理想に葛藤する男の目に映る世界、愛を裏切った夫を許すことのできない女の目に映る世界。
どの目からも世界は上手く回らず、理想とかけはなれていて薄暗い。
人は皆それぞれに自分の思いを抱え、時には葛藤し、ぶつかりあって生きていく。
本当に単純だが本当に難しい。
脚本、演出、そして俳優、特に主演の少年2人の憂いの演技は素晴らしかった。
また、心情描写が巧みすぎる。
描かれるそれぞれの心の痛みはどんな暴力描写よりも痛々しく、観ている我々の心に突き刺さる。
終始薄暗い世界観であるのに観終えた私達の心は自然と晴れている。
まさに感動とはこのことだ。
勇気と再挑戦。
名画座にて。
第83回アカデミー賞外国語映画賞を受賞したヒューマンドラマ。
さすがS・ビア、人間の愚かな性から一歩も退くことなく描いた。
暴力への対峙、よくいう目には目を。歯には歯を。を貫くべきか。
愚かな暴力には忍耐を持って対抗するべきか。
そんなこと分かっちゃいるけど、黙っていたらやられるばかり…
その辛さから耐えられずに報復に走るイジメの犠牲者は多い。
正確な答えの出ない、いわば人間の価値観と性に依る物語のため、
主人公一家のとる行動と選択に共感できるかどうかが試されるが、
今も止むことのない戦争問題を考えれば、単純に暴力⇔暴力が
正しいはずはないことを誰もが分かっている。
問題はタイトルにもある通り、これからの未来、子供達にそれを
どう伝え、どう育てていくかということなんだろうと思う。
多感な時期、様々な問題に直面した子供達が、自分の正義を由と
して自信をもって行動するためには、大人はどうしたらいいのか。
今作が面白いのは、大人達がそのスペシャリストではないところだ。
浮気が元で妻と別居中の夫、妻に急逝されたことで子供との関係を
保つことができないでいる父親、すぐに暴力にたよる職人、学校で
対処できない問題を家庭に押し付ける教師、難民を虐殺することに
何の抵抗感も持たない悪魔のような男、ろくな大人が出てこない…
結局皆が弱い人間で、欲望にも哀しみにも簡単には抗えないのだ。
(それは当たり前のことなんだけど)
しかし主人公一家の父親とその子供と近しくなる父親の価値観は
ほぼ同等で、子供にとって必要な愛情と真摯な眼差しを向けている。
ここは是非見習いたいところだと思った。
とはいえ学校で執拗なイジメを受けていたり、親友の父親が目前で
殴り倒される場面を見たりすれば、小さな心は傷みに揺れてしまう。
そのわずかな傷みが何を引き起こすかを監督は執拗に追いかけ描く。
誰もが誰もを認め合い、赦し合う時代はやってくるのだろうか。
やられてもやり返さない姿勢を臆病ではなく勇気だといえる時代。
イジメっ子を制するにはその倍返しで痛めつける方法が一番なのか。
暴力に訴えない方法はすぐに効果をみないが、損害を与える相手が
何のリアクションも示さなければ、いじめる側はいつかは諦めないか。
でもそれはだらしなくて卑怯な考え方だろうか。
日本が戦争に加担しないのは、それ相応の理由があるからである。
やれ卑怯だの臆病だのとどんなに言われても退いてはいけない勇気。
主人公の息子があれだけ虐められているにも拘らず、一日も休まず
学校へ通う勇気と、他人に見せる思いやりや笑顔を奪ってはいけない。
むしろあの勇気を見習うべきところである。
物語の後半は、赦しと癒しがテーマになってくる。
攻撃と悲劇の顛末は夫婦や親子や友人の赦しに依る再生で終わる。
最近知った言葉だが(某番組にて)、
何かとリベンジ(復讐)という言葉を掲げることが多い昨今、
これじゃなくてリトライ(再挑戦)を使った方が良くないかと思う。
何度でもリトライする根性をもつことで、人生はより良くできないか。
相手を許せないのは、ほとんどが自分の気質と考え方に依るもので、
自分の懐の狭さを考えさせてくれるのが、今作の最大の特徴である。
(人生リトライし続けるべきか。赦しを乞いたいことがありすぎまして^^;)
浄化
全体を見渡せば、至ってシンプルな構図となっています。
つまり前半は、誤解とわだかまり、暴力が積算されて、次第に熱が高まり混濁が極まり、未熟さゆえの爆発へ。
クリスチャンの悲鳴と、エリアスの母の慟哭が繋がり、この二人の対峙によって、本作の憎悪と緊張は頂点を迎えます。
後半は、和解と赦し、触れあいの除によって、深く静かで透明な、澄みきった世界を取り戻していきます。
『右の頬を打たれたら…』『汝、姦淫するなかれ』といった聖書から(?)の小節を連想させるシーンもありますが、
『罪と罰』あるいは贖罪あるいは赦し、そういった主題探しも、安易な処方箋を模索することも
本作を味わう助けとはならないでしょう。
自然光の中で、カメラが寄って捉える役者たちのわずかな仕種、首をかしげたり視線を変えるさまから滲みでる感情の移ろい。ほっと息をつくように挿入される穏やかな風景。
きめ細やかに紡ぎだされ織り成された、まるで生命さえ持ったかのような美しいフィルムに、ただ没頭するより他ないでしょう。
異なった世界をひとつに。
さらに、それらをこれほど異なった様相で提示してみせる手腕は、決して大袈裟手でなく当代一と言えるでしょう。
2011年、ベスト。
全21件中、1~20件目を表示