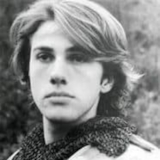太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男のレビュー・感想・評価
全58件中、1~20件目を表示
タイ・ラヨンでの撮影は経験したことのない暑さ
太平洋戦争末期のサイパン島で、米兵から“フォックス”と呼ばれて恐れられた陸軍大尉・大場栄。たった47人の兵を率い、4万5000人の米軍に立ち向かったという史実を題材にした実録小説を原作に、決して諦めずに生き抜いた日本兵たちの姿を竹野内豊主演で映画化した。
撮影はサイパンではなく、タイ南部の街ラヨンの海軍基地内(ジャングル)で行われた。気温は軽く40度を超え、肌感覚としてはずっとサウナにいるような気分のなか、大粒の汗を流しながら取材したことは忘れようがない。キャストそれぞれが真摯な面持ちで役に向き合い、かつて日本にいる大切な人達を守るために戦場へ赴いた男たちの思いを汲み取っているように感じ取った。
竹野内や唐沢寿明の立ち居振る舞いはもちろんだが、共演した岡田義徳の言葉が印象的だった。
「場所に酔わないようにしたい。自分がいい作品を撮っている気になる。一歩引いたところから見つめないと……」。
映画人たちも、必死に戦った作品と思えば、また違った見え方がしてくると思います。
撃たれるから撃つ、撃たれる前に撃つ
やはりガリガリに痩せ目玉ギョロギョロの人相。
飢え死にする兵も多かったから。
大場大尉率いる連隊が集合した面々、
何も言わずとも腹減った〜が伝わって来た。
wikiで大場栄を検索、
帰国後は、会社社長や政治家となる。
兵士になる前は教員資格取得、教鞭もとったらしい。
その人物像からなのかはわからないが、
米軍日本贔屓大尉に尊敬されていた、とは⁉️
恥ずかしながら本作で初めて知ったことは、
サイパン島では日本人が居住していたということ。
だから日本兵が従軍したのか、と。
激戦地サイパンは知っていた。
その戦地に駆り出されたのだと思っていた。
大正から日本家屋があり村が存在していた。
本作は戦争モノとしては好みの作品である。
主人公並びに周りの者も生還したからである。
アメリカ🇺🇸軍の様子も描かれ、
当たり前ながら同じ人間だとわかる。
同じく敵を嫌がり怖がり自分たちも命が惜しい。
降伏という言葉には抵抗あるだろうけど、
殺し合わない方法を選んでくれて良かった。
それが嬉しい、事実を元にしているのも尚更。
ただ
(ここの🇺🇸兵には関係ないけど、広島長崎があるけどね。)という一文挟む自分納得できないところもあるが。
本作は、米軍側視点、日本側視点が交互して展開されます これが今までの日本の戦争映画にない特色です
太平洋の奇跡 -フォックスと呼ばれた男
2011年公開
サイパンの戦いは1944年6月15日から7月9日にありました
サイパン島から東京までは2400キロほど
サイパン島はグァム島の北200キロ
当時の世界最大最新の巨大爆撃機Bー29が燃料と爆弾を満載して東京まで往復できるギリギリの所にあります
つまりここを米軍に占領されると東京が本格的に爆撃され、焼け野原にされてしまいます
なので、日本軍もこの島の死活的な重要性は良くわかっていて絶対国防圏と名付けて死守しようとしていました
が、戦局は既に劣勢で大きな兵力を送ることもままならないまま米軍の侵攻をうけました
米軍の輸送船団を護衛する米艦隊と日本の連合艦隊との決戦も6月19日に起きましたが、一方的なほどの完敗に終わりました
劇中で海軍陸戦隊の指揮官が連合艦隊はそこまで来ているのだと言っていますが、すでに海の藻屑になっていました
サイパン島の戦いは1944年6月15日に猛烈な艦砲射撃のあと米軍の上陸が行われ半月ほどで全島が占領されました
2万人ほどの島民が居住していましたので、1年ほど後の沖縄戦と同様の悲惨な民間人を巻き込んだ
戦いとなりました
本作はジャンルに覆われた山の中に逃げこんだ陸軍の生き残り部隊と島民の民間人200人ほどがそれからどうなったかが描かれます
期間は1944年7月上旬から翌1945年12月1日までの半年間のこと
つまり本土との通信もできず終戦も知らないでいたのです
その間、掃討戦を行う米軍から逃れながら、家も、飲料水も食糧も、薬品もなく、ジャングルの山中を逃げ隠れして、さ迷っていたのです
その中で指揮を執っていたのは、大場栄大尉でした
実在の人物で、当時30歳、元小学校教諭、23歳で出征、サイパン島には1944年2月に着任、戦後は市議会議員などをなされていたそうです
彼の展開した巧妙なゲリラ戦により、米軍は翻弄され、いつしか彼をフォックスと呼んで怖れるまでになります
これは実話で、この戦いに伍長としてに参加した米海兵隊員が戦後、書いた本が原作として映画化されたものです
原作は1980年代に日米で刊行されました
「硫黄島からの手紙」は2006年のクリントイーストウッド監督の映画
1945年2月から3月にかけて行われた硫黄島の戦いを日本側視点で描いた映画でした
恐らくこれのヒットを受けての本作の映画化かと思われます
渡辺謙が主人公の栗林中将を演じて、死に急ごうとする部下を押し止めて持久戦を展開する物語でしたから、本作に少し内容が似ています
また、岡本喜八監督の「激動の昭和史 沖縄決戦」にも題材は類似しています
以下ネタバレです
しかし、クライマックスの1945年12月1日の投降式のシーンには、そのどちらにもないもので、本当は硫黄島も沖縄戦もこのようになるべきだったと思えるものでした
部下には死に急がせることなく、民間人には収容所の人道状況を確かめた上で米軍への投降を勧めて、最後の最後にプライドを保って米軍指揮官に部隊で行進して投降を行うのです
とはいえ、大場大尉もそのような決断ができたのも、8月15日の玉音放送と、9月2日の降伏文書調印式があったからこそです
硫黄島の戦いと沖縄戦は、それ以前のことですから、大場大尉のような行動はとれなかったのです
本作は、米軍側視点、日本側視点が交互して展開されます
これが今までの日本の戦争映画にない特色です
これによって、日本側の視点を客観的に観ることができる効果があります
玉砕という自己陶酔に共感することなく、それを軍人の責任放棄では無いのかという批判的な視点を持って観ることができます
自分には1944年12月7日公開の木下恵介監督の「陸軍」という映画の続編のように感じました
陸軍省の後援映画ですから間違いなくプロパガンダ映画ですが、不思議なことに反戦のメッセージを感じる作品です
その作品では、日本陸軍というものは長州藩の奇兵隊を源流とし攘夷を実行する組織であり、それゆえに無謀であっても対米戦争は必然的なのだと説明しようとした映画にみえました
本作は、その結果がどうなるのかという続編と言うわけです
本作では陸軍の大場大尉が海軍の陸戦隊に食糧などを分けて欲しいと要請して断られるシーンがあります
まるで、長州藩と薩摩藩との会話のようでした
つまり、日本軍は国民の為の軍隊ではなく、攘夷を行う為の軍隊だったというシーンにみえました
やがて大場大尉は、陸軍はそんなものでは無く、本来、国民を守る為の軍隊であるべきではないのかとの考えに転換された結果、クライマックスのような結論にいたることができたのです
米軍視点パートは米ユニットで撮影されており、主なロケ地はタイで撮影されており、従来の日本の戦争映画にはない洋画的感覚に仕上がっています
戦闘シーンも迫力十分なもので、単なる銃声だけでなく、銃弾がすぐ近くをかすめ去っていく音響効果も多様されています
日本軍側視点パートでは大場大尉役の竹野内豊さんが素晴らしく、本当の昔の軍人にみえました
また、刺青のある一等兵を演じた唐沢寿明さんも強烈な印象を残しました
蛇足
台湾有事が近づいている不安をかんじます
もはや、攘夷を真面目にやろうなんて組織はあるはずもありません
本当に?
有事にそなえ、離島からの民間人の避難計画を進めようとすると反対する人がいるそうです
全く逆なのに玉砕を主張する軍人達のように感じます
長年染み付いた考えに凝り固まってしまっているのでしょうか?
うん、
大場大尉の生きざま
大場大尉が民間人を収容所へ送ることを決めた時の演説。
「日本に帰った暁には、タッポーチョ山で過ごした兵隊のことを思い出してください。それで我々の記憶は、日本へ帰ることができます」
これほんまヤバイ
大葉栄大尉の行動を通じて、日本に足りなかったものを考えさせられた
平山秀幸監督による2011年製作(128分/G)日本映画、配給:東宝、劇場公開日:2011年2月11日。
未読だが、敵将であったドン・ジョーンズによる原作によるらしい。玉砕が普通で民間人を平気で巻き込む戦闘が当たり前だっただけに、民間人は捕虜として差し出し、最後まで部下を統率して闘い続けた大場栄への大いなる興味は湧き立った。
ただ、彼に関する資料が残っておらず仕方が無いところがあるが、どういう思いで彼がそういう行動をとったのか分からず、大いなるモヤモヤは残ってしまった。まあ、軍士官学校出ではなく学校の先生だったキャリアが、まともな判断をもたらした様であったが。
そうすると軍大では何を教えていたのだろうか?最後まで抵抗する、或いは捕虜となって撹乱を図る方が、玉砕よりよほど戦争目的に合致していると思うのだが。あと、戦後もずっと生きていたのに、大場栄の類稀なリーダーシップ等に関して、なぜ自衛隊等からきちんとした聞き取り調査がなされていないのか?結局、戦争を科学的に捉えることができない国ということなのか?設備ばかりにお金掛けても、国防に重要な大事なとこが抜けている様な。
大場大尉を尊敬するルイス大尉を演じたショーン・マクゴーワンはとても好演だと思ったが、日本兵を説明するのに、敵にそのまま簡単に使われる将棋の駒の例えは相応しくないと思ってしまった。日本軍を買い被りすぎだとも。
実際、大場大尉が終戦情報が流れてもその確認も取らず、12/1にようやく上官の命令で初めて降伏するというのは、部下の生死を握る大尉としては、教育のせいにしても、いただけないと思ってしまった。映画を作ってる方々のカッコ良いだろう演出とは裏腹に、大尉レベルで自ら最善を思考し自律的に動けない部隊など、戦争の役に立ちえない、本質的にカッコ悪いと思えてしまったのだ。
日本人は物量で米国に負けたと思っているが、本質的には考え方(合理性や科学的思考力)の差で負けたことを、悔しいが、痛感させられた。
監督平山秀幸、原作ドン・ジョーンズ、音楽加古隆、US監督チェリン・グラック、大場栄大尉竹野内豊、堀内今朝松 一等兵唐沢寿明、青野千恵子井上真央、木谷敏男曹長山田孝之、奥野春子中嶋朋子、尾藤三郎軍曹岡田義徳、金原少尉板尾創路、永田少将光石研、池上上等兵柄本時生、伴野少尉近藤芳正、馬場明夫酒井敏也、大城一雄ベンガル、元木末吉阿部サダヲ、堀内今朝松 一等兵唐沢寿明。
総合的には良かったです
サイパンでの戦いはあまりよく知らないのですが、戦争映画とはいえフィクションなのでそう思って観ると良かったのかなとは思います。
ちょっと気になったのは、外国人俳優さんのセリフがあまりにも日本語が流暢すぎて、2年間の留学とは思えなかったですね。
外国人特有の日本語のイントネーションなんですが、そんな言葉知ってるの?とか文章に違和感無いとかちょっとご都合主義な設定なのかなと思います。
あと、将棋の例えのシーンがいまいちよく分からなかったですね。
本当にそういうシーンが事実としてあった出来事なら仕方ないですが、なんか無理やり日本びいきのシーンを入れました感が凄くて、必要性を感じなかったです。
例えの意味も伝わりづらかったですし、あのシーンだけはちょっとしらけました。
総じて綺麗な設定と展開だなと感じました。
戦争は悪
...............................................................................................................................................
太平洋戦争中にサイパンで日米が争う。
日本軍の総司令官は竹之内で、知的な戦術を使うため米軍からFOXと呼ばれた。
しかし戦力は圧倒的に劣っていたため、まもなく絶望的状況になる。
そこに捕虜になっていた阿部が降伏を勧めに来るも受けず。
というか、唐沢がいらん事したのが悪いねんけど。
しかしこれで捕虜への手厚い待遇を知った竹之内は、一般市民を降伏させる。
薬や食料の類がもう底をついていたからだった。
やがて日本が降伏して終戦し、竹之内も降伏を決める。
...............................................................................................................................................
大場大尉という人は知らなかったけど、優れた人だったようだ。
戦争のため多くの命を失いはしたが、彼の英断で多くの人が命を救われた。
それにしても日本軍が米軍を鬼畜と呼び、捕まれば虐殺されると吹聴したのは、
戦争における最大の悪の1つだったように思う。
原爆が最大の悪と言われがちだが、それに十分匹敵すると思う。
この洗脳のせいでどれだけの人が自決や玉砕の道を選んだのだろうか?
でもやっぱり減点となるのが、字幕。敵軍の英語のセリフが多すぎ。
何かをしながら映画を見る事を旨とするおれには、それが苦痛。
強いシーンは何処に?
戦争系、実話好きな人は見るべき映画の1つです。
ただ、、
戦争中と戦争終結のリアルな日本の感情が渦巻いているため雰囲気は凄く伝わりました。
さすが竹之内豊と山田孝之です。
ただ単刀直入に言います。
太平洋戦争で最強と言われた日本兵、通称「FOX」ですが、言うてそんな強いか?と思いました。
知能戦にしてはそこまで恐れられるくらいの内容か?と正直思った人もいたかと思います。
戦争映画なのでナイーブな部分はあるかと思いますが、見出しの最強に重点を置きすぎたか?
という印象はぬぐえなかったところはマイナスポイントでした。
無駄な命を犠牲にしない賢いリーダー
玉砕より投降(降伏)を選んだ男
2011年(日本)平山秀幸監督作品。
ナレーターがアメリカ兵の英語ですので、日米合作映画かと一瞬
思いました。
なるほど原作がアメリカ兵だったドン・ジョーンズの実録小説・・・
『タッポーチョ「敵ながら天晴」大場隊の勇戦512日』を原作としていたのですね。
当時(1944年)敗色濃い日本軍は45000の米兵に対して数百人しか残っていなかった。
ただし、日本の民間人が150人位も生活してたのですね。
大場は逃げ延びる途中で、民間人の投降をいち早く促しています。
大場の隊はゲリラ化してタッポーチョ山中を駆け巡り神出鬼没でアメリカ兵を翻弄した・・・
これも事実なのですね。
そして生き残った日本軍の大場大尉率いる連隊は、最終的に死ぬことより生きることを選びます。
アメリカ兵の攻撃から512日間も生き延びたのです。
投降したのは1945年の12月のこと。
ポチダム宣言でとっくに第二次世界大戦が終わっており、
日本軍が戦争に負けた事すらサイパン島の日本兵は知らなかったのです。
アメリカ人の目線の原作ですので、多少の違和感もありますし、米兵が友好的で、
“なわけあるかい・・・”的描写も多いです。
しかし大場栄と言う方は聡明な生き方上手な方とお見受けします。
地理教諭をしていた1934年20歳で徴兵を受けて陸軍に入営。
そして将校を目指して出世を重ねて大尉となる。
リーダーの器だったんですね。
1945年12月1日の投降の際の式たりは投降式典に則って行われたのです。
映画は全く嘘がなくその通りだったそうです。
投降のシーンは厳かで感動的でしたね。
(降伏の証として、軍刀をアメリカ軍将校に手渡した証拠の写真は現存しているそうです)
(アメリ人が写したと言うことでしょう、作者のドンさんかもしれませんね)
大場栄大尉は、アメリカ人からも日本人からも尊敬される立派な方だったのですね。
やはり当時の日本兵の決断としてはミラクル!
まさに『太平洋の奇跡』ですね。
太平洋戦争末期のサイパン、米軍から「フォックス」と呼ばれ畏れられた...
タイトルなし
終戦後3ヶ月以上、戦中から計500日以上に亘って少ない食糧、物資の中、サイパンの山奥で民間人合わせて200人以上を統率し、ラスト投降迄導いた大場大尉の史実は知らなかったし、素晴らしい。しかし、演出が残念。途中助ける赤ん坊や、出演者それぞれの描き方が中途半端。唐沢寿明とか中島ひろ子とか。特に中島ひろ子の演じ方は好きになれない。またアメリカの収容所に大尉自ら忍び込むってのは有り得ないと思った。
自己犠牲と投降の狭間
大げさ
心意気や良し
題材は嫌いじゃないけど、
演出がダメだ。説明台詞多すぎ。げんなり。
もっと大場大尉(竹野内豊)の人間味溢れるところを膨らまして、
言うなればもっと彼の顔アップのシーン多めで、
彼と関わる人々の心の動きを、説明無しで、表現すれば、
もっと染みる作品になったのではないか。
それを、戦争のしんどさを見せたいのか、
中途半端に戦闘シーン織り込んで流れを断ち切ったり、
目立つ役者を並べすぎてその良さを相殺してしまったり、
いくら史実に基づくとはいえ、
急に進んだり止まったり、話の転がりが悪い。
あと邦画の中での日本兵の狂気ぶり、
ここでもかなり過剰に(特に山田孝之)表現されてる。
この時期の日本人は特別だったんだよ、的に見えて、
その演出が言い訳がましくて逆にむかつく。
日本人がまともな戦争映画作れるのには
まだ50年くらい早いのかな。
全58件中、1~20件目を表示