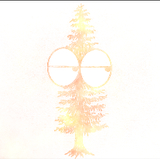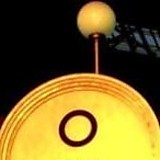ゲゲゲの女房のレビュー・感想・評価
全25件中、1~20件目を表示
勿体ねえ!!
水木しげるの漫画や人柄にハマりこの映画を見た。
朝ドラも世代じゃなかったから主題歌の「ありがとう」を知ってるくらい。話自体は奥さんが主体だから、どういうストーリーなのかと思ってた。
見てみると、戦後の雰囲気と今とは違う男尊女卑の価値観が描かれていた。勿論のように女性の結婚相手は親が決めるし、また姑も息子(この映画での水木しげる)ばかりを気遣って、奥さんの事は息子の使用人みたいな扱いだった。愛はあるけどね。
この当時、左手を失った人は働くのにはあまり向いていなかっただろうなぁとか、当時はSFが流行ってきていて妖怪ものは売れなかったのか、、とか色々時代背景含めて考えることがあった。
これだけなら星3くらいだったが、奥さんが漫画の原稿を出版社に持ち込む時、車がビュンビュン走っているわ、駅前にいるわ、その帰りには田んぼの奥に団地が建ってるわで、時代感が無茶苦茶だった。
監督はそこも含めて、時代の変わりようなどを示していたのかもしれないが、私としてはノイズだった。
色々考えてたのに、時代設定どうなってんねん!とツッコミを入れなきゃいけなくなっちゃったからね
描きたいもの
魂込めて描いてるのが伝わらない
NHKの朝ドラは鑑賞済み。歴史の長い朝ドラでも5本の指に入ると言っても過言でない程、それはもうおもしろかった!
対して映画版は、終始、映像もストーリーも暗く地味。
一言で表すなら、ひたすら、極貧生活を過ごしながら「これでしか生きられない」と妖怪漫画を描き続け、チャンスが巡って来た所でおしまい!のストーリー。この先が観たかったのに〜!とがっかりした。
二人はお見合いして五日後に結婚したのだから、二人の間に愛はない。育っていく愛と言えばそうなんだけど、期待してるものとは違う。「こういう運命だったんだから受け入れるしかない」という感じ。
それでも、お見合いで「生活は安定してる」と聞いていたのに、実際は、電気止まる、食材買えない、質札てんこもり、2階に間借りしてる男もいるの最悪な結婚生活。
茂が悪い男ではなかった事が唯一の救い。
観客としては、もう少しいろんな背景を知りたいところ。茂は一人でも生活が苦しい中、結婚しようと思った理由とか、そもそもなぜ漫画家になろうと思ったか、水木作品は不人気だったのにチャンスをもらえた理由とか。
ちょいちょい入る妖怪はやめた方がよかった!演出が下手すぎて妖怪に見えないし、入れる必要性がない。ストーリーが原作に忠実路線なのに、ファンタジーが入ってバランスが不自然!!怒
あと、ロケでの撮影が現代過ぎて最悪。興醒め。
原作はいいのに、作り手が違うとこうも違うという悪い見本になってしまった。とにかく、演出が下手だし作品に愛がない!
朝ドラでは、茂が片手で命込めて描いてるのが映像で伝わって来た。布絵もアシスタントして、夫婦二人で命を込めて描いてた。なのに、映画ではひょいと描いてる感じになって非常に残念。
完全に裏切られました
背景が
同年、NHK朝の連ドラで大ヒットした『ゲゲゲの女房』。すべてを観...
同年、NHK朝の連ドラで大ヒットした『ゲゲゲの女房』。すべてを観たわけではないが、もっと明るい家庭だった印象が残っていた。それをこの映画では赤貧時代だけにスポットを当て、暗さを強調しているかのよう。 時折、パラパラ漫画風のアニメーションを挿入していたことや、普通の人には見えない妖怪の姿が微笑ましい。
貧乏の様子と言えば、質札がかなり増えてきた様子と、税務署が年収18万円という申告に疑いを持って訪ねてくるところも強烈だった。編集の人が訪ねてきても、水と大根しか出せなかったりするが、野垂れ死にしそうな漫画家に食事を与えたりするところも人情味があってよかった。
夫の仕事のアシスタントを兼ねる主婦。ようやく夫と意思疎通が出来たような布枝。少年誌の編集者に「宇宙ものを描いてほしい」と言われても、苦手なジャンルだときっぱり断るとこにも反論を加えない。貧乏であっても黙って夫に従う昭和の妻といった印象さえあるが、テレビ版を見なければよくわからないのかもしれない・・・
奥さんが素晴らしい!
朝ドラを見ていないので、分からないけれど、水木しげるさんと結婚した当時の暮らしに怒らない奥さんが凄いな、と思った!そういう時代だったのかな。
クドカン合ってたね
朝ドラを見逃したため、映画で…
と思ったものの観たら少し疲れました。
なんでだろう…貧乏だからかな…
そぉ、貧乏だけど温かい家庭って言うのが描ききれてなくて全体的な暗い雰囲気と終わり方が中途半端な感じがしたからかも…
そもそも女房役は吹石じゃない。
幸薄そうだけど芯がある木村多江とかさ。
まぁ年齢的に難しいか…
水木さんも、もぉ少しズングリな方が…
でもクドカンは合ってたと言えば合ってた。
特に手がなくて痩せてる姿は、若い頃の水木さんを感じますね。
貧乏は全然苦にならない。
命までは取られないから…と言うシーン。
こんな人と結婚するのは御免だと思う反面、こんな人だけど漫画家としての彼の才能に惹かれた、彼の奥さんは素晴らしいと思えました。
新宿の木村屋のカレーとコーヒーとキャンディ
わたしも頑張らなきゃ!!
●嫁さんがエライ。
朝ドラ以外ゲゲゲ
カッコいい日本人
題材に対して...
細かいけどマズいミスが目立ち、ゲゲゲッ!と感じてしまった
「ゲゲゲの鬼太郎」で知られる漫画家・水木しげるの妻・布枝が、極貧時代からの夫婦愛のエピソードを記したエッセイの映画化。
NHKの連続テレビ小説でも映像化されており、もはや国民的物語となった感がある。
NHKのドラマでは松下奈緒&向井理の旬なカップリングで温かな人情ドラマとして描いて大好評を博した(未見だけど)。
映画版では吹石一恵&宮藤官九郎の異色のカップリングで淡々とした語り口で描かれている。
NHKドラマ版のファンの方はあまりの違いさには度肝を抜かれるだろうが、似たような雰囲気だと二番煎じと言われる為(最も、ブームの最中に立て続けに映像化され、二番煎じと言われても仕方ないと思うが)、これはこれで正解。
クドカンの水木しげるはイケメンの向井理よりしっくりくるし、地味な映画版はNHKドラマ版より史実に似通ってるだろう。
ただ、映画版には致命的なミスが。
昭和の香りが全く感じられない。
セット撮影は別として、ロケーションが、その辺で撮影しました感丸出しなのである。
特に、超高層ビルが映るシーンは変…というより、明らかにマズいでしょう。
しかも、その次のシーンで昭和風のボロボロの服を着た人が映り、一体何時代なの?と思わせる。
また、所々唐突に妖怪が登場するのも“?”。
妖怪漫画の大御所の伝記なので、妖怪を登場させて独特の演出(センス?)を狙ったのか分からないが、どういう意図なのかずっと違和感を感じた。
細かい点かもしれないが、こういう細かい点をしっかりやってこそ映画は成り立つので、その点を疎かにした本作の点数は敢えて低く。
(プラスになるか分からないが、エンディングの歌はユニークで良かった)
今度、NHKドラマ版と見比べてみようかな?(DVD出てたっけ?)
キャスト、演技には不満はないのだが…
朝ドラとは全くの別物です。暗い。
しかし、こっちの方が真実に近いのではないか?など思ってしまいましたが、さすがに高層ビルでたりしたのは、「あれ?これ昭和何年頃の話?」なんて思っちゃいました。
超低予算で作ったというより、ただカメラ回しました的な感じもします。
仮装した感100%の妖怪?オバケ?よくわからない人達…
嫌いではないんです…
出てる役者の方々は好きな方なのですが…
頭を抱える映画でした。
水木氏を支えた妻ってホントはどうなの?これは違う気がするけれど?
NHKの朝ドラを観ていない私には何の先入観も無く素直に作品に入り込めたのだが、あの水木しげるさんが本格デビューをするまでの貸し本屋時代の極貧の下済みの苦労の半生を女房殿の視点で描いている作品にしては、盛り上がりに欠けている点が少し残念でした。
朝ドラで人気を博した作品は、それと比較され、それだけでも映画化する事自体難しい点が多いと思うのだが、戦後日本の高度成長期に差し掛かる昭和30年半ばの激動の時代をかくもこれ程までに淡々と描いてしまって良いのだろうか?と言う疑問が涌いた。
東京オリンピックを3年後に控えた日本では、焼け野原の東京の街からオリンピックへ向けての復興が急ピッチで勧められていた時代だ。そろそろ自由恋愛で結婚する若者達が増える時代の中で、当時の地方に暮す娘としては晩婚になってしまう布枝が、親類の勧めでお見合い結婚し、当初見合い話で聴き及んでいた条件と、嫁ぎ先での実際の生活状況があまりに違う事で、新婚の新婦はうろたえるが、共に生活をする中で本当の家族、夫婦へと成長していくと言う物語。昭和一桁生れの布枝が、10歳も年上でしかも、南方で負傷して片腕を無くし、帰還した男の妻になると言うには、布枝の態度は少しばかり水木に対して理解に欠けている様に描いていると思うのだ。個人差も有るだろうが、この時代は未だ未だ戦後の混乱から完全に立ち直って復興を遂げた時代では決してなく、一般庶民の生活は物質的にも、まだ貧しい時代でもあり、みんなが貧乏でも助け合っていた時代だと思うのだ。そして人々の人情も厚い時代だと思われるのだ。その日に食べる米を調達するのがやっとと言うのも、サラリーマン家庭でなければ珍しい事でも無い。
まあ、しかし貸し本屋を覗いては、夫の本が面白いと本屋の主人に哀願するところはほほえましいが、戦争中最も激しい戦闘が行われていた南方で、腕を失った水木氏は地獄を見たに違いない。それ故人間の恐ろしい一面を嫌と言う程に体験し、人にとって何が大切なのかを悟って帰還したこの若き兵士。孤高の信念を貫く漫画家の妻の姿としては、いささか不自然な気がしてならないのだ。貧乏は苦労とは思わず、自分の信じる漫画を描き続ける水木さんだからこそ、彼の描く作品には妖怪でありながら、心をほっとさせるものが有り、きっと本当に妖怪も心を動かされきっと後押ししていたに違いない。
2階の下宿人と、出版社から後を追って来た若い漫画家の卵の青年達みんなで食卓を囲むシーンでは、すっかり布枝も水木婦人に納まったと言う象徴的なシーンで観ている私はほっと肩を撫で下ろした。しかしこの若い青年が後に餓死してしまう。もしこの青年が、ときわ荘にでも行き着いて、漫画家を目指したなら亡くなる事も無かったに違いないと残念に思う。昭和のこの時代に活躍した、多くの漫画家達が描いたその作品群からは、今の私達が学ぶべき点が本当に凝縮されている気が私はする。
只たんに懐古主義的に昔を懐かしいから、そう言うのでは決してない。年間自殺者3万人の記録を10年以上も更新するこの我が国の現状を社会全体で考え直そうとせずに、政治家先生も中々目先の事ばかりで、長く続く未来の日本の国益を考えて政治に臨んでくれているとは決して思えない現在、何処かでボタンを掛け違えてしまったのだろう。今一度私達は、新しいビジョンを各々が持ち、自分の夢と信念を持ち、自分に出来る事を真剣に取り組んで生きる事を、この映画は教えてくれた気がするのだが、貴方はこの映画をどう読むのだろうか?
これはヒドイ
面白くない映画のレビューは極力書かないようにしているけど、この作品はそれを突き抜けた。作品と呼んで良いのかとさえ思う。
まず何を伝えたいのか分からない。もし水木夫婦の自伝的なものなら、時代設定が滅茶苦茶だ。現在の街並みを写したりしたらダメでしょ!高層ビルや最近のバスなんかを平気で見せてる。途中で出てくる妖怪や意味の分からない人は何?完全フィクションで現在にワープした水木夫婦の妖怪生活みたいな設定なら少しは分かるけど、意味不明に妖怪を登場させるから、ラストシーンの火の玉さえ意味不明に感じてしまう。本来ならジーンとする場面であるはずなのに…
連ドラ人気にあやかって適当に作ったとしか思えない。水木しげる先生はこの映画をどう思うだろうか?
とてもプロが作った作品とは思えませんでした。映画を愛する者として残念です。
ほんわかした
全25件中、1~20件目を表示