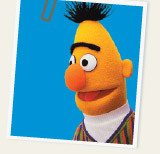グラン・トリノのレビュー・感想・評価
全265件中、241~260件目を表示
ヒーローのラストシーン
俳優としては最後と言われるこの作品
この映画としては、想定内のラストですが・・・・
クリント・イーストウッドがヒーローとしての
ラストシーンを演じたとすれば、非常に感慨深い
ものがあります。
不死身のヒーローの最期とは、これだ!!
欲するなら,まず与えよ.
この映画の主人公ウォルターの周りには,
与えることに無関心で,
欲することしか知らない人たちばかりがいた.
ソファが欲しいとか,宝石が欲しいとか,
野球のチケットが欲しいとか,
そういう連中ばかりに囲まれて暮らして来たがために,
ウォルターはすっかり偏屈になってしまっていた.
電話がかかってきたり,人が家に訪ねてきたりすると,
彼は挨拶も抜きにして,まず相手の要件を尋ねる.
「で,何が欲しい?」
彼に言わせれば,人が電話をかけて来たり
家に訪ねてきたりする理由は常に決まっているのだった.
挨拶の言葉やそれに続く世間話などは,
相手が要件を持ち出すまでの前置き,
つまりはご機嫌取りの欺瞞でしかない.
そのような状況の中で,
ウォルターの家の隣に引っ越して来た人たちだけは違った.
その人たちは,与えることを知っている人たちだった.
隣の家の娘は,
不健康な食生活を送っているヤモメ暮らしのウォルターに
おいしい食べ物があるからと言って,
自宅のパーティーに来るよう誘ってくれた.
ウォルターがある時,隣の家の少年を助けると,
その日以来,彼の家には,花や食べ物などの贈り物を
お礼として届ける少年の親族の人たちの列が絶えなくなった.
ウォルターは,自分の死後,
持ち物をすべてこのモン族の人たちに譲った.
一番の宝物であるヴィンテージ・カー「グラン・トリノ」も,
このモン族の少年に与えられた.
ウォルターがかわいがっていた犬は
モン族のおばあさんに与えられた.
いわば赤の他人であるモン族の人たちが
様々なものを譲り受ける一方で,
身内であるはずのアメリカ人家族の人たちには
何一つ与えられなかった.
欲するなら,まず与えよ.
欲することしか知らぬ者には,
何一つとして与えられないのだ.
しかし,そんな彼らも一度だけ
ウォルターに贈り物をしたことがあった.
ボタンの大きな電話機と老人ホームのパンフレット.
ただしこれは,厄介払いしたいという彼らの思惑が
透けて見えるものだった.
ボタンの大きな電話機は,老人であることの自覚を
ウォルターにうながすための小道具でしかない.
これらの物の贈り主らは,結局,
自分たちのことしか考えていないのだ.
「欲するなら,まず与えよ」の利他精神が
彼らに理解されることはまずない.
この利他精神こそ,
ウォルターが人生最後の瞬間に実践して見せたものだった.
彼は,モン族の人たちが町の無法者らによって
苦しめられていると知ったとき,
この精神にのっとって行動したのだった.
誰かを助けるためには,
まず自分が犠牲にならなければならない.
ウォルターは,命と引き換えに
モン族の人々の苦しみを取り除いた.
具体的に言うと,丸腰で無法者らに挑み,
無抵抗のまま奴らの一斉射撃を受けることによって,
奴らを一人残らず刑務所送りにし,
社会から追放したのだ.
彼がこのやり方を思いついた背景には,
過去の戦争体験があったものと思われる.
彼はかつて朝鮮戦争に従軍し,多数の敵を殺した.
しかもそれは軍の命令で仕方なくやったことではなく,
自分の意思で,自分のためにやったことだった.
(彼自身が神父を相手にそう語る)
しかし,それによって彼が得たものは何もなかった.
期待した充足感や勝利のよろこびは得られず,
罪の意識だけが後に残った.
もしこれが誰かのために,
誰かを守るためにやったことだったとしたら
結果は違っていたかもしれない.
だからこそ彼は無法者連中との対決を
ためらわなかったのだろう.
自分のためではなくモン族の人たちのために行う戦いは,
きっとかつての戦争での戦いとは
違った結果を彼にもたらしてくれる.
彼にはその確信があったのだ.
彼は,この最後の戦いを一人で行った.
本当は,彼にも一人味方がいたのだ.
しかし彼はその味方を戦いに連れて行かなかった.
なぜならその味方の人物は,
自分のために戦いを行おうとしていたからだ.
その人物は,かつてのウォルターと
同じ間違いを犯そうとしていた.
ウォルターが彼を一人残して
戦いへと向かった理由はこれ以外にない.
頼りにならないからとか,
自分ひとり良い格好をしたいから
とか言う理由では絶対にないのだ.
男の生き方ってこんなかんじなんだろうって思った。
イーストウッドがかっこよすぎる!
そう来ちゃうとは思いもよらなかった。だまされた。参ったよ!「ミリオンダラー・ベイビー」の時と同じような偏屈な頑固爺さんがはまりすぎていて、笑えた。利発なスーとの会話がおもしろかったし、奥手のタオとのかかわり方が微笑ましかった。牧師との関係の変化もよかったし、理髪店のおやじとのやりとりもおかしい。独り身の老人の孤独がひしひしと伝わってきた。でも、妥協しようとしないところがイーストウッドらしい。ラストは涙が出続けて、拭く気もしなかった。すごいね。これって、アメリカ自体が感じてることなのかな? そうだとうれしいな。オバマ大統領じゃないけど、CHANGEしたの? 世界の警察としてではなく、世界の一員としてのアメリカの姿だといいね。
最高!!
久々の当たり作品に出会った感じ。クリントイーストウッド監督作品の中でも私的には上位にランクインする!!ストーリーは単純ではあるが全てのシーンでアメリカに対しての皮肉的な発言をしている様にも思える。人種差別・銃・戦争等。特に主人公の朝鮮戦争帰還兵の払拭する事の出来ない心の痛み、最後に愛する人の為に身を張って守るが・・・・。この作品は絶対に観る価値がある。
今でもアメリカは怖い
見ながら色んな事を考えさせられた。イーストウッドと同じ歳の義父が一人で故郷にいて、母も一人で自分の故郷に住んでいて、最近電話してないなぁーと。
そして自分はあの長男みたいで・・・。
銃社会は怖い。見た人はラストでバンバン撃ち殺すと思った、といいましたが
ある意味それも有りか・・・と。でもそれだとダーティハリーと許されざる者のミックスに。殺人者になってもその方がスカッとするかも?
遠くの身内より、近くの他人 それは同じだなぁと。
でもあのラストはショックですよ。ファンとしては。
彼らいといえば彼らしいけど。
サンダーボルトとおくりびとの臭いを感じました。
アメリカ人にしか描けないアメリカ人に捧げる映画
クリント・イーストウッド監督、脚本、主演
という作品は珍しくないですが、
「グラン・トリノ」は昨今のハリウッド映画にない魂への呼びかけみたいなものを感じました。
タイトルの「グラン・トリノ」はヴィンテージ・カーの名前なのだそうですが
いかにもアメ車!という古い車を大切にしている主人公もまた頑固な老人。
いつもぴっかぴかに車をみがいて、それをご満悦に眺めてビールを飲んでいます。
もっぱら足にしているのはフォードのトラック。こちらの車はドアがさび付いています。
そんな主人公の隣家にタイ人の家族が引っ越してきて…とお話がはじまります。
日本の映画をリメイクしなくても、十分感動できる映画作れるじゃないか!
と泣きながら思いました。
クリント・イーストウッドさん、映画作りの後継者を作ってください
静かに泣ける作品です(^o^)
妻に先立たれた頑固で偏屈なおじいさん!
何処にでも居そうですな(笑)
そんな老人のウォルトが
隣人の少年タオやスーとの出逢いによって
心を開き穏やかになっていく・・・・
ストーリー的には、よくある話なんですが・・・
でもそこがちょっと違うイーストウッド監督!!!
彼は俳優だけじゃなく、本当に立派な監督ですね^^
私の期待通りの作品でした(^o^)
そしてシリアスの中にちょっとした笑いあり!
時々、クスッとさせてくれました。
誰にでもいつかは老いがやってくる・・・
ストーリーの裏で、そんな老後の孤独も考えさせられた感じです。
とにかく心に残る名作。
観る価値ありますよ^^
4月28109シネマズ高崎にて観賞
デッドボール、当てられた方も痛いが当てた方も痛い
この作品で俳優としてのクリント・イーストウッドは終了。っというのは本人談である。
この話が広まり、各方面の受けたショックの大きさに当のイーストウッド本人もビックリして「あぁ、いやね、ホントにホントの引退っていうか、まぁ主演とか最近はもう結構キツいなぁっと思ってさぁ」などと言い訳している所を見ると、まぁ完全に無いというワケでは無いのだろう。ただ、少なくとも自分監督で自分主演はもう無いのかもしれない。
「グラン・トリノ」一応は自作自演の最後に選んだ作品らしく劇中イーストウッドが演じるウォルト・コワルスキーは俳優クリント・イーストウッドが今まで演じてきたキャラクターの総括のような男であった。
トラブルに対して警察に頼らず自分で立ち向かうリバタリアンっぷりは西部時代の無法者のようだし、イタ公、黒んぼ(黒人軽称は『ニガー』よりもキツい『クーン(穴ぐま)』を使う。言われた黒人もあんまりヒドいのでビックリする程。)、米喰い野郎と全ての人種を侮蔑する様は「ダーティーハリー」そのままだ。
どちらにしても今までは拳銃で相手をブチ殺してきたワケだが、そんな人生にも終焉が訪れる。
「デッドボール、当てられた方も痛いが当てた方も痛い」
傷ついた側はもちろん痛いが、傷つけてしまった側も相手の痛みを想像してしまう。デッドボールなら相手の痛みの代償のやりとりをするチャンスもあるが、殺してしまった相手の痛みや喪失は計り知れない。
ピースマークのバックルをしたヒッピーの殺人鬼をブッ殺したハリー・キャラハン/クリント・イーストウッドは、その余波を受け止める。究極のリバタリアン、西部最後の男らしく自分一人で。
とにかく、見て!
クリント・イーストウッド4年ぶりの主演、そして監督作。終焉の時を迎えた男が選択する、“人生の幕の降ろし方”に、熱い涙がこぼれます。
どうしたらこんな素晴らしい映画を作れるのでしょう?イーストウッドは、本当に凄い。トンでもない人だと吾輩は思います。この映画、途中でラストがある程度想像出来てしまいます(そりゃあ、あれだけ『ラストが、ラストが…』って煽られたら、何となくわかっちゃいますって!)。で、その通りの展開になった時、『ああ、やっぱりな』と思った次の瞬間、吾輩は涙が止まらなくなってしまいました。悲しいシーンであることに間違いはありません。しかし、事前に結末は予見できていたにも関わらず、吾輩久々に“号泣”してしまいました。何故か?どうしてか?自分でもまったく説明が出来ません。ただ1つ言える事は、これこそが“イーストウッド映画の持つ魅力”なのだな~ってことです。上手く説明できませんが、吾輩の脳の中枢は、この魅力の前に、なす術もなく涙腺を決壊させたのです。悲しい、ホントに悲しいんですよ。でも、この悲しさは“未来に希望を抱かせる悲しさ”なんですよ。正直『もう少し、上手いやり方があったやろう?』とも思ってしまったのですが、無骨なまでに真っ直ぐ、その未来の為に自らを捧げたウォルトの決意。その心中を思った時、吾輩の涙腺は再び決壊してしまいました。人間こんな事、思うだけでなかなか出来ません。ウォルトが人生を賭して灯した“希望”という光は、スーやタオが人生に迷った時、必ず正しい道を照らしてくれる筈です。
決して悲しく、重い映画ではありません。随所に微笑ましい演出が為され、そして笑いのツボも用意されています。特にウォルトが度々怒りを露わにする(不義理な息子や孫達の、理不尽な振る舞いや、不良グループ達の許せない行動に)シーンには、『おお!まるで年老いたダーティハリーだ(^^;!』と、吾輩クスクス笑いが止まりませんでした。まるで『歳はとっても、俺の正義の怒りは不変だぜ!』という、イーストウッドの心の叫びが聞こえてくるようでした。このように、骨太な中にも軽妙洒落な演出を織り込み、そしてラストに希望の涙を流す大団円を用意する。派手さはないけれど、スクリーンを通して、人間の一人一人の存在が、どれだけ大切なものなのかを思い知らせてくれる。スマートじゃないけれど、一級の芸術として完成している…。この映画は、そんなイーストウッド映画の最高峰と呼べる作品に仕上がっていると思います。然るに何故、この映画はアカデミー賞にカスりもしなかったのでしょうか?吾輩個人的に“作品賞”あげてもイイくらいの映画だと思うんですがね~(現時点で「スラムドッグ$ミリオネア」は未見ですが)。今のところ間違いなく、今年のNo.1です!
本作でイーストウッドは、俳優業のリタイヤを宣言したそうです。確かに間もなく79歳(?!)になられることを考えれば、それもアリかな~とも思います。ラストでこれだけ素晴らしいモノを見せていただいたのですから、俳優人生の花道には相応しいと思います。これからは監督として、心の底から感動出来る映画をドンドン撮っていただきたいモンです。でも、気が向いたらまた演技も見せてください。
イーストウッド 天才!
この映画、公式ホームページに有るコピーの
今、大人が迷う世の中。でも、この男がいる。
そのまんまだと予想して見に行くと
『全然違うじゃん!』
ってな感じになります。
“腕っ節が強い、古き良き時代のアメリカの男が復活する話し”
では有りません。(私はそう思って見ていました)
もっとしっとりした、感慨のあるストーリーで、
じっくりと見たい映画です。
派手なアクションやお金のかかったセットはまるで無し。
情緒が有り、ウイットに富んでいて、リアルで
アメリカよりヨーロッパの香りがします。
製作に ワーナーブラザーズ が挙がっていますが
もし俳優・監督がクリント・イーストウッドじゃなかったら
お金出さなかったんじゃないかなって位
地味な内容です。
多分この作品については沢山の方がコメントを書くと思うので
私は印象に残った大切だと思える事だけを書きます。
冒頭シーン、主人公の妻の葬式に孫が出席します。
私はその孫達の、
色は黒いけどへそを出した服やおざなりな態度、
それを見て笑っている親や周りの人達を
『日本とは違うし、こんなもんだろうね。』
と違和感を覚えずに見ていました。
そしてラストでも葬式が出てきます。
そこではそんなアメリカ人(この場合白人)とは対極に
(多分)第一礼装をした少数派民族の人が出てきます。
そこに有る
“敬意”
の部分をクリント・イーストウッドは描きたかったんじゃないかなって
思いました。
それは生きている事への敬意であり、
死に行く人への敬意です。
とてもシンプルな映画だと感じました。
これは自分を大人だと自覚する男性には絶対お勧めできます。
特に
独りになりたい、だとか、独りを楽しみたい
そんな時。
あとは子供のいる夫婦。
家族のあり方を考えさせてくれます。
あっ、念のため。
歳の若いカップルや、甘いカップル向けではないと思います。
次世代へのメッセージ
「グラン・トリノ」
それはひと昔前のアメリカ・フォード社の大型車である。
ある意味、大量生産・大量消費・大量廃棄の時代の遺物ともいえる。
でも、主人公はこの車をつくることに愛情を込めていた。
一方、主人公の息子はトヨタのディーラーである。
時代にあっているんだろうが、彼は車そのものよりも売ることに余念がない、
経済合理主義だ。
そんな親子の関係は破綻している。
そんなとき、隣に引っ越していたモン族の家族。
そこには、忘れかけていたコミュニティがあった。
特に、そこの姉には、至極真っ当な主張とプライドがある。
その弟は人生に迷っているが、誠実さを感じることができる。
主人公と、少数民族の家族たちとの交流が楽しい。
遠くの親戚よりも近くの他人。
同じアメリカ人よりも、マイノリティとされる人たちに、
シンパシーを感じる。それは人間愛に近いものだと思う。
クリント・イーストウッドの視点には、いつもいつも、
共感してしまう。
「硫黄島からの手紙」の日本人へのまなざしにしても、
「チャンジリング」の母親・女性へのまなざしにしても、
今回の「グラン・トリノ」のモン族へのまなざしにしても、
その視点はひとつの民族を超えて、人間そのもの、いや、
生きとし生けるものへの限りないやさしさを
を感じずにはいられない。
この映画のクライマックスは、イーストウッド映画のファン
謎解きを提出しているように見える。
「荒野の用心棒」や「ダーティ・ハリー」の頃とは解決手段が
変わったけれど、それはひとつの時代のおわりであるとともに、
次世代へのメッセージのようにも思えるのだ。
「チャンジリング」に続いて、間髪をいれず、こんなに
すばらしい映画を見ることができたことに感謝したいと思う。
クリント・イーストウッドの回答
前2作は戦争映画、しかも米国、敵国日本の両視点からの映画。
もう、この辺で彼のメッセージはバリバリ、外部に発せられているわけですが、次は暴力と人種に絞り込んできました。これは、世界にというよりもアメリカに対する映画なんだと思います。アメリカのIMDbで極めて高得点(現時点で8.4)というのも何となくわかります。
途中のスーの魅力あふれる演技、タオの成長、とにかくアジア俳優が魅力的なんですが、主演のクリント・イーストウッドの前半の悪い人物像のこと・・・。
しかし、全ては最終的に彼の最終選択に集約します。これが、彼のメッセージなんです。これが、最終的に彼の考える平和の道なのかもしれません。
昨日見たスラムドッグ・・・には及びませんが、じんわり「あー、やっぱ映画っていいな・・・。」と思わせてくれる映画です。クリントと同年代のアラ還(またはオーバー還)のお父さん方、是非おすすめです。
名人芸の演出と究極の格好良さ
主役のキャラクターとしたら、有り得ないような偏屈さだ。しかし、頑迷というのとも違う。「しつこい」と毛嫌いしている筈の、何度拒絶されてもめげずに説得を続ける神父の話を、結局は真摯に耳を傾けていた酒場のシーンが証明しているだろう。
彼の偏屈さには筋が通っているのだ。ウォルトのこだわり、そのひとつひとつに私は共感を覚えた。人種差別と汚いののしりのオンパレードなのだが、だからだろうか、突き抜けた人物造型が爽快でもあった。
彼の偏屈さの最大の理由は、朝鮮戦争での罪悪感であり「自分を許せない」ことにあるのだ。自分を許せない人生は不幸だ。体調も悪く、人生の終焉が近いことを知った「生よりも死に詳しい」ウォルトが次第にタオ一家との交流を通じて心を開いていく様子は、何とも言えない優しさに満ちていて感動する。
この展開を先が読めるなんて言ってはいけない。その人物造形の確かさ、こんなに笑って良いのかと思うほどの洒落た会話の数々、心温まるエピソードの数々を堪能すべきなのだ。
そう、素直に、どれだけ笑えるか、これがこの映画を楽しめるバロメータだろう。特に床屋でタオに「男らしい会話」を教えるシーンは最高だ。
それにしてもクリント・イーストウッドは格好良い。
まるで神から最後の祝福を受けたかのような幸せを守るために、彼が最後に取った行動は、それこそ、「史上最も優しい衝撃のラスト」に相応しい。いかに今までの人生を生きてきたか、彼は見事に、それを証明してみせる。
是非、この深い余韻をたくさんの人に味わって貰いたい。
エンドロールの歌。必聴です。
2004年『ミリオンダラー・ベイビー』以来のクリント・イーストウッド出演作品。この作品では、監督・製作も兼ねています。
華が無く、家族からも疎まれ、社会の表舞台で大活躍をする事も無く老境に入った朝鮮戦争帰還兵ウォルト・コワルスキーをクリント・イーストウッドが非常に上手く演じています。そしてその演技は、渋いです。クリント・イーストウッドの映画で、明るい作品は少ないのですが(失礼!)、この作品もその法則に従っています。
この作品のもう一人の主人公は、ウォルトの隣家に引っ越してきた、アジアの少数民族モン族(と、映画では言っていますが、“ベトナム戦争で米軍に協力したため、後の共産勢力に迫害されてアメリカにやってきた”と言う説明の件からして、実際にはどうもミャオ族の様です)の家族。その一家の少年タオを演じるビー・バンですが、冴えないモン族の少年を非常に上手く演じています。ウォルトに何かと鍛えられながら(?)、徐々に自分に自信を付けて行きます。
そしてそのタオの姉スーを演じるのは、アーニー・ハー。彼女が、タオと自身を助けてくれたウォルトに何かと世話を焼く事でウォルトの心が徐々に開いて行くことが良くわかります。ああ言う強い姉さんがいると、弟はタオのように成りがちなような気がしますが、どうでしょう。
『生と死』。これが、この作品のテーマでしょうか。ウォルトが、あのような“計画”で最後を迎えた事も、タオに、自身が経験した辛い経験を味あわせたくないと言う“真の生と死”の意味を知ったウォルトだからこそ取り得た“計画”なのでしょう。
ここからはネタバレになりますが、最後にウォルトがスーツを仕立て直しているとき、「スーツ姿で、討ち入りか?」と思ったのですが、違いましたね。その間違いには、タオを地下室に監禁したところで気が付きました。それでも、最後の結末までは、予想できませんでした。
最後に。エンドロールに流れる歌は、クリント・イーストウッドが歌っています。何とも渋くて、いい味わいです。
ウォルトの人生講座
イーストウッドのツンデレ演技がみもの
イーストウッド作品というとシリアスという先入観を持って見ると、前半の笑えるパートの多さに驚く。最初はいかにもな頑固じじいとして登場する。やがてアジア系移民の少年タオと親しくなると彼にアメリカ流の行き方を伝授する。ここは教育のパートとなるわけだが、「お前が認めているわけじゃないんだぞ」というイーストウッドの不器用な愛情表現が良い。
もちろん終盤には修羅場が待っているわけだが、結末は予想できないとは言わないがやや意外な方へ行く。最近のイーストウッド作品はどちらかというと組織論、末端を気遣わない上層部という構造を描くのがうまかったが、ここでは個人を描いている。その行動は見事といえるものだが、本人もそれが時代遅れだと知っているからか、やはり寂しさも漂うものになっている。
スコアに関しては何点を付けたらいいかわからないので、とりあえずB+。
クリント・イーストウッドにしては一寸がっかり
クリント・イーストウッドは監督としても、素晴らしい人です。硫黄島からの手紙は最高。日本人がこの映画をつくれなかったのが残念。 それで、この映画もかなり期待して行った。良い映画ではあったが、彼のベストではない。 彼の良さは、どの映画も 愛があること、作り物でなく 血の通った登場人物 ストーリーということ、反権力、巨大な体制 又は 巨大な悪に対する反抗心があること。 ヒューマニズムを感じさせるところ。許されざる者 という西部劇で 銃弾に当たった痛みを感じさせた描写は とても伝統的な西部劇映画にはなかった驚きが感じられた。 彼には日本人に通ずるハートを感じる この映画の結末も 日本的 或いは サムライ精神的なものであった。 かなりの年だが、まだまだ頑張って良い映画を作って欲しい!
余韻が残る映画でした
全265件中、241~260件目を表示