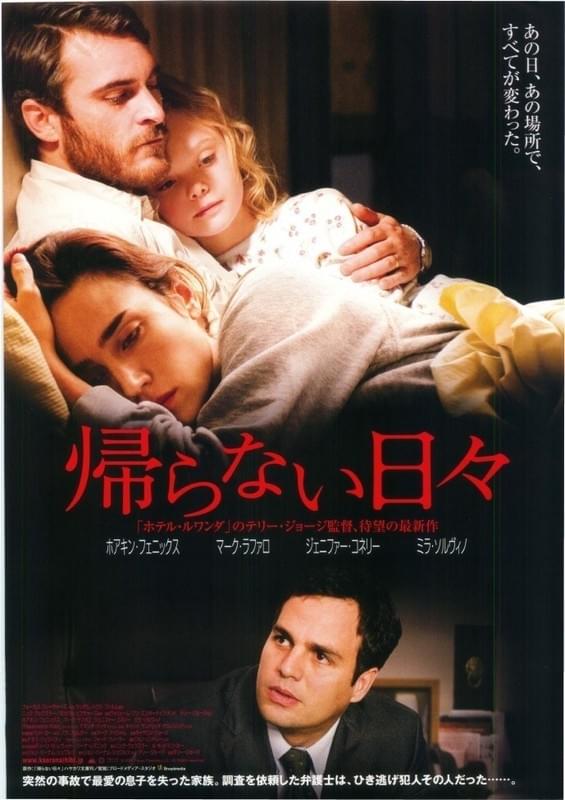帰らない日々
劇場公開日:2008年7月26日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ
「ホテル・ルワンダ」のテリー・ジョージ監督が描くシリアスドラマ。主演に「グラディエーター」のホアキン・フェニックス、「死ぬまでにしたい10のこと」のマーク・ラファロ。コネチカットの田舎町、大学教授のイーサンは最愛の家族と平穏に暮らしていた。だが突然のひき逃げ事故で息子を失くし、その悲しみと罪悪感から家族はバラバラになっていく。イーサンは犯人を突き止めるため弁護士に調査を依頼するが、実はその弁護士ドワイトがひき逃げの犯人で……。
2007年製作/102分/アメリカ
原題または英題:Reservation Road
配給:ブロードメディア・スタジオ
劇場公開日:2008年7月26日
スタッフ・キャスト
- 監督
- テリー・ジョージ
- 脚本
- ジョン・バーナム・シュワルツ
- テリー・ジョージ
- 原作
- ジョン・バーナム・シュワルツ
- 撮影
- ジョン・リンドレー
- 音楽
- マーク・アイシャム
- 美術
- フォード・ウィーラー
-

ホアキン・フェニックス
-

マーク・ラファロ
-

ジェニファー・コネリー
-

ミラ・ソルビノ
-

エル・ファニング
-

ショーン・カーリー
-

エディ・アルダーソン
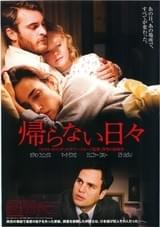
 ジョーカー
ジョーカー ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ
ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ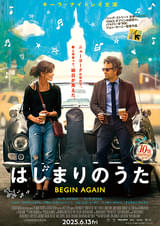 はじまりのうた
はじまりのうた グランド・イリュージョン 見破られたトリック
グランド・イリュージョン 見破られたトリック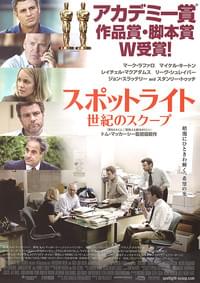 スポットライト 世紀のスクープ
スポットライト 世紀のスクープ グランド・イリュージョン
グランド・イリュージョン her/世界でひとつの彼女
her/世界でひとつの彼女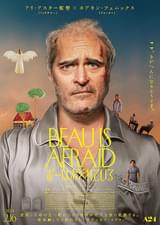 ボーはおそれている
ボーはおそれている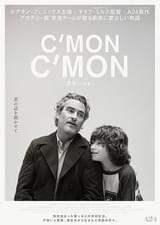 カモン カモン
カモン カモン シャッターアイランド
シャッターアイランド