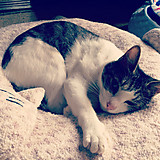巴里の屋根の下のレビュー・感想・評価
全14件を表示
演出とカメラが凄い
初めは映画の雰囲気になかなか入り込めなかった。スリにも居場所があって皆と共存してる街なのかあとぼんやり思ったり、バッグの口が開いたまま、嫌な男フレッドにつきまとわれてるのに煮え切らないポーラは馬鹿なのか?と思ったり・・・。
でも途中から闇と光と影の映像と音の使い方が凄い!と気がついた。アパルトマンには色んな人が住んでいる。その様子をアパルトマンのバルコニーを下から上へと映して私達に教えてくれる。アルベールとポーラが初めて共に歩くシーンは、夜の石畳とそこを歩く二人の足元と靴をひたすら映すだけ。いっときの二人だけの世界が目の前に広がる。セリフがあったりなかったり。なくても何を話しているか想像がつく。店の中に人物がいてもドアが閉まっていれば外のカメラは彼らだけ映して声は聞こえない。当たり前のことなのに新鮮だった。
「結婚するんだ!」のアルベールの声に盲目のアコーディオン弾きはすぐに結婚式の音楽を弾く。アルベールはポーラを迎えるために彼女用の美しい室内履き、花束、果物、バゲットを買ってくる。それらが一気に彼の部屋の床に散らばる。床のそれらはだんだんと朽ち、ネズミに食われてしまう、その経緯を少しずつ映すことでアルベールの不在が迫る。
フレッドとアルベールの決闘場面ではナイフの格選びシーンにすごく笑えた。お洒落なユーモア!誰が見てもハンサムで若いルイがポーラに選ばれたのは半分わかりつつも、アルベールの方が男気あって女たらしでなくてずっといいんだよと、まだ子どものポーラに言ってやりたかった。最初のシーンと最後のシーンがシンメトリーで、昔の邦画をなんとなく思い出した。
全然知らない映画なのに歌だけは知っていた。
サイレントとトーキーの過渡期のアバンギャルドな演出が素晴らしいクレールの名作
ルネ・クレール監督(1898年~1981年)は、26歳の時の短編「幕間」で注目され29歳の時制作した「イタリア麦の帽子」で一流監督として認められたフランス映画界戦前派の巨匠の一人。10代の頃テレビで確かフランソワーズ・モレシャンさんが、祖国フランスで最も尊敬されている映画監督がジャン・ルノワールで次にルネ・クレールと話していた記憶があります。戦前の日本では「望郷」「舞踏会の手帖」などのジュリアン・デュヴィヴィエが最も人気があったようです。そのクレール監督サイレント期の代表作「イタリア麦の帽子」は日本未公開ですが、幸運にも学生の頃フィルムセンターで鑑賞出来たことは幸せでした。(1962年にフランスのシネマテークから東京国立近代美術館に寄贈)これはチャップリン映画に匹敵するフランス喜劇の名画として深く感銘を受けて、個人的にも生涯のベスト映画に選びたいほどの衝撃でした。そして時代がサイレントからトーキーになって漸くクレール作品が日本で公開された第一作が、「巴里の屋根の下」です。
クレール監督の脚本と演出の特徴は、サイレントからトーキーの過渡期を反映させたもので、情景に合った柔らかさと軽快なメロディのフランス音楽が、台詞を省略した会話場面にも使われていることです。これによって男3人と女1人のシンプルなストーリー展開でも、所々で観る者の想像力を掻き立てる面白さがあり、映像のテンポは今日より遥かに遅くゆったりです。この映像のテンポが醸し出す独特な緊張感と情感が素晴らしい。これが詩的リアリズムと称されるのは、例えばチャップリンのサイレント映画のパントマイムの誇張した表現ではなく、登場人物の動きを日常生活に近い言動の自然さで描写している特徴からでしょう。1930年頃の巴里の市井の生活感が感じ取れます。その上で、クレール演出にアバンギャルド的(前衛的、革新的)な創意工夫が見られる斬新さも兼ね備えています。
それは主人公アルベールの無実が証明されて釈放になり、ルーマニア女性ポーラをめぐってヤクザなフレッドと対立し決闘するクライマックス場面の演出です。アルベールがやられると怖れたポーラが慌てて友人ルイに助けを求めるカットでは、“ルイ!”と呼ぶ台詞だけ聴こえて、バーの中に入ると無音になり、アルベールとフレッド一味の対決が始まろうとする路地の場面に繋がります。再びルイとポーラがもみ合っているバーに戻ると、ルイが出て来て“相手はフレッドか?ルイ!これを持っていけ”の友人の台詞だけが聴こえます。サイレントシーンに僅かな台詞だけで、路地の決闘シーンの緊張感を醸成する演出技巧です。いざ決闘シーンになりナイフを取り出すと音楽が流れ、アルベールのナイフが釣り合わずフレッドの仲間が皆差し出すカットでは、近くを走る列車と汽笛の音を被せます。一端フレッドが引いた後アルベールがフレッドを呼び止め殴り、遂に喧嘩が始まります。すると汽笛の鋭い音が響き、アルベールとフレッドが地面でもみ合うカットでは蒸気機関車の音と黒煙。この細かく丁寧な演出の見事さ。そして、そこに銃を持ったルイが漸く現れて、外灯を狙い撃ちして周りが暗くなります。遠くに光る外灯が場面上部に見えるだけで、殆ど真っ暗なカットで緊張感が最大になる。クレール監督の映像センスの、この粋な感覚にユーモアを少しでも感じたらクレールファンの証拠となるでしょう。そしてこの暗がりに警官の笛と野犬が吠える音を被せる展開の変化で彼らが逃げ惑うカットをモンタージュし、警察車両の丸いヘッドライトに照らされてつかみ合う人物が判明すると、それがなんとアルベールとルイの2人という落ち。フレッド一味が捕まり、アルベールとルイが逃げ切るシーンはサイレントのドタバタ喜劇タッチ宜しく、バーでアルベールとルイが取っ組み合いの喧嘩シーンでは、ロッシーニの歌劇『ウィリアム・テル』序曲で恋の鞘当てを演出します。ここからアルベールが身を引く結末のフランス映画らしさ。映画冒頭で予想する男女カップルの展開にならないところが如何にもフランス映画を思わせます。
アルベール役のアルベール・プレジャンは、「イタリア麦の帽子」でも主演して、この作品では歌唱も披露しているベテラン俳優。妖艶で可憐なポーラを演じたポーラ・イレリは、役柄と同じルーマニア出身のこの時20歳の若さ。当時のファッションに身を包み巴里っ子を好演しています。特徴のある飾りの帽子もお洒落で、脱いだ時とのギャップが大きい。女性を可愛くみせる帽子がファッションの必需品であった時代を窺わせます。恋敵フレッドのガストン・モドもベテラン俳優で、調べると1918年にモディリアーニ(1884年~1920年)のモデルをした経歴の持ち主。ルイを演じたエドモン・T・グレヴィルは、アラン・ドロンに似たフランス美青年の系統の俳優で、後に監督にも進出した映画人でした。
トーキー初期のサイレントとトーキーを併せ持つ面白さと、クレール監督の斬新で鋭い演出が、時代を象徴する映画の名作でした。セット撮影の美術も良く、クレーンを生かしたカメラワークの動的な工夫もあり、じっくり映画を楽しめる逸品。
ルネ・クレール監督は一度日本を訪れています。それは1970年の大阪万国博覧会に招待されて、講演のための来日でした。実は日本が招待の手続きをしたのは、「太陽がいっぱい」のルネ・クレマンだったのですが、何かの手違いでルネ・クレールに届いたのでした。淀川長治さんがその時の講演に同席し、クレール映画を役を演じながら紹介したと言います。近い未来に映画は人のポケットに入り持ち歩けると淀川さんに予言しました。お洒落で上品なフランス紳士のクレール監督の時代を見据えるセンスも窺えて興味深い逸話でした。
パリ・オリンピック開催記念‼️
私はこの作品が大好きです‼️初見から30年以上経つし、製作されてから94年、この作品が公開当時絶賛されていたトーキーとしての画期的なサウンドの活用法などは、現代では当たり前になっていて全然たいしたことないんですけれども、それが逆にいつ観ても新鮮で、観れば観るほど胸をときめかせてくれる作品ですね‼️パリの街角で相棒のルイと共に歌を奏でるアルベールは、美女のポーラに一目惚れ。ポーラも次第にアルベールに惹かれるが、アルベールは知人の罪を着せられ、留置所に。落ち込むポーラを支えるうちに、ルイとポーラが恋に落ちてしまう・・・‼️今でこそパリと言えばファッションの街という印象ですが、この作品では日本の柴又や浅草みたいな下町情緒あふれる街として描かれてます‼️しかもオールセット‼️これがまた素敵‼️そしてオープニングの屋根裏、三階、二階とスムースに移動するカメラワークと、そこに被さる有名な主題歌「スウ・レ・トワ・ド・パリ」‼️この主題歌の存在感がチョー大きい‼️ホント、名曲‼️アルベールや街の人たちの歌声が次第に大きくなる、音の遠近法みたいなシーンと、それぞれが気持ち良さそうに歌うカットの積み重ねは、後のミュージカル映画の先駆けですね‼️このオープニングだけで心が鷲掴みにされてしまう‼️加えて初期のトーキー映画らしく、サイレント映画のサウンド版みたいな演出がされてるのも微笑ましく、ガラス越しの会話で声を消したり、喧嘩のシーンで汽車の音をかぶせたりするシーンなんか、今ではみんなが使う手法なんですけれども、多分この作品が初めてだったんでしょうね‼️ルネ・クレール監督がパリの下町情緒の素晴らしさを満喫させてくれるという意味で「巴里祭」と双璧なんでしょうけれども、私としてはこの「巴里の屋根の下」の方がダンゼン好きですね‼️ポーラの幸せを願うアルベールの男らしさと男の優しさ‼️私も見習わないと‼️
技術的な限界とかではなく、無声映画とトーキーのハイブリッドで作るという製作方針で監督は撮ったのだとおもいます
1930年、フランス映画
ルネ・クレール監督の初トーキー作品
大人気監督なので人気作品は沢山ありますが、本作の「巴里の屋根の下」、1932年の「巴里祭」、1957年の「リラの門」の3本はパリの下町が舞台だけあって特に人気が高いです
パリの下町の人々への暖かい視線が心地良いです
大袈裟に言えばヒューマニティです
それが全編に溢れているのです
冒頭のシャンソンが本作のテーマそのものです
♪20歳の春、花咲き乱れる春
愛し合うふたりには最高の時
春風香る青き大地・・・
あ~~!20歳の頃に戻ってこんな恋をまたしてみたい!なんて遥か遠い目をしてしまいます
アルベールとポーラとルイの三角関係
はこれから一体どうなるんでしょう?
それは語られません
ラストシーンはカメラがどんどんクレーンで上りパリの街並みを安アパートの屋根の高さから俯瞰します
巴里の屋根の下で、こんな恋物語はあちこちで今日も明日も繰り返されているのでしょう
100年後近い21世紀の現代だって変わりないのだとおもいます
商業映画のトーキーは1927年の米国映画「ジャズシンガー」で、1928年頃にはトーキーの公開が本格化したそうです
欧州では翌年の1929年からトーキー映画が製作されはじめたそうです
でもフランスでは1932年後半になっても半数以上の劇場がトーキー未対応だったそうで、本作公開の1930年の時点ならば大都市の主要劇場ぐらいだけがトーキー対応ではなかったでしょうか
まだまだ無声映画も人気だったのでしょう
というかトーキー映画を設備が無くてもかけて無声映画として興行していた場末や田舎の映画館もあったのかも知れません
なので本作はトーキーで撮られているのですが、台詞が発声されているシーンは要所のみでほとんどのシーンは無声映画の流儀で撮られいます
演技だけで何を言っているのか分かるようになっています
つまり無声映画の文字画面が時折はいる所を台詞で発声させているのです
もちろんシャンソンの合唱や劇伴、効果音は全編で流れます
技術的な限界とかではなく、無声映画とトーキーのハイブリッドで作るという製作方針で監督は撮ったのだとおもいます
爬虫類と哺乳類の両方の特徴を合わせもつカモノハシみたいな映画技術史的にも注目すべき作品とおもいます
蛇足
日本のトーキー映画はというと、1931年の「マダムと女房」が全編トーキーで公開された初作品だそうです
欧州が米国の一足遅れなら、日本は二足遅れですが、技術革新にさほど遅れずについていってます
でも日本には活弁士という世界でも類のない興行方式がありました
なのでトーキー設備のない映画館でトーキーを無声で興行しても活弁士がいますからさほど違和感もなく困らなかったのかも知れません
成瀬巳喜男監督の初トーキーは「乙女ごころ三人姉妹」、小津安二郎監督の初トーキーは「一人息子」で、どちらも1935年公開ですからトーキー映画への取り組みは製作側でもゆっくりしたペースでした
日本がトーキー映画への転換がかなりゆっくりなペースになったのは、活弁士による興行が観客に支持されていたことも一因だったのかも知れません
でも一度設備投資をしてしまえば、あとは減価償却のみのトーキー映画の方が、日々結構なギャラの発生する活弁士や楽団を雇うより経済的ですから結局活弁士はトーキー映画に駆逐されてしまったわけです
本当?
アニメの声優さん、洋画の吹き替えの声優さん
これは活弁士の頃からのDNAが連綿として現代にまで繋がっているように思います
だから日本の声優さんはクォリティーが高いのだと思うのです
声優が職業として成立しているのは世界でも日本だけだそうです
活弁士もそうだったじゃないですか
恐竜が進化して鳥になったように、声優さんのご先祖は活弁士なのかも知れません
タイトルからして美しい
モノクロ映画は絵が綺麗!
フランス語を学ぶためにこの映画を観ましたが、やっぱり映画的視点で観てしまいます。
モノクロの映画は以前カサブランカや第三の男など観ていたのですがそれをなんと超えて今はこのフランス映画が一番好きです。
特に好きなのがフランス映画は語学が分からなくても絵が綺麗だから楽しめます。
多分二十代後半の若者の観客は私くらいしかいませんでした。
他の観客さん達はおじいさんおばあさんだけでしたが、私は笑えるシーンを観た時笑うのを避けていたのを今思います。
おじいさんおばあさんは真剣に観ていました。とても良い事だと思います。
また観たいけど水曜日で1400円かかったので、いつかDVDを探してみたいと思います。
もっと話したいけれども、今日はここまでにします。
ではまた。
【善性溢れる、品の良い1930年製作のコミカルラブファンタジー映画。モノクロ映像と音楽のバランスも良い。】
ー ”ルネ・クレール”レトロスペクティブが、伏見ミリオン座で10月から始まるというので、一足早く今作を鑑賞。ー
◆感想
・ストーリーはシンプル。路上で楽譜を売る男、アルベール(ソンナ、そんな商売があったんだ・・)は、集まってきた人々の中の口元の黒子が印象的な美しき女性ポーラに気付き、彼女をスリから助ける。
ポーラにまとわりつく、フレドに鍵を盗られたポーラはアルベールの部屋に泊めさせてもらうことになるが・・。
ー 二人が、お互いにベッドを譲り合い、翌朝ちゃっかりとポーラがベッドの上で寝ていたり(優しいアルベールがベッドに寝かせてあげたのかな?)、知人のドロボーから預かった荷物のためにアルベールが警察に捕まっちゃったり、ショックを受けたポーラをアルベールの友達、ルイが慰めているうちに・・。ー
・恋敵、アルベールとフレドの路上での決闘シーンで流れる蒸気機関車の汽笛の音の効果的な事や、当時の男性の殆んどがハンチング帽を被っていたり、時折映し出される石畳が、何だかセンス良く感じたり・・。
<愛した娘を、友人ルイに取られちゃったけれど、翌朝、明るい顔で、再び楽譜を売るアルベールの姿。
善性溢れる、高潔な映画。
”ルネ・クレール”の作品を少しづつ鑑賞して行こうと思わせてくれたほど、鑑賞後の気分が良い映画でもある。
劇中流れる数々の音楽も良いね。>
街角で歌の光景
トーキー映画の始まりの良さがぎっしり
ルネ・クレール「巴里の屋根の下」(1930)
1時間36分の上映時間。パリらしい建物の住人たちの様子と一人のルーマニア人の若い女性を巡る三人の男性の話。流石にデジタル再生されている画像なものの、映画は古く、かつトーキーかサイレントかでどちらつかずの画面。トーキー黎明期代表作品と言う。最初はつまらなく感じた。でもシンプルな良さを次第に感じた。不必要なセリフはなく、逆に仕草から理解出来る。台詞は歌も多く「詩的リアリズム」作品として有名らしい。街頭歌手アルベールと最初の親しい出会いの寝室の暗がりの喧嘩、そして女を巡る暗がりでの男の果し合いと電車通過など。今は画像がごちゃごちゃしていて疲れるがそれはない。観客の想像にまかされるはとても心地よい。最近テレビで流行の歌舞伎流のドアップ顔演技の連続とは対照的。
楽譜を売って生活するアルベール
旧き善きパリよ
隔世の感拭えず
映画史的に観ればréalisme poétiqueなどと興味深いのだろうが流石に90年前の映画となると別世界の趣でとっつきにくいことおびただしい。男も皆ハンチング帽をかぶっているから誰が誰やら分かりにくいしストーリーも街のゴロツキと移民の若い女をめぐる面倒臭く退屈なエピソードと相場は決まっている。
女をめぐるオヤジ同士の決闘があったかと思ったら若い女はお似合いの若い男に譲って去ってゆくというオヤジのダンディズムか。
シャンソンはフランスの歌謡曲のようなものと聞いたことがあるので市民に根付いていることは分かるが街角で皆で合唱したりするものなのだろうか、おしゃれなパリ―ではシャルル・トレネの歌のようにどこからともなく聞こえてくる方が似合っているような気もするが・・。
サイレントからトーキーの狭間には歌が橋渡し。
全14件を表示