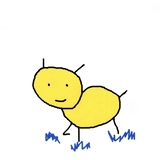異邦人のレビュー・感想・評価
全18件を表示
美しく狂気もはらんだムルソー
まず思ったのはマストロヤンニってこんなに美しかったのかということ。
自分の裁判だというのにある種他人事のような視線で見ているムルソーの姿が印象的。なぜ殺したのかと聞かれても太陽のせいだというのみで、言葉も少ない。
神を信じないというだけで普通ではないとみなされるような時代。
母の死に涙を流さなかったり、葬儀翌日に恋人と喜劇映画を観に行くということが普通ではないとみなされるのは今の時代と変わらないかもしれない。
いつ死刑が執行されるか分からない、その状況で彼はどんな境地に至ったのか。最後の神父との対話はよく分からなかった。
絶妙なものを観ることができた
汗と神
アルジェリアの話なのですね。
ぼうっとして観てたので、アラブ圏の話なのか、イタリアの話なのか、どこが舞台になっているのか最後までよくわかっていませんでした(原作も読んでいないので)。スミマセン。
それにしても、アルジェリアってイタリア人があんなに住んでいたんですか?
いやいや、ちょっと調べたらアルジェリアはフランス領だったというじゃないですか。カミュもフランス人だし。
これって、フランス人の話をイタリア人に置きかえて撮ったようですね。ややこし。
さて、ルキノ・ヴィスコンティ監督『異邦人』。
主人公ムルソーは、どこか虚無的でありながら、美しい恋人や友人たちと人生を享楽するが、やがてそこに不穏な空気が漂いはじめ……。
シンプルなストーリーですが、テンポがあり、興味深く鑑賞できました。
最近の映画ではあまり用いられないような唐突なクローズアップを多用する撮り方にも、観ているうちにすぐに慣れました。
作中、象徴的に「汗」が映し出されますが、これが本作のキーポイントになっていると思います。
それから、終盤の法廷や監獄のシーンでは、「神」がわりと重要なポイントになってくると思うのですが、そのあたりのやりとりがちょっとわかりにくかった(ぼうっと観ていたからでしょうか)。
そんなわけで、(西洋的な)「神」に対して馴染みのうすい我々日本人には、本作が描こうとするものを完全に読み解くのはなかなかむずかしいのではないか、この映画は、キリスト教圏の人々と、そうでない人々が観るのとでは、その印象がかなり異なるのではないか、などという感想も抱きました。
機会があれば、もう一度鑑賞して、そのへんのことを注意深く検証したいと思います。
あと、本作は「不条理」がテーマになっているようですが、それもあまりピンとこなかった。
昨今の日本における様々な事象のほうがよほど不条理かと……。
タイトルの意味するところを確認するためにも、ぜひ原作も読みたいです。
おかしな行動と偏った裁判なのかな
第2次世界大戦前のフランス領アルジェで働いているムルソーのもとに母の死の知らせが届いた。養老院に着いたムルソーは、柩を開けず遺体の確認もせず、葬儀で涙も流さなかった。そして翌日、元同僚の女性と海水浴に行き、喜劇映画を観て、夜を共にした。その後、トラブルに巻き込まれたムルソーは友人から預かっていた拳銃でアラブ人を射殺してしまった。太陽がまぶしかった、という事以外、ムルソー自身も理由が分からなかった。裁判では、非人道的で不道徳だと非難され、母の死後の様子なども検察官から追及され、陪審員から死刑を宣告されたという話。
2021年3月に復元されたイタリア語オリジナル復元版だったが、フランス語圏での話なのにイタリア語なのかぁ、って思った、
この映画の字幕が妙に文学的な表現だと思って観てたが、観賞後、ノーベル賞を取ったフランス作家の原作だと知って、なるほど、と思った。
見所は裁判での検察官、と裁判長の偏った意見なのかな、と感じた。
カミュ好きな方、良さが読み込めず、申し訳ない気分でいっぱいです。
晴れた日には「異邦人」を読もう
日本におけるカミュ研究の第一人者、東浦弘樹氏は表題の著作にて本作の事を
「小説を読んだ者にとっては、いまひとつ面白みに欠ける。
最大の理由は、小説ではムルソーがカメラアイの役目を果たしているのに対し、映画では必然的にムルソーを映す事になるからだ。
マストロヤンニが無表情を装っても観客はそこに何かを読んでしまう。そうなるとムルソーの奇妙な無関心から生まれる小説の味わいは失われてしまう。それを表現出来るのは小説だけなのかもしれない」
と評しています。
まったく見事な指摘だと思われます。
ただ、ヴィスコンティを弁護するならば、故カミュの未亡人が「原作を僅かでも違えない事」を条件に映画化を許可したというから、ヴィスコンティとしては「優れた映画作品」に仕立て上げる為の創意工夫を施す事が許されず、あくまで「小説の挿絵のような」映像化をせざるを得なかったのです。ヴィスコンティにしてみれば、大いに不本意な妥協作品になってしまった事でしょう。
観客としては、原作に忠実であった事は非常に嬉しい事ではありますが、なんといっても鬼才ヴィスコンティですから、その手腕を存分に発揮した作品も観たかった!と切に思います。
アルベール・カミュの生育歴を知れば、ムルソーはカミュの潜在意識が自己投影した姿であると思えます。
息子に対して無関心であった母親を正当化し、子供時代のトラウマを癒す装置こそが『異邦人』であると感じます。
21世紀の世の中を見渡すと、ムルソーは決して異邦人だとは思われません。
ムルソーは、他人に対して必要以上に気を使います。他人を不快にしないように先回りして行動します。しかし、それが「世の常識」には反してしまい奇異の目で見られてしまう。
つくづく人見知りでシャイで不器用なのです。他人への無関心が度を超えている為にマジョリティーの感覚を掴めないのでしょう。(しかし、マンションの隣人の顔すら知らない現代人に相通ずるものがあります)
ムルソーは他者の気持ちに対する想像力が未熟であり、その分、目先の感覚的な欲望には忠実です。
また、己れの感覚に嘘がつけず建前を言わずに、正直過ぎるほど正直に本音で語ります。
それは言ってみれば「無垢な幼い子供」に等しいです。ムルソーは不条理な人間なのではなく「不条理以前」の「純粋な子供」なのかも知れません。
東浦氏は、裁判における検事の大仰な弁舌の滑稽さを説明するのに、チャップリンの『独裁者』を引き合いに出しています。
宗教に寄りすぎる長広舌や芝居じみた身振り手振りを誇張する事により、検事も弁護士も観客の理解を得られません。
観客はムルソーと同じ視点で、法律家達を奇異の目で眺めるのです。ヴィスコンティはこの部分も見事に映像化していると言えましょう。
本作の裁判は、証人も偏っており、正当防衛にも触れられる事なく、まったく奇妙です。しかし、新聞記者として政治絡みの大きな裁判を複数取材して記事にしていたカミュが、裁判の実態を知らないはずはありません。
この奇妙な裁判はムルソーを「純粋無垢な善人」かつ「極刑に処される被告人」という矛盾した存在に仕立て上げる為の仕掛けだったと考えられます。
死刑前、聴聞の司祭に対して、初めてムルソーは激昂します。社会や既成道徳に対する批判や怒りが込められている事はもちろんですが、このクライマックスを通過する事によって、ムルソーは「自分が幸福であった」という気付きに至ります。あろう事か、死刑を目前に控えた今においてさえも「幸福である」と言い放ちます。
作品中、繰り返し登場するキーワード
「無関心」と「幸福」の同一化、癒合がカミュの無意識下のテーマだったのでしょうか?
自分にとって無関心だった母親を正当化し、優しい無関心の腕(かいな)に抱かれる事で世界と和合する。その方法がムルソーにとっては自死だったのでしょうか。
アラビア人殺しのきっかけは、冗談ではなく本当に本気で「太陽のせい」でしたが、その後の彼の行動は「ママン」を理解し、赦し、和解する為の手段だったのかもしれません。その為に必要となる手の込んだ自殺方法だったのかもしれません。
しかしながら、カミュの生きた1900年代初頭に萌芽した「無関心」或いは「過干渉」による幼少期がトラウマになってしまう事例は、それから100年を経た現在、深刻な社会問題に発展したのではないでしょうか。
コロナ禍によって益々、人と人の関わりが希薄になる事が望まれるかのような空気が蔓延しつつある気が致します。
ムルソーの奇妙さは決して不条理ではなく無垢な子供の未熟さによるものであるならば?
昨今の「他者との希薄過ぎる距離感」は決して肯定されるべきものではなく、人類の未来を窮地に陥れかねない危険な風潮であるのでは?
そう感じてしまう自分は、古い人間なのでしょうか?
人間社会におけるコミュニケーション能力や他者共感力の重要性は、改めて真摯に検討されるべきではないでしょうか。
デジタル復刻版を機に、より多くの人々が『異邦人』について解釈を楽しんで欲しいと思います。
その折には原作のみならず、是非とも東浦氏の
「晴れた日には『異邦人』を読もう」を一読する事をお勧め致します。
復刻版文学作品
カミュの名作の巨匠ヴィスコンティと名優マストロヤンニによる映画化だけど、正直言って古く感じました。人間を狂わせるようなアルジェの息苦しい暑さや雰囲気はよく出ているけど、前半はやや退屈で眠気を感じるくらい。後半の裁判シーンで持ち直すものの、殺人罪の公判なのに、検察側の宗教観に偏った被告の人間性の否定にシフトしていきます。本来は主人公の行動の不条理がテーマなんだろうけど、殺人はともかく神への無関心や他人との距離感は、むしろ今の感覚的にはあまり不条理ではなく、論点の違う裁判の方が不条理に感じます。そう言う意味で異邦人は主人公なのか、周りの社会なのか、もういっぺん、原作を読み直してみよっかな。役者は、さすが天下の二枚目マストロヤンニだけど、この役にしてはちょい老けすぎかな。
今となっては、これは喜劇ではないか?
大好きなマルチェロ マストロヤンニの腑抜けの名演技が、
最高に良かった。
今風に言えば、肉親の死も希望をなくしても、
普通に生きている。
結婚も愛情も友情も普通なんだ。
信仰なんて、神も、あるもないも、ない。
死刑となって必死に、
贖罪を懺悔を信仰を薦められても、
キモイ。
信仰者である司祭や検事が、
救済を贖う姿は正に喜劇でしかない。
原作当時は、
これは反社会的な行為だったのであろう。
オーム真理教を経験した時代のものには、
同じ匂いを嗅ぎ取る。
ちょっとふり向いてみただけの
肝心のアラブ人殺しよりも、母親の死の翌日に女の子と海に泳ぎに行って喜劇映画を見たことで断罪されるかのような不条理な物語はそのままなぞってはいるが、原作の文体は消えてしまう。「きょう、ママンが死んだ」と小説で読むのと、映像にヴォイスオーヴァーで語られるのではまるで印象が違う。もちろん映画作家にも映画としての文体はあるが、ルキノ・ヴィスコンティの文体はカミュには合っていないように思える(たとえばロベール・ブレッソンならどうか?)。
原作は若い頃読んで感銘を受けた作品だが、殺人のくだりなどこうして絵解きされてしまうと、何だか白々しさが目立つ。熱中症でふらついた挙句、岩場をちょっとふり向いただけで…なんてね。
仏領アルジェリアが舞台なのに、全員イタリア語を話しているのもやはり違和感がある。
ちなみに、イギリスのロックバンド、キュアーがデビュー曲の“KILLING AN ARAB”でほぼそのままの内容を歌っている。
ヴィスコンティ流の挿絵?
観た後に知ったが、ヴィスコンティは最初から原作の挿絵として、この映画を作ったらしい。作った本人としては、かなり良い出来の挿絵になったらしいが、どんなに素晴らしい絵でも所詮は挿絵、やはり、これは原作を読んでから観た方が良さそうだ。
但し、ラストシーンのマストロヤンニの表情だけは挿絵を超えて、ヴィスコンティが自分流の翻案にした気がする。
まだ原作を読んでないが、おそらく最後まで徹底して乾いた虚無感の余白を残して終わっているような気がするので。
というか、仮に原作がそうでなかったとしても映画の方は、そういったラストにして欲しかった。
あと、アンナ・カリーナはミスキャストに感じた。ゴダール映画の観過ぎか、奔放でない彼女は何処か物足りない。
イタリア語のアフレコを当てるくらいなら、ヴィスコンティ常連のクラウディア・カルディナーレの方が良かった。役にも合っていたはず。
ちなみに主人公の方は、最初はアラン・ドロンで考えていたらしいが、これはマストロヤンニで正解だったと思う。
アラン・ドロンも確かに虚無感はあるが、マストロヤンニと比べると虚無的な佇まいに少し余白が足りないので。
あとアラブ人を撃ってしまうシーンは、拳銃のアップではなく、銃声がなっている間は、思考停止になるほど、ひたすら眩しい太陽にして欲しかった。
そして撃ち殺した後には、引きのロングショットで、もっと乾いた空気感を出して欲しかった。
そして、本当は、この世界観はフランス語の方がリアルだったはず。
イタリア語ならではの人懐っこい感じや独特の感情表現が、ちょっと合わなかった気がする。
フランス語版もありそうなので、是非そちらも見てみたい。
タイトルなし(ネタバレ)
無神論者であるということは現代の日本ではさして驚かれることはない。寧ろ、熱心に信仰しているという人の方が、周りに引かれてしまうかもしれない。
しかし今作の舞台は、1940年代のフランス占領下のアルジェリア。当時のヨーロッパの世論では無神論者=異邦人という式が成り立つぐらい、神を信じないということは冒涜だと思われた。正義や倫理の指針である宗教を無意味だと言ってのける主人公ムルソーは、検察や陪審員から憎悪されるが、決して極悪人ではないのだ。彼なりに人生を歩み、彼なりに死を捉えたのだ。
流石貴族監督ヴィスコンティ。画が全てのシーン美しい。ギラギラと太陽が照りつけるアルジェの街。無機質な霊安室。光輝く海。暗い独房。
内容が日本人には難しいかもしれないが、映像だけでも観る価値あり。
名作だと思う
マルチェロ・マストロヤンニは年齢を経て味を出した俳優のように思っていたが、それは当方の勘違いで、栴檀は双葉より芳し、若い頃から素晴らしくハンサムで存在感のある俳優だった。演出のせいもあろうが、本作品では他の登場人物と一線を画した重厚な迫力がある。
アルベール・カミュの小説「異邦人」そのままのストーリーと台詞の映画だが、イタリア語とフランス語で少しニュアンスが異なる気がした。母音を力強く発音するイタリア語と、鼻母音が鼻に抜けるフランス語とでは、耳触りがかなり違ってくる。しかしマストロヤンニ演じる主人公ムルソーのモノローグは抑揚を抑え気味で、演出を原作のニュアンスに近づけている気がする。
約80年前に刊行された小説はいまでも新しさを少しも失っていない。同様に53年前に製作された本作品も、新しさを失っていないと思う。名匠ルキノ・ビスコンティは原作の意味するところを完全に理解して映画化した。つまりパラダイムに反する分子は常に異邦人として裁かれるということである。
ムルソーのモノローグや発言には「何の意味もない」「僕にとって無意味」という台詞が数多く現れる。裁判で検事は、既存の価値観を無視するかのようなムルソーの発言を、冷酷さ、無慈悲の発現だと決めつける。しかしムルソーの戸惑ったような表情からは、無意味という発言は怒りや憎悪とは無関係で、素朴に率直に気持ちを表現しただけのように見て取れる。このあたりのマストロヤンニの演技は光っている。
ムルソーは無神論者だが、神を信じている人々を否定することはない。ママの葬儀がキリスト式であることを嫌がりもしない。しかしキリスト教徒から信仰を強制されることは断固として拒否する。極めつけは「神のために時間を無駄にしたくない」と司祭に言い放つシーンだ。人間が信仰から精神を解き放っている証左の言葉である。この言葉がキリスト教社会においてどれほどセンセーショナルな言葉であるかは想像を絶する。ドストエフスキーに聞かせてやりたかった言葉だと思うのは当方だけだろうか。
人間は死を恐れ、死を夢見る。死の恐怖と生への執着は一体的で、まだ生きていたいと思う一方、この人生に何の意味もないことに気づいてもいる。死刑囚となったムルソーにも勿論死の恐怖はある。その死に何の意味があるのか。自分の存在価値は死刑執行のときに多くの人々の憎悪の的になることだと彼は思う。当然の帰結である。
本作品の意義はキリスト教のパラダイムから脱した精神性が生と死、存在と無というテーマにどのようにして挑んでいくのかを描いたところである。ビスコンティ監督は光と影のコントラストの多いシーンに不穏な音楽を合わせることで、上手にカミュの世界を描き出してみせた。名作だと思う。
原作を読みたい
残念作
監督、プロデューサー、そして俳優の名前を見て期待が高まったが、蓋を開けてみれば残念作であった。
途中、退屈して居眠りした自分にレビューの資格があるかは、とりあえず置くとして、「本当に、ビスコンティ監督作品なの?」と言いたくなるような、あっさりした作りだ。
「とりあえず小説を再現してみました」というだけに見える。
自分のイメージが間違っているのかもしれないが、マストロヤンニは年を取り過ぎているだけでなく(1967年公開時、43歳)、少しまとも過ぎる。
本作において、検事が正しいか、主人公が正しいかは問題ではない。(単なるモラルや宗教の話だけなら、刊行した1942年において、何も珍しくはないはず。)
検事を怒らせるほどの何かがズレた“異邦人”ぶり、つまり“鈍感力”や傲慢さ、自己防衛のための嘘をつかない率直さの表現に失敗していると思う。
原作は一人称である。
本作は、主人公の内面の表現が、決定的に欠けている。
他人が主人公を理解できないように、主人公も他人を理解できないという、不思議世界を三人称で描くのは、巨匠ビスコンティをもってしても不可能だったということかもしれない。
「神は死んだ」のではなかったか?
原作邦題の「異邦人」は素敵な訳だと思う。でもかなり違うと思う。他者、自分たちと異なる人、変わった人、訳わからない人、理解不能な人、考えも価値観も異なる人。そんな感じだと思う。
神はとっくに死んでいるのに、まして法廷の場面なのに、中立で冷静に判断すべき司法の人間が、陪審員の情に訴えるような芝居がかった話し方で、殺人のことに集中せずに、神のことや、母の死にあたってどうだったのかと、関係ないことばかりを言う。全く理性的でない。そして司祭(この役者さん、ベルモンドの映画に出てた!ブルーノ・クレメル!)もしつこい。
要するに、とりあえずマジョリティーである自分たちの思考の枠内でしか、物事を考えることも、想像力を働かせることもできない人達が、ムルソーを「他者」としている。が、ムルソーからしたら、ムルソーを弾劾する人々がまさに、他者で、理解不能な人々だ。
母とあまりいい関係ではなかったのかもしれない、でも養老院に行った母は親友もできて、自分と居たよりも幸せな晩年を過ごすことができたのではないか。母は死んだ。でも泣くことがそれへの一番の対応とは限らない。
ガールフレンドも男友達も犬のおじちゃんも、みんなムルソーのことを理解している。社会の上層には属していない人、マイノリティだけれど人数的には圧倒的多数にとって、ムルソーは他者ではない。まさに自分たちのことだ。今の世界とまるで同じだ。
大昔、文庫本で読んだけど全然わからなかった。原作と映画は異なると思うが、この映画をみることができて良かった。マストロヤンニ、素晴らしい。
全18件を表示