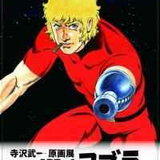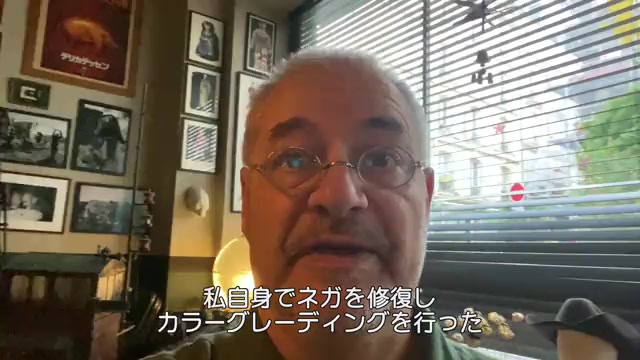デリカテッセンのレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
メアリを見る前に
シュールで不穏でブラックで美しい…ラブコメディ(!?)
不思議な世界観と、不穏な雰囲気、緊張感とシュールさに釘付けであっという間の100分!
SF!?ロマンス!?ブラックコメディ!?オムニバス!?形容しがたい独特な味があった。映像の色味とか美術のセンスもクセになった!
みんなとち狂ってるけど、オシャレで構成も綺麗で絶妙なバランスだった!ブラックな笑いが多いのに不思議と下品さがなく、どこか上品さがあるのがすごい。
主人公とジュリーのラブロマンスが可愛かったし、水中で見つめ合うシーンや2人で楽器を奏でるシーンなんかとてもロマンチックだった!
でもなんだかんだでお気に入りのシーン…というかしばらく頭に残りそうなシーンは、
ベッドの軋む音に合わせて住民たちがリズミカルにシンクロするシーンと、オーロールが全自動自殺機(!?)で何度も自殺を試みるシーン。笑
青春の思い出加点したら満点に
一度味わうとクセになるジュネ亭メニュー
ジャン=ピエール・ジュネがマルク・キャロと共同で監督した作品で、とてもデビュー作とは思えないぶっ飛んだ世界観が魅力です。世紀末のパリで人肉を売る精肉店で働くことになった男の文字通り食うか食われるかのブラック・コメディです。なんと言っても、セピア調でドロっとした映像や不気味な小道具、エグさたっぷりの強烈なキャラの登場人物達と、ジュネの作品に共通するスタイルが既に完成しているのが凄いです。また、主役または準主役にどこか未成熟で不安定な女性が出て来るのも、後年の『ロストチルドレン』『エイリアン4』にも通じるジュネの嗜好性があって面白いです。直接的な残酷なシーンはなく観客に想像させながら、独特のグロテスクで歪んだ情念を感じさせる映像はインパクトがありますが、ストーリーを動かすのは男女の恋であるのがフランス映画らしい所です。役者では、以後の作品でも常連になるドミニク・ピノンが妙な味合いです。意外とまともに見えるのは妖艶な肉屋の女房役のカリン・ビアールで、観る側もジュネの毒に当てられたのかな。
ジュネ&キャロの完成された長編デビュー作
笑った
スチームパンクの世界で繰り広げられる、食うか食われるかの争い。大昔にラジオCMでタイトルを聞いた覚えがあり(KBCシネマ北天神、のフレーズとともに)、辛気臭い(?)文芸作品系だと思い込んでいたら、笑えるブラックコメディであった。 オチは腹抱えて笑った。ちょっとカンフー映画っぽいコミカルさである。最後だけヒューマンドラマ風になっているのも皮肉っぽくて良い。/チンパンジーは、『NOPE』の源流のひとつかな??/あ、ひとつだけ、ジュリーがひどい近視で悩む場面があるが、どう見ても掛けてるの遠視用のメガネ!
建築の上下構造を徹底的に活用し、魔窟アパートを人体のごとく表現した悪夢的アイディア!
いやあ、懐かしい!
まさかリヴァイヴァルされるなんてね。
ちなみに僕は、この映画でミュージカル・ソウの存在を知った。
(この映画にしか出てこない架空の芸かと思ったら、実在した)
『デリカテッセン』は思い出深い映画だ。
大学時代、今は某県で地裁の裁判長をやっている友人といっしょに観に行った。僕は自分から人を誘って映画に行ったことはほとんどないので(大学の後輩を連れて『ガルシアの首』を観に行ったことが一度あるくらいw)、たぶんあいつから誘われたんだと思う。というか、彼は当時『ファミ通』の愛読者で、そこの映画紹介欄を見ては面白そうな映画があったら、よく僕に声をかけてくれていた。
彼は『デリカテッセン』をいたくお気に召したらしく、他の友人にも激賞して薦めまくっていたのをよく覚えている。今回のが30周年レストア版ということは、あれからもう30年経っているということだ。ああ、わが青春は遠くなりにけり(笑)。
いざ観直してみると、想像以上に何にも覚えていなかったことに、まあまあ衝撃を受けた。
アヴァンタイトルのゴミ箱に隠れるシークエンスと、
ラストシーンだけは細部までよく覚えていたのだが、
肝心の本編のほうを、まるっきり忘れ去っていた。
なんてポンコツな僕の記憶力。
でもおかげで、とても新鮮な気持ちで楽しむことができた。
『シリアル・ママ』のついでに前プロから行ってみたのだが、本当に観てよかった。
『デリカテッセン』は、30年前の感覚でいっても、きわめて斬新な映画だったと思う。
当時でも、これだけ映像にこだわりぬいた作品は稀だったし、
CGもない時代にそのこだわりを実写で貫きとおした作品も稀だった。
日本では諸般の事情で、およそ映画化不可能のブラックなカニバリズムネタ。
奇怪な住人たちにまつわる不謹慎なネタのオンパレードを、驚くほどセンス良く、抜群のテンポ感で、紡いでいく。
笑いとアクション、サスペンス、独特の美意識、社会風刺。
すべてがハイレヴェルな次元で融合している。
出演者たちの漫画チックな顔芸がまた、すばらしい。
ただあの時期には、こういう作品が生まれる「土壌」と「時代の空気感」があったのも確かだ。
まずは世紀末が近づくなかで、ディストピア的な映画が流行っていたのがひとつ。
82年の『ブレードランナー』(フィリップ・K・ディック原作、リドリー・スコット監督)で描かれた酸性雨に閉ざされた暗い未来世界の幻視的風景は、89年の『バンカー・パレス・ホテル』(エンキ・ビラル監督)へと引き継がれ、さらに本作へと引き継がれている。
一方で、ダークなユーモアと社会風刺とノスタルジックな映像感覚が融合した幻視的なディストピアものとしては、すでに85年に『未来世紀ブラジル』(テリー・ギリアム監督)が撮られており、主人公のキャラクターや「地底人」の造形(『ブラジル』におけるレジスタンス)も含めて、かなり影響を受けているように思う。ちなみに本作はアメリカでは「presented by Terry Gilliam」として発売されたらしい。
あと、フランスには、『ラ・ジュテ』(1962年)というディストピア映画の古典があって、『デリカテッセン』に出てくる変な眼鏡のオヤジなどは、明らかに『ラ・ジュテ』へのオマージュだろう。
カニバリズムを扱ったホラー・コメディにも先駆的作品があり、有名なものだと1980年のアメリカ映画『地獄のモーテル』(客を庭に埋めて太らせてからソーセージにする)がある。
もともと、英国のソニー・ビーンやスウィーニー・トッド(←伝説上の人物とされるが)、ドイツのフリッツ・ハールマンやカール・デンケなど、食肉目的で連続殺人を犯していた(もしくは死体の処理のために食用に卸していた)著名なシリアルキラーには枚挙に暇がない。
あるいは、泊り客を殺し続けていた宿屋のシリアルキラーというのも、H.H.ホームズを筆頭に結構知られている。
この従来からある欧米の「カニバリズム殺人鬼」「宿屋の殺人鬼」ネタと、『ブレードランナー』以降のディストピア幻想(毒の雨&荒廃した地上世界&食糧難)が交わったところに、『デリカテッセン』という異形の果実は実を結んだのだった。
― ― ― ―
それにしても、これだけアヴァンタイトルがうまくいっている映画もなかなかないような気がする。
「冒頭の数秒でわしづかみにされる」。よく言う定型句だが、実際に体験することはめったにない。でも、僕は間違いなくこの映画の出だしから、胸倉をつかまれるみたいに映画世界に引きずり込まれた。
靄のかかったようなセピア色の画面。
ヒエロニムス・ボスの絵に出てくるような、廃墟感のある建築のシルエット。
サイレント時代のドイツ表現主義映画のような雰囲気に、
ユニバーサル・ホラーっぽい「お化け屋敷」感が加わる。
ああ、これは「あちらの世界」の物語だ。
この世のものではない、わくわくするような幻想の世界。
ポーや、乱歩や、澁澤に耽溺してきた自分にとっての、本当の世界。
暗雲たれこめる「外」は、地獄のような情景だ。
ではあの建物の「なか」はどうか。
通声管を通してカメラが潜り込んでゆく。
聴こえてくる、まがまがしい包丁の研ぎ音。
ああ、なかも変わらぬ地獄のようだ。
得体のしれない巨漢の二刀流ブッチャー。
挙動不審の男の、いちかばちかの脱出作戦。
残酷に振り下ろされる巨大な肉切り包丁。
「上から落ちてくる」デリカテッセンの文字。
ああ、なんて魅力的なアヴァンタイトル!!
スタッフ紹介がまた、実にセンスにあふれている!!
(「衣装」の名前がわざわざ布の刺繍されているとか)
この映画が僕を魅了するのは、
すべての要素がまるで「からくり細工」のように構成されているからだ。
リヴィングストン博士の正体がチンパンジーだったり、あの世からの声が実在していたり、いきなり主人公が首だけで出迎えたりと、全編に「はぐらかし」と「仕掛け」があふれていて、建物の構造自体がきわめてトリッキー。おばあちゃんを呼び出す罠とか、オーロールの自動自殺装置(まさにピタゴラ装置!)だとか、地底人の地下迷宮だとか、キューブ兄弟の手作りおもちゃだとか、すべての要素が「からくり」の精神で構築されている。
稚気にとんだアイディアとトリックでしつらえられた「おもちゃ箱」のような世界。
こんなわくわくするような映画、めったにない。
僕が本作においていちばん感心するのは、
建築物の「上下構造」を巧みに用いて、
物語が組み立てられているところだ。
ダストシュート。通声管。
この建物には、謎の「管」が張り巡らされている。
この「管」を通じて、人々は、
モノを捨て、声を伝え、鍵を部屋に戻し、
幽霊を偽装し、相手の情勢をうかがう。
「モノ」や「音」が常に「上・下」に動いている。
建物の中央には螺旋階段があって、
住人の部屋が各階に配されているのだが、
とにかく上下動の移動アクションが
徹底的に強調される。
「上から落ちる」「壁をよじ昇る」
「上から落とす」「下から投げる」
「階段を上がる」「階段を下がる」
「部屋に穴が開く」「水が押し寄せる」などなど……。
他にも、
「下の階の女性の下着を、釣り糸で釣り上げる」
「赤い毛糸の玉を階段から落として拾いにいかせる」
「銃口にひもを垂らして、牛乳を拳銃に流しこむ」
「モノが上から落ちることで起動する自動自殺装置」
などなど、印象的な「上・下」のシーンは目白押しだ。
終盤になると、「地底人」を呼びにジュリーはマンホールから地下に「下る」。
「地底人」はダストシュートを使って「地下から上がって来る」。
肉屋とピエロの、アンテナをめぐる攻防戦の舞台は「屋根の上」。
やがて「火」は下から上を炙り、「水」は上から下へと押し寄せる。
その後の展開は、ご覧になったとおりだ。
その象徴的なアイコンとして、
「丸い穴から首を出す」
あるいは「蓋を持ち上げて首を出す」
カットが執拗に繰り返される。
アヴァンの「ゴミ箱の蓋を持ち上げて様子をうかがう男」。
奇術用の箱から首を出している「頭に包丁を叩き込まれた男」。
マンホールを持ち上げて地上世界の様子をうかがう「地底人」。
おなじくマンホールを持ち上げて顔を出す「肉屋の愛人」。
「建築の上下構造を巧みに用いた映画」としては、なんといっても『ダイ・ハード』(1988)が想起されるが、本作はまさにその衣鉢を継いでいるといってよい(このノリはやがて、『JUNK HEAD』『マッドゴッド』(いずれも2021)へと引き継がれることになる)。僕と同世代の人間には、昔懐かしいロールプレイングゲーム『ドルアーガの塔』の上下構造を思い出す人もいるかもしれない。
「ダストシュート」や「伝声管」といった、建物内に張り巡らされた「管」の存在は、一義的には『未来世紀ブラジル』から引き継いだ要素だろう。
ただし、伝声管を用いてスパイするネタは『会議は踊る』(31)までさかのぼれるし、カメラが「気送管」の中身の移動を追うショットは、トリュフォーの『夜霧の恋人たち』(68)にも登場した。そもそもパリでは気送便(プヌマティック)――エアシューターを利用した郵便サービスが1984年まで稼働していたことを忘れてはならない。我々から見ると、なんでも「管」で行き来させるのはいささか奇異な仕掛けに思えるが、パリジャンにとっては意外にそうではないのだ。
こうして「上下構造」を「管」で結び付け、
各部屋をたがいに連動させた結果として、
本作に登場する下宿屋兼肉屋デリカテッセンは、
ある種「人体」のような「有機性」を帯びることになる。
建物自体が、ある種の「生物」として浮かび上がるのだ。
そもそも、映画内で何度も挿入される外観の不気味なカットは、明らかにユニバーサル・ホラーあたりの「お化け屋敷」を意識したもので、建物自体に禍々しい何かがあると思わせる狙いがある。
張り巡らされた「管」は、まさに屋敷の「血管」のようなものだ。
いま流行りの『はたらく細胞』そのままに、すべての部屋がさまざまな「管」によって有機的に結びつけられ、どこかの部屋で何かが起きれば、それは瞬く間に周知され、別の部屋での活動に結びついていく。
この建物は「肉食」(地底人は「草食」)で、基本的に「外から栄養源を吸収している」(求人広告によって募集される下宿人)が、栄養供給が断たれると「貯えられている脂肪分や筋肉を分解して栄養分に変える」(ほかの住人の誰かを食べる)ことになる。
司令塔(脳機能)にあたるのは一階の肉屋だが、「夜に階段に出てきてくれないと処理できない」というルールは、肉屋にも破れない。そこにサーカスの元ピエロだった「異物」が取り込まれたことで、既存の「代謝」のシステムが崩壊してゆく……。
本当によく出来た話だと思う。
本作には、社会風刺的な部分があって、特にドイツ支配下(ヴィシー政権下)のフランスにおける相互監視と隣人殺し、およびレジスタンスの活動といった部分は、間違いなく念頭に置いて作られている。近未来における食糧問題と、食肉やビーガンの問題もまた然り。
ただ、そこにことさら焦点を当てているかというと、そうでもない気がする。
やはり本作はあくまでコメディであり、アクションであり、何よりラブ・ロマンスなわけで、本筋としては観客を楽しませることがいちばんの映画だと思うし、観客も流れに身を任せてとにかく楽しむことがたいせつだと思う。
特に、ラストで肉屋を待ち受ける「因果応報」のオチは爆笑必至。
そのあと訪れるラスト・シーンも、夢見るように美しい。
ていうか、肉屋の映画だから、ミュージカル・ソウ(鋸)なんだよね。
あと、肉屋役のジャン=クロード・ドレフュスは控えめにいって最高(とくに婆さんを脅すシーン)とか、足を食べるシーンは『ジャバーウォッキー』(77)由来だとか、殺人アパートといえば『13 みんなのしあわせ』(2000)だとか、いろいろいいたいことはあるんだが、紙幅が尽きました。
ご覧になったことがある方もぜひ劇場で!
当時と変わらず…
ポップでかわいくて狂気
ここ数年、レストア版のリバイバルが多くて嬉しいかぎり。
これも当然のことながら田舎では上映されず、中高生の頃に悔しい思いをした作品のひとつ。
ジュネ作品の中では『ミックマック』が一番好きなのだけど、これはもっとぶっ飛んでる。
食人族vsベジタリアンの地底人なんて荒唐無稽なアイデア、しかも人肉だって事を客も知ってるとか頭おかしすぎて素晴らしい、天才ですか?
カメラアングルや美術も、随所に細かいこだわりが。
近未来という曖昧な時代設定のおかげでまったく古さは感じないし、ベッドの軋む音を様々な音とリンクさせるシーンはかなりポップな仕上がり。
それにしてもずいぶんと製作費が掛かっている印象だけど、当時30代半ばだった新人監督に思い切った投資をしたもんだ。
4Kレストアするほど古くはないけれど『ミックマック』『天才スピヴェット』をもう一度スクリーンで観たいなぁ。
癖になるブラックユーモアの世界
もともと「映画」って…。
DVD特典の監督自身のコメントによれば、本作は、監督がオンボロアパートに引っ越した折に「変わり者がたくさん住んでいて、いろいろとトラブルが絶えないアパートかも知れない。もし、そうだったら、面白い。」と妄想したことから着想を膨らませ、低予算で作った作品だったとのことでした。
映画作品の内容としては、実話モノ(ドキュメンタリー)あり、小説などの原作を底本とするものなど、いろいろとありますが、映画作品というものが、そもそも監督の知的創造の産物であるとすれば、本作のように監督の想念を少しずつ膨らませて、一本の作品に仕上げるというのは、案外とオーソドックスな製作方法と言えるのかも知れません。
◯アパートの大家は、建物に同居しているのがいい。
◯建物の一階で(入居者も顧客にして)商売をしているというのが良い。
◯肉屋はどうだろう。入居者から家賃を取るほか(食材として誰でも買う)肉を売って儲けている。
◯毎朝、決まった時間に肉切り包丁を研ぐ様子が不気味。
◯古いアパートで、変わり者もたくさん住んでいるし、ドブネズミ(トログロ団)も出没する。
監督の想念を、少しずつ膨らませて(映像化して)一本の作品として仕上げる―そういう意味では「映画らしい映画」ともいえる一本だったと思います。
佳作であったとも思います。
評論子は。
ツボでした
なんだかよくわからないな映画
個性が溢れる住人で、ストーリーの途中途中もクスッと笑えるところがあった。カエルとかナメクジがいる住人の部屋を見た時は、気持ち悪くなった。それがマイナスの減点。うーーん、見てて共感できる部分がなかったのが残念。昔ながらの映画だ思うけど、自分には合わなかったなー
共食い
こういう映画を撮れるのは、
ルイ国王やマリー・アントワネットをギロチンで殺して 快哉を叫んだフランス国民ならではなんだろうなあ。
国歌「ラ・マルセイエーズ」も、歌詞を見れば眉をひそめますよ。卒倒するような血の海と喉笛を掻き切る残虐さですもん。
🇫🇷
「アメリ」のジャン・ピエール・ジュネ監督が「アメリ」の10年前に撮ったとのこと。
なるほど、両方の作品に共通するのは・・恋愛に発展するファンタジーなのかな?と思いきや、実に奇っ怪でサイケデリックな暗黒もの。
うっかり子供と一緒に観てしまっては慌ててしまう明け透けな性行為と、そして本作ではカニバリズムなんですよ。
🇫🇷
おどろおどろしくて、画像は同じ年に公開されたジョニーデップの「シザーハンズ」の系譜かもしれない。
でも特殊メイクではないのです。
人間が持っている生の面相が、そのままのグロテスクさで勝負しているところがいい。
これ、キャスティング担当者は奇天烈な顔の俳優をオーディションで選りすぐったのだろうし、魚眼レンズで写す住人たちの薄気味悪さがどの人も最高でした。
🇫🇷
最終戦争後の地球が舞台とのこと。
小さなアパルトマン=地球号に同居していながら、お互いに喰い合ってでも生き残ろうとする我ら人類の「共食いの醜さ」を、ニヒリズムたっぷりに描いているのかも。
【陽光も降り注がない近未来のデリカテッセンで、行われていた事を描く、ブラックシュールなコメディ。】
ー ジャン=ピエール・ジュネ監督作品は、「ミック・マック」で出会い、その不可思議な世界観に嵌ったモノである。
その後、新作は欠かさず見てきたが、初期作品は鑑賞する機会が無かった。-
◆感想
・どこのどの時代にあるのか分からない舞台設定。初期からブレない世界観。
・デリカテッセンの求人募集にやって来た人の良いルイゾン(ドミニク・ピノン:彼は、今作以降ジャン=ピエール・ジュネ監督作品には欠かせない存在となる。)
・どこからか、供給される”肉”。何もない筈なのに・・。
・徐々に明かされる、デリカテッセンの秘密とは・・。
<最初期作品と言う事もあり、ストーリー展開に粗さはあるが、ジャン=ピエール・ジュネワールドはこの作品が出来た時点で、厳然と出来上がっていた事を確認した作品。>
おフランスのスウィーニートッド?
あれ?ドミニク・ピノンがカッコいい。
18年5本目。 【デリカテッセン】観た。舞台は核戦争後、荒廃したフ...
全23件中、1~20件目を表示