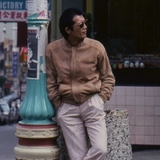サムライ(1967)のレビュー・感想・評価
全27件中、1~20件目を表示
アラン・ドロンの孤高の存在感とメルヴィルの創造性が融合した一作
本作において、“サムライ”と直接結びつくのは冒頭に掲げられた文言だけで、あとは殺し屋の日常が淡々と描かれていくのみ。おそらく監督は、この孤独な生き様や、何事にも特殊なこだわりを持った生活様式を、サムライのそれと重ね合わせたかったのだろう。
見所なのは、冒頭のシーン。雨の音が絶え間無く続く中、クレジットを映し終えると、ほぼ不動に近かった室内が急にボワンボワンと膨張と収縮を始める。これはカメラを後退させてはズームしたり、ストップ・モーションを加えたりする操作の産物らしいが、この場面を通じて「すべてが動き、同時にすべてがそこにとどまったまま」という象徴的な状況を描きたかったそうだ。
主人公は決して刀を振り回したりしないが、かくも精神性の部分で、サムライにも似た特殊な境地を表現しようとする。何者にも束縛されず、自由に創造性を羽ばたかせる。そんなメルヴィルの研ぎ澄まされた流儀がとても粋な一作だ。
警察が一番怖い
原題からして「サムライ」、そして冒頭に「武士道」のテロップ
完全に日本かぶれしたフランス映画だと確信して見始めたが、
1968年という年代も、アランドロンという当時を席巻した大物俳優の主演に 少し意外に感じる。
中身は単純。
○し屋の主人公が巧妙に警察の追及を免れるも、依頼主から消されそうになり、
その報復は果たすものの、自滅の道を選ぶ。
散る美学というものを日本の侍に重ねたように思えなくもない。
この当時の警察の強引さは想像に難くないが、
それでも映画の中の捜査には引く。
家宅侵入、盗聴などの違法捜査に加えて、
証言の誘導、偽証強要、脅迫、違法捜査の見本市と、見込み捜査のためなら何でもやっている。
この映画はたまたま真犯人だが、
「アラン・ドロン主演の「暗黒街の二人」では、
強引な刑事の思い込み捜査の為に 更生していた前科者が破滅に追い込まれる」
というある意味、逆パターンも起こりえる。
意外だったのは、カティ・ロジェ。
本作品で とても雰囲気のある演技をしているのに、その後あまり脚光を浴びていない。
ナタリー・ドロンの演技と比べても決して見劣りしないが、カティ・ロジェが売れなかったのは、やはり肌の色のせいたろうか。
フランスの差別の根深さを感じてしまう。
好き嫌いはあるだろうけれど完璧な映像美と完璧なアラン・ドロンを観ることができる完璧な作品
冒頭、新渡戸稲造の著書『武士道』からの引用と覚しき一節が映し出されるのだけど、『武士道』にはそのような一節はないそうである。
でも、それでいいのである。
映画とは壮大なウソであり、作品を面白くするためなら監督はいくらでも大胆なウソをついていいのである。二流、三流の監督はリアリズムや物語の整合性にこだわりすぎてしばしば作品の面白さを見失ってしまうことがあるが、本末転倒と言うべきだろう。
この作品の中の世界で出版されている『武士道』にはそういう一節が確かに書かれているのだ。
これはそういう、現実とは違うもうひとつの別の世界の物語なのである。
監督のジャン=ピエール・メルヴィル自身も「私はリアリズムには興味がない。私の映画は全て空想に依存している。私はドキュメンタリー作家ではない。映画は何よりもまず夢である」と語っている。
本作でアラン・ドロンが演じるのは孤独な殺し屋だ。仕事に行く前、自宅のアパートの部屋で身支度をするのだが、身に着けるのはグレーのスーツにベージュのトレンチコート、グレーのソフト帽というクールな出で立ちである。
普通に考えれば、殺し屋がこれから汚れ仕事をやろうというのにトレンチコートとソフト帽でスタイリッシュにビシッと決める必要はない。
でも、リアリズムから遠く離れたこの場面こそがこの映画の最大の見せ場と言ってもいい。
この場面こそが、サムライが死地に赴く際に身支度をきちんと整える、言わば死装束の場面だからだ。
トレンチコートの襟を立て、鏡の前でソフト帽のつばに指を滑らせるアラン・ドロンの完璧な美しさ。ここにこの映画の全てが凝縮されていると言っても過言ではないだろう。
映画という虚構の世界、夢の世界であるからこそ、我々は現実には決して存在しない完璧な美しさを備えた殺し屋を目の当たりにすることができるのである。
「映画を観る」という喜びの一つの極致がここにある、と言ったら言い過ぎだろうか。
さらには、メルヴィル・ブルーと呼ばれる青みがかった灰色の映像美も素晴らしい。
さびれた路地裏も美しい。安アパートも美しい。ナイトクラブのような現代的な場所はすぐに古臭くなってしまうものだけれど驚くべきことにこういう場所も美しい。どこを切り取っても完璧なまでに美しいのである。
物語自体はやや単調な印象を受けるが、自分はこの作品を、メルヴィルがアメリカ的な犯罪パルプ小説を一人の孤独な戦士(サムライ)の叙事詩にまで高めたもののように感じた。
娯楽作品ではなく叙事詩だ、などと言ったらやっぱりちょっと言い過ぎだろうか(笑)。
コッポラ、スコセッシ、北野武、ジム・ジャームッシュ、サム・ペキンパー、ジョン・ウー、ジョニー・トー、タランティーノ、リュック・ベッソンなど、自分のスタイルに強いこだわりを持ち独特のノワール的な作品を撮ることで知られる監督たちがメルヴィルの影響、特に『サムライ』の影響を受けているようだが、それもむべなるかな。
本作は、もちろん好き嫌いはあるだろうけれど、一つの完璧なフィルム・ノワールである。
ノワール的な作品を撮る作家性の強い監督たちが、これほど完璧に造り上げられた作品の影響を受けずにいられるわけがないのだ。
NHKBSにて2度目の鑑賞 フランスらしいというのか、どんよりとし...
ナタリードロンのデビュー作だった。
とにかくたくさん歩くサムライ
アラン・ドロンが暗い暗い、中折れ帽とトレンチコートを身にまとう一匹...
映画鑑賞の原点
1968年7月14日、私は「サムライ」を観た。
近所の名画座で「サムライ」「続夕陽のガンマン」「007は二度死ぬ」の3本立てであった。他の2本も楽しめたが、何と言っても私の心を捉えたのは「サムライ」である。
淡いブルーの色調に抑えたアンリ・ドカエのカメラ。フランソワ・ド・ルーベの音楽。派手に流れないジャン・ピエール・メルビルの演出。アラン・ドロンの演じたストイックな一匹狼の殺し屋に魅せられてしまい、ラストシーンでは思わず涙が出てしまった。
映画とは素晴らしい物だと思い、少しでも多くの素晴らしい映画と出逢うために映画館通いが始まった。
最初は名画座ばかりだったが、そのうちロードショーへも行くようになり試写会へも応募するようになった。観た映画をノートに記し、映画雑誌を読み、スタッフやキャストも気にするようになった。初めのうちは洋画オンリーであったが、黒澤明の「七人の侍」を観てからは邦画へも目を向けるようになった。いつしか映画を観る事が生活の一部になった。
この映画は、私の映画鑑賞の原点である。
あの日流した涙は何だったのか。その答えとの出逢いを求めて、私は今日も映画館の暗闇の中へと出かけて行くのである。
1968. 7.14 東十条オデオン座(併映 続夕陽のガンマン、007は二度死ぬ)
1968. 7.16 赤羽オデオン座(併映 続夕陽のガンマン)
1970. 7.25 シネマ新宿
1970. 9. 6 テアトル新宿(併映 泥棒を消せ、華麗なる賭け)
1971. 2. 7 テアトル新宿(併映 さらば友よ)
1971. 6.27 テアトル新宿(併映 冒険者たち)
1971.10.22 テアトル新宿(併映 さすらいの狼)
1973. 4. 9 池袋文芸座
1973. 7. 7 テアトル新宿(併映 さらば友よ、リスボン特急)
追記:1990年代以前の鑑賞日の設定は出来ませんでした。
追記2:映画の冒頭「ジャングルの中の虎に似てサムライの孤独ほど深く、厳しいものはない−武士道-」という字幕が入ります。
これは武士道が出展ではなく、ジャン・ピエール・メルビルが考えたものだと、本人がインタビューで語っています。
孤独が深く、厳しいものとしてのサムライだと言う事でしょう。
追記3(2024.7.29NHK-BS 字幕・大城哲郎⇒追記2の翻訳のニュアンスが若干違う)
・当時アラン・ドロン夫人だったナタリー・ドロンは本作が映画デビュー。
・ナタリー・ドロンの部屋を訪ねて来る記憶力のいい男はミシェル・ボワロン監督。
・ナタリー・ドロンは、この後ミシェル・ボワロン監督の「個人教授」に出演して日本で人気が出る。
【笑顔無き、自身の殺しの流儀を変えない孤高の殺し屋を演じたアラン・ドロンのスタイリッシュな魅力炸裂作品。】
■恋人ジャーヌ(ナタリー・ドロン)にアリバイを頼み仕事に出掛けていく殺し屋・ジェフ。(アラン・ドロン)クラブの経営者を殺害し、現場を後にしようとしたその時、黒人歌手・バレリー(カティ・ロジェ)に顔を見られてしまう。
だが警察で行われた面通しで、なぜかバレリーはジェフが犯人であることを否定する。
◆感想
・灰色がかった硬質な映像と、最小限の音楽。そして、ニヒルなまでに、自身の殺しの流儀を変えない孤高の殺し屋ジェフを演じたアラン・ドロンが、格好良すぎる。
ー トレンチコートに、帽子。長身痩躯なアラン・ドロンの姿が印象的である。-
・資料によると、ジャン・ピエール・メルヴィル監督は、日本の侍をイメージしてジェフのスタイルを考えたそうである。
<抑制したトーンの中、警察に追われるジェフが地下鉄を巧みに使うシーンや、バレリーが演奏するバーに現れた時に、彼の拳銃には銃弾が入っていなかった所など、作品全体が醸し出す雰囲気が、格好良すぎる作品である。>
ジャングルの中の虎に似てサムライの孤独ほど深く、厳しいものはない‼️
アラン・ドロン扮するジェフ・コステロ‼️彼こそサムライである‼️目深にかぶったソフト帽、襟を立てたトレンチコートが虚無感を漂わせて何ともカッコいい‼️サムライですね‼️「武士道」の厳しいルールを自分に課しながら生きている彼は、常に深く熟考し、引っ切りなしに煙草を吸い、部屋の中でも決して帽子を脱がないような男‼️サムライですね‼️ジェフは孤独で無口で、暗い部屋に一人暮らし、小鳥一羽を同居人としている‼️サムライですね‼️常に死と対決しながら冷静に行動し、裏切られることはあっても裏切ることはなく、殆ど表情を変えず、落ち着いて相手を射殺するが冷酷ではない‼️サムライですね‼️わが道は死ぬことと知っている‼️本物のサムライですね‼️カラーなのにまるでモノクロ画面のような渋い色彩設計、セリフではなくジェフの行動のみで物語を語るジャン=ピエール・メルヴィル監督のスタイリッシュな演出‼️彼もまたサムライですね‼️他人を一切寄せ付けず、己のスタイルを貫き通して死んでいく殺し屋を、日本の侍のイメージとダブらせるなんて、フツー思いつかない‼️天才ですね‼️線路にかかった陸橋の上で、ジェフが金髪の男に襲撃されるシーンは何度観ても息を呑む素晴らしさ‼️サイコーのフィルムノワールの一本ですね‼️
かっこよさがかっこよさであった時代
アラン・ドロンの孤独な殺し屋
1967年(仏/伊)監督:ジャン=ピエール・メルヴィル
孤独な殺し屋のアラン・ドロン。
ソフト帽にベージュのトレンチコート。
着こなしが完璧な上にその姿・お顔の美しいこと。
アラン・ドロンを堪能する映画でした。
ジェフ・コステロ(アラン・ドロン)は金で人殺しを請け負う孤独な殺し屋。
題名は「サムライ」ですが、誤解が海外にはあるようです。
サムライ(武士)は組織(主君とか藩に属する職業で、大義のためには命を捨てて戦うけれど、
殺し屋ではない。特に孤独な訳でもない・・・)
ジェフはナイトクラブで《殺しの仕事》を果たして部屋を出る時、黒人のピアニストに
顔を目撃されてしまいます。
面通しでピアニスト(カティ・ロジェ)は嘘をつき、ジェフをかばう。
事前にコールガールのジャーヌ(ナタリー・ドロン)に、アリバイ工作を頼んでいたジェフ。
一旦釈放されたものの。
主任警部(フランソワ・ペリエ)は、犯人はジェフに違いないと確信して、
包囲網を引いて行く。
メトロの追っかけっこ=逃亡劇は、スリルがあります。
マンツーマンで警察官がマークする中、彼らを巻くジェフのカッコ良さ!!
ジェフが車を盗む手口。
鍵束がネックレスのようです。
一個一個試して即、エンジンが掛かりスタート!!
盗んだ車を仲間のアジトに持ち込んでプレートを変えて、ついでに銃を受け取る。
と、かなり周到な仕事ぶり。
孤独なサムライの心を慰めてくれるのは毛色の悪い、声も悪いカナリアだけ。
この映画、カラーなのにほとんど色味がないです。
肌の色と車のライトが目立つくらいで、ほぼ無彩色。
会話も少なく、心の繋がりを断つジェフだけがポッカリと浮かび上がります。
しかし殺し屋の嗅覚は鋭い。
部屋に押し入ってきた殺し屋。
ジェフの首に銃を押しつける。
ジェフの目つきが瞬時に殺気立ちます。
目の前に肉塊をぶら下げられたドーベルマンのように、素早く襲いかかるジェフ。
流石の凄腕だ!
この暴力=心底プロの殺し屋だと知ります。
ラストの展開は、覚悟を決めたのでしょうか?
孤独な男は最後まで、1人ぽっち・・・でした。
一匹狼の殺し屋の運命
フィルムノワールとはこれのことだと思います
冒頭に武士道の一節が出てくる。よく判らないが新渡戸稲造のだと思う。
外国人は、孤独と侍を結びつけて捉えている。日本での侍の位置付けとは少し異なっている──と思う。
日本で侍が描かれるとき、それは七人の侍のごとく多様だが、孤独のエレメントよりは、概して、秩序を重んじ義理がたく豪胆に描かれる。平生は穏健で、理想は久蔵の宮口精二の感じ。
日本人が侍のイメージを孤独とつなげないのは、おそらくメディアに孤独な男の話が少ないから──でもあるだろう。ふつう、しゃべらない男の映画なんて作ろうと思わない。
転じて、それをやっている映画には自負があるに違いない。フォレストウィテカーのゴーストドッグ、ジョージクルーニーのThe American、ライアンゴズリングのドライブ、フレッドジンネマンのジャッカルの日。孤独で寡黙な一匹狼──それらの基点となる映画がメルヴィルのサムライだと思う。
フィルムノワールという定義があり、それをよく判ってはいないが、個人的には、とても狭義な枠と捉えている。
私見としては、幸福、饒舌、陽気、人情、楽観などの属性を持った人間がひとりも出てこない映画で、何事にも動じない男が自律や掟に副って生きている。
かれは幸福にならないが、不幸にもならない。なぜなら悲劇臭を出さないのがフィルムノワールだからだ。死のうが生きようが、たんなるファクトとして置かれる。
哀感は多少あってもいいが、訴えるのはだめ。仲間や相棒はいいが、仲良しはだめ。女はいいが、情愛はだめ。ミッションを成し遂げるのはいいが、無償はだめ。生き残るのはいいが、ハッピーエンドはだめ。──それが私的認識のなかのフィルムノワールである。
すると誰もが聞いたことがあるこの定義が、ほとんど数作に絞られてしまう。本編はその筆頭だと思う。かえりみて、外国人の定義によって侍を教わったところは大きい。
アラン・ドロンがカッコ良すぎる。警察と依頼人、双方から追われる孤独...
全27件中、1~20件目を表示