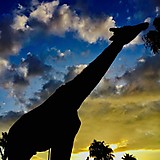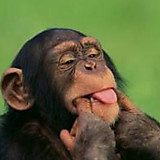軽蔑(1963)のレビュー・感想・評価
全39件中、21~39件目を表示
観たかった度◎鑑賞後の満足度◎ 冒頭の「映画とは欲望世界の視覚化である」というゴダールの言葉が頭を巡り、BBの美尻から目が離せない。鑑賞中ずっと“ああ、映画だ”と思わせてくれたのは流石ゴダール。
①この10月にパリに行った時にお世話になったガイドさんの日本語の生徒さんであるフランス人のご婦人を2名、先週奈良を案内させて貰ったのだけれども、その内のお一人のボーイフレンドがフランスでも高名な映画批評家だったということで、当たり前だが古今東西の映画にお詳しいこと(ビリー・ワイルダー監督を記念しての映画上映会で本物のグロリア・スワンソンにお会いしたことがある、と聞いてぶっ飛びました-ということは私も間接的にグロリア・スワンソンに会ったということ?-ってな訳ねえだろ)。
映画談議が弾んで楽しかったのですが、“来週ゴダールの『軽蔑』を観に行くんですよ”と言ったら“あれは良い映画よ”とのお言葉。
“でもゴダールの映画って難しいんですよね”と言ったら、“ゴダールの映画は考えるより感じるのよ”って仰いました。
本作を観たら確かにそのような気がする。
②ギリシャ哲学を始め色んな古典から引用された台詞が多いけれども、内容は有って無いようなものかな。
ゴダールは本作で映画を作っている人達やその周りの人達を描きながら“映画”を語っているような印象を受ける。
③映画のラスト近くの事故シーンはシモーヌの女としての落とし前の付け方のような気がする。
④なお、フランスの友達によると、今のフランスの若者にとってブリジッド・バルドーは、フランスを代表するセックスシンボルというより、動物愛護熱がヒートアッブしているアブナイお婆さんというイメージらしい。ああ、栄枯盛衰😢
⑤フリッツ・ラング監督はよく出演を承諾したなァ、と思います。
⑥ジョルジュ・ドリリューの音楽もすこぶる宜し。
夫婦の絆、西欧の起源、映画。
1963年。ジャン=リュック・ゴダール監督。妻の心変わりを察した男の右往左往の物語と、その要因を補足する(かもしれない)話として、夫の仕事(映画の脚本)と金をめぐる話と、映画を製作するプロデューサーや監督、出演者の話(特にアメリカ資本と映画監督の関係)と、さらにその映画作品自体(オデュッセイア)の物語(ユリシーズとその妻の関係)が複雑に重なりながら進行する。だから、例えばブリジッド・バルドーは心変わりをする妻であり、アメリカ資本の力に揺れるフランス人であり、映画製作につきあう素人であり、ユリシーズの妻である(ついでにブレヒトでもある。みればわかる)。作中の映画監督フリッツ・ラングが原作とプロデューサーの要求の間で微妙な距離とバランスをとって自分らしい映画をつくろうとするように、ゴダール監督も原作小説と微妙な距離とバランスを取っている。それがつまり映画というものだということらしい。
赤、青、黄の原色が意味を持って配置され(特に金の色ともいうべき黄色が特徴的)、イタリアの撮影所を自転車が走り、映画館ではロッセリーニの「イタリア旅行」が上映されている。アメリカ資本、ドイツ人監督、イタリアの撮影所。そこにフランス人の脚本家夫婦が入ってきて、ヨーロッパの起源ともいうべき物語をテーマに、映画撮影という営みが遂行される。ゴダール監督の作品に通底する組み合わせ。しかも、他の監督作品に比べて、引用元は明言されていることが多いし、物語の展開も心理的にわかりやすく、困惑するところがほとんどない。ゴダール監督はこの作品から入るべき。
意識下に色
予想を超える難しい映画だった。
脚本家であるポール(ミシェル・ピッコリ)は、妻カミーユ(ブリジッド・バルドー)とローマのアパートで幸せだったが、アメリカ人のプロデューサーのジェレミー(ジャック・パランス)から、フリッツ・ラング監督の映画「オデュッセイア」の難解な脚本の修正を依頼される。アパートの購入代などが気になるポールは、妻がジェレミーに誘われるのを、黙認する。
ここで、ギリシアの叙事詩に親しんでいる西欧人ならば、イタケーの王オデュッセイア(ラテン語だとウリッセ、英語読みだとユリシーズ)が、トロイア戦争ののち10年間も漂泊し、彼の不在の間、妃のペーネロペー(ペネロペ)が多くの男たちに求婚されることから、容易に、ポールとユリシーズ、カミーユとペネロペ、ジェレミーと求婚者を対比できるのだが、我々日本人には手に余る。
結局、3人は、フリッツ・ラングが撮影を進めている映画のロケ地、あまりにも美しいカプリ島を訪ねるが、カミーユのポールに対する愛は冷めてしまい(軽蔑)、あまつさえ、カミーユとジェレミーは出奔する。おそらく、その背景には巷間伝えられているようなゴダール監督と(私の一番好きな)当時の妻アンナ・カリーナとの不安定な関係が影を落としているのだろう。
すると、人間関係だけでも、3層の構造があることに気づくのだ。底辺にゴダールの個人的な事情が横たわり、その上にポールとカミーユの劇的な関係、しかし、それにはユリシーズから由来する規範が存在する。
映画として見ると、ゴダールの始めたヌーヴェル・ヴァーグを基層に、長編第6作にして初めての大規模な予算をかけて製作に乗り出したイタリア・フランス合作映画であるが、ハリウッド映画の影もある。特に驚いたのが、62年当時すでにヨーロッパの映画産業には衰退が目立つこと。ハリウッドでは早くからテレビに押されていたことは知っていたが。そこでバルドーを登用したことは、よく判る。製作者からの要請があったとは言え、バルドーの肢体は、この世のものとは思えないくらい素晴らしいのだが、演技者となると疑問もある。表面上は、あんなに避けていたジェレミーと出奔したのち、表情に何の曇りもみられない。もちろんゴダールは、それを狙っていたのだろうが。
それにしても、あの「勝手にしやがれ」で輝いていた手持ちカメラの使用による疾走感はどこに行ったのか。セリフや演技の自発性は感じられ、カットの多さ、引用癖も十分、残っていたものの。やはり、64年のBande à part、65年の「気狂いピエロ」を待たなければいけないのだろう。
【”愛は一瞬にして消える・・。”妻から、”軽蔑してる”と言われたくはないなあ・・。ラストも物凄くシニカルな作品である。】
ー 本当かどうかは定かではないが、今作はゴダール監督が当時の妻であるアンナ・カリーナとの関係性が不安定な時期に制作された事から、今作の映画監督ポールとその妻カミーユ(ブリジット・バルドー)の夫婦仲が、一夜にして一方的にカミーユのポールへの想いが冷え切る姿に、ゴダールの苦悩を反映していると言われた作品である。-
■劇作家のポールは、大作映画『オデュッセイア』の脚本の手直しをプロデューサーのプロコシュから依頼される。
そんな彼を、女優である妻・カミーユは軽蔑のまなざしで見つめている。
ポールとカミーユは映画ロケ地に招かれるが、夫婦の間に流れる倦怠感は変わらず、さらなる悲劇を招く。
◆感想
・前の晩は仲良くベッドを共にしていたのに、翌日のカミーユのポールに対する冷たく、ぶっきら棒な態度が凄い。怖い。
・ポールはそんなカミーユに色々と理由を訪ねるのだが、カミーユは死んでも答えないと言い、ポールの見える所でプロコシュとキスをするのである。
<妻ある男にとっては、今作は実にキツイ映画である。
何故に、妻の愛が消え去ったのか分からない男の、焦燥と不安。
だが、ゴダールはローマに車で出かけたカミーユとプロコシュに対して、シニカル過ぎるラストを用意するのである。
当時のヨーロッパの映画産業の斜陽化と、ハリウッド化への警鐘を鳴らした作品とも言われているようである。>
解説させて頂きましょう
オデュッセウスがトロイに置き去りにされてから、故郷に生還して奥さんを窮地から救うまでの物語をオデュッセイアと言います。夫婦の愛と絆を描いた物語です。
さて
この主人公は奥さんに枕営業させたわけです。しかしそれが完全に計画したものであったのか、そうなることが分かっていたのか、それともわかっていなかったのか?意識的にやったのか無意識的にやったのか?金が欲しかったのか映画界で成功したかったのか、彼女に判断を委ねなかったのか自分のせいじゃないことにしたかったのか・・・そこら辺が本人自身も曖昧なのです。ところが彼女には明確なのです。それで彼女は旦那を軽蔑し始めるわけですが旦那を愛する気持ちも残っているしセックスもしたいのでその辺の矛盾が彼女の中で悶々としているわけです。旦那は彼女をうまく誤魔化したいし自分自身をもうまく誤魔化したいのです。そのシーンが延々と続いて島でボートで誘われるシーンになってくるわけです。そこで彼女は旦那がしっかりと「お前は行くな」と言ってくれるのを待っているわけですけども、今度は旦那が確信犯的に「一緒に行けよ」と言うわけです。そういう心理を「俺はこういうつもりだったんだ」とか「あなたはそういう計画で言ったのでしょう」とか、そういうことを一言も言わずに描いた・・・二人がそういう馬鹿な争いをしたくないから・・・と、そこが面白いところです。多分そこら辺がフランス人的なのでしょう。・・最後の事故は自殺でしょう。彼女は横からハンドルをぐいと掴んでひねったんです。
ということで監督が何をやりたいのか分かったが、その芸術性と言うか作品の良さと言うか、そういうものがイマイチ伝わってこなかった・・・と言うか分からなかったと言うか、出来が悪かったと言うか・・どう評価するのが正解なのかわからないですね。ただ・・見て良かったか悪かったかといえばやっぱり見てよかったかな。
これがブリジットバルドーか!!
カプリ島 マラパルテ邸 BB 神話 そして カリーナ
原作はモラヴィアの同名小説(1954)
彼と嫁とヴィスコンティの三角関係時に書かれたものらしい
ボロニーニの「金曜日の別荘で」をみて
これを鑑賞しようと思った
ヴィスコンティの誘惑の場所はイスキア島の
自身の別荘で
ゴダールはプロデューサーの別荘で打ち合わせ(誘惑)場所にカプリ島の
マラパルテ邸を選んでいますね
BBが日光浴するのには抜群のロケーション
そしてマラパルテは窮地のモラヴィアを救っているらしい
モラヴィアの嫁は二股だったみたいだが
この映画では三角関係というより
他者の関与により増幅される夫婦の感情のすれ違い
それにより崩壊してゆく結婚生活を描いているようだった
美しい妻と新しいアパートの為の夫の努力が
妻には、忖度や堕落と受け止められたようで 軽蔑される
(ラングの「英雄の帰還」遅延説は面白い)
また、ゴダールにとってラングは英雄だが
プロデューサー(=ハリウッド)は海と大地を揺るがし破壊するネプチューンなのだろう
作家性のある監督と作品を潰し、商業主義に邁進する
ヨーロッパ映画界の斜陽の原因でもある
(ノルマンディー上陸作戦の正式名称はネプチューン作戦でしたね)
BBの存在感も抜群で完成度の高い作品となった
「地獄に堕ちた勇者ども」のモデルになった
ドイツ鉄鋼財閥クルップの三代目もこの島を愛したが
スキャンダルに巻き込まれ自殺(多分…)
婿グスタフが後継に……
魅惑の島では(このプロデューサーのように)
セレブもやらかしてしまうのかも
神になったような気がする場所なのだろうか
ブリジット・バルドーが最高に綺麗だった頃
夫婦のぎくしゃくした会話が延々と続き、見ていて相当退屈してしまったが、結局二人はどうなるかと、名監督の作品なので最後まで見届けようと思っていたら、まさに突然という感じで、妻役のブリジット・バルドーと彼女に近寄ってきていたジャック・パランスが事故で死んでしまう。それって、主人公や主要人物が亡くなることによって強制的にラストにして、その意味するところは観客の皆さんにお任せします・・・という一番安直なパターンでがっかり。
この時期のブリジット・バルドーは全盛期のカトリーヌ・ドヌーブ以上に綺麗だったが、そのブリジット・バルドーの良さを出し切れていない。
唯一良かったのは音楽。調べたら、後にプラトーンの音楽を担当したジョルジュ・ドルリューだった。
魅惑のBB
ベッドシーン、本物のチネチッタスタジオが登場。フランチェスカという何ヶ国語も話す通訳もすごい。フランス語と英語の狭間で言葉の重要性を仄めかす。脚本の契約を終えて、皆でカプリ島へ行く中でカミーユだけが行かないと言う。
その後、二人のアパートでの会話が中心となるが、夫婦仲の危機が訪れそうになる会話を見事に心理描写している。そしてカプリ島ではトロイの神話をモチーフにして妻への愛をどう貫くかという葛藤をする中、キスシーンを目撃してしまう。夫が妻をどれだけ愛しても妻は夫を愛していないという苦悩。映画は作るか作らないかのAllorNothing。妥協してしまうことが堕落になるという監督の映画に対する信念が表れている。
全て会話にして表現する戯曲的作風にしているところも映画の登場人物そのものなのであろうなぁ。オデュッセイアを撮り続けるラング監督もゴダールが褒め称えているのでしょうね。
フェルメールの名絵画「青いターバンの少女」(真珠の耳飾りの少女)が答え
英雄ユリシーズとその妻ペネロープとその求婚者
主人公とその妻とプロデューサー
この相似形を骨格に、なぜブリジットバルドー演じる妻が不機嫌になったのか、主人公を軽蔑するようになったのかについて展開する
映画が始まってすぐオデュッセウスを読んでいるなら、そんなことなんてすぐわかることだろう?とゴダールが判じかけてくる
彼女が軽蔑する理由なんて説明不要
読んだならもう自明のことなんだから
だから物語なんか不要だろう?と
さらに、そこに映画業界の内幕を舞台装置として選んで観客の興味を牽引しようとする
そして同時に映画製作に於ける自らの不満を訴えかけている
巨匠のラング監督を引っ張りだしてまでして
何故ならこんな連中が相手なんだぜと
連中とは、私達観客と映画産業の関係者のことだ
ラング監督の作品名を出してついてこれるのかをまず観客に問いただしている
Mは当然観ているよね?と
さらに映画産業の関係者に、そのMをラング監督の代表作の一番に挙げれないようなレベルで映画に関わっているのかよと軽蔑の視線を送るのだ
凝った作りだと思う、バルドーのまるで心が読めない不機嫌さの演技や演出、二人の状況を示すゴダール監督の演出の的確さは素晴らしい
しかし、この作りにこれが芸術だと感銘をうけるかどうかだ、本作を評価するかしないかはそこにあると思う
ラストシーンの事故に至るアクセル音と序盤のスポーツカーのアクセル音との対比と劇的幕切れでようやく物語性が思い出されて終わるのみだ
つまり物語の欠如と芸術との狭間にある作品で、どちら側に寄って立つかによるのだ
バルドーの有名な幅広のヘアバンドをしたヘアスタイルに注目しなければならない
明らかにフェルメールの名画「青いターバンの少女」(真珠の耳飾りの少女)をモチーフにしている
これは単にヘアメイクさんが適当にアレンジしたものではない
間違いなくゴダール自身による意志を持った演出なのだ
この絵はオランダのモナリザといわれている
有名なスチール写真をみれば顔の向きまでその絵に似せているではないか
つまり何を考えているかわからない表情を敢えてさせていることをゴダールは表現しているのだ
つまり本作のテーマはこのヘアスタイルに込められていたのだ
もっといえば、これが判らないようなら、俺の映画は理解できないからつまらないよ、ハリウッド映画でも観てなさいとも言っているのだ
ラストシーンは自らの映画作りへの信念を象徴する人物がハリウッドを象徴する人物と赤いスポーツカーに同乗して走り出したところで、大事故になり二人とも死んでしまうところで終わる
ハリウッドと俺が組んでも、ろくな結末にならないとゴダールは表明している
大惨事になるだけだと
初のゴダール作品、最高だ
映画好きを語るならば絶対に見ておかなくてはいけない監督の作品。ジャン=リュック・ゴダールの軽蔑。デジタルリマスター版を劇場にて観賞。
ぼくの年齢ではまだ、この映画の良さが半分もわかっていないんだろうな、と映画を見て思った。だけど、本当に美しく、素晴らしい作品だということはとても伝わった。
まず、映像と音楽が素晴らしい。赤と白のバスタオル、青い海、黄色いバスローブ、色彩が鮮やかですごく素敵。そして、ジョルジュ・ドリリューの音楽が本当に綺麗で最高でした。
どうして、女性は旦那を軽蔑するようになるのか。この映画の、夫婦間でのちょっとしたすれ違いが大きな溝になる、という部分が僕には少し理解が難しかった。大人になってもう一度必ず見ると思うので、現時点では星4。
BBが魅力的
早稲田松竹で最終日に見ました。結構混んでました。
ゴダールの作品はあまり見ていないのですが、これはたぶん分かりやすい方かと。
それでも「オデュッセイア」や詩の引用がいっぱい出てきて、あ〜、こういうのが全部分かれば違うんだろうな〜と。
モラヴィアの原作の方は前に読んだことがあって、それ以来ずっとカプリ島に行ってみたいと思っていますが、まだ果たせず。もしかして一生行かれないままかも。
だからこの映画、期待して見たのですが、カプリ島に行く前が長い。隣の席の人は寝てしまいました。
BBを映画館で見たのは私は初めてだったかも。本当にきれいな体です。
赤や青の使い方にも、もちろん意味があるんですよね。ブルネットのかつらにも。
一年の最後に映画館できれいな映像を観ることができて良かったです。
ブリジット・バルドーのお尻!?
シレンシオ!
ゴダール作品には珍しく大金をつぎ込んだ大作である。そのため製作者側からのかなりの横槍が入ったらしく、冒頭のカミーユ(バルドー)の全裸シーンも製作者側からの要望によって後から付け加えられたらしい。英、仏、伊の三ヶ国語が入り混じった脚本を、製作側で一ヶ国語に勝手に書き換えるという騒動もあったという。
当時ハリウッド側からプログラムピクチャーを撮らされていた名匠F・ラングを起用したところや、アメリカ人の映画プロデューサー・プロコシュ(ジャック・パランス)を俗物として描いたところにも、ゴダールが何を軽蔑していたのかが明確に伝わってくる作品だ。
「なぜ、愛する者の間にも金が入りこむのか」優柔不断の雇われ脚本家ポール(M・ピコリ)が劇中告白するように、大衆が望むものと芸術家の志向するものとの隔たりが、そのままポールとカミーユの心のすれ違いとなって描かれる。繰り返し挿入される主題曲が、ヴィスコンティのごとき演劇的空間に観客を誘い込み、普通の映画とは一味ちがうゴダールらしい演出が光っている。
劇中劇のオデュッセウスとペネロペイアになぞらえた悲劇は、ポールが隠し持っていた拳銃ではなく、カミーユの心中ともいえる事故によって幕を閉じる。「シレンシオ(静かに)」ただ静かに青く広がる地中海に放たれたこの言葉は、かまびすしく映画に横槍を入れたがる製作者たちに向けられていたのかもしれない
胸毛すんごかった
なぜ軽蔑されるのか。ハッキリした答えが出ないままに終わってしまった。途中でそれらしき回答はあったものの何か釈然としないままに。そりゃあ現代の日本人目線からすれば、その態度は振られるわと思うけど、、男の人には分からない部分があるのかなあなんて、ゴダールもこれアンナカリーナと別れて作ったんでしたっけ(?)
軽蔑って言葉に何とも決定的な破壊力がありました。女は女であるみたいに、なんだかんだ元どおりになるとタカをくくって見てきたので、あれよあれよとどん詰まりして振られるポールを見ていて、これは完膚なきまでにやられたなと思いました。大失恋ってなんだか男のロマンですね。
全39件中、21~39件目を表示