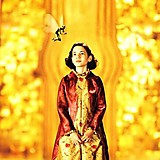イントレランスのレビュー・感想・評価
全10件を表示
映画の歴史の分岐点
1916年。D・W・グリフィス監督。これはすごい。長尺に気圧されて後回しにしていたことを後悔しました。誰かが「イントレラスには映画のすべてがある」と言っていたらしいが、それは誰でもいい。まさにその通りだから、いつでも誰でも言うことができるからだ。これも誰かが言っていてもおかしくない。
まず、制作された時代がすごい。第一次世界大戦中で、日本では夏目漱石が「明暗」を新聞連載していたころだ。この時代に、生まれてからさほど時間が経ってない映画という新しいメディアによって、4つの物語を平行して描くという離れ業をやっている。なんてことだ。有名なラストミニッツレスキュー(締め切りに向かって緊張感が高まること)は4つもあるので迫力満点なのはもちろんだが(人が走る。機関車も車も馬車も走る)、画角も画面の割り方もクロースアップもすばらしい。動きと静止、光と影、場面の反復などの「リズム」によって緊張と弛緩を自在に作り出している。劇中に音があるかないかや演技のはやりすたりは映画にとって本質的ではないことがよくわかる。
前作「國民の創生」に対する人種差別的だという批判をかわすという目的があったというが、社会がいかに「不寛容」(=イントレランス)に満ちているか、そのなかで人々の生命や愛情や生活がいかに生まれてはつぶされていくかという明確な主題がある。4つの物語のうち、現代アメリカ篇だけが最後に救われるがあとは悲劇。歴史は悲劇に満ちており、現代は可能性に満ちているという楽天的な結末だと捉えれば、これほど映画的な特徴をもった映画もないだろう。
「孤独な娘」のミリアム・クーパーと「山の娘」のコンスタンス・タルマッジが魅力的。
シネマの夜明け‼️
タイトルの意味は "不寛容"‼️人間の心の狭さが生む悲劇の事です‼️ストライキに騒ぐ現代の貧民街、ゴルゴダの丘を舞台にユダの裏切りによるキリストの磔、バビロニアをペルシャの侵略から守ろうとする山の娘、聖バルテルミーの虐殺の四つのエピソードが、オムニバスとしてではなく交錯して描かれています‼️そんな物語構成や、グリフィス監督が「国民の創生」と今作で確立した様々な映画技法は現代では当たり前になっているので、今この二作を観ても公開当時のような感激はないでしょうが、"映画の父" グリフィス監督に敬意を払い、1916年に脳内タイムスリップして観てみると、やはりこの作品の功績は偉大‼️特に力が入っているバビロニア編‼️その有名な巨大セットは映像で観ても驚嘆させられる‼️石器や石弓、象、巨大な火炎放射車、膨大な数のエキストラなどで展開するペルシャ軍とバビロニア軍の戦いは、現代のスペクタクル史劇の原点なのでしょう‼️戦いに勝ったバビロニアの盛大な宴のシーンも含めてホントにスゴい‼️そして四つのエピソードは、それぞれの悲劇に向かって収束していき、現代のエピソードだけが人間の善意によってハッピーエンドに終わる‼️この多少の救いがあるエンディングも素晴らしいですね‼️1916年、映画が見世物小屋的なエンタメに終始していた時代、その芸術性をいち早く世に示したグリフィス監督‼️ありがとうございました‼️
初心者が軽い気持ちで見るものではなかった
飛行機の中で無声映画を観ようと思い、色々調べるとこちらが名作とのことだったので挑戦しました。
結果、難しすぎて40分残して1時間半でリタイア…。
時代や場所を超えた4つの話が並行して進むというのは分かったのですが、誰が誰だかわからなくなる!それぞれの話が何を目指しているのかもわからない!画質という表現はおかしいかもしれませんが、白黒で画面がガサガサしているので正直みんな同じに見えます。辛うじて服装で見分けられるか?というレベル…。
色々な理不尽が降りかかってきて、それぞれの主役の女性(時に周りの男性も)がひたすらに大変な思いをしているなあという感想しか持てず…。
もっと映画や歴史や時代背景の知識が豊富な方が見ると違う感想を抱けるのだろうと思います。
一般教養必須科目
この作品の評価には気を付けなくてはいけません。
そもそもこの作品を観ようというような人間はそこそこの映画マニアに限られ、且つそういう人たちは私も含めて観る前にあちこちで「映画史に燦然と輝く不朽の名作」といった評価や記事を目にしているので、点数はかなり上げ底になっています。
全く予備知識のない人にとっては「何だかよくわからなくて、やたら長い罰ゲーム無声映画」というのが公平でまっとうな評価です。
四つの独立したお話が「不寛容=許さない」という主題で並行的に進んでゆく点は初めの字幕で示され、そこは良心的です。
しかし、それぞれのエピソードは「本筋」の話に「脇道」の話が絡んで進んでゆくわけですが、「脇道」についての説明が不十分、且つ「本筋」にどう関係してゆくのかわかりにくく、更に無声映画全般にいえることですが、無声であるが故に登場人物や場所を特定しづらく、主題がどうこういう以前にあらすじがよくわかりません。とりあえず、あらすじの記載されたブログなどを横に置い観ることをお薦めします。
音楽についても「国民の創生」と同様に、戦闘シーンだろうが恋愛シーンだろうが、場面の雰囲気に関係なく、初めから終わりまで有名なクラシック音楽を、ただひたすら「かけっぱなし」で、音響効果も何もあったもんじゃありません。まあ、大正時代はこんなもんなんですかね?
映画史的には極めて重要な作品ではあるので、映画ファンなら一度は観ておくべき必須科目ではありますが「風と共に去りぬ」「七人の侍」「ゴッドファーザー」などの時代を超えた不朽の名作ではありません。
108年を経て、今改めて「不寛容」を問う
遂に本作を映画館で観る事が出来ました。嬉しい!。108年前の映画で著作権もとっくに切れているので今ならば Youtube で観る事もできるのですが、「映画は映画館」での信念の下、これまで我慢し続け初めての鑑賞です。
本作監督の J.W.グリフィスは、現代に通じる様々な映画的技法を映画黎明期に築き上げた監督として知られ、本作は彼の代表作であるのみならず映画史上の金字塔とも呼ばれる3時間近い大作です。本作は勿論サイレントなのですが、今回はそこに澤登翠さん・片岡一郎さんという当代一の活動弁士お二人の語りが付きます。これ以上望めない条件を見逃す手はありません。たった一日の特別上映だったこともあり、場内は満席でした。
実は、グリフィスには『國民の創生』(1915) というもう一つの代表作があります。こちらは様々な訳があって映画館で上映される事はもうない(アメリカでは実質上上映禁止状態らしい)だろうと思われたのでDVDで鑑賞しました。これも、「斬新な手法で」と紹介される事が多いのですが、僕には「杜撰な物語だなぁ」としか思えませんでした。だから、「もしかしたら今回も・・」と危惧する面があったのです。でも、それは全くの杞憂でした。
本作は、紀元前6世紀の新バビロニア・キリスト最期の日々・16世紀フランスのサンバルテルミの虐殺・現代(1910年代)の4つの時代の悲劇を「不寛容(Intolerance)」という観点から描いた物語です。この四つの物語が並行して進むと言う設定が、本作独特のスピード感を生んでいます。この映画では、やはりバビロニア・パートの壮大な映像に息を吞んでしまいます。ポスター写真にある途轍もない神殿なのですが、今ならばPCの前に座って作り上げる事も出来るのでしょうが、この時代は勿論全てセットです。
「どれだけバカでかい物を作ってるんだぁ~」
「一体、何千人のエキストラを投入してるんだぁ」
とその迫力に只々口をアングリなのでした。
いや、そうしたお金を掛けた映像のみならず、無実の罪による死刑を食い止めようとする現代パートではハラハラ・ドキドキの演出が巧みですっかり手に汗を握ってしまいます。百年以上前に、これはやっぱり凄いなぁ。
そして、活動弁士のお二人の語りは、決して出過ぎる事がないながらも物語をグイグイと牽引しました。
これは値打ちもの。台風を押してでも出かけてよかったぁ。
PS. でも、今回も「僕は西洋史の知見が足りてないなぁ。欧米の人々にはこんな事は常識的前提なんだろうな」と感じる点が少なからずありました。この歳でも、勉強、勉強。
一体総勢何人の出演者がいる?!
古代バビロニア帝国での国王と高僧の対立、キリストの生涯における有名な挿話で断片的に構成されたユダヤ篇、サン・バルテルミの虐殺を題材としたとされる政治的決定を下すまでの宮廷内での件や結婚を翌日に控えた娘ブラウン・アイズとその婚約者の末路、現代篇と4つのエピソードで構成されているのだが、整合性のとれた形式によって、それぞれのエピソードが同尺で提示されるわけではない。
それは、D・W・グリフィス監督の映画的なモンタージュや数々の歴史的背景、それに纏わる監督独自の不寛容の視点、壮大なセットの建造、試行錯誤の末導き出したショットといったあらゆる要素が組み合わさってできたある種映像への挑戦がこの映画の凄みを強調させるのではないかと思う。
他方、率直な感想においては、
トーキーがゆえに、役者の表情、息づかいがとても細やかで引き立ち、感情を動かされるなということ。
作中、脳内で何度も"不寛容"について反芻された。
それほど不寛容にまつわる話が立て続けに起こるのだ。
そして時代の変化と共にそれぞれの境遇で悲劇や歴史の再生は繰り返されど、少しずつ希望に向かっていくのが心地いい。
勿論その背景や裏には幾重もの裏切り哀しみ淘汰が繰り広げられているわけだが、それでも人生に希望を持っても良いんだなと思わせてくれた。
クライマックスへの畳み掛けがすごい
大作を見終わったという達成感
グリフィスこそが「映画の父」
グリフィスこそが「映画の父」であり、歴史に名高い偉人達と並び称されるに値する偉大なパイオニアである。
「イントラレンス」に於いて映画作家としての頂点を極めている。
その画期的な撮影技術の数々はさることながらこの作品は壮大な大河ドラマであり、大活劇であり、スリラーであり、サスペンスであり、そしてヒューマンドラマである。
"不寛容"のテーマの元に作り出された4つの悲劇の物語で"過去"と"今"を映し出し、地球という揺りかごの元で繰り返される人間の不寛容の歴史という命題にアプローチする。
時間軸を支配し、過去と今のアプローチから未来を掲示する手法は今に於いても全く色褪せない。
また、物語だけでなくその画だけでも芸術性の高さが見てとれる。
特にかの有名なバビロンは、恐ろしいほど優雅で豪華絢爛である。
全10件を表示